 リーダー
リーダー Not To Do List: 失敗を避けて、よりよい人生にするためのやってはいけないことリスト(ロルフ・ドベリ)の書評
成功の法則を追うより、52の「人生の落とし穴」を避ける方が確実で早い!『Think clearly』の著者ロルフ・ドベリが放つ、失敗を回避するための逆転の成功哲学。断酒と朝型生活で人生を激変させた書評家・徳本昌大が、被害者意識を捨て「学習マシン」として生きるためのNot To Doリストを解説します。
 リーダー
リーダー 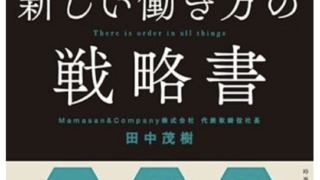 チームワーク
チームワーク 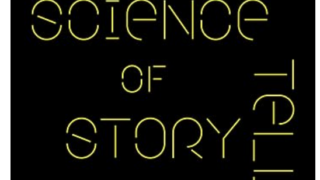 フレームワーク
フレームワーク 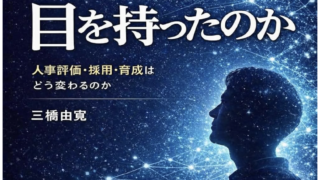 ウェルビーイング
ウェルビーイング 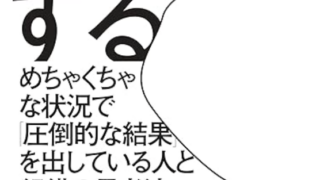 イノベーション
イノベーション 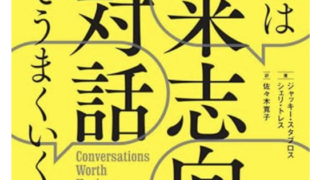 イノベーション
イノベーション 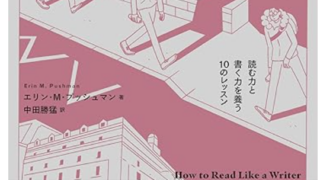 コミュニケーション
コミュニケーション 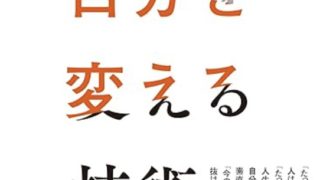 イノベーション
イノベーション 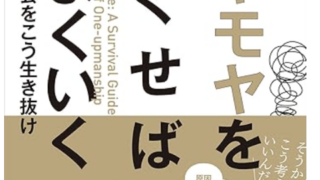 コミュニケーション
コミュニケーション  コミュニケーション
コミュニケーション