 イノベーション
イノベーション 進化するシン富裕層 (大森健史)の書評
シン富裕層とは、親の資産に頼らず、ごく普通の家庭から数年で富を築いた新しい富裕層を指します。彼らは直感を信じて即行動し、楽しさや好奇心を原動力に自己投資を重ねます。身の丈思考から脱却し、支出を将来の収益につなげる戦略的な視点を持ちます。挑戦を恐れず、柔軟に変化を受け入れることで成長を続け、人生を自ら設計していく姿勢が特徴です。
 イノベーション
イノベーション 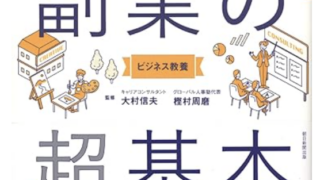 書評
書評 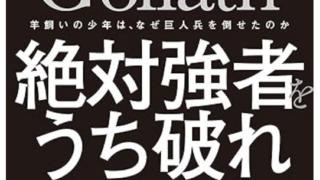 行動経済学
行動経済学 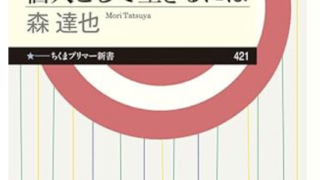 コミュニケーション
コミュニケーション 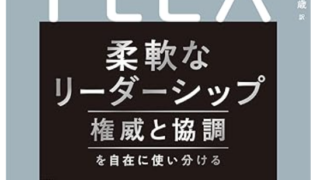 フレームワーク
フレームワーク 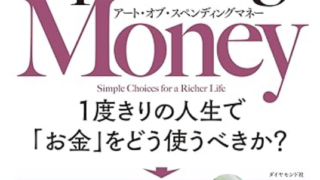 パーパス
パーパス 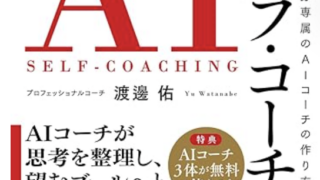 AI
AI 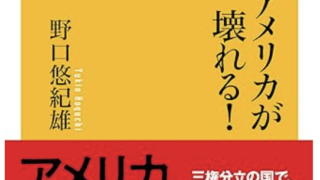 コミュニケーション
コミュニケーション 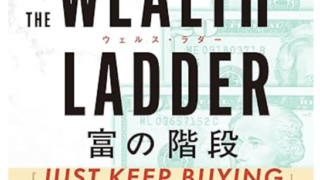 資産運用
資産運用  戦略
戦略