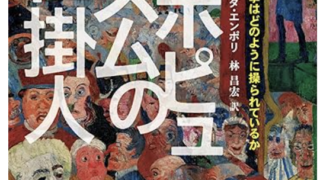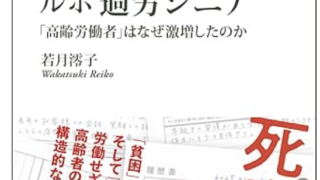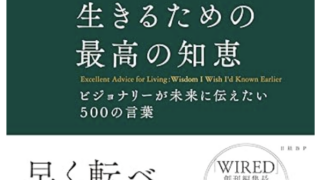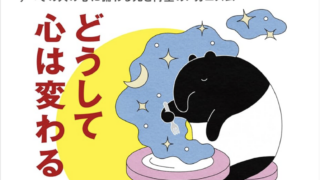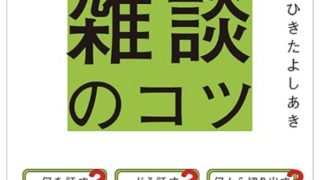 コミュニケーション
コミュニケーション 「何を話していいかわからない」がなくなる 雑談のコツ (ひきたよしあき)の書評
雑談力は才能ではなく、日々の中で育てられる“仕組み化”の積み重ねです。感情を丁寧に言葉にし、相手の魅力に気づき、リアクションで返す。そのうえで、5W1Hの質問で会話のトスを繰り返し、教えてもらう姿勢を大切にする。しくじり体験や感謝を伝える習慣も、雑談の質を高める重要な要素です。雑談を無理なく続けるための「仕組み化」を意識することで、会話は自然と広がり、信頼を育てる力に変わっていきます。