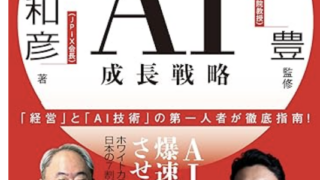 パーパス
パーパス ホワイトカラー消滅?冨山和彦氏が説く「AX時代」に生き残るリーダーの条件 【書評】日本経済AI成長戦略の書評
AI時代、リーダーに求められるのは分析ではなく「判断する勇気」だ。冨山和彦氏が提言する「AX(AIトランスフォーメーション)」の本質を凝縮。人手不足の日本こそ勝機がある理由、アドバンスト・ブルーカラーの台頭など、次世代の経営OSを読み解きます。
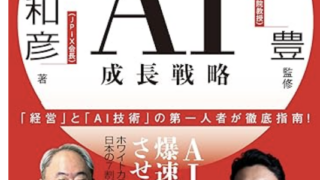 パーパス
パーパス 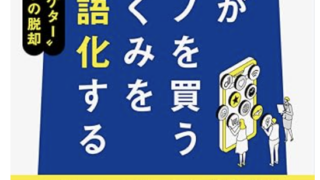 イノベーション
イノベーション 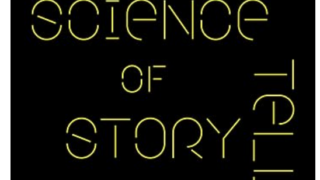 フレームワーク
フレームワーク 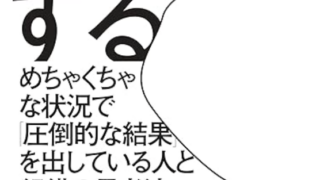 イノベーション
イノベーション 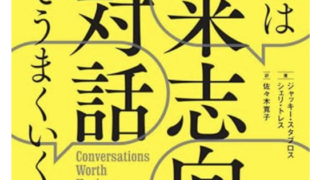 イノベーション
イノベーション 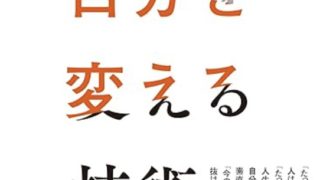 イノベーション
イノベーション  イノベーション
イノベーション  ブランディング
ブランディング 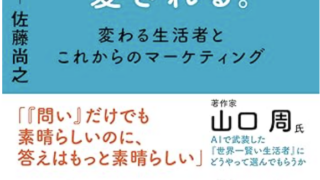 フレームワーク
フレームワーク 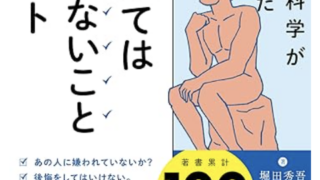 パーパス
パーパス