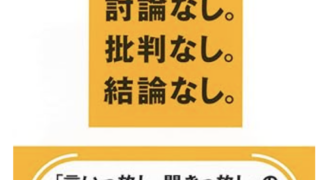 パーパス
パーパス ほんとうの会議 ネガティブ・ケイパビリティ実践法(帚木蓬生)の書評
本書は、日本の会議文化の限界を見直し、「ネガティブ・ケイパビリティ」と「オープン・ダイアローグ」を基盤とした新しい会議の形を提案しています。ギャンブル依存症の自助グループの実例や哲学的考察を通じて、結論を急がず、問い続ける対話の価値を見出し、人間の再生とつながりの本質に迫る一冊です。
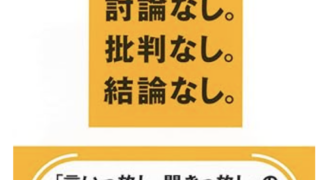 パーパス
パーパス 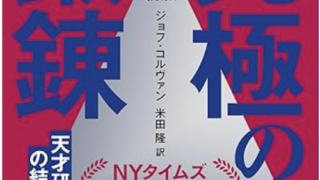 リーダー
リーダー 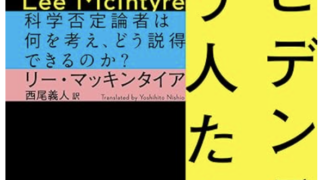 イノベーション
イノベーション 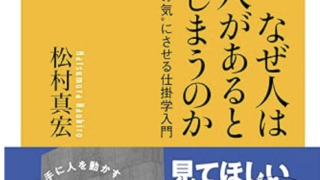 行動経済学
行動経済学 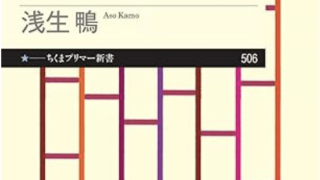 パーパス
パーパス 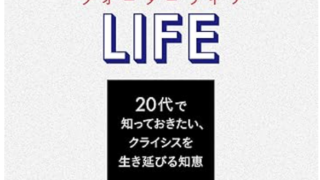 コミュニケーション
コミュニケーション 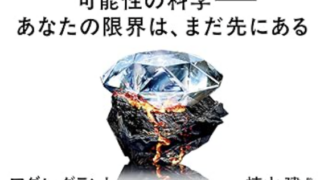 イノベーション
イノベーション  ウェルビーイング
ウェルビーイング  イノベーション
イノベーション 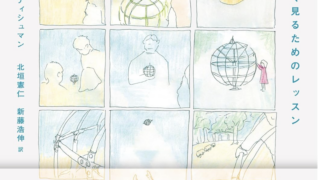 フレームワーク
フレームワーク