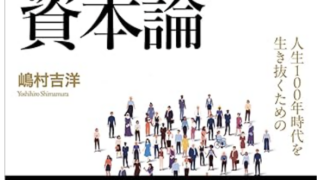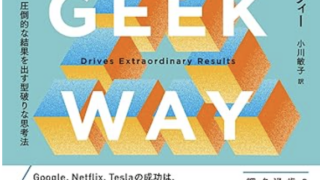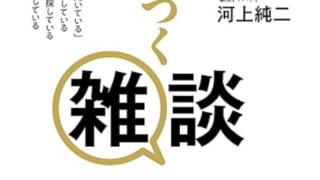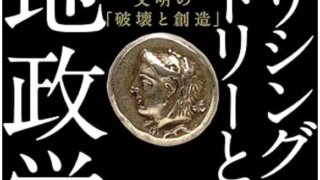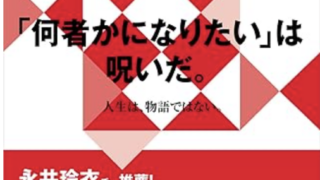経営学
経営学 越境人材――個人の葛藤、組織の揺らぎを変革の力に変える(原田未来)の書評
越境は、不確実性が高まる時代において、個人の成長と組織変革の双方を促す実践的な働き方として定着しつつあります。社外で得た経験を自分の価値観へ統合し、元の組織へ持ち帰って融合させるプロセスが本質であり、個人の視野拡大や内面的変化を引き起こします。また、越境者を中心に小さなイノベーションが生まれ、組織風土にも新しい刺激が広がります。企業間レンタル移籍のような制度を通じて、多様な視点を持つ人材が循環することで、企業文化は刷新され、イノベーションの土壌が育まれます