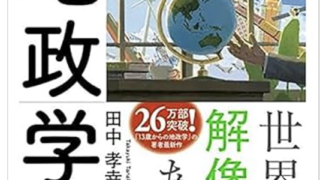 文化
文化 【書評】世界を解き明かす 地政学 (田中孝幸) 地政学が教える「国家生存」の非情なシナリオ
田中孝幸氏の『世界を解き明かす 地政学』を徹底解説。地理的条件が国家の行動を縛る冷徹なリアリズムとは?米国、中国、ロシアの戦略から、日本が直面する「静かなる侵略」の正体、文化破壊や参政権付与に潜むリスクまで。覇権交代期を生き抜くための生存戦略を読み解く一冊です。
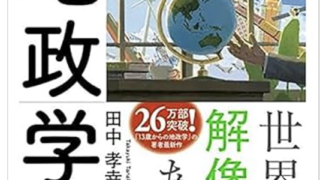 文化
文化 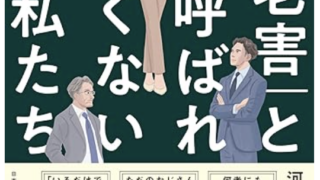 チームワーク
チームワーク 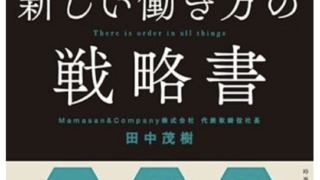 戦略
戦略 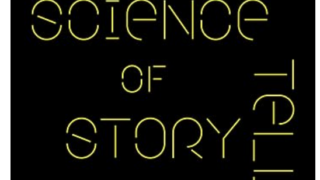 フレームワーク
フレームワーク 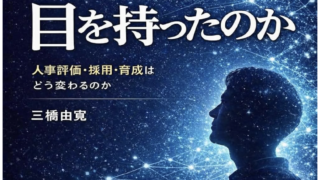 チームワーク
チームワーク 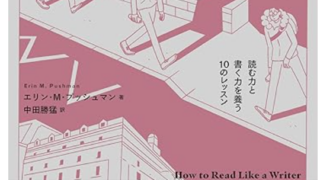 コミュニケーション
コミュニケーション  文化
文化 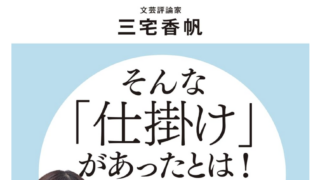 文化
文化  コミュニケーション
コミュニケーション 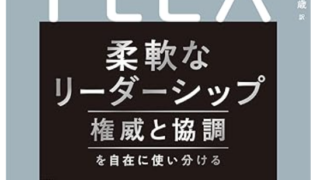 組織
組織