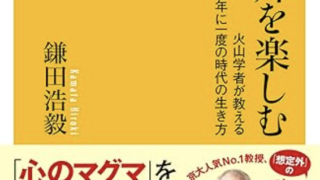 パーパス
パーパス 想定外を楽しむ 火山学者が教える一〇〇〇年に一度の時代の生き方 (鎌田浩毅)の書評
火山学者・鎌田浩毅氏が説く、不確実な時代を生き抜く知恵。人生の「想定外」をチャンスに変える「計画的偶発性理論」と、内なる情熱を活かす「心のマグマ」の付き合い方を解説します。意志に頼らず、習慣の力で未来を切り拓きたい方へ贈る一冊です。
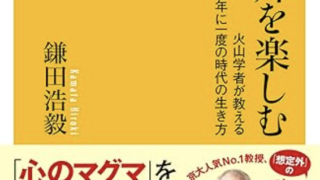 パーパス
パーパス 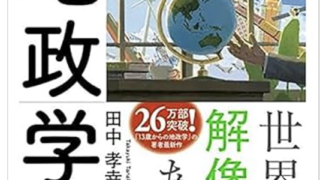 文化
文化 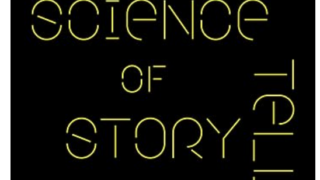 フレームワーク
フレームワーク 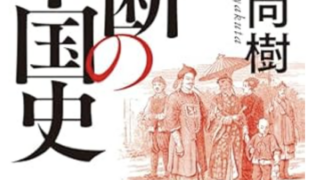 戦略
戦略  組織
組織 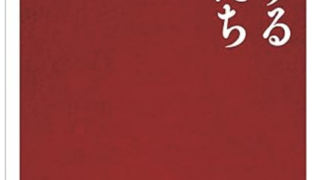 コミュニケーション
コミュニケーション  哲学
哲学  コミュニケーション
コミュニケーション  ブランディング
ブランディング  リーダー
リーダー