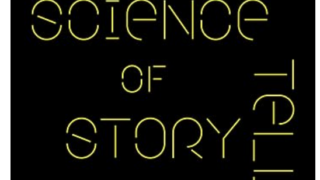 フレームワーク
フレームワーク ストーリーテリングの科学 (ウィル・ストー)の書評
「英雄の旅」等の型に頼る物語はなぜ響かないのか?書評ブロガー徳本昌大が『ストーリーテリングの科学』を徹底解説。脳の認知システムに基づき、読者の心を掴む「不合理な信念」と「情報ギャップ」の作り方を公開。AI時代にこそ必要な、人間にしか描けない物語の真髄がここにあります。
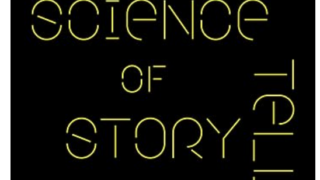 フレームワーク
フレームワーク  投資
投資  文化
文化 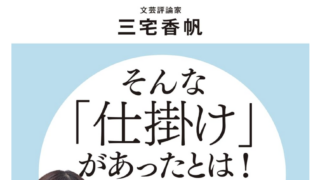 文化
文化 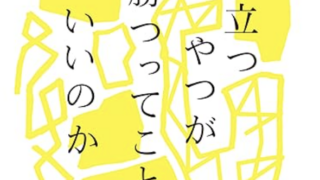 コミュニケーション
コミュニケーション 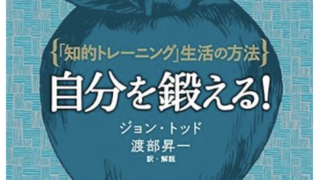 コミュニケーション
コミュニケーション 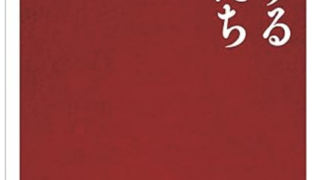 コミュニケーション
コミュニケーション 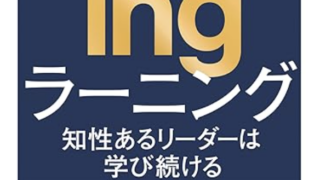 ウェルビーイング
ウェルビーイング 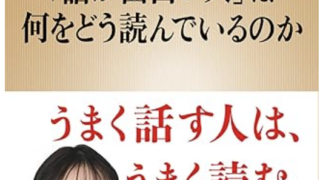 フレームワーク
フレームワーク 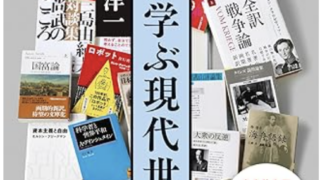 哲学
哲学