だからあれほど言ったのに
内田樹
マガジンハウス
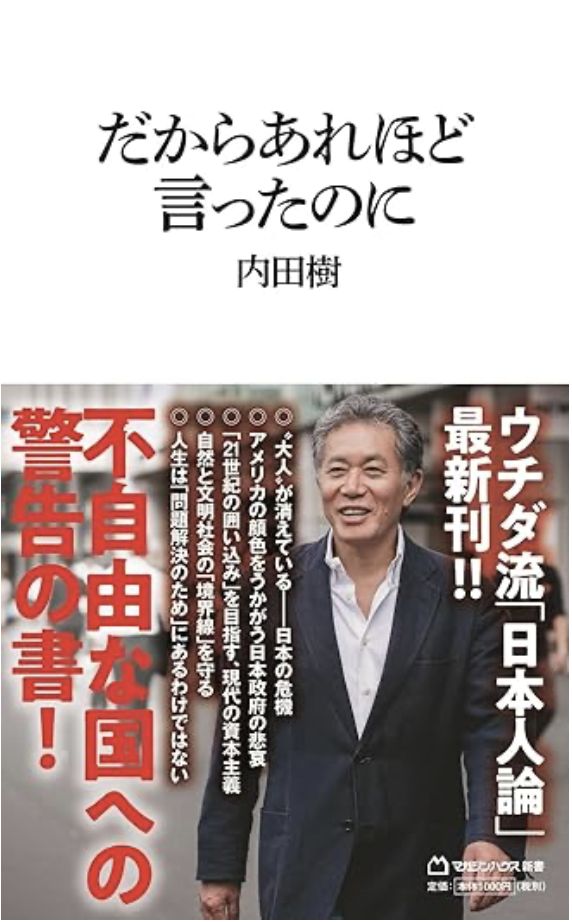
だからあれほど言ったのに(内田樹)の要約
本書は、思想家の内田樹氏が独自の視点から政治、社会、教育、文化など幅広いテーマについて論じており、その鋭い分析力と啓発的で独特な思考が読者を引き込みます。著者は、複雑な問題を分かりやすく解説し、読者に現状に疑問を投げかけることで、自らの考えを深めるきっかけを提供しています。
政治家やリーダーが堕落する日本
日本国民は属国の身分にすっかり慣れ切っているので、自国政権の正統性の根拠を第一に「アメリカから承認されていること」だと思い込んでいる。「国民のための政治を行っていること」ではないのだ。アメリカに気に入られている政権であることが何よりも重要だと国民自身が思い込んでいるので、自公政権がずるずると続いている。(内田樹)
2024年6月の時事通信の調査によると、岸田内閣の支持率はわずか16.4%にまで低下しています。これほどの低支持にもかかわらず、閣議決定で次々と重要事項を決定し、民主主義を蔑ろにしています。政治家たちの悪政が続く中で、国民の一部がそのシステムに諦めを感じるなかで、逆にシステムを「活用」する人々が出現するという深刻な状況に直面しています。
自公政権は、防衛増税やインボイス制度、マイナンバーカードの導入など、国民の負担を増大させる政策を次々と進めています。これに加え、メディアが政権批判をやめておとなしくなる中で、国民は「政府は国民の生活のために政策を実施するものではない」という認識に慣れ切ってしまっています。
現在の自民党がめざしている政治改革はシンガポールの政体を模範にしている。反政府的な野党勢力に国会議席を与えず、労働運動を抱え込み、メディアを支配下に置き、「世襲貴族」たちが権力の座を占有して、政権との親疎がそのままキャリア 形成に直結するネポティズム政治である。
この10年の自民党政治は、「シンガポール化」と呼ぶにふさわしい状況だと著者は言います。シンガポールは国民監視システムをパッケージで中国から輸入しています。中国政府の発明である「社会的信用システム」を採用し、政権に批判的な市民の信用スコアを下げ、海外旅行を禁止したり、列車やホテルの予約を取れないようにしたりするなど、市民の行動を制限しているのです。
自民党が目指しているところは、中国やシンガポールのような監視体制と変わりません。 マイナンバーカードという不出来なシステムの導入により、日本でも市民の行動や情報が厳しく監視されることになり、プライバシーや自由が制限される恐れがあります。
多くの国民は、「政府はアメリカや国内の鉄板支持層の利益を優先して政治を行っている」という現実を理解し、政治に対して諦めの感情を抱いています。このような諦念が広がると、国民の間には「この不出来なシステムを主権国家としてのあるべき姿にどう生き返らせるか」という考えよりも、「この不出来なシステムをどう利用するか」という発想が芽生えます。
現行のシステムには多くの「穴」が存在します。これらの欠陥を利用すれば、公権力を私的目的に用い、公共財を私財に付け替えることで自己利益を最大化することが可能です。現代の日本では、このような行動をとる人々が増え、システムをhackしながら利益を貪っています。これが一部の勢力が政権を支持する背景となっています。
このような状況が続くと、日本の政治システムがさらに機能不全に陥る危険性があります。国民の中には、システムの欠陥を利用して自己利益を追求する人々が増え、結果として公共の利益が損なわれる恐れがあります。これは、国家としての本来の機能を果たせなくなる危険性を孕んでいます。
貧乏くさい国から脱却する方法
現代日本の際立った特徴は、富裕層に属する人たちほど「貧乏くさい」ということである。富裕層に属し、権力の近くにいる人たちは、それをもっぱら「公共財を切り取って私有財産に付け替える権利」「公権力を私用に流用する権利」を付与されたことだと解釈している。公的な事業に投じるべき税金を「中抜き」して、公金を私物化することに官民あげてこれほど熱心になったことは私の知る限り過去にない。
現代日本の際立った特徴の一つは、富裕層に属する人たちほど「貧乏くさい」ということです。これは一見奇妙に思えるかもしれませんが、その背景には深刻な社会問題が潜んでいます。富裕層に属し、権力の近くにいる人たちが、公的な資源を私有財産に付け替えることに躍起になっているのです。
現代の日本では、富裕層や権力者たちは「公共財を切り取って私有財産に付け替える権利」や「公権力を私用に流用する権利」を持っているかのように振る舞っています。公的な事業に投じるべき税金を「中抜き」し、公金を私物化する行為が蔓延しています。これは、官民あげて行われており、過去には例を見ないほどの規模と熱意で行われています。
このような現象を著者は「貧乏くさい」と表現します。税金を集め、その使い道を決める人たちが、自らの利益を優先し、公金を私財に付け替えることを「本務」としているからです。一部の経営者は政治家への献金を行い、自社の利益アップを目指し、政治家は裏金作りに奔走しています。この「貧乏くささ」は、社会的地位が上昇するほど顕著になります。社会的上昇を遂げるということが「より貧乏くさくなること」を意味しています。
権力者やリーダーが貧乏くさくなり、モラルがなくなることが、社会に荒廃をもたらしています。公共の利益を顧みず、自己利益を追求する姿勢が広がることで、社会全体の信頼が損なわれています。税金の使い道が透明で公正であるべきところが、不透明で不公正なものとなり、国民の信頼を失っているのです。
システムの欠陥を利用する人々がいる一方で、このシステムの内側で生きることを止めて「システムの外」に出ようとする人々もいます。地方移住者や海外移住者はその一例です。彼らは、このシステムを変えることはできないと諦め、システムの外に「逃げ出す」ことを選びました。
私たちは今、二者択一を迫られています。システムの欠陥を利用して自己利益を追求する「hack」か、システムの外に逃げ出す「run」か。その選択が令和日本の、特に若者に突きつけられています。そしてここには、「システムの内側に踏みとどまって、システムをより良いものに補正する」という選択肢が欠落していると著者は言います。
現在の日本は、政治家の悪政と国民の諦念が相まって、システムの欠陥を利用する人々が増加するという深刻な事態に直面しています。このような状況を改善するためには、国民が再び政治に対する信頼を取り戻し、システムの健全な運用を目指すことが求められます。
システムの「穴」を利用するのではなく、システムを改善し、持続可能な社会を築くための努力が必要です。若者を中心に、このシステムの改修に向けた新たなアプローチが求められています。政治家などのリーダーの世代交代を起こすために、今こそ選挙で国民は正しい選択を行うべきです。
公共をかたち作るためにまず身を削るのは「おまえ」ではないし「やつら」でもない。それは「私」である。 そう思い切ることからしか豊かな社会は生まれない。同意してくれる人はまだ少ないけれど、私はそう確信している。
現代日本における富裕層の「貧乏くささ」は、公共財の私物化と公権力の私用化という深刻な社会問題を反映しています。この状況を改善するためには、大人が自ら行動を起こし、他者(コミュニティ)のために資産やリソースを提供することが重要です。これにより社会全体の信頼を回復し、持続可能な未来を築くことができるでしょう。
社会的な地位の上昇が「貧乏くさくなること」を意味しないよう、私たちはシステムを変え、より公正で持続可能な社会を目指していく必要があります。




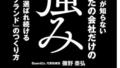

コメント