 コミュニケーション
コミュニケーション 棺桶まで歩こう (萬田緑平)の書評
緩和ケア医・萬田緑平氏は、歩く力は気力と直結しており、寿命を左右する重要な指標だと説きます。がんや老化に屈するのではなく、自分の足で歩き、自宅で穏やかに旅立つことこそが、尊厳ある最期のかたち。死を遠ざけるのではなく、日常に引き寄せてこそ、生きる意味と時間の使い方が見えてくる──それが、本書の力強いメッセージです。
 コミュニケーション
コミュニケーション 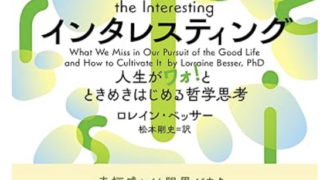 パーパス
パーパス 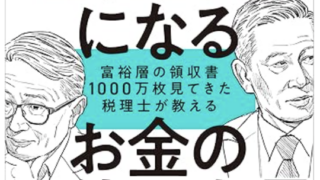 リーダー
リーダー  コミュニケーション
コミュニケーション 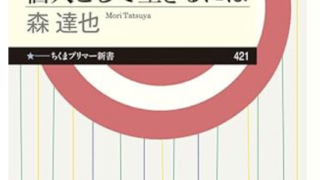 コミュニケーション
コミュニケーション 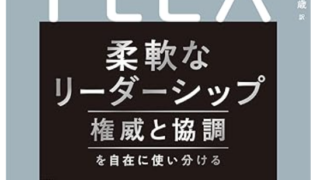 コミュニケーション
コミュニケーション 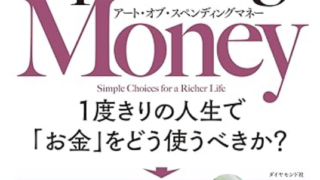 資産運用
資産運用 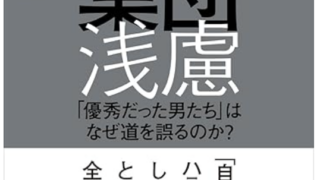 チームワーク
チームワーク 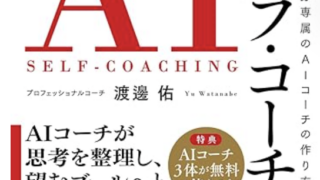 ウェルビーイング
ウェルビーイング  コミュニケーション
コミュニケーション