 戦略
戦略 作家で食っていく方法 (今村翔吾)の書評
今村翔吾氏の『作家で食っていく方法』は、作家を“職業”ではなく“生き方”と定義し、夢を現実にするための戦略を徹底的に言語化した一冊です。創作論に加え、ビジネス視点・時間管理・行動力・自己投資の重要性までを網羅。作家志望者はもちろん、何かを始めたいすべての挑戦者に向けた、リアルで実践的な仕事論です。
 戦略
戦略  コミュニケーション
コミュニケーション  哲学
哲学  哲学
哲学  フレームワーク
フレームワーク  哲学
哲学 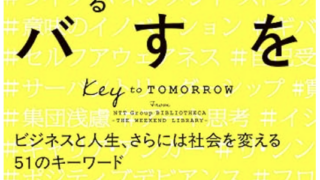 コミュニケーション
コミュニケーション  哲学
哲学 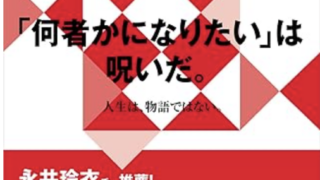 戦略
戦略 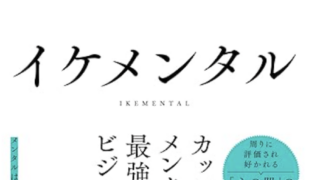 哲学
哲学