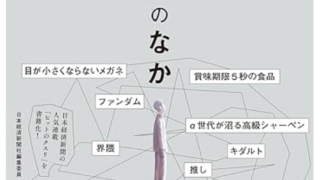 イノベーション
イノベーション 「ヒットの達人」の頭のなか (中村直文)の書評
ヒットは偶然ではなく設計された結果です。日経MJ元編集長の中村直文氏が、名だたるヒットメーカーの思考回路を解剖。顧客の「言葉にならない本音」を言語化し、市場を創り出すための4つの条件とは?停滞する企画を突破し、マーケティングの解像度を劇的に高める一冊を徹底解説します。
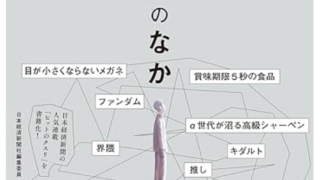 イノベーション
イノベーション 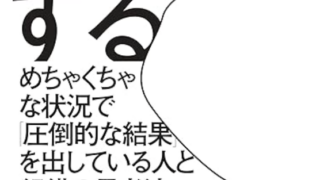 イノベーション
イノベーション 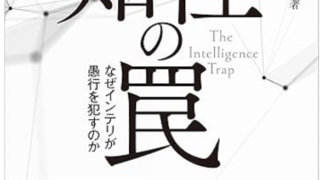 天才
天才 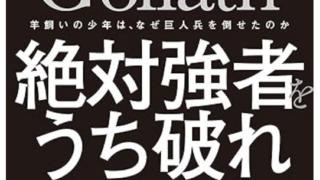 イノベーション
イノベーション 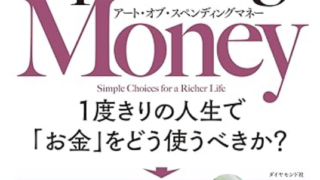 パーパス
パーパス 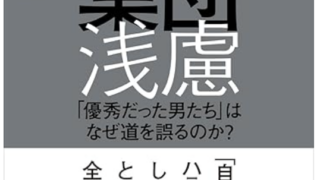 行動経済学
行動経済学  イノベーション
イノベーション 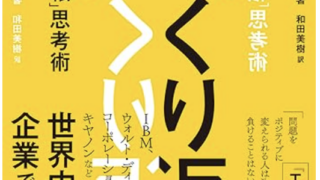 行動経済学
行動経済学  組織
組織 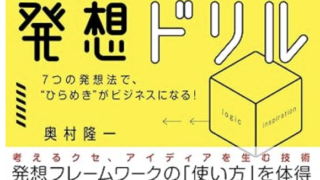 イノベーション
イノベーション