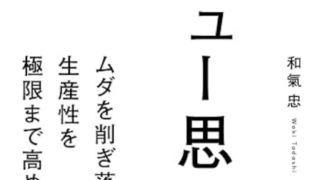 パーパス
パーパス イシュー思考(和氣忠)の書評
イシュー思考は、課題を的確に捉え、効率的に解決へ導く思考法です。まず「イシューの特定」で目的を明確にし、本質的な課題を抽出します。次に「イシューアナリシス」で論理的に分解し、サブイシューへ整理。ツリー構造の「イシューの体系図」を活用し、問題解決を視覚化します。これにより無駄を削減し、生産性向上や論理的思考力の強化が可能になり、ビジネスや個人の成長に役立ちます。
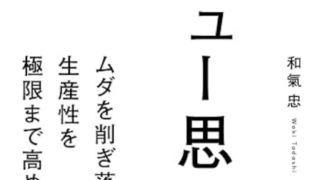 パーパス
パーパス 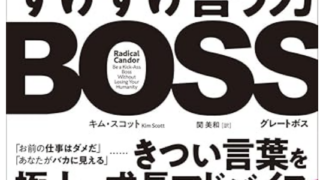 戦略
戦略  イノベーション
イノベーション 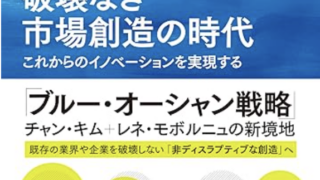 イノベーション
イノベーション  フレームワーク
フレームワーク  イノベーション
イノベーション  戦略
戦略 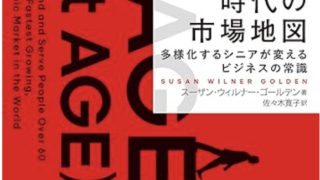 フレームワーク
フレームワーク  パーパス
パーパス  イノベーション
イノベーション