感情戦略
ブリアンナ・ウィースト
日経BP
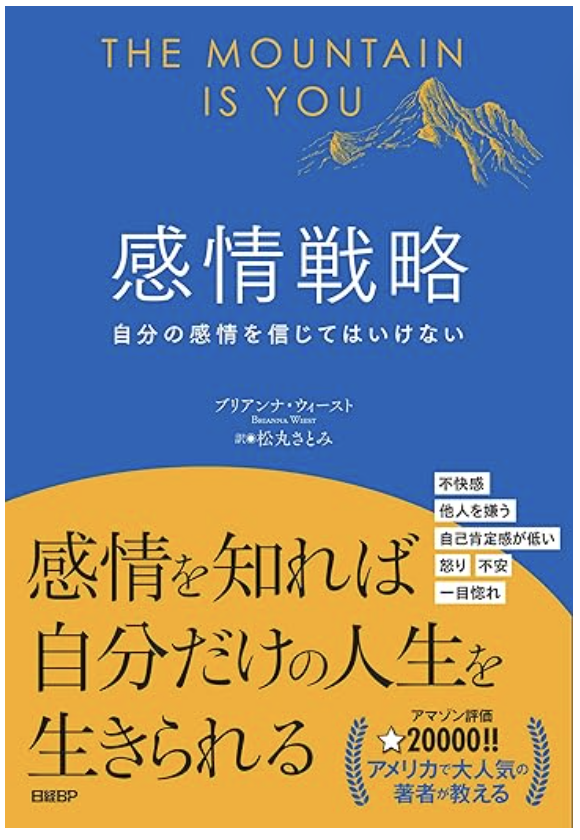
感情戦略(ブリアンナ・ウィースト)の要約
私たちが変われない原因は、無意識に持つ信念や「未知」への恐れにあります。自己破壊的な行動はその防衛反応にすぎません。本当に変化を起こすには、感情に向き合い、コア・コミットメントを理解することが鍵です。嫉妬や後悔は、心の奥にある本音を映すヒントです。変化は劇的な一歩ではなく、小さな決意の積み重ねから始まります。今この瞬間に意識を向けることが、人生を動かすもっとも現実的な方法なのです。
気づかないうちに“自分で足を引っ張る人”の共通点とは?
本当の問題が何であるかが分かれば、自分がいつもどう主導権を手放してしまうか、なぜ受け身でいるかを考えるなど、解決に向けた努力を始められます。しかし本当の問題が分からなければ、車の助手席に座り続けながら、不安にならないように、と自分に言い聞かせ続けることになります。その間、症状はただただ悪化するばかりです。(ブリアンナ・ウィースト)
何度も同じ失敗を繰り返してしまう、やろうと決めたのに動けない、気づけば自分を責めている――。そんな経験はありませんか。気持ちはあるのに、行動がともなわない。目標に近づくどころか、むしろ自分で自分の足を引っ張ってしまっている。そんな状態が続くと、「自分は何をしても変われないのでは」と無力感を覚え、次第に人生そのものへの意欲も薄れてしまいます。
意識では前に進みたいと思っているのに、無意識のどこかでブレーキを踏んでしまっている。その正体がわからないまま日々を過ごしていると、気づけば本当は望んでいなかった場所へと流されてしまうのです。「何かおかしい」とは感じているものの、具体的にどこをどう変えればよいのかが分からない。だから、今日もまた自分に言い聞かせます――「これでいいんだ」「不安になる必要はない」と。
ブリアンナ・ウィースト著感情戦略(原題:The Mountain Is You)は、自己破壊的な行動や慢性的な内面の葛藤に悩む人々に向けて書かれた一冊です。著者はそのような状態を、車の助手席に座ったまま「安全運転でお願いします」と繰り返しているようなものだと言います。自分の人生という車のハンドルを握っていない以上、どれだけポジティブな言葉をかけても、本当の安心感は得られません。
そしてその間にも、不安や焦り、自己否定といった内なる“症状”は、静かに、確実に悪化していくのです。 その背景には、ある根深い心理が潜んでいることがあります。私たちは自分が達成したいと願うことに対してさえ、心の奥底では「よくないこと」「ふさわしくないこと」と感じてしまうことがあるのです。
たとえば「金銭的に安定したい」と願っているにもかかわらず、なぜか努力を途中で台無しにしてしまう。そんな場合には、まず「自分はお金というものに対して、本当はどう感じているのか」を見つめ直す必要があります。育った家庭で親はお金をどう扱っていたのか。お金持ちや貧しい人についてどんな価値観を語っていたのか。そうした環境が、「お金を得ることは悪いこと」「お金持ちは傲慢だ」といった無意識の信念を生み、それが自分自身のブレーキになっているのかもしれません。
また、日常の習慣に表れる行動にも、深層の信念が反映されていることがあります。たとえば、ついジャンクフードばかり食べてしまうのは、もしかしたら「心を落ち着かせたい」という無意識のニーズから来ているのかもしれません。しかし、そのさらに奥には、「なぜそんなにも心を落ち着けたいのか」という問いが隠されています。
同様に、悲観的な性格ではないのに、つい他人に不平不満ばかりを口にしてしまう人がいます。その根底には、「不満を共有することでしか人とつながれない」という思い込みがある可能性も否定できません。 こうした行動パターンを変えていくには、まず自分の中にある前提――つまり「これが当たり前」「こうするしかない」という思考の土台そのものに疑問を持つことが必要です。
たとえば、「お金を持っている人は皆、不正をしている」という見方は、現実を単純化しすぎています。確かに利己的な使い方をする人もいますが、その一方で、自分や他者に時間・チャンス・健やかな環境を与えるために、お金を得ようと努力している人も存在します。
自分の思い込みに気づき、より柔軟で現実的な新しい考え方を選び取ること。それが変化への第一歩になるのです。 本当の問題が何であるかが分かれば、自分がいつもどのように主導権を手放してしまうのか、なぜ受け身でいるのかを見つめ直すことができます。
そこからようやく、解決に向けた具体的な努力を始められるのです。けれども、もしその本質が分からなければ、私たちは助手席に座り続けながら、「不安にならないように」と自分に言い聞かせることしかできません。そしてその間にも、状況は静かに、しかし確実に悪化していくのです。
弱い自分から脱却し、変化するために必要なこと
人間は、未知のものに自然と抵抗します。というのもそもそも人は、知らないものはコントロールできないからです。「未知のもの」がたとえ善意だったり、恩恵をもたらしてくれるものだったりしてもです。
もう一つ重要なことは、「未知」への感情です。人間は本能的に、未知のものに対して抵抗を示します。なぜなら、知らないものはコントロールできず、不確実性を伴うからです。たとえその「未知」が善意だったり、恩恵をもたらすものであったとしても、脳はそれを避けようとします。
多くの自己破壊的な行動も、実は単に「慣れていないもの」への拒絶反応から来ている場合があります。 変化とは、新しい環境や新しい感覚への適応です。しかし私たちは、良い変化ですら「異質」であるという理由だけで不快に感じ、「これは間違っている」「自分には合わない」と早合点してしまうのです。けれど、必要なのは拒絶ではなく、「慣れること」です。
心理学者ゲイ・ヘンドリックスはこれを「上限(Upper Limit)」と呼びました。人には「どこまで幸せを許容できるか」という無意識の限界が存在し、知らず知らずのうちに「快適すぎる状態」を自ら壊してしまう傾向があるのです。いい気分になること、満たされること、うまくいくこと――それらを自分に許す度合いには、限界があります。そしてその限界を超えようとするとき、違和感や不安というかたちで自己破壊が顔を出します。
この「幸福の上限」を押し広げていくには、まず自分の中にある未知への恐れや違和感を見極め、それが悪いものではなく、新しいものであると再認識することが不可欠です。 そして、自分の本当の恐れを知り、深い意味で癒されていくためには、「考え方そのもの」を変える必要があります。
私たちはしばしば、知らず知らずのうちにネガティブで、しかも誤った信念に従って生きています。それが当たり前だと思い込んでいるからこそ、疑うことすらしないのです。 癒しとは、そうした信念に意識的に注意を向け、「本当にこれは自分の役に立っているのか?」と問い直すところから始まります。
そして、自分のためになる思考、より自由で健全な視点を持てるようになってはじめて、内面的な癒しや変容が始まるのです。
どん底の状態はチャンスです。問題の共通点は唯一、自分だけだと気づかされ、ようやく自分に向き合う状態になったからです。ちょっと落ち込んだだけの日には、「もう二度とこんな思いはしたくない」とは思いません。限界点に達するのは、自分が抱えている問題が、世の中のせいではなく、自分のせいだとようやく受け入れられるようになったときです。
自分の本当の恐れを知り、深い意味で癒されていくためには、「考え方そのもの」を変える必要があります。私たちはしばしば、知らず知らずのうちにネガティブで、しかも誤った信念に従って生きています。それが当たり前だと思い込んでいるからこそ、疑うことすらしないのです。
癒しとは、そうした信念に意識的に注意を向け、「本当にこれは自分の役に立っているのか?」と問い直すところから始まります。そして、自分のためになる思考、より自由で健全な視点を持てるようになってはじめて、内面的な癒しや変容が始まるのです。 とはいえ、ほとんどの人は、変わらないままでいることのほうが不快だと本気で感じる瞬間が来るまで、人生を変えようとはしません。
それはつまり、ほかに手の打ちようがない、打つ手が尽きた――そんな極限の状態に至って、ようやく人は「変わるしかない」と決断するのです。どん底の状態は、実はチャンスでもあります。
なぜなら、自分が抱える問題のすべてに共通していたのは「自分自身だった」と気づかされ、逃げ場のない現実と向き合うことになるからです。 ほんの少し落ち込んだ日には、「もう二度とこんな思いはしたくない」とまでは思いません。
しかし限界点に達すると、言い訳や他責思考が剥がれ落ち、ようやく、「今まで変わらなかったのは環境のせいでも、誰かのせいでもなく、自分の在り方の問題だった」と受け入れられるようになります。
私自身、まさにそのような経験をしました。 今のように変われたのは、アルコール依存症というどん底の時期を経験したからです。 飲まないとやっていられない日々。感情をごまかし、空虚な時間をアルコールで埋め続ける毎日。理性ではまずいと分かっていながらも、感情の渦に呑まれ、自分をコントロールできない自分に対する怒りと恥。 本当は誰よりも満たされた日々を送りたかったのに、自分の手でそれを壊し続けていました。
当時の私は、「どうしてこんなにも自己破壊的なのか」「なぜ繰り返してしまうのか」さえ分からず、ただひたすらに自己嫌悪の中で生きていました。 でも医師からのアドバイスによって、「もう無理だ。体と心が壊れる」と心底思った瞬間、自分の中にある「何か」が音を立てて崩れました。そしてようやく、自分と向き合う覚悟が生まれたのです。
依存症とは、今にして思えば「感情の痛み止め」のようなものでした。感じたくない感情や、直視したくない現実から自分を守るための手段だったのです。けれど、その痛みの奥には、自分が本当に求めていたものが確かに存在していました。
そこに向き合わないまま、ただ表面的に行動を変えても、何ひとつ根本的な解決にはなりません。 その事実に気づいたとき、私はようやく断酒という決断に踏み切ることができました。アルコールという、かつての自分の象徴=執着を手放したことで、ようやく人生を立て直す旅が始まったのです。
私は理想の自分を描き、それにフォーカスすることで、断酒を成功させ、自分のビジョンを実現できるようになったのです。
コア・コミットメントを理解することで、人生が変わる!
嫉妬とは、別の感情を隠すための感情です。怒りや批判として表現されますが、本当にそこにあるのは、悲しみや自己不満です。自分が人生で何を本当に求めているのかを知りたければ、誰に対して嫉妬を感じるかを見てみましょう。もちろん、その人が手にしているものとまったく同じものが欲しい、というわけではないかもしれません。けれどあなたが味わっているその感情は、「あの人はあれを追いかけることができているのに、私にはできない」という怒りなのです。
自己破壊的な行動の背景には、自分でも気づいていない無意識の目標が隠れていることがあります。それが「コア・コミットメント」と呼ばれるものです。これは、自分が人生で最も大切にしている価値観や、本当に求めていることを指します。
コア・コミットメントは通常、表面的には見えません。けれども、何に悩み、何に強く動機づけられるかをよく見ていくと、その核心が浮かび上がってきます。たとえば複数の悩みがあったとしても、それらを丁寧に掘り下げていくと、いつも同じ「根っこ」にたどり着く感覚があるはずです。それこそが、あなたのコア・コミットメントなのです。
たとえば「状況をコントロールしたい」という思いが強い人は、実は「信頼すること」ができずにいるのかもしれません。「必要とされたい」と願っている人は、「自分が求められていると実感すること」を無意識に求めています。そして「誰かに愛されたい」と思っている人にとって本当に必要なのは、「まず自分を愛すること」なのです。
これらは一見すると矛盾しているようですが、実はすべて、コア・コミットメントとそれを満たすための「コア・ニーズ」という構造でつながっています。
そして、私たちが抱える感情の中でも、特に深く根を張るもののひとつが「嫉妬」です。嫉妬とは、別の感情を隠すための感情です。怒りや批判として表現されますが、本当にそこにあるのは、悲しみや自己不満です。
自分が人生で何を本当に求めているのかを知りたければ、誰に対して嫉妬を感じるかを見てみましょう。もちろん、その人が手にしているものとまったく同じものが欲しい、というわけではないかもしれません。けれどあなたが味わっているその感情は、「あの人はあれを追いかけることができているのに、私にはできない」という怒りなのです。
たとえばこうです。とても欲しいものがあるけれど、追いかけたい気持ちを我慢しているとします。それを手に入れている誰かを見たとき、私たちは、その人を非難せずにはいられなくなります。そうすれば、追いかけたいのに我慢している自分の行動を正当化できるからです。 コア・コミットメントを理解することで、人生の選択が変わり始めます。
後悔は、自分が本当に望んでいることを照らし出す内なるコンパスです。だからこそ、感情に耳を傾けることは弱さではなく、自分自身への誠実さの表れです。自分が抱える感情の正体に気づいたとき、初めて本当の意味で自分の人生を選べるようになるのです。
心の知能指数が高い人は、さまざまなタイプの人とうまくやっていくことができ、毎日の生活にも満足度が高く、自分の正直な感情を処理、表現するための時間を常にきちんと取っています。心の知能指数とは主に、体の中に湧き上がってくる感覚を解釈し、その感覚が人生について何を教えようとしているのか理解する能力のことです。
無意識は、「快適さの門番」だと著者は指摘します。人生で癒しや変化を経験しているとき、新しい日常の感覚に体を慣らす必要があります。だからこそ、変化はどれだけ前向きなものであれ、慣れるまでは居心地悪く感じてしまいます。頭脳を使って、優れた判断を下す必要があります。
最高の知性を使って、自分がどこへ向かいたいのか、何者になりたいのかを決め、時間をかけて体を慣らさなければいけません。ラクをしたいという無意識には、反抗をすべきなのです。
毎日の行動は、人生の質と成功の度合いを決定します。努力していると「感じる」か否かではなく、とにかく実際に努力するか否かです。人生でどのような結果が出るかは、情熱によって決まるわけではありません。原則によって決まります。今朝自分が取った行動がそこまで重要だったとは、思わないかもしれません。でも、重要だったのです。
そんな小さなことに意味があるとは、思わないかもしれません。でも、意味があるのです。 大きな変化を気にすることが難しいのは、人間が欠陥のある無能な存在だからではありません。人間が快適ゾーンの外で暮らすようにはできていないからです。
人生を変えたいなら、ほとんど気づかないような小さな決意を、それが習慣になるまでいついかなるときも毎日、していく必要があります。そうすれば、ある日それがカチリと身につくときがくるのです。
スマートフォンを使いすぎていると感じるのであれば、次にチェックしたくなったとき、その一回だけ我慢してみることから始めてみましょう。もっと健康的な食事を心がけたいと思うのなら、今日は一日、野菜を中心としたメニューに置き換えてみるのです。運動不足を感じているのであれば、10分だけでも構いません。今この瞬間に体を動かしてみてください。読書を習慣にしたいのであれば、まずは1ページだけ開いてみることです。
私自身、このブログを書くためにテレビの電源を切り、早朝に起きる習慣を取り入れました。人生を変えるとは、大きな決断を下すことではありません。むしろ、自分の感情と丁寧に向き合い、思考のクセに気づき、小さな行動を積み重ねていくプロセスそのものなのです。
過去への後悔や、他人への嫉妬といった感情もまた、無視すべきものではありません。それらは、私たちが何を求め、どこに向かうべきかを静かに示してくれるサインです。だからこそ、不快だからといってそれらにフタをするのではなく、その感情に含まれているメッセージに目を向けるようにするのです。
今にエネルギーを注ごう!
信じられないかもしれませんが、「今」にエネルギーを注ぐと、無限の可能性がある世界へと自由に足を踏み入れられるようになります。そうすればなりたかった自分になれ、つくりたかったものをつくれ、欲しかったものを手に入れられるようになります。時間は今であり、場所はここなのです。
人間が実際に行動を起こせるのは、過去でも未来でもなく「今この瞬間」だけです。これは単なる精神論ではなく、習慣形成や脳の働きといった科学的な知見とも一致しています。「今に集中する」ことは、意志力や集中力、創造性といった私たちの行動の原動力と深く関わっています。
現代の神経科学においても、私たちの選択や判断の質は、どれだけ「今ここ」に意識を向けているかによって大きく左右されることがわかっています。つまり、「今」にエネルギーを注ぐことで、視野が広がり、主体的な選択ができるようになり、結果として望む変化に近づいていけるのです。 目指していた自分になることも、何かを創造することも、結果を得ることも、そのすべては「今」に集中することから始まります。
時間はいつも「今」にしか存在せず、人生のスタート地点もまた「ここ」でしかありません。 人生が変わるのは、「前に進みたい」と願いながらも、今という現実にも感謝できるときです。理想の外見でなくても、自分を認め、愛することができたとき。経済的な不安があっても、お金に対して希望と信念を持てたとき。そして、他人を上下ではなく対等に見る視点を持ったとき。私たちの生き方は、大きな出来事によって変わるのではありません。日々の心の姿勢と行動の積み重ねによって、静かに確実に変わっていくのです。
人生が本当に変わるのは、もっとも避けたいと思っていた感情に、正面から向き合った瞬間です。ありのままの自分を認め、恥や不安を抱きしめたとき、ようやく私たちは「本来の自分」に近づきます。不快感は敵ではありません。それは、あなたの感受性が正常に働いている証であり、癒しの扉の前にある合図なのです。
お金、人間関係、健康――次から次へと浮かんでくる問題の数々は、実はどれも“表面の症状”にすぎません。その奥にある、繰り返し浮上する感情こそが本当の課題です。「何かを変えなければ」と思ったとき、自分を変えようとする前に、自分の感情と対話することが先決なのです。
人生の問題の多くは、「今この瞬間」に意識を戻すことができないことから生まれます。けれども、今こそが唯一の現実です。未来の不安も、過去の後悔も、「今」には存在しません。
だからこそ、私たちは今日を丁寧に生きる必要があります。 未来の自分のために行動することと、今という瞬間に集中すること。そのバランスを取りながら、「いま、ここ」を丁寧に積み重ねていきましょう。結局のところ、人生を変えるのは特別な日ではなく、今日という一日なのです。





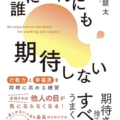


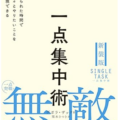


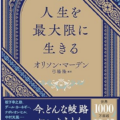
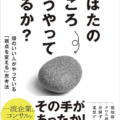
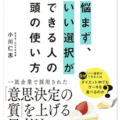
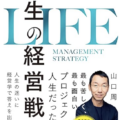
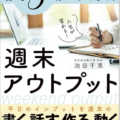


コメント