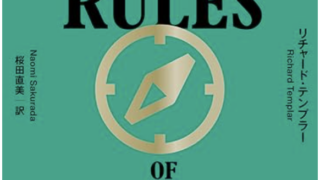 投資
投資 できる人の人生のルール (リチャード・テンプラー)の書評
リチャード・テンプラーの『できる人の人生のルール』は、幸福を長い時間軸で捉える視点と、若いうちの挑戦や失敗の価値を教えてくれます。失敗は行動の証であり、未来の糧となる経験です。完璧を求めるより、学びを重ねて柔軟に前進する姿勢こそが、豊かで自分らしい人生へとつながっていきます。
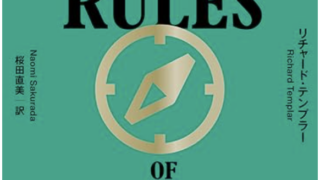 投資
投資 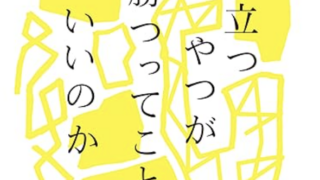 コミュニケーション
コミュニケーション 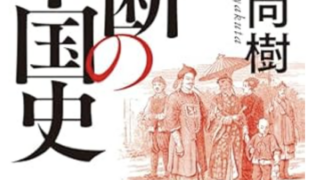 戦略
戦略  イノベーション
イノベーション  リーダー
リーダー 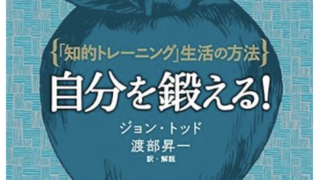 パーパス
パーパス 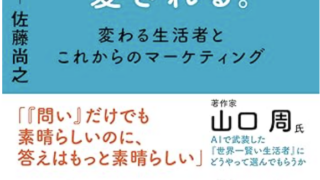 ChatGPT
ChatGPT 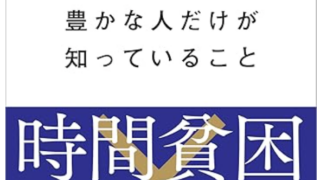 ウェルビーイング
ウェルビーイング 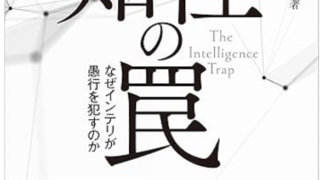 リーダー
リーダー  イノベーション
イノベーション