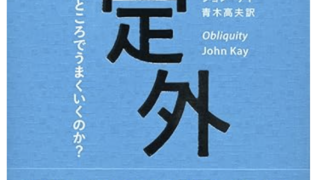 コミュニケーション
コミュニケーション 想定外 なぜ物事は思わぬところでうまくいくのか? (ジョン・ケイ)の書評
なぜ一直線に目標を追うほど幸福や成功は遠ざかるのか?ジョン・ケイ著『想定外』から、試行錯誤と学習を繰り返す「回り道」の思考法を紐解きます。計画的偶発性理論にも通じる、不確実な時代を生き抜くための新しい意思決定のあり方を提示します。
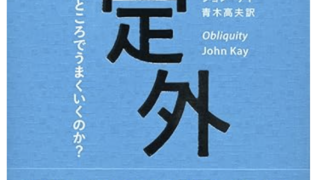 コミュニケーション
コミュニケーション 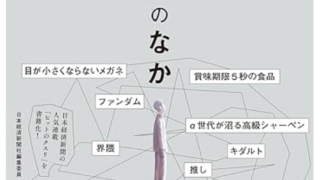 パーパス
パーパス 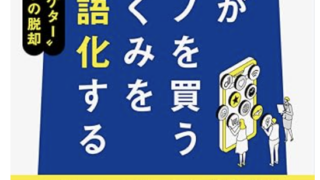 ブランディング
ブランディング  チームワーク
チームワーク 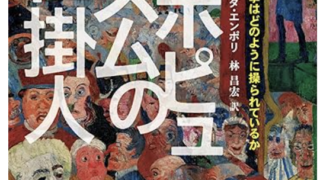 コミュニケーション
コミュニケーション  イノベーション
イノベーション  コミュニケーション
コミュニケーション 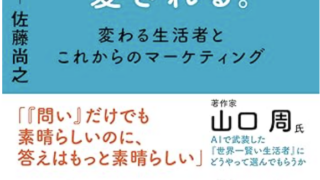 パーパス
パーパス 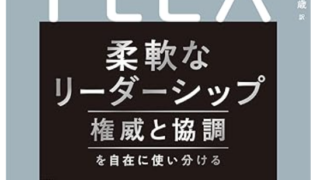 チームワーク
チームワーク  ウェルビーイング
ウェルビーイング