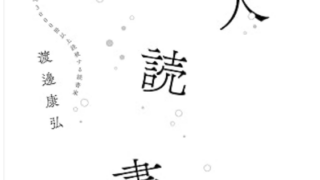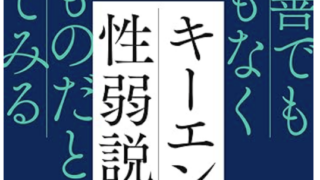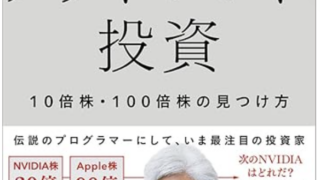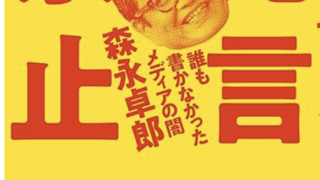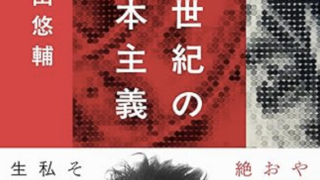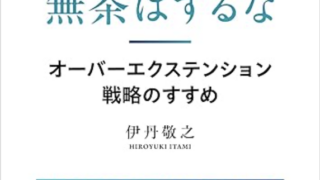 フレームワーク
フレームワーク 経営は無理をせよ、無茶はするな オーバーエクステンション戦略のすすめ(伊丹敬之)の書評
成長が強く求められている日本企業にとって、これまでの延長線上にある戦略だけではもはや限界に直面しています。そうした中で注目されるのが、「オーバーエクステンション戦略」です。これは、自社の能力に足りない部分があると認識しながらも、あえてその限界を超えて挑戦し、現場の学習を通じて能力基盤を拡大していく、いわば“背伸びの戦略”です。 この戦略を成功させるには、「無理」と「無茶」の境界を見極めながら、あえて困難なプロセスに踏み出し、やり抜く姿勢が不可欠です。