ぼくたちはどう老いるか
高橋源一郎
朝日新聞出版
30秒でわかる本書のポイント
結論:老いとは単なる「喪失」ではなく、人生の速度を落として、自分との対話の時間を持つ移行期間である。 記憶が薄れても思考を止めず、過去の断片を編集しながら自分を更新し続ける技術こそが老いの本質。
原因:身体や記憶の精度が落ちる「もうろく」により、これまでの社会的な枠組みや役割から外れていく。 死が抽象的な概念から「自分の問題」へと具体化し、効率や生産性を追えない「空白の時間」が生まれる。
対策:効率や正解を求めるのをやめ、「もうろく」を徹底的に味わい尽くす観察者として生きる。 記憶の欠落を嘆くのではなく、残された断片を「目印」にして自分自身との対話(編集)を止めない。
本書の3行要約
本書は、老いを単なる「肉体の衰え」や「喪失」としてではなく、「時間の使い方を組み替え、叡知を得るための移行期間」と捉え直す一冊です。記憶や身体が自由を失っていく「もうろく」の過程を、自分自身や過去と対話するための貴重な思考の時間として肯定しています。作家ならではの視点で、文学作品や身近な死を通じ、老いゆく自分や家族とどう向き合うべきかの指針を示しています。
おすすめの人
・「老い」に対して漠然とした不安や恐怖を感じている人
・親の介護や自身の加齢に直面し、家族との距離感に悩んでいる人
・効率や生産性を重視する社会に疲れ、人生の後半戦の「時間の使い方」を模索している人
読者が得られるメリット
・価値観の転換: 衰えを「マイナス」ではなく、世界を捉え直す「新しい視点」として受け入れられるようになります。
・精神的な安らぎ: 「不完全なまま生きる」ことの肯定感を得て、老いに対する過度な取り乱しが軽減されます。 ・対人関係のヒント: 家族や他者の老いを「未来の自分の姿」として慈しむ、寛容な視点が身につきます。
「もうろく」する過程の意義とは?
「老いる」とは「叡知」を得るということなのだ。「叡知」の生まれない「老い」は、単なる「老化」にすぎないのだ。(高橋源一郎)
私は今月63歳になります。鏡に映る自分を見て、以前よりもはっきり「老い」を意識するようになりました。近ごろは「人生100年時代」という言葉に背中を押されるように、老いをテーマにした本も目立ちます。今回は、作家・批評家の高橋源一郎氏によるぼくたちはどう老いるかを取り上げます。
高橋氏は冒頭で、読者に子どもの頃からの記憶を遡るよう促します。老いとは衰えの話に見えて、実は「時間の使い方」を組み替える出来事でもある。老いることで「時間ができる」とは、単に暇が増えることではなく、考えるための時間と場所を得ることなのだ、という見立てがここにあります。
本書の前半は、「もうろく」を手がかりに、老いによって変化していく身体や記憶、思考とどう付き合えばよいかを描いています。衰えを嘆いて終わるのではなく、衰えつつある自分と、どう対話を続けるかに焦点を当てた内容です。
その議論の背骨になっているのが、鶴見俊輔の『もうろく帖』です。高橋氏は鶴見の言葉を参照しながら、記憶や身体が弱っていくとしても、「考えること」まで同じ速度で衰えるとは限らないことを確認しています。
誰もが老い、誰もが死へ向かう。その避けがたい道を、必要以上に取り乱さず、状況を見つめながら歩けること――その態度こそが、本書のいう叡知に近いのだと思います。 ここで言う「もうろく」とは、死の直前に訪れる劇的な局面ではありません。死がはっきり見えてくる手前にある、もっと茫洋とした期間のことです。
記憶が衰え、認知も揺らぎはじめる。日常は続いているのに、判断や集中、段取り、記憶の呼び出しが少しずつ鈍くなり、自分の輪郭がゆるんでいく。完全に何かが壊れるわけではないけれど、以前と同じ精度では生きられない。その微妙な不確かさが、案外長く続きます。
だから「もうろく」は、衰えの事実を受け入れながら、欠けた部分を抱えたまま暮らしを続け、自分と対話し続けるための時間だと言えます。死へ向かう一本道の途中で、速度を落とし、世界の見え方を組み替えていく――そのための「移行の時間」。本書はその期間を、恐怖や敗北としてではなく、思考を続けるための条件として捉え直しているのです。
私たちは、たとえ、記憶を失たっとしても考えることができるのです。老いとは、記憶が減ること以上に、減っていく条件のなかで思考を続ける、過去との対話の技術を身につけることなのかもしれません。
著者が繰り返し触れるのは、死が「他人の出来事」から「自分の問題」へと移る瞬間です。近親者や知人の死が重なると、死は抽象ではなく、具体的な現実として足元に現れます。ただし、その気づきは陰鬱さだけに回収されません。
人は弱り、混乱することがあっても、過去を呼び戻す「目印」や「記号」によって立ち直れる、と著者は述べます。ここで大事なのは、過去が完全な形で保存されているという話ではないことです。少しだけ残った目印が呼び水になり、欠落を抱えたままでも現在に接続できる。その「不完全な回復」こそ、老いの現実に沿っています。
私にとっても、老いはある日突然訪れる出来事ではなく、日々のなかで静かに進行しているものです。行動の時間が少しずつ減り、思考の時間が増えていく。その変化のなかで、私はもうろくし、忘れることが増え、かつての自分をそのまま保てなくなっていくでしょう。
けれど、その過程を「喪失」だけで記述する必要はないのだと、本書は教えてくれました。記憶を失いながらも思考を続けること、その継続のなかで自分を更新し続けること。
新しいことはなにも起こらない。それが「老い」の本質だ。会うべき人にはもうすべて会った。読むべき本は読み尽くした。やるべきことはすべてやった。いや、やるべきことでやれなかったこともたくさんある。けれども、もうやる機会はやって来ないのだ。やるべきことはもうない。もうすぐやって来る「死」だけが「未来」なのだ。だから、「老い」た人間にとって、存在しているのは、過去に存在しているもの、「おもいで」だけなのである。
さらに本書は、老いを「この世」と「あの世」の中間に立つ視点から捉えます。まだ生きている。けれど、この世で「やるべき」とされてきたことの多くをやり終え、社会の網目から少しずつ外れはじめる。すると逆に、網目に絡め取られて身動きできない人々の姿がよく見えるようになる。老いは視界を狭めるだけでなく、世界の見え方そのものを変えてしまうのだ、という観察です。
そこに、老いの知恵が生まれる余地がある。 私たちは闇から歩み出し、闇に向かって歩いていく存在です。闇が「自分がいない世界」を指すのだとしたら、生きている最後の時間だけでも思考を続けることが、人生に彩りを与えてくれるのです。
老いで記憶が薄れても、思考は続けられる。
「老い」は、「家族」の問題でもある。あるいは、いつか自分もたどり着く場所を、あらかじめ確認する作業でもあるのだ。目の前にいる「老い」た誰かは、遠くない未来の自分の姿なのである。どうして、そんな人間を疎ましい目で見ることができるだろうか。
本書の中盤で、高橋源一郎氏の視点は「家族」へ移ります。老いは本人の内面の変化であると同時に、家族にとってははっきりした「出来事」になるからです。
まず参照されるのが、吉本隆明の晩年を長女であるハルノ宵子が記した『隆明だもの』です。そこにあるのは、偉大な思想家の「最後」ではなく、生活者としての老いが家族の時間に入り込んでくる現実です。老いる本人の変化は、家族の役割や距離感を徐々に組み替え、看取る側の感情もまた揺れ動きます。老いは個人の問題であると同時に、関係の問題でもあるのだと先に示しておくことで、この章の視野が定まります。
そのうえで登場するのが、有吉佐和子の『恍惚の人』です。高橋氏はこの作品を足場にして、老いが家族にもたらす現実を掘り下げます。支える側と見守る側の葛藤、介護と愛情がぶつかり合う緊張、そして本人と家族の距離が少しずつ組み替わっていく過程が、ぼけの始まりから死に至るまでの時間のなかで、具体的に描かれていきます。
さらに私小説作家・耕治人の作品が参照され、老いと向き合う「家族の知恵」が、文学の側から拾い上げられていきます。
ここで重要なのは、「死」もまた老いと同じく、二つの視点を持つという点です。ひとつは当人にとっての死であり、もうひとつは他者、とりわけ家族から見た死です。当事者は「老い」や「死」のただ中に最後まで居続けることができません。
「死」もまた、「老い」と同じように、「自分」の「死」と、「他人」(とりわけ「家族」)から見た「死」の二つの問題があるのだ。考えてみれば、それは当然のことだ。ぼくたちは、「老い」て「死ぬ」。そこにどんな問題があったとしても、当事者は、そのさなかに最後までとどまることはできない。「老い」は進行してゆくと、やがて、自分自身を失う世界へ退行してゆく。その先には、「死」が待っていて、そこではもう当人の役割はないのだ。
老いが進むほど、当人は自己の存在を手放す方向へと移っていき、その先に死が待っています。そこではもう、当人が「当事者」として何かを完結させる役割は残せません。老いと死は、当事者が現場から退場せざるを得ない出来事であり、残された家族が後始末を引き受けざるを得ないのです。
老いをどれほど深く考えたとしても、私たちはその最終地点に自分の足で立つことはできないのです。高橋氏の文章は、その厳然たる事実を言語化します。
この観点に立つと、社会と家族の役割の違いも見えてきます。社会は制度や効率で人を分類し、ときに高齢者を「不要」として扱います。しかし家族は、最後にはその人を「その人」として認め直してくれます。
もちろん家族が万能だという話ではありません。負担や葛藤は現実にあります。それでも、当事者が退場していく過程を、最後まで現実として引き受けるのは多くの場合、家族になるのです。
後半では、谷川俊太郎と著者の弟のトシちゃんを軸に、死と老い、そして「ひとりで老い、ひとりで死ぬ」ことの意味がより掘り下げられていきます。
高橋氏は身近な死とも向き合い、死を感情の噴出で終わらせず、複数の角度から捉え直します。 ここで、鶴見俊輔の視点がもう一度効いてきます。鶴見が見つけた「ゴール」は、初めて経験する老いを避けるのではなく、徹底的に味わい尽くすことです。
老いを特別な出来事として隔離せず、「老い」を含む世界の言葉を拾いながら、進行している自分の身体と心の変化を観察していく。老いが単独で存在するのではなく、日々の風景や会話の隙間に紛れているのだとすれば、言葉を拾う作業は、そのまま老いを受け止める作業になります。
老いとは、徐々にもうろくしていく自分と対話しながら、あえて速度を落として生きることでもあります。効率やタイパが正義になりがちな時代に、ゆっくり考え、ゆっくり感じ、ゆっくり選び直す。記憶が目減りしていくからこそ、思考の形が変わっていくのです。
記憶の中で残っている過去の断片を並べ替え、意味をつくり直し、いまの自分にとって必要な形に変えていく。老いとは、その編集をやめないことなのです。
耕治人の老々介護を描く作品は、家族がいない孤独のなかで生きるとはどういうことかを、別の角度から突きつけます。耕治人が示しているのは、人生の終わり方の「一つの型」です。孤独は、悲劇の演出ではなく条件として立ち上がり、記憶がまだ薄れきっていない残された時間をどう過ごすのかを、本人に問い返します。
支える人がいないからこそ、老人は自分で考えざるを得ない。その現実を直視したとき、私たちに残る選択肢は、孤独を避けることだけではありません。孤独という条件のなかで、何を思い、誰とどう関係を結び直し、どんな言葉を拾いながら日々を組み立てていくのか。本書が呼び戻すのは、その具体的な問いのほうです。
60歳を過ぎた私にとって、老いは「いつか来る出来事」ではなく、すでに始まっている日々の変化です。動ける時間が少しずつ減り、その分、考える時間が増えていく。その流れのなかで私はもうろくし、忘れることが増え、以前の自分を同じ形のまま保てなくなっていくのでしょう。けれど本書は、それを単純な「喪失」として片づけない視点を与えてくれました。
記憶は薄れても、思考まで消えるとは限りません。残った断片で考え直し、意味を組み替え、更新していくことはできるのです。
私はこの本から、残り時間を「延ばす」より、どう「使うか」を問い直すヒントを受け取りました。忘れる自分を責めるのではなく、忘れていく条件のなかで、何を考え、何を残し、誰とどう生きるかを選び直していく、ということです。
家族に迷惑をかけたくはありません。しかし、当たり前ですが、死に方を選ぶことはできません。だからこそ、家族との時間を私たちは大事にすべきなのです。
本書のまとめ
本書が教えてくれるのは、「もうろく」を嘆くのではなく、それを一つの条件として思考を続け、過去を今の自分に合わせて編み直していく「編集」の技術です。記憶が薄れ、身体が思うように動かなくなったとしても、そこにはまだ、あなたにしか見えない世界の風景が広がっています。
老いゆく日々は、誰もが初めて経験する未知の領域です。だからこそ、無理に抗うのではなく、変化を観察し、言葉を拾い続け、不完全なままの自分を愛おしむ。そんな「老いの作法」を身につけたとき、私たちの人生は最後の瞬間まで彩りに満ちたものになるはずです。




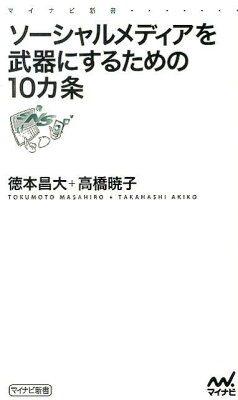










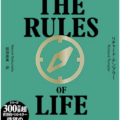


コメント