働きすぎで休むのが下手な人のための 休息する技術
菅原道仁
アスコム
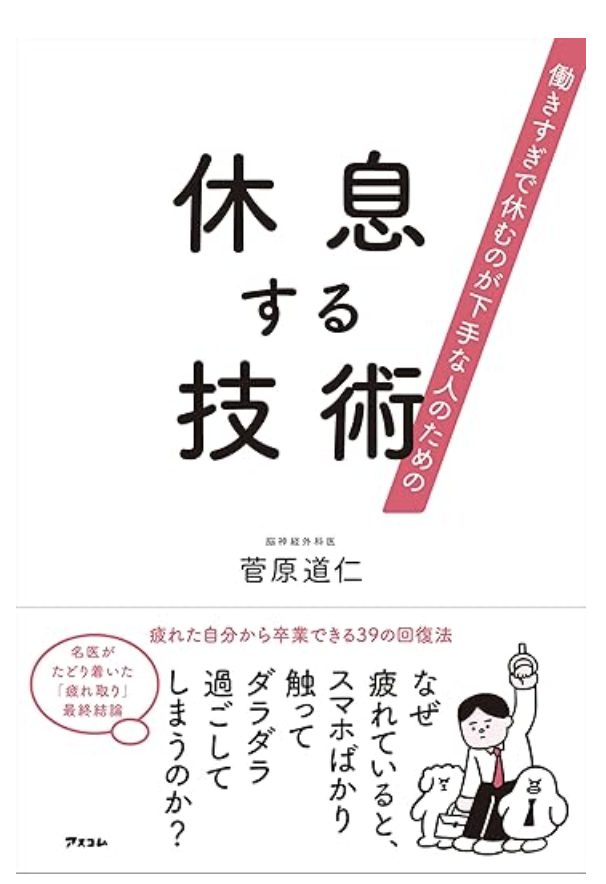
働きすぎで休むのが下手な人のための 休息する技術(菅原道仁)の要約
現代人の疲れは、自律神経体・心・体の3つの疲労が複雑に絡み合うことで生じる「取れない疲れ」です。特に自律神経の乱れによる脳の疲労は深刻で、従来の休み方では回復が難しくなっています。本書では、瞑想や呼吸法、リフレーミングなどを通じて自分を意識的に休ませる技術を紹介しています。
疲れとは、体だけでなく脳も疲れているという事実
体や脳を使いすぎたことによって「疲れた」と感じることーそれが疲れの正体なのです。(菅原道仁)
現代社会では、仕事に追われ、いつも何かに追いつこうとしている感覚に苛まれている人が少なくありません。常にタスクに追われ、時間に追われ、成果を求められ続ける。頭も体も休まる間がなく、ようやくひと息ついたときには、「いったい何にこんなに疲れているのか」すら見失ってしまう。そんな状態が慢性化しているのが、今の私たちの働き方の現実ではないでしょうか?
これは他人事ではなく、私自身の実感でもあります。社外取締役や複数企業のアドバイザーとして、日々複雑な意思決定や調整業務に向き合うなかで、明らかに「脳の疲労」を感じる場面が増えています。
肉体的にはそれほど動いていないはずなのに、終日会議が続いた日や、複数の課題を並行して処理した日には、心身ともに重たい疲労感がのしかかる。その疲れは、眠れば解消するような単純なものではなく、次の日にも残る「頭の疲れ」として蓄積していくような感覚です。
「しっかり寝ているのに疲れが取れない」「休日なのに気が休まらない」「何もしないと逆に不安になる」──このような感覚に覚えがあるなら、それはあなたのせいではありません。疲れの原因が「脳」にあるとしたら、従来の休み方では対応できないのです。
その解決策を紹介しているのが、働きすぎで休むのが下手な人のための 休息する技術です。著者の菅原道仁氏は、現役の脳神経外科医であり、杏林大学医学部卒業後、東京女子医科大学病院で研修を積み、脳卒中センター長などを歴任。25年以上にわたり脳と疲労の関係に向き合い続け、これまでに50万人以上の患者と向き合ってきた臨床経験の持ち主です。
本書では、「体の休息」だけでなく、「脳の休息」がいかに重要かを繰り返し説いています。疲れを感じるのは単なる気分や感覚ではなく、明確な生理的サインであり、それを正しく理解しないままでは、休息しても疲労は抜けないのです。
ポイントになるのが「DMN(デフォルト・モード・ネットワーク)」という脳の働きです。これは、何もしていないとき、いわゆる“ぼーっとしている”ときに活性化する脳内ネットワークのことで、記憶の整理や創造性の発揮、自分自身の振り返りといった作業に関与しています。
DMNが適度に働くことで、脳の疲労は回復へと向かいます。つまり、脳疲労がたまりにくい状態、疲れにくい状態を保つには、「意識してぼーっとする」ことが効果的なのです。 しかし、ここにも落とし穴があります。DMNは適度に働かせるからこそ意味があります。
考えごとが止まらず、頭の中で思考がループし続ければ、DMNが過剰に稼働してしまい、逆に脳はさらに疲れてしまうのです。ぼーっとする時間は重要ですが、何事にも限度があります。メリハリをつけながら脳を正しく使い、自然に回復するサイクルを整えていくことこそが、疲れにくい脳への第一歩です。
現代人の疲れとは3つの疲れの複合体
自分の疲れを理解して自分に合った回復法でリセットすれば、みるみる疲れが抜けて体がすうっと軽くなる。
疲労には、大きく分けて3つの種類があります。体の疲れ、心の疲れ、そして自律神経の乱れからくる疲れです。これらはそれぞれ独立しているようで、実は密接につながっており、複雑に絡み合うことで「なかなか取れない現代特有の疲れ」を生み出しています。
どれか1つだけをケアすれば済むというわけではなく、3つの疲れが連動することで、私たちの集中力や判断力、意欲といったパフォーマンスをじわじわと低下させていくのです。
なかでも厄介なのは、自律神経の疲労です。交感神経と副交感神経のバランスが崩れると、脳はまるでオーバーヒートしたかのような状態に陥ります。通常であれば、活動と回復の切り替えがスムーズに行われることで、脳は緊張と緩和をバランスよく繰り返しながら安定を保ちます。
しかし、いったんその切り替え機能がうまく働かなくなると、自律神経は暴走状態に入り、脳の疲労は加速度的に増していくのです。菅原氏は、これこそが「見えにくい疲れの本質」であると指摘しています。
日常生活の中で、私たちは気づかないうちに自律神経に負荷をかけ続けています。例えば、スマートフォンから絶え間なく流れてくる情報、マルチタスクをこなす日々、そして会話のなかでも常に即時の反応を求められるような緊張感。これらすべてが交感神経を過剰に刺激しています。
反対に、副交感神経が優位になる「回復の時間」は意識的に確保されていないのが現状です。たとえ休憩しているつもりでも、SNSを見ながら別のことを考え、頭の中では別のタスクを処理しているような状態では、脳は決して休まっていません。
こうした背景のもとで注目されているのが、「アクティブレスト」という考え方です。これまでのように、疲れたら何もせず静かに過ごす「パッシブレスト」だけでは、十分に回復できないケースも増えています。むしろ、軽く体を動かすことで回復を促す「アクティブレスト」によって、副交感神経を穏やかに刺激し、心身のバランスを整えていくアプローチが効果的なのです。
無理にがんばる必要はありません。あくまで心地よい範囲で、気分よく体を動かすことがポイントです。 自律神経の働きを整えることで、結果的に脳の疲労を防ぐ好循環が生まれます。
印象的なのは、休息を「偶然に起こるもの」ではなく、「意識的に設計するもの」として捉える視点です。つまり、休息を生活の中にあらかじめ組み込んでおくことが必要なのです。いつ、どのように、どれくらい脳を休ませるか。その設計力こそが、これからの働き方の質を左右する鍵になります。
人間の脳は、やりたいことがあるときには不思議と疲れを感じにくくなります。好きなことに没頭している時間、私たちは自然に脳のギアを切り替え、活性と回復を絶妙に使い分けています。これもまた、アクティブレストのひとつのかたちと言えるでしょう。
本書では、自律神経の疲労をリセットするために、1分間の瞑想法や1:2の呼吸法、骨盤矯正などが紹介されています。さらに、心の疲れに対処するための10分間の休憩やリフレーミング、「忘れる力」を鍛えるためのテクニック、そして身体の疲れを和らげる運動や栄養の摂取といった、多角的なアプローチが39個提案されています。
実際に私自身も、骨盤矯正や呼吸法、瞑想を取り入れることで、以前よりも疲労感が軽減されるのを感じており、著者のアドバイスには大いに共感できました。
著者が「休むのが上手だな」と感じる人々には、「休息=ダラダラ過ごす」という発想はあまり見られないと言います。彼らは忙しい日々のなかでも、週末にはスポーツ観戦や映画鑑賞、趣味や人との交流を楽しみながら、自然と脳を切り替え、結果的に回復しているのです。
つまり、休息とは止まることではなく、切り替えることなのです。疲労を放置せず、意識的に回復の時間を設けることで、私たちは次のステージへと進む力を取り戻すことができます。
働きすぎが常態化する時代だからこそ、休み方にも技術と創造性が求められます。休息の時間割をつくり、それを習慣化することで、疲れにくい自分へとアップデートすることが可能になるのです。
※本書はアスコム様からご恵贈いただきました。




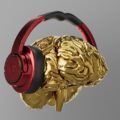
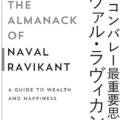


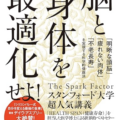


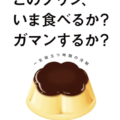



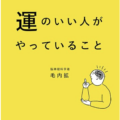


コメント