新しい階級社会 最新データが明かす<格差拡大の果て>
橋本健二
講談社
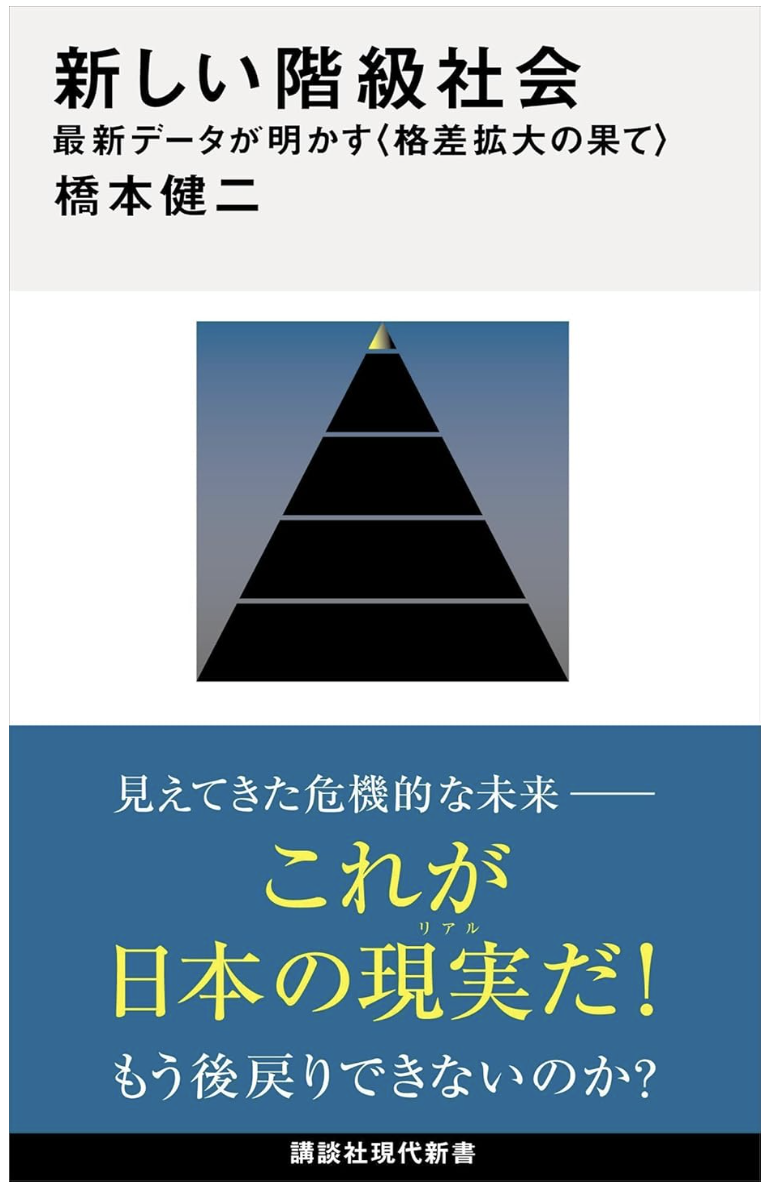
新しい階級社会 最新データが明かす<格差拡大の果て> (橋本健二)の要約
かつての「一億総中流」は過去の幻想となり、現代日本は教育・雇用・家族形成まで格差が固定化された階級社会へと変貌しています。橋本健二氏は、最新データをもとにアンダークラスの拡大や階級間・階級内格差の深刻化を描き出し、構造的な問題の本質を明らかにします。単なる再分配では解決できず、資本主義の在り方そのものを問い直す必要があるとし、再生産可能な社会への変革を提言しています。
新しい階級社会とは何か?
格差拡大とは、何よりもまず、階級間の格差が拡大することである。したがってどの階級に所属するかが、いままで以上に人生に重大な結果をもたらすようになった。さらに格差拡大は、階級内部の格差をも拡大した。 (橋本健二)
かつて「一億総中流」と称された日本社会は、すでにその幻想を過去のものとしています。現在、私たちが直面しているのは、所得や雇用の安定性にとどまらず、教育、医療、家族形成といった生活のあらゆる側面にまで格差が及ぶ、固定化された階級社会の現実です。
この「新しい階級社会」は、1980年前後から加速した構造的な変化の果てに形成されたものであり、「中流」の概念はすでに時代遅れの神話となったのです。
新しい階級社会 最新データが明かす<格差拡大の果て>のなかで、社会学者の橋本健二氏は、2022年の三大都市圏調査など最新のデータに基づき、現代日本における格差の実態を具体的に描き出しています。 本書が提示するのは、階級という構造が私たちの日常に深く入り込み、その所属によって人生の選択肢や可能性が大きく制限されているという厳しい現実です。
とりわけ注目すべきは、新たな階級として登場した「アンダークラス」の存在です。非正規雇用を中心とした約890万人が該当し、就業人口の13.9%を占めています。平均年収は216万円にとどまり、貧困率は37.2%と深刻です。働きながらも生活の再生産が困難であり、将来どころか現在を生き抜くことさえ難しい状況に置かれています。
橋本氏は、日本社会を五つの階級――資本家階級、新中間階級、正規労働者階級、アンダークラス、旧中間階級――に分類しています。経済的な位置づけでは、資本家階級が頂点に立ち、アンダークラスが最下層に位置します。その中間には、収入や資産、雇用形態の違いに応じて他の階級が存在しています。
これらの階級は単に所得や職業で区別されるだけではなく、結婚や家族形成のしやすさ、仕事への満足感、人生に対する主観的な豊かさといった面でも大きく異なります。
たとえば、資本家階級や旧中間階級は自由度も満足感も高く、自身を「豊か」と認識している一方、アンダークラスに属する人々は、家族を築くことすら難しいと感じており、自らを社会の最下層に位置する存在と認識しています。
本来、賃金は生活を支え、将来の労働力を再生産するためのコストを含むべきですが、アンダークラスに支払われている賃金はその基本的前提を満たしていません。企業は必要なときに安価な労働力を調達することだけを重視し、次世代の育成には責任を負わないという構造が定着しています。
資本主義が短期的利益に偏重し、長期的な持続性を軽視している現れでもあります。 このような構造のなかで、アンダークラスの労働は再生産という視点を欠いたまま使い捨てのように扱われています。
結果として、雇用や所得の安定性は奪われ、労働そのものの価値が問い直される状況にあります。 格差の拡大は、階級間の差異だけでなく、各階級内部においても進行しています。とくに労働者階級では、雇用の安定した正規労働者と、非正規の最下層労働者とのあいだに大きな断絶が生まれています。
また、格差は男女間にも広がり、多くの女性がアンダークラスに転落を強いられるという現象も見逃せません。 格差社会がもたらすのは、経済的な不平等にとどまりません。教育機会の不均衡、健康格差、医療アクセスの格差など、「命の格差」と呼ぶべき深刻な問題が発生しています。
若年層の貧困は未婚化や少子化を招き、社会保障費の増加を通じて国家財政にも影響を及ぼします。加えて、消費性向の高い中下層の所得が減少すれば、経済全体の需要が縮小し、景気は低迷します。 格差の拡大は社会全体に病理をもたらします。連帯感や相互信頼は損なわれ、ストレスの増加、社会参加の減少、健康水準の低下、いじめや犯罪の増加といった現象が連鎖的に広がっていきます。多くの研究が示すように、格差の大きな社会は「病んだ社会」と化すのです。
なぜ格差は拡大するのか?
資本家階級は明確に、新中間階級もある程度まで、自分は豊かだと認識しているのに対して、アンダークラスは自分が社会のなかの下層に位置していること、貧困層であることを認識している。
資本主義経済が発展するなかで、経営者のマインドセットは大きく変化してきました。かつては企業の持続可能性や従業員の生活安定を重視していた日本の経営陣も、現在では株主価値や短期的利益の最大化を最優先とする傾向が強まり、報酬体系においてもその変化が顕著に表れています。これにより、経営者と労働者のあいだの所得格差は急速に広がりを見せています。
近年では、経営者が労働者の数十倍から百数十倍もの報酬を受け取るケースが増えています。また、新中間階級の中にも、企業の利潤分配を受けて高額の報酬を得る層が出現しており、格差の構造はより複雑になっています。つまり、新中間階級の一部が、労働者階級を搾取する側に立ち始めたのです。
資本家階級は、これまで以上に労働者階級からの搾取を強めています。新中間階級の中にも、その構造に組み込まれ、搾取に加担する層が増加しています。そうなると当然、労働者階級の取り分は相対的に減少せざるを得ません。
この構図の中で、アンダークラスは重要な役割を担わされているのです。 視点を変えれば、アンダークラスが存在することによって、正規労働者階級の賃金水準が一定程度維持されているとも言えます。つまり、労働市場における過剰供給を背景に、正規雇用者の待遇が下支えされる一方で、アンダークラスはその犠牲となっているのです。
このように見た場合、正規労働者階級とアンダークラスとのあいだに利害の対立が生じている構造が浮かび上がります。 他者への信頼感があれば、人は関係性を築くことができます。関係が築かれれば、そこに新たな信頼が生まれる可能性も高まります。
しかしアンダークラス、とくに失業者や無業者には、そのようなつながりを形成するための回路が欠けていることが多いのが実情です。その結果、孤立が信頼を損ない、信頼の欠如がさらなる孤立を招くという悪循環が生じています。
アンダークラスは、20代から40代にかけて心理的な不安定さを抱える傾向があります。特に30代に差しかかる時期には、その不安定さが顕著となります。20代のうちは、まだいくらかの希望を持てたとしても、年齢を重ねることで「もう若くはない」という感覚が生まれ、焦燥感が高まるのです。非正規雇用に就いている場合、50代に至れば多少の安定を得られることもありますが、失業者や無業者は依然として不安定な状態に置かれ続けます。
このように現代社会は、階級構造という目に見えにくい「舞台装置」のもとで成立しており、多くの人々の人生がその構造によって規定されています。著者は、この舞台装置が協調よりも対立を、平和よりも争いを、幸福よりも不幸を生み出しやすい構造であると指摘しています。そして、それはもはや喜劇ではなく、悲劇と呼ぶにふさわしいものとなっているのです。
しかし、私たちはこの舞台装置にただ従属するだけの存在ではありません。その本質を見極め、必要であれば変革を試みる力を持つ、能動的な主体でもあるのです。もしこの構造が私たちに過酷な現実を突きつけているのであれば、それを問い直し、新たな仕組みへと作り変えていく努力こそが求められているのではないでしょうか。
資本家階級、そして一部の新中間階級は、アンダークラスを使い捨てることによって自らの利益を確保し、さらには他の階級の子どもたちまでもアンダークラスへと引き入れていきます。
しかも、現代社会においては出生率が各階層で低下しており、人口は急速に減少しつつあります。このままの構造が維持され続ければ、社会の持続可能性は失われていくことになるでしょう。 こうした問題を放置すれば、社会の閉塞感は深まり、未来への希望すらも失われかねません。
「あなたはどのくらい幸せだと思いますか」という設問への回答は、所属する階級によって大きく異なります。2022年三大都市圏調査によると、資本家階級では20.7%が「非常に幸せ」と答え、「やや幸せ」を含めると85.3%の人々が自分を幸せだと考えています。新中間階級では80.2%、正規労働者階級では74.2%、旧中間階級では74.8%と、大きな違いはないものの、大多数が一定の幸福感を持っていることがわかります。
ところが、アンダークラスでは「非常に幸せ」と答えた人はわずか8.0%。「やや幸せ」との合計でも59.0%にとどまり、逆に言えば約4割が自分を不幸だと感じています。失業者や無業者ではさらに深刻で、幸せだと感じる人は42.8%。「まったく幸せではない」とする人が22.0%、「あまり幸せではない」とする人が35.1%に達しています。 将来の生活に対する不安も、階級によって顕著な差があります。
また、「とても不安を感じる」と答えた割合はアンダークラスで42.8%、失業者・無業者では45.1%にのぼります。「やや不安を感じる」を含めると、それぞれ84.1%、78.6%と、圧倒的多数が将来への強い不安を抱えていることが明らかです。資本家階級でも7.0%、正規労働者階級でも26.0%が「とても不安」と答えていますが、不安の深刻度は明らかに異なります。 このように現代日本社会の底辺には、不幸と不安を抱えながら日々を過ごす人々が沈んでいます。
固定化する階級?私たちにできることとは?
1980年代から始まった格差拡大は階級構造を一変させ、日本社会を新しい階級社会へと変貌させた。そしてその背景には、フレクシ=グローバル資本主義への移行という、大きな構造的変化があった。だから問題の解決のためには、所得再分配という、いわば事後的な対症療法にとどまるのではなく、フレクシ=グローバル資本主義そのものを制御して、格差の構造そのものを変 えるような対策が必要になる。
現代日本の社会構造を読み解くうえで、見過ごすことのできない重大な課題が「格差の固定化」です。これは単なる一時的な社会問題ではなく、次の世代にまで影響を及ぼす深刻な連鎖構造を内包しています。教育の質や進学の可能性、家庭の経済力、資産の有無といったファクターが、子どもたちの将来を決定づける状況が常態化しつつあるのです。
つまり、どの階級に生まれるかが、そのまま人生の軌道を決めてしまうという、ある種の「見えない階級制度」が進行しているのです。 この傾向は、一部の識者だけでなく、多くの市民が「いまの日本では格差が広がりすぎている」と肌感覚で感じ取っており、その認識が社会的合意として徐々に形成されつつあります。
従来は、貧困や格差を「本人の努力不足」や「自己責任」で片づける見方も根強くありましたが、現在ではそうした考えは明らかに少数派に追いやられていると著者は指摘します。リベラル層はもちろんのこと、伝統的な保守層においても、再分配や格差是正の必要性を認める声が高まり、対策の必要性についての共通基盤が見え始めているのは注目に値します。 しかしながら、再分配政策を導入するだけでは根本的な解決には至りません。
1980年代から進行してきた格差の拡大は、単なる一過性の経済変動ではなく、日本社会の階級構造そのものを変容させてきました。その背景には、グローバル化した資本主義の論理があり、利潤を最優先にする企業活動が非正規雇用を拡大させ、下層労働者の数を増やしてきた現実があります。格差の構造を本気で変えていくには、こうした経済システムの根幹にまで目を向ける必要があります。
たとえば、「格差是正のためには自由競争の制限が必要だ」と考える人の割合は必ずしも高くはなく、全体では4割強にとどまっていますが、リベラル層では6割以上が賛同し、伝統保守層でも半数を超える共感が得られています。
つまり、経済の自由と社会的公正のバランスを問い直す機運が、すでに広がり始めているのです。これは単に制度を変えるだけでなく、価値観そのものを再定義していく契機にもなり得ます。
また、忘れてはならないのが、これまで社会にとって不可欠な役割を果たしてきたにもかかわらず、低賃金に据え置かれてきたアンダークラスの労働の存在です。医療・介護、物流、サービス業など、人々の日常を支える仕事に対して、きちんと報酬と評価を与える社会への転換が求められています。さらに、新型コロナウイルスの影響やグローバル競争によって打撃を受けた旧中間階級にも、再生のための手当てが必要です。
かつて「不要不急」とされた産業の多くは、実際には生活の豊かさや個人の選択肢を支える、かけがえのない存在です。 もし旧中間階級が市場原理の中で淘汰されていけば、その働き方に共感し、同様の生活を目指してきた新中間階級や労働者階級の希望も断たれることになります。自由競争という名のもとに多様性が削られ、富裕層だけが恩恵を受ける社会になれば、そのひずみはやがて社会全体に広がるでしょう。だからこそ、旧中間階級の価値を見直し、その存在を社会的に支える必要があるのです。
さらに言えば、日本の政治構造もまた、格差問題への対処を難しくしてきました。長らく続いた「保守対革新」のイデオロギー対立が、本来は一致可能な政策課題までも不毛な対立へと持ち込んでしまった感は否めません。特に与党の一部には、リベラル側からの提言を「反対勢力の主張」と一括りにし、真剣な議論の機会を逸してきました。
しかし、格差と貧困の問題はもはや党派を超えて、社会全体で向き合うべき「人間の幸福」に直結するテーマです。 仮に、リベラルと伝統保守という二大勢力が現実的な合意形成に成功し、教育制度や税制改革、雇用政策といった分野で対話を行い、協働できれば、日本社会は再び希望のある未来を描けるかもしれません。
格差の連鎖を断ち切ることで、すべての人が再生産可能な所得を得られるようになれば、少子化にも歯止めがかかり、経済の安定や社会保障制度の持続可能性も担保されるはずです。
そして最後に重要なのは、階級の固定化がすでに現実のものとなっているという認識です。1985年以降、とくに資本家階級と労働者階級では、明確な固定化の傾向が見られます。一方、旧中間階級ではある程度の流動性が維持されているものの、全体的には階級間移動の機会が減少しています。
かつて存在していた「努力によって上の階級へと進める道筋」は、高度経済成長の終焉とともに閉ざされてしまいました。 いま、社会全体が硬直化の只中にあります。この現実に背を向けるのではなく、構造的な変革へと舵を切ることが、日本の未来にとって不可欠な選択となるという思いが私の中でも強くなりました。
著者は、こうした実態を明らかにすると同時に、再分配政策や教育制度の抜本的改革が今こそ必要であると強調しています。本書は、統計と社会理論を融合させ、格差とその固定化がもたらす課題を体系的に読み解きながら、読者に思考のきっかけと行動のヒントを与えてくれる、知的刺激に満ちた一冊です。格差をこれ以上固定させないためには、本書の主張に耳を傾け、早急に議論をスタートすべきです。




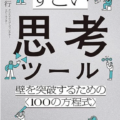
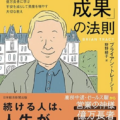





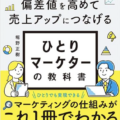


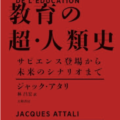

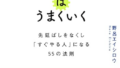

コメント