すべてやめれば、うまくいく 自分の時間を取り戻すための最高の習慣
マツダミヒロ
Gakken
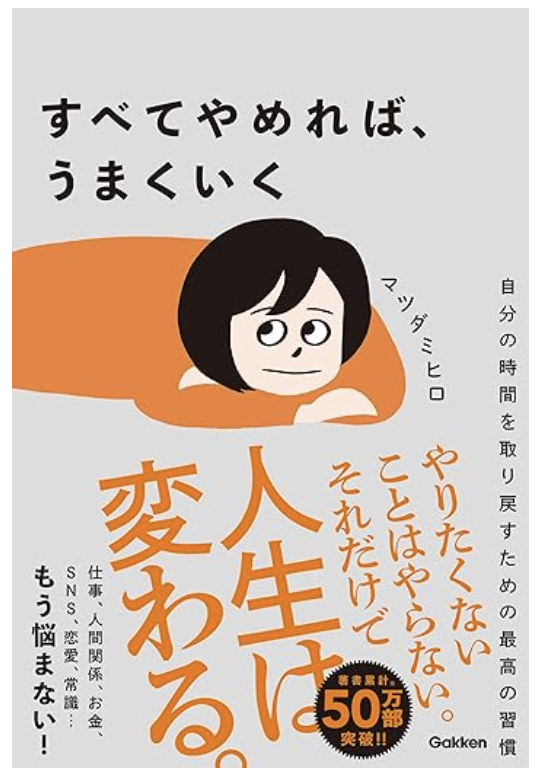
すべてやめれば、うまくいく 自分の時間を取り戻すための最高の習慣(マツダミヒロ)の要約
「続けること」が美徳とされる社会では「やめる」は否定的に見られがちですが、マツダミヒロ氏の『すべてやめれば、うまくいく』は、その価値観を問い直します。本当に必要なこと以外をやめることで、自分の時間とエネルギーに余白が生まれ、自己肯定感や創造性が高まります。人生は有限だからこそ、「やめる」は前向きな選択なのです。
やめることはネガティブではない!
「やめる」ことをネガティブに捉えていると感じています。でも、「それは違うよ」と声を大にして言いたい。 生産性を上げ、無駄なことをやめ、人生に余白を作り、自分らしく生きるために「やめる」ことは必要なことなんだと。(マツダミヒロ)
「続けること」が美徳とされる日本において、「やめる」という選択は、とかくネガティブに捉えられがちです。学校教育や企業文化の中で、継続や我慢が正義のように語られてきた背景があるからでしょう。しかし、本当にそれが人生を豊かにする唯一の道なのでしょうか?
私はこれまで、多くの経営者やコンサルタントのライフスタイルや働き方に触れる中で、「何かをやめたことによって得られた自由や創造性」が、人生を大きく好転させるきっかけになっていることを何度も目の当たりにしてきました。
そんな思考を深めてくれるのが、問答家・余白家のマツダミヒロ氏のすべてやめれば、うまくいく 自分の時間を取り戻すための最高の習慣です。本書は、現代人が無自覚に抱え込んでいる「忙しさ」の正体に切り込み、「やめること」の持つポジティブな可能性を明快に示してくれます。
印象的なのは、著者が日本人の生産性が低いことを明らかにしている件です。
誰かのために自分を犠牲にして頑張ることが、社会的にも美徳とされる風潮があるため、多くの人が「やめたくてもやめられない」という状況に陥ってしまっているのではないでしょうか。ぼくは、日本人の性格や社会的風潮が、結果的に生産性が下がる要因につながっているのではないかと考えています。 一方でぼくは、 やめるということには、人生を変えるものすごい力が秘められていると思っています。
「仕事は最後までやり遂げるべきだ」「一度始めたことは続けるべきだ」——こうした価値観が根強く残る中で、多くの人が惰性で時間を費やしています。しかし、その仕事が本当に社会に貢献しているのか、自分にとって意味があるのかを立ち止まって考えることは、今の時代において非常に重要です。
日々の忙しさに身を任せるのではなく、本当に大切なことと、実はやめても支障のないことを見極める視点を持つことで、時間にも心にも余裕が生まれます。
限りある集中力を不要なタスクに分散させるのではなく、本質的に価値のある活動に向けることで、より自分らしく、納得感のある人生を築くことが可能になります。
また、「会社員でいるべきだ」という思い込みが、フリーランスとしての働き方や起業といった選択肢を初めから排除してしまうケースも少なくありません。
このように、「〜べき」という固定観念に縛られていると、自分の人生に本来あるはずの選択肢や可能性にすら気づけなくなってしまうのです。 だからこそ、一度立ち止まり、現在の行動や環境が本当に自分にフィットしているのかを見直すことが必要です。思考の自由が、行動の自由を生み出し、人生の質そのものを変えていきます。
本書の中で、マツダ氏は「シャンパンタワーの法則」という印象的な考え方を紹介しています。この法則は、シャンパンタワーの構造を人生に見立てたもので、上から順に1段目を「自分」、2段目を「家族」、3段目を「友人・知人」、そして4段目を「社会」と定義しています。
ここで重要なのは、どのグラスも上から順番にしか満たされないという点です。つまり、1番上の「自分」というグラスを満たさなければ、次の段階にある家族も、友人・社会も、満たすことはできないということです。これは、自己犠牲を美徳とする日本的価値観とは逆のアプローチですが、非常に本質的です。
私たちはつい、他人の期待に応えようとしたり、家族や組織のために自分を後回しにしがちです。しかし、自分の内面が枯れていれば、他者に与えられるものも枯渇していくのは当然のこと。だからこそ、まずは自分を優先的に満たすことが大切です。自分の感情や欲求に素直になり、自分の選択に責任を持ち、そして誇りを持つ。それが結果として、周囲にも良い影響を与えることにつながります。 私自身も、自分の気持ちを無視して外側ばかり整えようとしていた時期がありました。
しかし、自分を満たすことを最優先にするようになってから、不思議と他人の評価が気にならなくなりました。むしろ、心に余裕が生まれたことで、周囲にもより良いエネルギーを循環できるようになった実感があります。
この「シャンパンタワーの法則」は、自己肯定感を育てるための有効な視点です。自分を信じ、自分を満たし、自分の人生に価値を感じること。それは、わがままでも利己的でもなく、自分と他人を同時に大切にするための合理的なスタンスなのです。
何かを始めるには、まず何かをやめる!
何かを始めるには、まず何かをやめる!
本書では、「何かを始めるには、まず何かをやめる!」という視点の重要性が繰り返し語られています。私たちは毎日、無意識のうちに数多くの行動パターンや思考のクセを反復しています。それ自体が悪いわけではありませんが、その多くはすでに役割を終えたものや、もはや意味を持たないルーティンであることも少なくありません。
だからこそ、「これは本当に必要なのか?」と自分自身に問い直すことが欠かせないのです。新しいことを始めたいと願うなら、まず現在抱えているものを手放す必要があります。物理的な時間は有限であり、何かを加えたければ、何かを削るという意思決定が求められます。そうした棚卸しのプロセスを経て初めて、人生に余白と自由が生まれてくるのです。
私自身、過去に数多くの「やめる」決断をしてきました。たとえば、リアルでの会議を減らして、オンラインでの仕事に軸足を移しました。その結果、空いた時間をより価値のある活動に再配分することができました。また、移動の自由と家族との時間を増やしながら、自分の強みを活かせる仕事に注力できたことで、結果的に生産性も満足度も向上しています。
やめるという行為は、一見ネガティブに映るかもしれませんが、実際には再構築のための前提条件です。現状に対する問い直しがなければ、変化も成長も起こりません。そして、マツダ氏はこうも述べています。 「疑わなければ、あなたの人生には何の変化も起きません。疑わない人生の先に待っているのは、良くて現状維持か、現状からの悪化しかないと思っています。」 この言葉には深く共感します。
私が2007年に独立を決意したのも、まさに「疑い」から始まりました。iPhoneが登場し、SNSがアメリカで急速に広がりつつあったその時期、私は広告業界の将来に対して強い違和感を覚えました。既存のモデルのままでは、この先の時代に適応できないと直感し、会社を離れて著者としての道を歩み出したのです。
その後、社外取締役や大学教授といった新しい役割を得られたのも、あのとき未来を疑い、手放す決断をしたからこそだと思います。変化の入口に立つためには、現状を疑い、不要なものを勇気を持ってやめることが重要です。 何かを始めたいと感じたときこそ、自分の中にある「やめるべきこと」と真剣に向き合うタイミングなのかもしれません。
何かをやめたあとには、必ず新しいアイデアやチャンスなど、楽しくワクワクするようなことが舞い込んできました。やめたことで空白が生まれるから、そこに何かが吸い寄せられてきたのです。
本書の根底には、「やめることは終わりではなく、新しい可能性への入り口である」という一貫した思想です。完璧を目指すあまり、かえって身動きが取れなくなる人も少なくありません。しかし、「ほどほど」で良しとする勇気を持つことで、心には余裕が生まれ、自分らしい選択が可能になります。 その余白は、思考のスペースであり、再構築のための土壌です。何かをやめるからこそ、新しいことにチャレンジできるのです。
私はその空白の中で自分との対話を深め、やりたいことの優先順位を明確にすることができました。そして、その想いを言語化し、発信することで、偶然のような出会いや機会がいくつも舞い込んできたのです。
社外取締役や大学教授といったポジションを得られたのも、余白を持ち、それを他者と共有し、応援してもらえたからです。ここで重要なのが、「弱い紐帯」の力です。マーク・グラノヴェッターが提唱したこの社会学的概念は、緩やかなつながりが意外性のあるチャンスをもたらすことを示しています。強い結びつきだけでは見えない世界が、そこにはあります。
人生は有限。だから「やめる」
当たり前ですが、私たちの人生には限りがあります。時間もエネルギーも無尽蔵ではありません。だからこそ、「やめる」という行為には深い意味があります。
マツダ氏は、「やめること」に対する罪悪感を手放し、それを生き方の戦略として捉える視点を私たちに提示してくれます。 現代社会では、忙しさがステータスのように扱われ、何かをやめることは「逃げ」や「根気がない」と見なされがちです。
しかし実際には、やめることは自己放棄ではなく、自分を肯定し、自分にとって意味のあることに集中するための前向きな意思決定です。
本書の中で紹介されている「魔法の質問術」や「マンダラチャート」を活用した思考の整理法は、そうした“やめる力”を高める実践的な手法です。特に「まずは小さなことからやめてみる」というアドバイスは、やめることに慣れていない人にとって大きなヒントになります。
すべてを一度に変える必要はありません。たとえば、惰性で見ていたSNSのフォローを整理する、毎朝なんとなくチェックしていた情報源を見直す——そのような小さな「やめる」の積み重ねが、やがて思考と行動に明確な軸を与えてくれます。
やめることは、人生の選択肢を狭める行為ではなく、本当に大切なことに集中するための余白づくりです。むしろ、やめなければ新しいものは入ってこない。何かを始めたければ、まず何かをやめる。そのシンプルな原則に立ち返ることが、現代をしなやかに生き抜くための重要な戦略となるのです。
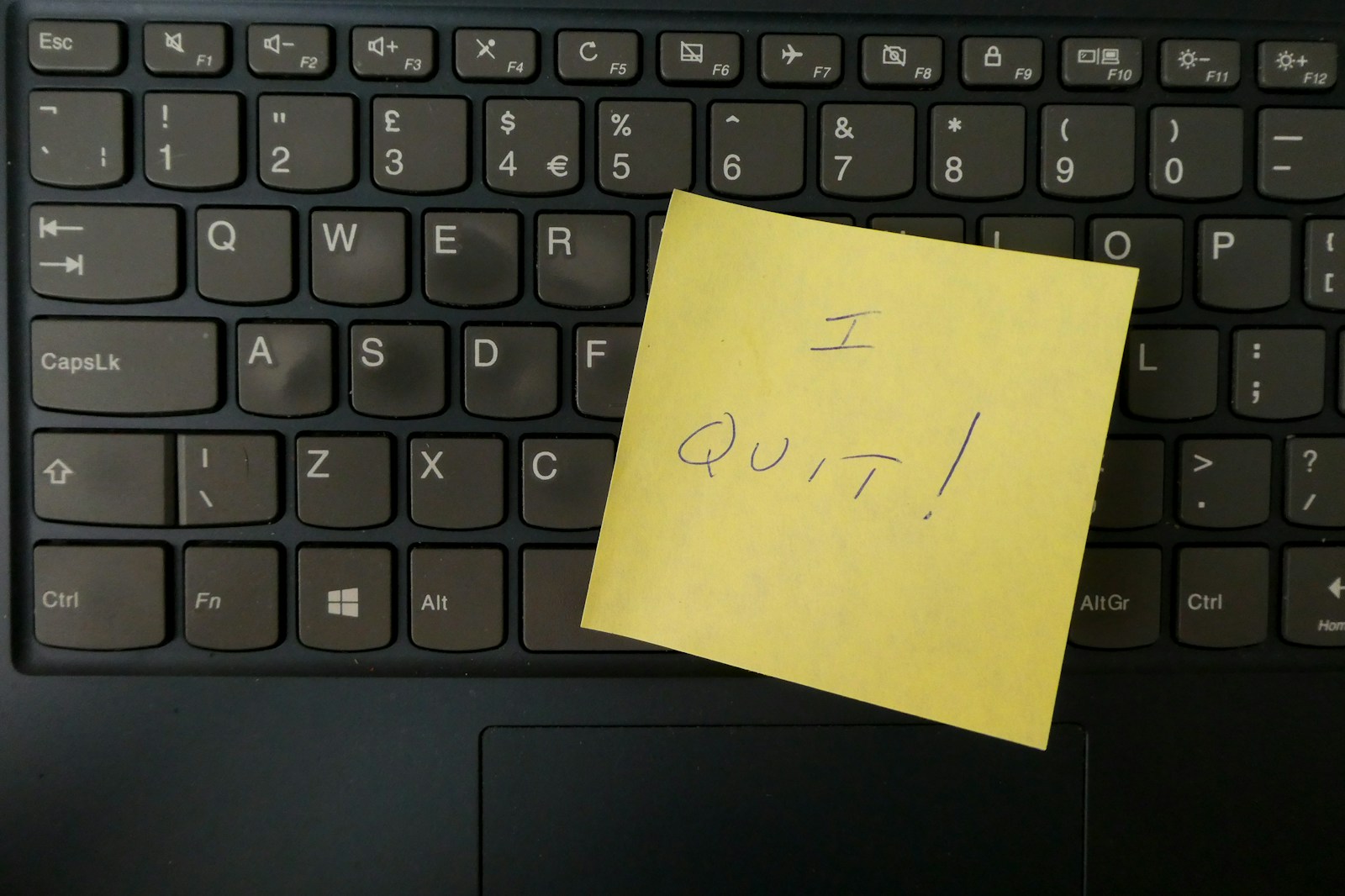








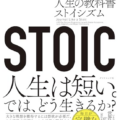

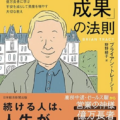


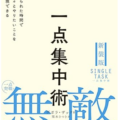


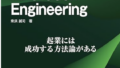
コメント