会話の0.2秒を言語学する
水野太貴
新潮社
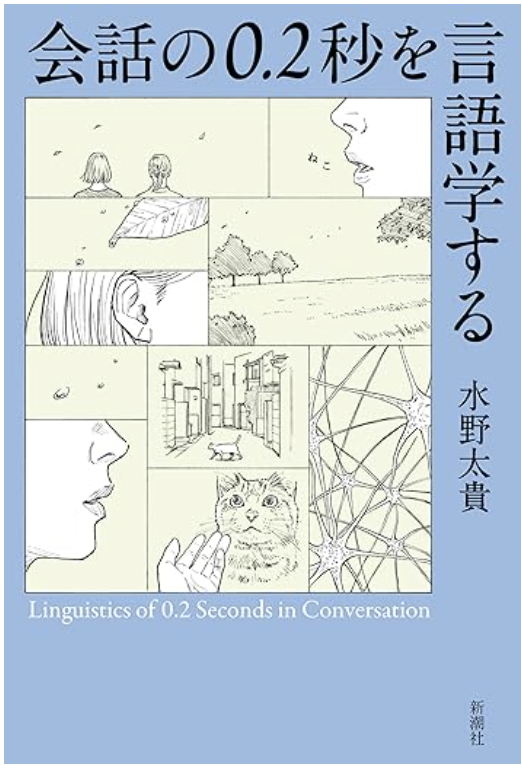
会話の0.2秒を言語学する (水野太貴)の要約
言葉が通じないのは、単なる性格や相性の問題ではありません。言語には、伝達の不確かさがあらかじめ織り込まれているのです。0.2秒のやりとりに複雑な推論が走り、わずかな“間”やフィラー、沈黙すら意味を持ちます。言語学は、こうした曖昧さを解き明かし、通じにくさの構造を可視化します。だからこそ、私たちは言語を通じて他者だけでなく、自分自身とも出会い直すことができるのです。
会話における0.2秒の勝負とは?
あなたも毎日のように、1秒以下のわずかな時間で競争を繰り広げている。それが、会話だ。会話では、一人の話者が話し、それが終わると別の人が話し始める。話者が交替するまでの発話を「ターン」といい、話者の交替を「ターンテイキング」というが、イギリスの言語学者であるスティーヴン・C・レヴィンソンらの研究によると、ターンテイキングには平均して200ミリ秒──つまり0.2秒しかかからないという。(水野太貴)
相手との対話が思うようにかみ合わない――こうしたコミュニケーション上の齟齬は、私たちの日常において最も頻繁に起こるにもかかわらず、その正体は意外なほど理解されていません。意図がうまく伝わらない。沈黙が場の空気を微妙に変えてしまう。こうした違和感を、単なる性格の相性や気まずさの問題として片付けてしまうのは早計です。
そこには、言語学が取り組むべき本質的な課題――「0.2秒の謎」が潜んでいます。私たちが相手の発話を聞き取り、その意味を把握し、文脈を読み取りながら自らの応答を準備し、実際に言葉として発するまでに要する時間は、平均してわずか200ミリ秒。意味の理解、状況判断、感情のコントロールといった複雑な処理が、このわずかな時間に集中的に行われているのです。
言い換えれば、コミュニケーションとは、誰もが日常的に無意識のうちにこなしている極めて高度な認知的プロセスです。そしてその構造があまりに繊細であるがゆえに、ほんの一瞬の遅れや、解釈のズレが、即座に関係性のひずみとして表出します。相手の反応がなぜか引っかかる、あるいはこちらの言葉が誤解されてしまう――そうした“わずかなズレ”の蓄積こそが、コミュニケーションのペインを生み出しているのです。
水野太貴氏の会話の0.2秒を言語学するは、誰もが日常的に直面するこの“無理ゲー”のようなコミュニケーションの難しさを、言語学の最前線から鮮やかに解き明かしていく一冊です。
著者の水野氏は、名古屋大学文学部で言語学を専攻。卒業後は出版社で雑誌編集者としてキャリアを積み、現在はポッドキャスト番組「ゆる言語学ラジオ」のパーソナリティとしても広く知られています。高度な理論をわかりやすく伝える手腕と、軽やかな語り口が多くのリスナー・読者の支持を集めています。
私もPodcastでときどき拝聴していますが、その博識ぶりには毎回驚かされます。難解になりがちな話も、日常の具体例と絡めながら軽やかに語られていて、知的でありながらも肩の力を抜いて聴けるところに、大きな魅力を感じています。
実際に言語学の視点から捉え直してみると、私たちが日常的に交わしている会話の風景は、これまでとはまったく異なる構造を帯びて立ち上がってきます。たとえば、日銀総裁による一見あいまいな発言が、なぜか市場に過剰な反応を引き起こす過程。あるいは、サッチャー元首相と記者のあいだに生じた、質問と応答のわずかなタイミングのズレ。
そして、「えーと」や「うーん」といったフィラーが埋める沈黙の質――いずれも、日常的で取るに足らないと思われがちなやりとりの中に潜む、言語的なメカニズムの一端です。
水野氏は、こうした現象を一つひとつ丁寧に掘り下げながら、「言葉はなぜ伝わるのか、あるいはなぜ伝わらないのか」という根本的な問いに対して、言語学の理論と具体的な実例を交差させながら謎解きを進めていきます。まるで日常の会話に仕掛けられた精巧なパズルを解くように、一見当たり前に見えるやりとりの裏側に潜む構造や意図を、少しずつ可視化していくのです。
そうして浮かび上がるのは、私たちが当たり前のように成立していると思い込んでいるコミュニケーションが、実はきわめて精緻で不安定なプロセスの上に成り立っているという事実です。わずかなタイミング、言い回し、沈黙。そのいずれが欠けても、意味の伝達は容易に揺らいでしまうことが明らかになっていきます。
本書の真骨頂は、単なるエピソードの羅列にとどまらず、言語学や哲学の理論を土台に据えている点にあります。ジョン・オースティンは「発話とは、事実を伝えるというよりも、それを通じて聞き手や世界に何らかの影響を与える行為である」と指摘しています。
つまり、私たちが何かを口にするとき、その言葉は常に相手への働きかけとして機能しており、たとえそれが一見情報の提示に見えるものであっても、そこには発話者の意図や行動が潜んでいるのです。
さらにポール・グライスは、会話の背後にある「協調の原理」を提唱し、人々が意味をやり取りする際には「量・質・関連性・様態」という4つの公理に従っていることを示しました。発話の裏にある「何を、どこまで、どのように伝えるか」という判断が、相手との理解の土台になっているという視点です。
たとえば、日銀総裁によるわかりづらい一言が市場を揺るがすプロセスを見てみましょう。植田総裁はある会見で、「チャレンジングな状況が続いているが、年末から来年にかけて一段とチャレンジングになる」と語りました。一見すると当たり障りのないコメントに見えますが、この直後、マーケットは大きく反応し、円相場が3円も円高に振れるという異常事態が起こります。何が問題だったのでしょうか。
ここで注目すべきは、「量の公理」です。これは「必要とされるだけの情報を提供せよ、過不足のある情報は避けよ」という原則です。植田総裁の発言には、まさに必要以上の情報が含まれていたのです。具体的には、「年末から来年にかけて」という時期をわざわざ明言したことで、聞き手――この場合は市場関係者――はそれを「金融政策の転換時期」として過剰に読み取ってしまったのです。
当時、日銀はマイナス金利政策を継続中であり、「いつ解除されるのか」はマーケットの最重要関心事でした。そのため、たとえ発言自体が金融政策に直接言及していなかったとしても、「年末から来年」という時間軸の提示だけで、市場は「この時期に政策転換があるのではないか」と読み込み、反応してしまったわけです。結果として、市場との間に大きな“意味のずれ”が生まれたのです。
私たちは、伝えきれなさを前提に会話している
話し手の言語化も聞き手の解釈も、不安定な土台のもとで行なわれているのだ。しかも僕たちは、こうした高速の翻訳作業を200ミリ秒の間で行なっている。
言語学というレンズを通して会話を見直してみると、普段交わしている言葉のやりとりが、まったく別の風景として立ち上がってきます。そこには、文法や語彙といった学校で習う要素以上に、タイミング、意図、そして沈黙までもが意味を帯びて配置されていることがわかります。
人は言葉を交わす際、単に情報を伝えているのではなく、複数の層にまたがる推論を、200ミリ秒というごく短い時間のうちに走らせています。
関連性理論は、この認知的プロセスの解明に寄与してきました。 ダン・スペルベルとデイドラ・ウィルソンによれば、人は発話を受け取ると、それが自分にとってどれほど意味があるかを瞬時に評価し、最大の関連性が得られると判断した時点で解釈を終了します。理解とは、情報のすべてを受け入れることではなく、むしろ“推論をどこで打ち切るか”の判断にほかなりません。
ノーム・チョムスキーの生成文法は、文が単なる単語の羅列ではなく、いわゆる樹形図に基づいた階層的な構造をもっていることを示しました。この構文的な土台を前提に、形式意味論は単語の意味を集合として捉え、そこから文全体の意味を導き出そうとします。ただし、単語の意味は常に明確とは限らず、文脈によって解釈が揺れ動くため、意味の理解には常に不確かさがつきまといます。
「チョムスキーがすごかったのは、自然な文を生み出せて、なおかつ文法的におかしな文を除外できるようなルールを考えようとしたところだった」と著者は彼の功績を評価します。
言語は、構造、意味、解釈という三層が複雑に絡み合いながら動いている知的なシステムです。そこには明快なロジックがありながらも、絶えず揺らぎと曖昧さが共存しています。会話とは、この不安定さの上に構築された営みであり、だからこそ一つひとつの言葉の選び方や並び方が、驚くほど大きな影響を及ぼしているのです。 この精密な処理を、人は無意識のうちに、ごく自然なかたちでやってのけています。
ただし、意味を理解するためには、そもそも「文がどう構成されているか」を認識している必要があります。 言葉でのコミュニケーションは、不確かさを抱えながら、それでも機能しているのです。この不安定さを前提とした考え方が、認知意味論の出発点です。
ジョージ・レイコフとマーク・ジョンソンが打ち立てたこの理論は、「言葉は比喩でできている」と喝破します。 言語とは、世界そのものではなく、私たちの捉え方を映し出す認知の枠組みにすぎません。そしてその枠組みは、文化や身体感覚によって形成される可変的なものです。
こうして文の構造、単語の意味、そして文脈の推論を見ていくと、日常の会話がいかに多層的で複雑なプロセスであるかが明らかになります。 それでもなお、私たちは200ミリ秒のなかでこれを処理し、相手と通じ合おうとしています。たとえ、通じていないときでさえ。実際、人は応答のタイミングからも、相手の心理を読み取っています。
フェリシア・ロバーツとアレクサンダー・フランシスの研究によれば、頼みごとに対する返答の速度が、相手の気持ちの強さに直結していることが示されています。「いいですよ」という言葉が依頼の直後、たとえば200ミリ秒以内に返ってくれば快諾と受け取られますが、それが2秒遅れるだけで、途端に乗り気でないという印象を与えてしまいます。 人はこの間に敏感であり、600ミリ秒を境に印象は大きく変わります。
こうした繊細なタイミングの調整は、発話のターンを維持する際にも求められます。沈黙が1秒以上続くと、人は相手の感情を読み取りはじめるのです。
言葉を補うフィラーとジェスチャー
フィラーは相手にメッセージを伝えることはあるが、相手のために言っているのでなく、自分のために言いよどんでいるのだ。そして、自分のために用いているのだが、結果的に相手に情報を伝えてしまっているツールはまだある。それが、ジェスチャーだ。
「えーと」や「あのー」などのフィラーは単なる言いよどみではなく、発言権を保持したり、考えを整理したりするための重要なツールです。「えーと」は内容を探っている段階で出やすく、「あのー」はそれをどう伝えるかを考えているときに出る傾向があります。つまり、言葉になりきれなかった思考の輪郭が、フィラーというかたちで相手に伝わっているのです。
ジェスチャーもまた、言葉と並ぶ重要なコミュニケーション手段です。心理言語学者の喜多壮太郎は、言語には「からだ的思考」と「分析的思考」という二系統があると指摘します。ジェスチャーやオノマトペのような身体感覚に近い表現は前者、抽象的で論理的な言語は後者。それぞれが相互に補い合いながら、言葉を組み立てているのです。
沈黙、フィラー、視線、手ぶり。こうした言葉にならない要素のすべてが、コミュニケーションに組み込まれています。にもかかわらず、私たちは言語というものを驚くほど言語化できていない。だからこそ、言語学に触れると、自分がどれだけ言葉について知らないかを痛感させられるのです。
その気づきは、対話そのものへの向き合い方を少しずつ変えていきます。言葉が通じないことに苛立つのではなく、「通じにくさ」が構造的なものであると知ることで、コミュニケーションに対する視点が更新されていく。そうした静かな変化こそが、言語学が私たちの日常にもたらす最大の効用なのかもしれません。
言語学の本を読むと、自分が言語化できている知識がいかにわずかで、そして自分の言語化スキルがいかに乏しいかを痛感することができる。言語学とは、言語化に対する過剰な信頼を相対化できる学問なのである。
言語学に触れることで、私たちは、自分自身が当たり前だと思い込んでいた世界を、少し距離を置いて見つめ直すことができるようになると著者は指摘します。 つまり、自分を一度、他者として捉え直す経験が得られるということです。そして、この視点の切り替えこそが、人文学の大きな魅力であり、自然科学とは異なるもう一つの知のかたちを形づくっています。
私自身、日々書評ブログを更新するなかで、他者の視点や考え方に触れ、自分の認識が揺さぶられる瞬間を何度も経験してきました。書くこと、読むこと。その繰り返しの中で、自分の思考や感覚が少しずつ変化していく。その実感が、人文学における「学び」の輪郭を、静かに、しかし確かに浮かび上がらせてくれているのです。









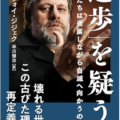


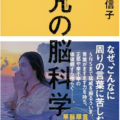
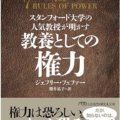
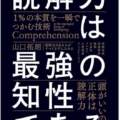
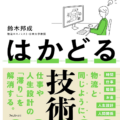


コメント