この国でそれでも生きていく人たちへ
森永卓郎、森永康平
講談社
この国でそれでも生きていく人たちへ (森永卓郎、森永康平) の要約
日本経済の先行きが不透明さを増す中で、私たち一人ひとりに求められているのは、現状を冷静に見つめ、主体的に判断し行動する力です。地政学リスクの高まりや物価上昇、賃金の伸び悩みといった複合的な要因が、将来に対する不安をいっそう強めています。こうした中で本当に必要なのは、問題の本質を見極める思考力と、変化に対応できる柔軟さ、そして自らの言葉で声を上げ続ける姿勢です。
リスクだらけの日本という国家
実際、現在の世界経済が想定していないリスクは確実に存在しており、もしリスクが顕在化したら、父の言うように大暴落が発生しかねない、と考えている。(森永康平)
トランプ大統領による強硬な関税政策が、日米の株価の急落を引き遅しています。この数年の大幅な為替の変動や物価高に苦しむ日本社会においても、多くの人々が将来への不安を抱え、生活のリスクはかつてないほど高まっています。こうした不安定な時代において、私たちはどのように生き抜くべきなのでしょうか。
本書この国でそれでも生きていく人たちへは、そんな時代の劇的な変化の中、今年惜しまれつつ逝去した経済アナリスト・森永卓郎氏が、息子の康平氏と共に現代の日本人に向けて遺した数々の大切なメッセージがあります。 親子による対談形式を通じて、2人の異なる視点から「生き抜く知恵」を整理・提案した本書は、将来に不安を感じている人々に、大きな勇気を与えてくれる内容となっています。
これまで何度か森永卓郎氏の書籍を取り上げてきましたが、今回はその息子である経済アナリストの森永康平氏にフォーカスしてご紹介していきます。森永卓郎氏の関連記事
日本には、表面化していないさまざまなリスク要因が存在しています。中でも注目すべきは、地政学リスクによる株価暴落の可能性です。康平氏は、特に「台湾有事」が現実味を帯びており、今後の日本経済に深刻な影響を与える恐れがあると警鐘を鳴らしています。
もし中国が武力行使によって台湾統一に踏み切った場合、日本も無関係ではいられません。日本の国土が攻撃対象となるリスクに加え、経済活動にも多大な影響が及びます。台湾周辺は日本の主要な海上貿易ルート(シーレーン)上に位置しており、戦闘が発生すれば物流がストップし、輸出入が混乱する可能性があります。これは結果として、日本の株式市場にも大きな打撃を与える要因となり得ます。
実際、2024年10月には中国軍による台湾包囲の大規模演習が行われ、その規模や準備の周到さから、中国政府の強い意図が明らかになりました。こうした動きは、日本の安全保障環境にも直接的な影響を及ぼすものです。米軍基地や自衛隊施設が攻撃対象となる可能性があり、ミサイル攻撃や空爆のリスクも現実的な懸念となっています。
加えて、国内には約82万人の中国人が在留しており、中国の「国防動員法」や「国家情報法」に基づいて、有事の際には母国政府からの協力要請を受ける可能性もあります。これは、国内の社会不安や企業リスクを高める要因となり、大企業や研究機関における安全保障上の対策強化が求められています。
また、サイバー攻撃のリスクも見過ごせません。2022年には、ペロシ米下院議長の台湾訪問時に、台湾のデジタルサイネージがハッキングされました。将来的に日本も標的となる恐れがあり、インフラや重要システムへのサイバー防衛体制の強化が急務です。
康平氏は、「台湾有事」だけでなく、朝鮮半島とのダブル有事が発生する可能性についても警戒を促しています。こうした複合的なリスクに対し、日本社会全体での危機意識と備えの強化が急務だと言えます。
日本経済を良くするために必要なこととは?
経済アナリストとして日々マクロ経済のデータを見るようになって、つくづく思ったことがある。それは、「政治家で日本のことを真面目に考えている人間はほとんどいないのではないか」ということだ。日本経済が良くなる政策を体を張って通そうという政治家はほとんどいない。
康平氏は、日々マクロ経済のデータと向き合うなかで、日本が置かれている現実に強い危機感を抱いています。今年になり、トランプ前大統領の強硬な関税政策が再び注目を集め、世界的な供給網の混乱や株価の急落など、経済不安はより深刻化しています。
物価高に悩む日本では、生活コストの上昇に多くの人々が喘いでおり、いまや誰もが、未来に不透明感を感じざるを得ない状況です。 こうした経済的・社会的リスクが高まる中で、政治が果たすべき役割は本来、極めて大きいはずです。しかし、康平氏は次のように指摘します。
「いまの日本に、本気でこの国の未来を考えて行動している政治家がどれほどいるだろうか」。実際には、長期的なビジョンよりも、利権や選挙の論理に支配された政治が繰り返されており、本質的な政策転換は進んでいません。
このような政治の劣化を招いている一因として、康平氏は「国民側の無関心」にも着目しています。戦後、日本は長いあいだ戦争や大規模な内乱と無縁の社会を維持してきました。誰が総理になっても生活に大きな影響はない──そんな「ぬるま湯の平和」が続いたことで、選挙や政策選択への当事者意識は徐々に薄れていったのです。
その結果、「誰が政治を担っても同じ」という諦念が広がり、結果的に現状維持を望むような政治家ばかりが選ばれる構造が生まれました。
一方で、政治家の側もまた、国民の信頼に応えようとする姿勢を徐々に失っていきました。利権、選挙、党内力学といった「自分たちの論理」が優先されるなか、政治と国民の距離はますます開いていったのです。
こうした政治構造の裏で、見逃してはならないのが、財務省をはじめとするエリート官僚の存在です。森永卓郎氏は、その象徴として長年にわたる増税政策を厳しく批判しています。とくに消費税率の引き上げは、国民の生活を直接的に圧迫し、個人消費を冷え込ませ、経済回復の足かせとなってきました。
財務省は「財政再建」を理由に挙げていますが、実際には自らの省益を守るために、政治家やメディアを巧みに巻き込みながら、国民に“痛み”を押し付けてきた側面があるとされています。
康平氏もこの点に強く言及し、「誰も責任を取らない構造」が政策の失敗を繰り返していると冷静に指摘しています。このような構造の中で、反対の声を上げる者は「非現実的」「空気が読めない」と切り捨てられることも少なくありません。現代日本では、合理的な批判ですら通らない風潮が一部に存在し、それこそが民主主義の根幹を揺るがすものではないでしょうか。
いま日本がやるべきなのは「格差縮小を目指す」政策ではない。むしろ「全員の所得を増やす」政策を優先すべきだ。
康平氏は、現代日本の政策論議においても重要な論点を提示しています。それは、「格差の是正」に注目するあまり、根本的な問題である「全体の所得の低さ」が見過ごされているのではないか、という問いです。
日本がいま本当にやるべきことは、単に格差を縮小することではありません。むしろ、すべての国民の所得を底上げすること――すなわち「成長と分配の両立」ではなく、「まず成長を取り戻す」政策が優先されるべきだと康平氏は主張します。
所得の分配をどうするか以前に、分配の原資となる“パイ”そのものが小さすぎるという現実を直視しなければ、格差の是正も絵に描いた餅にすぎません。 そのためには、消費を抑制する増税ではなく、投資や労働インセンティブを高めるような政策転換が求められます。家計にゆとりが生まれ、企業が安心して雇用や賃上げに踏み出せる経済環境を整えること。これは、一部の層ではなく「すべての人」に恩恵をもたらす道でもあります。
本書は、こうした問題意識を土台に、森永親子がそれぞれの立場から率直な対話を展開する一冊です。怒りと覚悟をにじませた父・卓郎氏。一方、康平氏はそれを受け止めつつ、異なる視点から冷静に日本経済を分析しています。
だから、国がダメ、政治がダメと人のせいにしていても仕方がない。 自分のためにやれることを どんどんやっていくほうが、成功に近づけるだろう。
森永親子2人が読者に訴えかけているのは、単なる政治批判ではありません。「声を上げ続けることの意味」「現状に疑問を持ち続けることの大切さ」「批判だけではなく、自分のために行動する重要性」です。
社会の構造に不満を持っていても、沈黙してしまえば現実は何も変わりません。小さな声でも、疑問や違和感を言葉にし、共有し、行動に移す。その積み重ねこそが、次の社会を動かす原動力になるはずです。 いまを生きる私たち一人ひとりに、「あなたはどう生きますか?」と問いかけてくるこの本は、不安な時代にこそ手に取るべき一冊です。
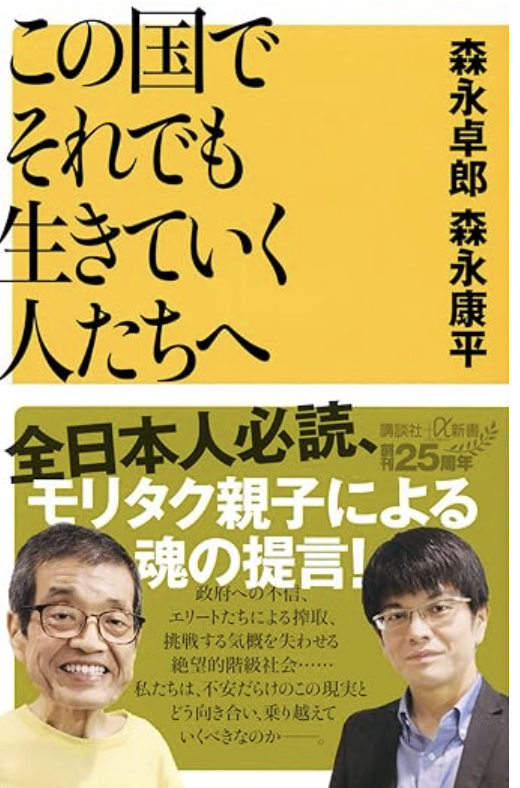





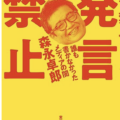

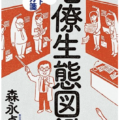



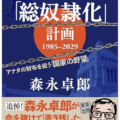
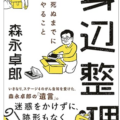
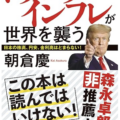
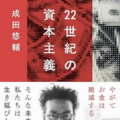

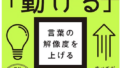

コメント