セカンド・チャンス シェイクスピアとフロイトに学ぶ「やり直しの人生」
スティーブン グリーンブラット, アダム フィリップス
岩波書店

セカンド・チャンス シェイクスピアとフロイトに学ぶ「やり直しの人生」 (スティーブン グリーンブラット, アダム フィリップス)の要約
『セカンド・チャンス』は、文学と精神分析の視点から「やり直し」の本質に迫る一冊です。シェイクスピアやフロイトの著作を通じて、再出発の可能性とその困難さが描かれます。セカンド・チャンスとは偶然に訪れるものではなく、自分自身の変化への準備が不可欠であると気づかせてくれます。
セカンドチャンスによって、人生を変えられる?
シェイクスピアは、セカンド・チャンスの最高の巨匠である。フロイトは、その最高の解釈者である。二人を一緒にすれば、フロイトに照らしながらシェイクスピアを読み、シェイクスピアに照らしながらフロイトを読むことができる。 (スティーブン グリーンブラット, アダム フィリップス)
私はの人生において重要な転換点になったのは、今から18年前の時の断酒体験でした。それまでの私は、毎日のように酒に手を出し、心身ともにどんどん疲弊していました。44歳の時に、体調を壊したことが分岐点となりました。
検査入院した病院のドクターから、「10年後は生きていないだろう」と告げられ、初めて「このままではだめだ、自分の人生を変えなければ」と真剣に考え始めました。 最初の半年間は、每日のように断酒の誓いを繰り返し、酒を遠ざけることを意識しました。
酒を飲む機会を防ぐために友人との交流も断ち、夜型の生活を朝型に切り替え、ライフスタイルを徹底的に見直しました。この過程で私が始めたのは、内なる自分との真摯な対話でした。
読書によるインプットと文章を書くことで、自分の気持ちを整理し、自分の人生のビジョンを明らかにして行ったのです。その後、著者や社外取締役や大学教授になれたのもあの時の選択があったからです。
今回、セカンド・チャンス シェイクスピアとフロイトに学ぶ「やり直しの人生」に出会い、当時のことが鮮明に思い出されました。その語りは、私の再生の物語を裏付けてくれたように感じられたのです。
『セカンド・チャンス』は、人生の「やり直し」というテーマを、文学と精神分析という一見かけ離れた分野から照射することで、現代人の深層心理に鋭く迫ります。スティーブン・グリーンブラットがシェイクスピア作品における回復と再構築の物語を丹念に読み解く一方で、アダム・フィリップスはフロイトやウィニコットといった精神分析の理論を引き合いに、「なぜ人は二度目の機会を求めるのか」を深掘りしています。
この作品が示すのは、セカンド・チャンスとは、単なるリセットではなく、記憶と欲望の文脈の中で再構築される「新たな選択肢」であるという点です。グリーンブラットによれば、シェイクスピアの喜劇には再生の希望が、悲劇にはその不在が描かれているとされます。
たとえば『冬物語』におけるリオンティーズの悔恨と再会は、過去の過ちがもたらす損失と、それを受け入れ再構成するプロセスを強く印象づけます。 対照的に、『ハムレット』では主人公が自らの誤解やためらいに絡め取られ、セカンド・チャンスを手にできないまま、物語は破局を迎えます。
このように、やり直しが叶うか否かは、物語構造だけでなく、人間の心理の深部を抉る主題として捉えられているのです。 フィリップスが提示するのは、「セカンド・チャンスがあると思えること」が、人間の精神的成長における鍵であるという視点です。彼によれば、自分が間違っているかもしれないという認識こそが、自己再編の出発点であり、そこに心理的な成熟が生まれると説きます。 この考え方は、私自身の断酒のプロセスと不思議なほど重なります。
悲劇のヒーロをやめ、セカンドチャンスを選択しよう!
まじめな人ほど自分はこれまでの人生で正しいことをやってきたと信じている人ほど自分を見直す必要があるとは認めようとしない。しかし、どんな人にも反省すべき点、改めるべき点があると気づけないと、決してセカンド・チャンスはやってこない。そして、セカンド・ チャンスという大きな変革は、自分が生み出して自分でつかむものではなく、環境や人間関係のチャンス中から偶然として生まれてくるものなので、その態勢を整えて待つしかないのです。
フロイトの「陰性治療反応」とは、まさにその心理的抵抗のメカニズムを表しています。人は無意識のうちに、自らの苦しみにしがみつく傾向がある。なぜなら、その苦しみこそが、自分を守ってくれていたシステムの一部だったからです。
『セカンド・チャンス』は、こうした心理の複雑さに鋭い光を当てながら、同時に文学的想像力を活用することで、その解像度を高めています。
プルーストの記憶論においては、「思い出すこと自体が回復である」とされるように、過去の体験をどのように語り直すかが、自己理解の鍵を握るのです。 つまり、セカンド・チャンスとは、単に過去の過ちをやり直す機会ではなく、「新たな意味」を付与する営みであり、それは「語る」ことによって可能になるのです。
私が日記を書くことで断酒を支えたのも、まさにこの「再物語化」による力を直感的に感じていたからかもしれません。 この書は、読者に対して問いかけます。「あなたのセカンド・チャンスは、どこにあるのか?」「その機会をつかむ準備はできているのか?」と。
この問いかけは実に重要です。なぜなら、行動を促す文章とは、読者が内なる声に耳を傾け、自ら選択するプロセスを支援するものでなければならないからです。
まじめな人ほど、自分はこれまでの人生で正しいことをやってきたと信じている傾向があり、だからこそ自分を見直す必要があるとはなかなか認めようとしません。しかし、どんな人にも反省すべき点や改めるべきところがあるという事実に気づけない限り、セカンド・チャンスは決して訪れません。
セカンド・チャンスという大きな変革は、自分が生み出して自分でつかむものではなく、むしろ環境や人間関係のなかで偶然として現れるものです。重要なのは、それを受け入れるだけの「態勢」を整えておくことです。変化を望む気持ちはあっても、現状に留まるほうが「安全」だという錯覚が、選択肢を狭めてしまうのです。
『セカンド・チャンス』は、過去の痛みと向き合いながらも、それをただの記憶にせず、再び価値ある経験として位置づけることの大切さを教えてくれます。読後に残るのは、後悔でも感傷でもなく、「これから何ができるか」という希望です。
断酒という一つの選択から始まった私の再生は、この書によって言語化され、意味づけされました。人生には常に“次”がある。その“次”を意識するだけで、目の前の風景は変わります。そして、選択の積み重ねこそが、自分自身を形作っていくのだと、本書は静かに教えてくれました。
『セカンド・チャンス』は、短い書評だけでは語りきれない奥行きを持った一冊です。シェイクスピアやフロイトが取り上げられることで、自己啓発的な内容にも関わらず、読後に多くの学びを得られます。 セカンド・チャンスという、まだ生きていない人生には、自分に秘められた可能性がこめられています。
セカンド・チャンスは、少なくともその展望において、ファースト・チャンスよりよいものでなければなりません。それは、人生に何かが起こる、いや、もっと豊かな人生に何かが起こるという機会です。 つまり、それは私たちが自分のために、そして関わりのあるほかの人たちのために、自分の欲しいものを明確にする機会でもあるのです。
セカンド・チャンスは、願望から始まるかもしれませんし、ユートピア的な空想から始まるかもしれません。けれども、すべては、どうやったらそれが実現するか、実現させることができるかにかかっています。 自分の過去を問い直し、未来を主体的に選び取る覚悟がある人にとって、この本は力強い伴走者となってくれます。




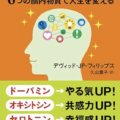

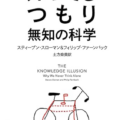








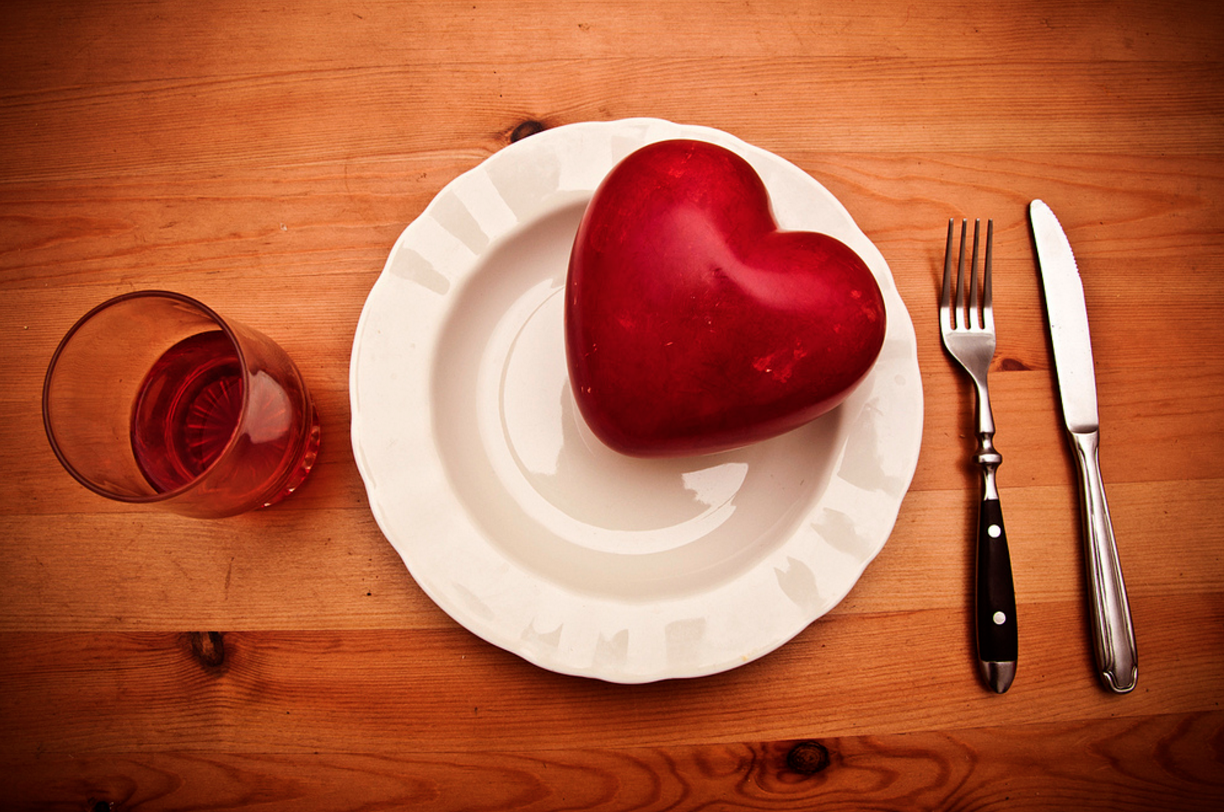


コメント