AIに書けない文章を書く
前田安正
筑摩書房
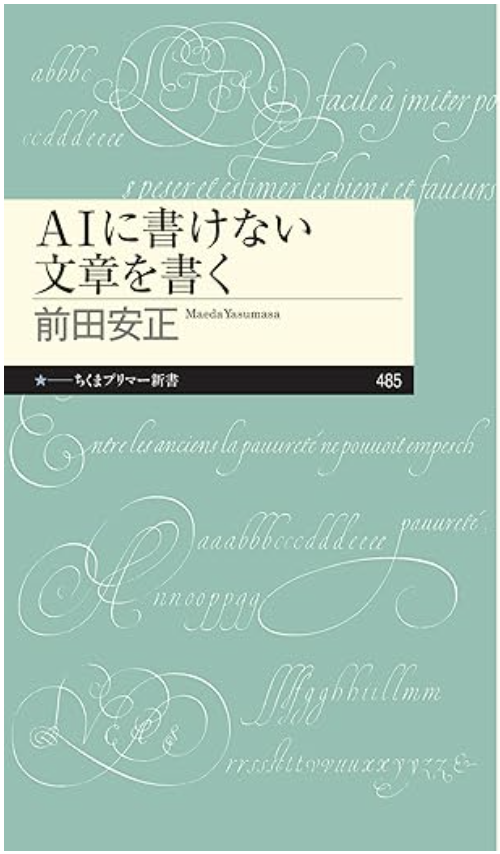
AIに書けない文章を書く (前田安正)の要約
生成AIが進化し、文章が同質化する危機にある中、前田安正氏は「文書」と「文章」の違いを明確にします。文章とは思考や感情がにじむ存在の証であり、Whyを織り込むことで物語となります。曖昧さを余白として活かし、骨・肉・脈を備えることで言葉に生命が宿ります。書くことは時を刻み、未来への手紙であり過去からの贈り物でもあるのです。
読み手が共感できる文章を書く
AIも「表現し尽くされた」ものを書いているわけではありません。なぜなら、僕たちが書いたものをベースにして、学習しているからです。完璧でないものを真似しても、完璧なものはできません。その意味で、AIは将来、人の思考・感情に近づくことはあってもそれを超えることはないと、僕は考えているのです。(前田安正)
生成AIはますます進化していきます。ものを書くという行為が人から奪われていくかもしれません。気づけば、SNSやブログの文章も、ビジネスレポートや学生のレポートまでもAIが代筆するのが当たり前になってしまいました。
私たちは効率と便利さに慣れすぎてしまい、「なぜ自分が書くのか」という根本的な問いを見失いかけています。文章が同質化し、誰が書いても変わらない情報の羅列に堕してしまえば、言葉はただの記録や伝達の道具に過ぎなくなります。
読み手の心を揺さぶる力を失い、思考や感情を残す「証」としての役割を失う──これは今、多くの人が気づかないうちに直面している深刻な課題なのです。
その不安に真正面から応えるのが、文章コンサルタントの前田安正氏のAIに書けない文章を書くです。本書は、生成AIが得意とする「文書」と、人間だけが生み出せる「文章」とを峻別し、両者の違いを鮮明に描き出します。AIは膨大なテキストを学習し、既存の情報を整理し、確定したデータを整える能力においては比類のない存在です。けれども、そのアウトプットは「文章」ではなく「文書」にとどまります。
大辞林の定義によれば、「文章」とは「書き手の思考や感情がほぼ表現し尽くされたもの」です。AIには思考も感情もありません。だからこそ、いかに進化しても、あなたの存在を言葉で表す「文章」を書くことはできないのです。人が自らの感情や体験を織り込みながら紡ぐ言葉こそが、本当の意味での「文章」であると、著者は繰り返し強調しています。 本書はその違いを出発点に、書くという行為の意味を再定義していきます。
大人になっても、手の届かない山の上に宝物があるはずなのに、それを経験や知識でわかったような気になってしまいます。それは、感性の摩滅につながり、無感動と無関心を醸成してしまいます。それでは言語能力も表現力も育ちません。曖昧であること、もやもやしていることを楽しんで、山の上に何があるのかを探し続けることが、文章を書く重要な役割だと考えます。
通常、曖昧さは「わかりにくい」「伝わりにくい」とネガティブに受け止められがちですが、著者はむしろその曖昧さを「読み手に解釈の自由を与える余地」として肯定的に評価します。言葉を最後まで規定してしまわないことで、読み手はその隙間に自分自身の体験や価値観を重ね合わせることができます。つまり、文章が「作者のもの」から「読み手自身のもの」へと変換される瞬間を生み出すのです。
日本語には「ぼんやりとした表現」や「言い切らない言い回し」が多く存在します。「かもしれない」「ような気がする」「どこか懐かしい」などの言葉は、厳密な意味を確定させることを避けつつも、読み手にさまざまな想像を促します。そこには断定の強さではなく、解釈を委ねる柔軟さが宿っています。
曖昧さは、情報としては不完全かもしれません。しかし表現としては完成度を高める力を持っています。それは、人間の感情や記憶が必ずしも明確な形をしていないからです。むしろ曖昧さこそが、人間の内面を映し出すリアルさを担保しているのです。
AIは曖昧さを嫌い、常に一つの答えへと収束させようとします。しかし人間の表現はその逆で、あえて曖昧さを残すことで深みや広がりを持つようになります。
大切なのは、曖昧さを欠点とみなすのではなく、むしろ読者の想像力や共感を引き出す力として活かすことです。それを意識的に織り込むことで、ただの情報伝達にとどまる「文書」は、心を動かす「文章」へと生まれ変わるのです。
文章を書くことで得られること
「状況」→「行動」→「変化」を綴ったものがストーリーなのです。人はいまの状況があって、それに対して行動し、変化が生まれます。その変化が新たな状況となって次の行動を生み、変化をつくります。人はこうしたスパイラルを経ながら進んでいきます。
人は「状況」に直面し、それに応じて「行動」を起こし、その結果として「変化」を得ます。そしてその変化は次の「状況」をつくり、再び新たな行動へとつながっていく──この繰り返しが人生の流れであり、同時にストーリーの基本構造でもあります。
この構造を整理するために役立つのが4W1Dです。When(いつ)、Who(誰が)、Where(どこで)、What(何を)、Do(どうした)をそろえれば、出来事の説明としては十分に成り立ちます。しかし、これだけでは読み手の心に届かず、ただの報告に終わってしまいます。
ここで欠かせないのが「Why(なぜ)」です。Whyが加わることで、行動や出来事の背後にある理由や動機が浮かび上がり、文章は事実の羅列から「物語」へと変貌します。
「なぜその行動を取ったのか」「なぜその出来事を語るのか」という問いを自分に投げかけながら書くことで、読み手は単なる情報以上のものを受け取ります。そこに込められた思いや意図に触れることで、共感や理解が生まれ、言葉は自分ごととして響き始めるのです。
つまり4W1Dは出来事を説明する骨格に過ぎませんが、4W1Dの要素それぞれにWhyを重ねることで、状況から行動、そして変化までをつなぐストーリーが描けます。Whyを織り込むことこそが、文章を「文書」から「文章」へと昇華させ、相手に伝わる力を宿すのです。
さらに著者は
・主語と述語の関係を明確にする。
・一つの要素で一つの文を書く。
・文章を短くする
ことを強調し、文章に不要な装飾や曖昧な表現を削ぎ落とすことを勧めます。
また、著者は文書の構造を「骨・肉・脈」として捉えています。まず「骨」は文章の中心となる骨格であり、伝えたい核心を支える柱です。そこに「肉」をまとわせることで、具体性や厚みが生まれ、言葉に生命が宿ります。そして「脈」が通うことで、文章全体に流れが生まれ、読む人の心に血が巡るように意味が伝わっていく。
この三層がそろって初めて、文章は単なる言葉の集まりではなく、生命力を持った表現となるのです。 この比喩は、文章術のテクニックを超えて、書くという行為そのものの本質を映し出しているように思えます。
骨を持たない文章は軸を失い、肉を欠けば痩せ細り、脈が通わなければ生命を感じさせない。逆に骨がしっかりとし、肉が豊かに付き、脈が通っている文章は、人の思考や感情を余すことなく伝えることができます。
文章には、自分という存在がにじみます。自分の存在は、過去から未来に流れる瞬間瞬間に積み重ねられた「時」によって形づくられます。人生観や思考はその「時」に大きく依っています。つまり、文章は自分自身の「時」を記すことでもあるのです。「時」を記すことは、自分自身の存在意義を明らかにする行為でもあります。それは、いつでも自分に立ち返ることができる「場」をつくることにもなりました。しんどい作業かもしれないけれど、自分自身への救いでもあります。
私自身も、書くことの素晴らしさを身をもって味わってきました。起業家や経営者の悩みを解決するヒントを求めて本を開き、著者との対話を繰り返し、その学びを言葉にまとめてブログに刻んできたのです。15年間書き続けるなかで、文章力は確実に磨かれ、課題を解決するスピードも格段に上がりました。
問いを立て、答えを探し、思考を深める。この営みを積み重ねたからこそ、自分自身の物語を紡ぐことができたのだと実感しています。思考や感情は人に紐づくストーリーであり、そこに行動や変化が描かれてこそ、初めて読み手の心に届くのです。
AIが生み出す文書は、状況の記録としては優れていても、その背後にある人間的な動機や感情の揺らぎを描き出すことはできません。だからこそ、文章を書くことは「時」を刻む行為であるといえるのです。人の存在は、過去から未来へと流れる一瞬一瞬の積み重ねによって形づくられます。
その「時」を言葉として残すことは、自分の存在意義を確かめる営みであり、いつでも立ち返ることのできる「場」を築くことにもつながります。
書くことは、ときに苦しい作業に思えるかもしれません。しかし、その苦しさこそが自分を支え、やがて救いへと変わっていきます。書き続ける中で、自分の成長を実感し、喜びや幸せを感じる瞬間がきっと訪れるのです。 なにより大切なのは、かつて書いた記事──過去の自分の言葉が、いまの自分を励まし、助けてくれる瞬間があるということです。文章は未来への手紙であると同時に、過去からの贈り物でもあります。
たとえAIがどれほど進化したとしても、この「時」と「存在」を刻み、自分自身と対話する力だけは、人間にしか宿りません。AIには旅をすることも、人とのつながりを築くこともできないのです。
私たちは、読書をはじめとした日々の体験のなかで「Why」を問い、自分の思考や感情を言葉にすることで、人との出会いや対話をデザインしてきました。
だからこそ、私は今日も本を開き、著者と向き合い、自分の思考と感情を言葉に刻み続けます。書くことは未来の自分への手紙であり、そして何より、自分が確かにここに存在した証なのです。





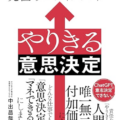



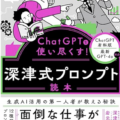

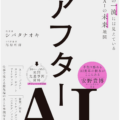
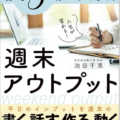


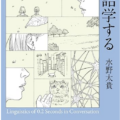

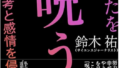
コメント