苦境(ピンチ)を好機(チャンス)にかえる法則
ライアン・ホリデイ
パンローリング株式会社
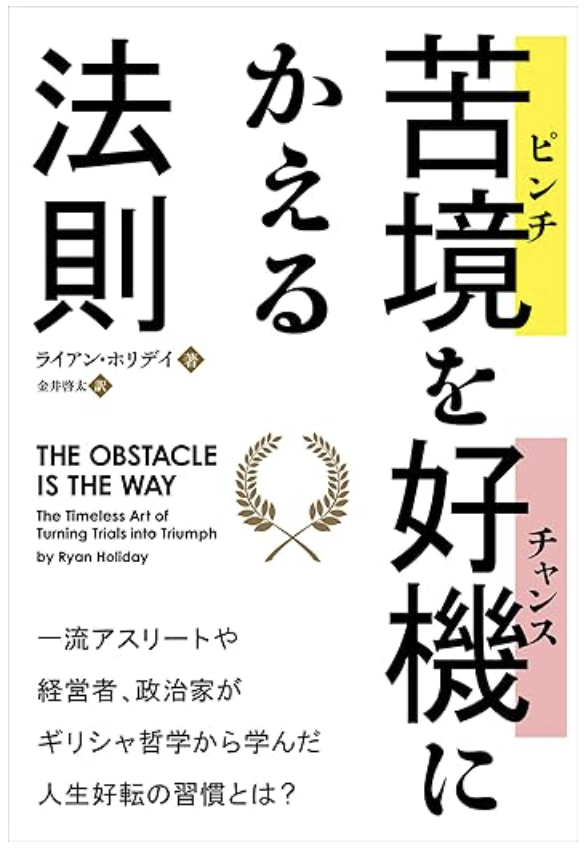
苦境(ピンチ)を好機(チャンス)にかえる法則 (ライアン・ホリデイ)の要約
ライアン・ホリデイは、ストア哲学を現代に応用し、困難を成長の糧へと変える方法を教えてくれます。彼は、障害は避けるものではなく、「道」として受け入れるべきだと説いています。物事をありのままに見つめ、自分にできることを淡々と実行し、耐えるべきことは耐え、受け入れるべきことは受け入れる。そのような姿勢によって、私たちは逆境に強くなり、より豊かで意味のある人生を歩むことができるのです。
ストア哲学を自分の課題解決に活用する!
どうにもならない状況に縛られていても、目的地へ行くための抜け道や迂回路は必ず存在する。旅の途中で、障害に道を阻まれることは覚悟しておかねばならないが、その状況がいつまでも続くわけではない。道を阻むものが、かえって力を与えてくれるのだということを頭に刻んでほしい。 (ライアン・ホリデイ)
多くの人は、どうにもならない現実に押しつぶされそうになる瞬間を経験します。努力しても報われず、理不尽なできごとが続き、心が折れそうになることもあるはずです。私自身も、困難に直面するたびに、本の力を借りて乗り越える術を学んできました。
そんなときにおすすめできる一冊が、ライアン・ホリデイの苦境(ピンチ)を好機(チャンス)にかえる法則(The Obstacle Is the Way)です。(ライアン・ホリデイの関連記事)
本書は、古代ローマの哲学者マルクス・アウレリウスの言葉――「行動への障害が行動を前進させる。道を遮るものが、道となる」――を基軸に、ストア哲学を日常の課題解決に活かす方法を説いています。
著者のライアン・ホリデイは、ストア哲学をわかりやすく現代に伝えることで知られており、古代の知恵を、私たちが困難を乗り越えるための実践的な考え方として紹介しています。
本書の中心には、「障害をどう捉え、どう乗り越えるか」という問いがあります。ストア哲学が教えているのは、出来事そのものを変えるのではなく、「それをどう受け止めるか」を変えるという姿勢です。
人は起きた出来事に対して、つい意味づけをしてしまいます。失敗すれば「自分はダメだ」と思い、誰かに裏切られれば「もう信じない」と決めつけつけます。
しかし、出来事そのものはただの事実であり、それにどう反応するかがすべてなのです。他人が「絶望的だ」と感じる状況でも、それを悲劇と見るか、チャンスと見るかは自分次第なのです。評価と結果は異なり、人生をどう物語として紡いでいくかは常に自分で決めることができます。
障害を乗り越えるには自分を鍛える必要があり、それは3つの重要な段階からなる。(1)個々の問題に対する見方や態度、向き合い方。(2)問題を克服してチャンスに変えるためのエネルギーとクリエイティビティ(創造性)。(3)敗北を認め、困難と向き合うために内なる意志を育て養うこと。
ホリデイは、「状況そのものが障害になることはない。投げ出したときに初めて、それが障害になるのだ」と語ります。 本書では、障害を乗り越えるための実践的なフレームワークとして、「ものの見方(Perception)」「行動(Action)」「意志(Will)」という3つの柱が提示されています。
まず、「ものの見方」とは、自分の感情に流されず、物事を冷静かつ客観的に捉える力を意味します。たとえ困難な状況であっても、そこに機会を見出す柔軟さがあれば、状況に振り回されることはありません。
著者は障害に直面した時のコツを教えてくれます。
●客観的になる
●感情を抑えて平静を保つ
●良い面に目を向けるようにする
●焦らない・慌てない
●他人のことは気にしない
●大局的に判断する
●今この瞬間に立ち戻る
●自分の力でコントロールできることに集中する
ものの見方が変われば、これまで当たり前だと思っていたことや、恐れていたことが、実はただの思い込みにすぎなかったと気づくことができます。「問題」だと思っていたものが、実は問題ではないとわかリマス。そして、ようやく本当に向き合うべき課題に集中できるのです。
次に、「行動」とは、粘り強く、目的をもって一歩を踏み出すことです。著者は、行動とは自ら逆境に打ち勝ち、乗り越えるための手段であると指摘しています。 大きな問題に直面したときは、それを小さなステップに分解し、恐れを抱えながらでも前へ進むことが大切です。そうすることで、やがてはその問題を解決できるようになります。
ギリシャ・アテネのデモステネスは、吃音を克服するためにさまざまな練習法を取り入れ、やがて偉大な演説家として名声を確立しました。彼のモットーは、「行動・行動・行動!」だったと言われています。
アメリア・イアハートが、危険を承知のうえで大西洋を女性で初めて単独飛行したように、困難な状況にあっても動き続けることで、人は自らを解放し、力を得ることができるのです。
また、南北戦争におけるビックスバーグの戦いで、グラント将軍は二つの重要なことを学びました。一つは、根気強さや粘り強さがかけがえのない財産であるということ。特にリーダーであるグラントにとって、それは最大の資質と言っても過言ではありません。
もう一つは、粘り強く挑み続けるなかで従来の手段が通用しなくなったとき、新しいやり方を試す必要に迫られるということです。これは、真剣に行動を続ける者が必ず直面する課題でもあります。
いったん障害との闘いを始めたなら、途中でやめるという選択肢はありません。諦めずに行動を重ねることで、私たちはやがて結果を出すことができるのです。
スタートアップの経営者は、MVP(Minimum Viable Product)を通じて顧客からフィードバックを得ます。MVPの考え方では、あらかじめ「失敗」と「フィードバック」を前提にしているため、失敗するたびに学び、より強くなっていくのです。 市場の反応を見ながら、消費者に響かない機能はどんどん削ぎ落とし、支持される機能の改善に、限られた資金とリソースを集中させていきます。
著者は、偉大な起業家に共通する特徴として、次のような点を挙げています。
・ひとつの立場に執着しない。
・投資資金を少し失うくらいは恐れない。
・悔しがったり、恥ずかしがったりしない。
・長い間、ゲームから離脱しない。
何度も滑って転ぶことはあっても、崖から落ちるような致命的な失敗はしない――それが彼らの強さなのです。
意志の力で逆境を克服しよう!
意志は、私たちの内なる力であり、外部の状況に左右されることがない。言ってみれば、最後の切り札だ。行動というものが、現状に対してまだ打つ手があるときにするものであるとしたら、意志とは、打つ手がほぼ尽きたときにすがるものである。どう考えても最悪で手の施しようがない状況に置かれたときは、それを何かを学び謙虚になるための経験に変えてしまえばいいし、他者のために働くチャンスだと考えてもいい。それが意志の力である。
最後に、「意志」とは、変えられない現実を受け入れる内なる強さのことです。 多くの人は、意志とは「どれだけ強く何かを求めるか」だと考えています。しかし実際には、意志とは力強さというより、むしろ降参に近いものです。
「勝つ意志」や「実現する意志」を持つことも大切ですが、ときには「運を天に任せる意志」を持ってみると良いと著者は言います。なぜなら、前者の意志は、ときに挫折や結果に左右されてしまうからです。
真の意志とは、穏やかな謙虚さと、打たれ強さ、そして柔軟さを兼ね備えたものです。それ以外の意志は、威勢やかけ声だけが目立つ、見せかけの強さに過ぎません。
では、本当に困難な障害にぶつかったとき、どちらの意志の方が長く持ちこたえることができるでしょうか。 これこそが、私たちが鍛えるべき最後の力――「意志」です。
「ものの見方」が頭の鍛錬であり、「行動」が体の鍛錬だとすれば、「意志」は心と魂の鍛錬です。意志は、私たちがどんなときでも完全にコントロールできる、唯一の力でもあります。
たしかに、有害な「ものの見方」を避けたり、エネルギーを100%「行動」に注ぐことは、努力次第で可能です。しかし、それでもどうしてもうまくいかないことはあります。
けれども、「意志」は違います。意志は自分の内側にあり、他人や環境に左右されません。意志とは胆力であり、知恵でもあります。それは、特定の障害に対処するだけでなく、人生そのものに向き合うための力です。私たちが直面するすべての障害は、意志の力で受け止めることができるのです。
意志は、私たちに究極の力を与えてくれます。つまり、とても乗り越えられそうにない障害を耐え抜き、それをより大きな文脈の中で捉え、意味を見出す力です。それこそが、「ひっくり返せないものをひっくり返す」ための、唯一の方法なのです。
自分の力で変えられるものと、変えられないものを見極める。 そして、どうにもできない不運に見舞われたときは、残されたたったひとつの選択――「受け入れること」を実行するのです。
シュートが外れた。 株価が大暴落した。 海が荒れて、船の航行が妨げられた。 そんなときは、著者が勧めるこの言葉を、私も口癖にしたいと思います。 「人生なんて、そんなものさ。大丈夫」
神よ、変えることのできないものについては、どうか穏やかに受け入れられますように 変えることのできるものについては、どうか変える勇気をもてますように そしてどうか、この2つを見分ける知恵をお与えください。(ニーバーの祈り)
アルコール依存症の回復プログラムでも引用される「ニーバーの祈り」にあるように、天気や境遇、他人の感情など、自分にはどうにもできないことで悩むのはやめましょう。
その代わりに、変えられることには勇気を持って立ち向かい、何が変えられて何が変えられないのか、その違いを見極める知恵を持つことが大切です。自分が変えられることに意識を集中すれば、やがて結果そのものを変えていくことも可能になります。
自分の力が及ぶことに専念すれば、そこに倍の力が生まれると著者は指摘します。反対に、自分ではどうしようもできないことにエネルギーを注いでも、それはすべて無駄になってしまうのです。それでは単なる自己満足に終わり、いずれは自分をすり減らすことになりかねません。
私たちは皆、気づかないうちにこうしたエネルギーの浪費を繰り返しています。だからこそ、目の前に立ちはだかる障害を試練として受け止め、「ならば最大限に活用しよう」と思えるかどうか――それもまた、自分自身の選択なのです。
これらの姿勢が、ストア哲学の本質でもあります。私たちは過去を変えることはできませんが、現在の行動を選ぶことはできます。出来事に執着するのではなく、「これから何をするか」に意識を向けることで、未来への小さな一歩が始まります。
「どんな困難に直面しても、道は2つある。障害に立ち止まるか、それを越えて進むか」――そんな著者の言葉に、前へ進む勇気と未来を変える力をもらえます。自分の感情に左右されず、自分への問いを変えることで、逆境をチャンスに変えられるようになります。
「結局のところ、どんな苦境にあっても死ぬことはまずないのだ」という著者の言葉を信じて、自分のものの見方、行動、意志を変えるようにしましょう。
偉人たちの行動から逆境の乗り越え方を学ぼう!
苦境に陥っても理性的に対処することはできるのだ。それどころかロックフェラーのように、どんな苦境のなかにもチャンスを見いだし、何かを学んだりスキルを身につけたりする機会に、つまり幸運に変えることさえできるのだ。
「天才とは、心に思ったことを実現できる能力のことだ。それ以外の定義はない」――F・スコット・フィッツジェラルドはそう述べています。そして多くの偉人たちは、まさにその言葉どおり、思い描いたことを実際の行動に移してきました。
ジョン・D・ロックフェラーは、金融恐慌の混乱の中で市場に冷静に向き合い、利益を得る方法を見出しました。彼は、大恐慌という困難を「逆境と苦境の学び舎」として捉え、厳しく自己を律しながら客観的に投資を行い、巨大な富を築いたのです。
トーマス・エジソンは、火災で工場を失ったときにも「大丈夫。ゴミが片付いてよかった」と語り、すぐに再建に向けて行動を開始しました。
ストア哲学の「Amor Fati(運命を愛せ)」という思想は、まさにこの受容の精神を体現しています。 私たちは、自分の身に何が起きるかを選ぶことはできません。しかし、それについてどう感じるかは、いつだって自分で選ぶことができます。
私たちはどんな状況にあっても、自分の選択次第で、立派な振る舞いをすることができるのです。 もし、それが「起こるべくして起こったこと」だとしたら――ニーチェの言葉に従って、堂々とアモール・ファティ(運命愛)を受け入れましょう。
「本当は何を期待していたか」なんて考えても、それは時間の無駄です。前を向いて、微笑みながら事態を受け入れる。それこそがストア哲学の実践なのです。
エジソンも決して受け身ではありませんでした。ただ苦境に耐えていたわけではないのです。 彼は、自分の身に起きたことを受け入れ、そして歓迎していたのです。 人生に起こるすべての出来事を肯定し、歓迎する姿勢こそが、私たちを内面的な自由へと導いてくれます。
バラク・オバマは、大統領選のさなか、師と仰ぐ人物が人種問題に関わるスキャンダルを起こしたことで、大きな試練に直面しました。しかし彼は、それを「学びの機会」として捉え、逃げることなく人種問題と正面から向き合うことで、最終的に勝利を掴んだのです。
エジソンもオバマは、身に降りかかったトラブルを、行動によってチャンスへと変えたのです。
起業家というのは、何もなかったところに何かを生み出せる自信をもった人だ。起業家にとって「誰もやったことがない」というのは良いことなのだ。不公平な課題を与えられても、ある種の人々はそれを正しい目で見て、自分の可能性を試すチャンスだと受け止める。そして勝つのは難しいのを承知のうえで、全力を傾けるのである。
スティーブ・ジョブズは、「現実歪曲フィールド」と呼ばれるほどの話術で、誰もが不可能だと思うことを「できる」と信じ込ませました。彼には、「無理です」「もっと時間が必要です」といった言い訳は一切通用しませんでした。ジョブズは人生の早い段階で、私たちが信じている現実の多くは、子どものころに教え込まれたルールや妥協によって形づくられていると気づいていたのです。
そのため、何が可能で何が不可能かについて、普通の人よりもはるかに大胆で挑戦的な視点を持っていました。彼にとっては、ビジョンと働き方さえ変えれば、人生のたいていのことはどうにかなる――そう信じていたのです。
そして、ヴァージン・グループのリチャード・ブランソンはこう言っています。「ビジネスチャンスとはバスのようなものだ。何度でも次がやってくる」。たとえひとつのチャンスを逃しても、悲観する必要はありません。次のチャンスは、きっとまた巡ってくるのです。
これらの人物たちは皆、苦境を味方にし、逆境を自己鍛錬の道具に変えることで、チャンスをものにしてきたのです。
近年のスポーツ心理学の研究でも、人は大きな試練を経験したあとに「逆境後の成長」や「外傷後の成長」を遂げることが示されています。けがや挫折を経て、自分の真の強さを知り、他者への共感や人生の意味が深まる。苦しみは一時的な痛みであり、やがて自己成長の肥料となります。
さらにホリデイは、「他者のために頑張ること」の力を強調します。 人は、自分のためだけに戦っていると、心が折れてしまうことがあります。
しかし、「誰かを支えたい」「誰かの役に立ちたい」という思いがあるとき、人は不思議なほど強くなれるのです。 思いやりや仲間意識は、どんな境遇にも決して奪われることのない「意志の力」です。 そして、他者を思うことでこそ、人は自分を超えていけるのです。
著者は、人とのコミュニケーションについても的確なアドバイスを示しています。たとえば、苦手な人と仕事をしなければならない場面では、ストア派に伝わる「侮蔑の技法」を使うことを勧めています。
これは、あえて辛口の言葉で相手の虚勢や偽りをあぶり出し、表面的な権威をはぎ取ることで、冷静にその本質を見極めようとする手法です。 また、自分の置かれた状況をしっかりと見据えたうえで、「自分には関係のないことだ」「それは重要ではない、どうでもいいことだ」とあえて装うことも、ひとつの対処法として紹介されています。
そうすることで、今なすべきことがより明確に見えてくるといいます。 これから先にどんなシナリオが考えられ、どんな選択肢があるのか。それを感情に流されることなく見極める力が養われるはずです。そして、そのシナリオが気に入らなければ受け入れなければいい。
納得できるなら、淡々とそれを受け入れればいいのです。 ある問題を解決するために、どんな方法があるのか。どんな可能性があるのか。あらゆる角度から本気で考えてみよう。感情ではなく理性で向き合うとき、状況は違った顔を見せてくれるはずです。
毎日、自分が死すべき存在であることを思い出せば、それまでの時間が贈り物だと感じられる。終わりの時を意識する者は、不可能なことに挑戦したりしないし、本当はこうだったらいいのにと不平を並べて時間を無駄に過ごしたりもしない。
日々、自分の死を意識している人は、自分が本当にすべきことを理解し、それを実行に移します。 そして、時間切れになる前に、なんとか間に合わせようと努力するのです。 疑いようもなく、「死」とは、私たちにとって最も普遍的な障害であり、同時に、最も手の打ちようがない障害でもあります。
せいぜい、その時が少しでも遅れるようにと願うことしかできません。たとえそれがかなったとしても、結局のところ、誰もが死に屈することになります。 しかし、だからといって、死が無価値なものであるわけではありません。 むしろ、死の存在こそが、生きている私たちにとって最大の指針となるのです。
死の影があるからこそ、私たちは人生において本当に大切なことを見極め、優先順位をつけることができます。 死とは、私たちを脅かす存在ではなく、やさしく、ありがたい存在です。生き方を教えてくれる教師のように、静かに背中を押してくれます。
人生で起こる「悪い」出来事も、後悔の念ではなく感謝の念をもって受け止めることができれば、 惨事は恩恵へ、敗北は勝利へと変わっていきます。
本書は、現代における心を鍛えるトレーニングの書です。苦しみを排除しようとせず、むしろ歓迎する姿勢が大切であることを学べます。障害は私たちへの試練ではなく、人生をより良くするチャンスだと捉えるのです。
私たちはハードシングスによって磨かれ、成長し、より豊かに生きることを学びます。だからこそ、目の前の壁に怯えず、それを「道」に変えて歩み続ける――それこそが、「障害こそが道である」という生き方なのです。






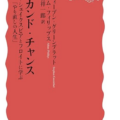











コメント