「老害」と呼ばれたくない私たち 大人が尊重されない時代のミドル社員の新しい働き方
河合薫
日本経済新聞出版社

30秒でわかる本書の要点
結論: 役職や世間の評価といった「外のモノサシ」を捨て、自分の内側にある「本来的な自己(原点)」に基づいた心の土台を再構築すること。
原因: 激変する労働環境と「老害」というレッテルへの過剰な恐怖により、自分らしさを見失い、精神的な脆ささが起きているため。
対策: 「家庭・仕事・健康」という3つの幸せのボールを自分なりの価値観でジャグリングし、半径3メートルの誰かに優しくすることから信頼を積み上げる。
本書の3行要約
「老害」を恐れる40代から60代の不安は、誰かの役に立ちたいという願いの裏返しです。「尊重されるべき」という特権意識を捨て、尊重される努力を続けることで、人生後半戦を豊かにできます。まずは利他の心を持って、半径3メートルの人たちに優しく接することから始めてみましょう。
おすすめの人
・「老害」と思われていないか、若手との距離感に悩む40代〜60代
・役職定年やセカンドキャリアを前に、自分の存在意義を見失いかけている方
・コンプライアンスや世間の目に萎縮し、本音で話せなくなっているミドル層
・「今の働き方をあと何年続けられるのか」と、漠然とした不安を抱えている人
読者が得られるメリット
・精神的なレジリエンスの向上: 周囲の評価に一喜一憂しない、揺るぎない「心の土台」の作り方がわかる。
・人間関係のストレス軽減: 年下の上司や若手社員との、無理に迎合しない誠実な向き合い方が見つかる。
・キャリアの再定義: 組織に依存せず、一人の人間として「幸せ」に生きるための具体的な指針が得られる。 ・幸福感の安定: 仕事一辺倒ではない、「家庭・仕事・健康」のバランスを自分で取れるようになる。
組織に老害と言われる存在が増える理由
今の中高年は、高度成長期を生きた諸先輩がたのように、職場で、家庭で、社会的な地位や尊敬を得ることも難しくなり、社会の激しい変化と若い世代との価値観の違いに翻弄されている。本来的な自己はおろか、無限の可能性すら感じる余裕もない。(河合薫)
現代の日本では、かつて社会の中心を支えてきた中高年が、その存在意義を見失いかけています。40代は「何者にもなれなかった」という漠然とした喪失感を抱き、50代は「ただの中年」として扱われ、60代に差し掛かると「老害」と揶揄されることすらあります。
実際、私も60歳を超えてから、自分の言動や振る舞いが「老害」だと思われていないか、ふと立ち止まって考える瞬間が増えました。年齢を重ねること自体が“リスク”に転じるような空気の中で、ミドル世代自身もまた、自らを「老害かもしれない」と疑いはじめているのです。
世の中は今や中高年であふれ、年長者の希少性は著しく低下しています。ただ年齢を重ねただけで職場や地域社会で威厳を保てた時代は終わり、かつてのような待遇はもはや望むべくもありません。年長者であることが自動的に敬意を生む時代は過ぎ去り、年齢と信頼が結びつかない今、誰もが「どう年齢を重ねるか」という問いと向き合わざるを得ない局面に立たされています。
近年では、年下の上司と年上の部下という構図が当たり前になりつつあり、そこで生まれる微妙な感情の行き違いが、職場の空気をより複雑にしています。上司である若手は「年上の部下をコントロールできるか」というプレッシャーを抱え、部下である中高年は「舐められたくない」「自分の立場を守りたい」という思いから、時に過剰にプライドを張ってしまいます。こうした相互の緊張感が、コミュニケーションをぎこちなくし、信頼関係の構築を困難にしているのです。
表面的には円滑に見えても、内心では互いに距離を感じている——そのような“無言の摩擦”は、多くの職場で密かに進行しています。
河合薫氏の「老害」と呼ばれたくない私たち 大人が尊重されない時代のミドル社員の新しい働き方は、こうした中高年の不安や孤独、そして人間関係の難しさに真正面から向き合い、その閉塞感を突破するための視点を提供してくれます。
40代は若者の気持ちをわかったふりをする「ソフト老害」を恐れるあまり、遠回しな伝え方しかできずに、自分でも何を言いたいのかわからなくなり、 50代は「これは老害意見ですけど……」と前置きした上でしか部下や後輩に意見できなくなり、 60代にいたっては、もはや「老害」の自称すら空しく、「もう何も言わない方がいいのだろう」と口をつぐむ人たちもいる。
本書では、誰かにアドバイスする際に、「老害かもしれないけど……」という自虐的な前置きが広まりつつある現実にも鋭く切り込みます。多くの中高年が、衝突を避けるために本音を抑え、意見を曖昧にすることで周囲に合わせようとしますが、著者はそれが自己評価の低下と信頼喪失を招く危険な行動だと警告します。
一方、世間は40代以降のビジネスパーソンに対して、根強いステレオタイプのレッテルを貼り続けています。とくに40代・50代の中高年層に対しては、「もう伸びしろがない」「変化に消極的」「学ばない」といった固定観念が蔓延しています。
40代・50代は「変われない」といった決めつけは、本人の意欲や能力とは無関係に社会的評価を引き下げ、再就職、昇進、地域社会への参加など、あらゆる場面での機会を奪っています。 さらに厄介なのは、こうしたレッテル貼りの多くが、本人の意図とは無関係に“無意識のうちに”行われていることです。
レッテルを貼られた側は、他者のまなざし、つまり社会に染みついたステレオタイプによって、自分の可能性を制限されている感覚に苦しみます。そこには、言葉にされない圧力があり、それが孤立感や生きづらさを深めていく。
対照的に、「貼った側」はその行為にすら気づかず、無自覚なまま関係性にヒビを入れてしまう。この非対称な構造こそが、世代間の分断を加速させ、中高年世代の心を静かに傷つけているのです。 加えて、実際に中高年が直面している壁は想像以上に高く、連続しています。
40代には昇進の行き詰まりという「役職の壁」が立ちはだかり、50代には役職定年や「肩たたき」、セカンドキャリア選択の現実が重くのしかかります。60代に入れば、収入は激減し、現場での労災リスクも高まります。そして65歳を過ぎると、多くの人が「もう転職できない」という焦りと向き合うことになります。
ジジイの壁なき後に残された「構造的負債」としての3大悪癖
職場では役職者として、家庭では親として年長者が尊重されていた時代は、それなりの役職と権力を手に入れ、階層最上階につながる「ジジイ・ゲート」を通過してしまえば、あとは安泰だった。やがて時代が変わり、組織のスリム化が進むにつれ、役員も大幅に減らされ、「ジジイ・ゲート」は急激に狭まった。
かつての日本社会において、年齢を重ねることはそれ自体が大きな「価値」を持っていました。年功序列というエスカレーターに乗り、一定の勤続年数を経て「ジジイ・ゲート」と呼ばれる昇進の関門を突破すれば、あとは定年というゴールまで安泰なルートが保証されていたと河合氏は指摘します。そこには、組織への忠誠が確実に報われるという、強固な「成功のプロトコル」が存在したのです。
しかし、現代においてそのゲートは跡形もなく消え去りました。組織のスリム化によってポストは激減し、将来の見通しは極めて不透明です。中高年が「ジジイ」として踏んり返る余地すら奪われた後に残されたのは、やり場のない孤独でした。
皮肉なことに、権限を失ったはずの現代のミドル層が、かつての上司世代が持っていた負の行動特性——新しいものへの拒絶、事なかれ主義、そして過度な忖度——を、無意識のうちに再生産してしまっています。 当事者たちは、「自分たちは権限など持っていない。昔のようなジジイではない」と反論するかもしれません。しかし、組織文化に定着してしまった「縦の力学(経営陣の締め付け)」が、今もなお彼らの行動を縛り続けているのです。
経営陣からは「イノベーションを起こせ」という抽象的なプレッシャーが降り注ぎ、部下からは「パワハラ」を警戒する視線が突き刺さる。この板挟みの中で、多くのミドル層は「空気を読む」という安全装置に逃げ込まざるを得なくなっています。
結果として、組織は「コンプライアンス」という名の見えない監獄と化していきます。批判を恐れ、議論を平坦なものに留め、変革に挑むより現状を維持することに延命のエネルギーを注ぐ。波風を立てないことだけが、唯一の正解になってしまう——これが、令和における「忖度」の正体です。
かつてのジジイ時代には、忖度には昇進や昇給という「見返り」がありましたが、今、どれだけ空気を読み、不条理を飲み込んだとしても、明確なリターンは存在しません。彼らはただ、かつての「上司への愚痴」を「若手への愚痴」にスライドさせ、日々の停滞をやり過ごしているのが現実です。
こうした「波風を立てないための自己保身」こそが、未来を創ろうとする若い世代との間に決定的な断絶を生んでいます。
ミドル世代が過去の処世術をアップデートできず、組織の力学に埋没し続ける限り、若手にとって彼らは「停滞の象徴」と映り、その存在価値は失われ続けます。こうした姿勢が生む世代間のギャップが人間関係を硬直化させ、結果としてミドル自身から「本来あるべき居場所」を奪い去っているのです。
自分へのイライラ、激変する労働環境で長く働き続けられるのかというモヤモヤ、いつか見捨てられるのではないかというヒヤヒヤ。これらのストレスにより、まるで極細繊維のように摩擦に弱く、ガラスのように壊れやすくなっているのが新世代型の中高年であり、これこそが彼らのしんどさ、生きづらさの正体だ。
「働かないおじさん・おばさん」と揶揄されることへの不安、「コンプライアンス違反」と言われることへの過剰な恐れ、そして「自分の感覚はもう時代遅れなのではないか」という疑念——そんな目に見えない精神的なプレッシャーが、中高年の言動を静かに縛っています。
「こんなこと言ったら古い人間だと思われるかも」と自分の感覚に自信を持てず、「自分はもう古いのかもしれない」と気後れしてしまう。その萎縮の連鎖は、自分らしさの根っこである“心の土台”を揺るがしていきます。
著者は、こうした不安を抱える中高年に「心の土台の再構築」が必要だと語ります。役職や評価といった外の軸から距離を取り、自分の“原点”に立ち返ることが、これからの人生を前向きに生きるための鍵になるのです。
本来的な自己とは、たとえば子どものころに夢中で遊んだ記憶や、誰かのために自然と行動できたあの瞬間に宿っていた、純粋なエネルギーのようなもの。社会に適応するなかで、私たちはいつしかその感覚を覆い隠してしまったのかもしれません。
大切なのは、「どう働くか」ではなく「どう生きるか」を自分に問い直すことです。他人の視線に振り回されるのではなく、自分の内側から人生のハンドルを握り直すこと。「もう年だから」「今さら無理」といった制限を外し、「今から何ができるか?」と問い直す習慣が、年齢に関係なく可能性を広げてくれます。
豊かな人生を実現する「3つの幸せのボール」|家庭・仕事・健康のバランス
人は「家庭=身近な人間関係」「仕事=社会的活動」「健康=生存に関わる問題」という3つの幸せのボールを持つ。どのボールも決して落とすことなく、ジャグリングのように回し続けてこそ、豊かな人生、幸せな人生、納得いく人生は実現する。
人はお金だけでは幸せになれないことを数々の調査が明らかにしています。家族や友人との時間、自分の学び、健康づくり、誰かのために動くこと、趣味に没頭する時間、がんばった自分をねぎらう時間——そうした「自分の大切なもの」のために、時間やお金やエネルギーを使うことは、未来への投資なのです。
家庭、仕事、健康 この3つのボールの回し方に正解はありません。社会や世間が決めるものではなく、自分の価値判断で決めればいいのです。すべてはあなた次第。その選択を支えるのが「心の土台」であり、その核となるのが「本来的な自己」です。 自分のことをよく知り、自分なりの価値観に基づいて行動できる人は、環境に埋没せず、他人と共存しながらも自分らしくいられます。
他者を尊重しながら、自分の喜びが誰かの幸せにつながることを理解している。そんな人こそ、「本当に幸せだ」と感じる瞬間を迎えられるのではないでしょうか。
本書は、若者に迎合するテクニックを紹介する本ではありません。「老害」と呼ばれることへの不安の裏には、「まだ誰かの役に立ちたい」という願いがあり、それこそが中高年の価値の証です。著者は、冷静に現実を見つめながらも、私たちがキャリアの主導権を取り戻せるよう力強く背中を押してくれます。
私たちは「尊重されるべき大人」ではなく、「尊重される大人であろうと努力する人」であるべきだと、著者は指摘します。大切なのは、完璧を目指すことではなく、今の自分にできることを一つひとつ誠実に積み重ねていくことです。
まずは、日々顔を合わせる半径3メートルの誰かに、さりげない優しさを向けてみる。そんな小さな行動の積み重ねが、やがて信頼という心の土台を育てていきます。
そして、その半径3メートルの世界を少しずつ増やしていくことで、私たちは「積極的他者関係」を築くことができます。それは、安心感や充実感を支える人間関係を、自らの手で少しずつ広げていくということです。健康的で幸福な人生の基盤は、遠くの誰かや抽象的な評価ではなく、ごく身近な人との関係にこそあるのです。
健全な心の土台に従って働くとは、誰かの役に立つ喜びを感じたり、自分の内面が満たされる選択をしたりすることです。それは役職や年齢に左右されるものではなく、自分のあり方に正直でいるという意思の表れです。 そう思えるようになったとき、中高年というライフステージは、停滞ではなく変化の始まりとして輝き出します。他人の期待に応える“いい大人”の型に縛られることなく、自分自身の心の声に耳を傾けて生きることが大切になります。
社会の構造が変わり、年齢への敬意が薄れてきている今だからこそ、自分の価値を問い直すことには、これまで以上に深い意味があります。
本書は、そんな時代を生きる私たちに、新しい働き方と生き方をわかりやすく提示してくれます。それは単なるスキルの習得ではなく、組織や肩書きといった外的要素から自分を解き放ち、一人のプロフェッショナルとして、幸せに生きるための心の再設計です。
変化が当たり前になった今、私たちが本当に守るべきものは、過去の自分やプライドではありません。本書は、それよりも他者との良好な関係こそが、これからの人生を支える土台になるのだと教えてくれます。
「老害」と呼ばれることを恐れて立ち止まるのではなく、そのエネルギーを、いま目の前にいる半径3メートルの人たちのために使いましょう。小さくても確かな価値を届けることが、信頼を生み、自分自身の変化にもつながっていきます。
本記事は書評ブロガー・ビジネスプロデューサーの徳本昌大が執筆しました。



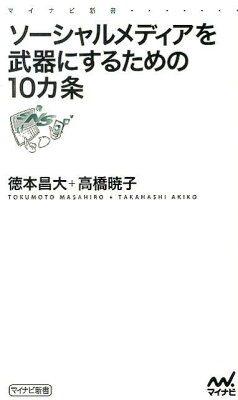













コメント