ハーバードの人生を変えるライティング
ソン・スッキ
かんき出版
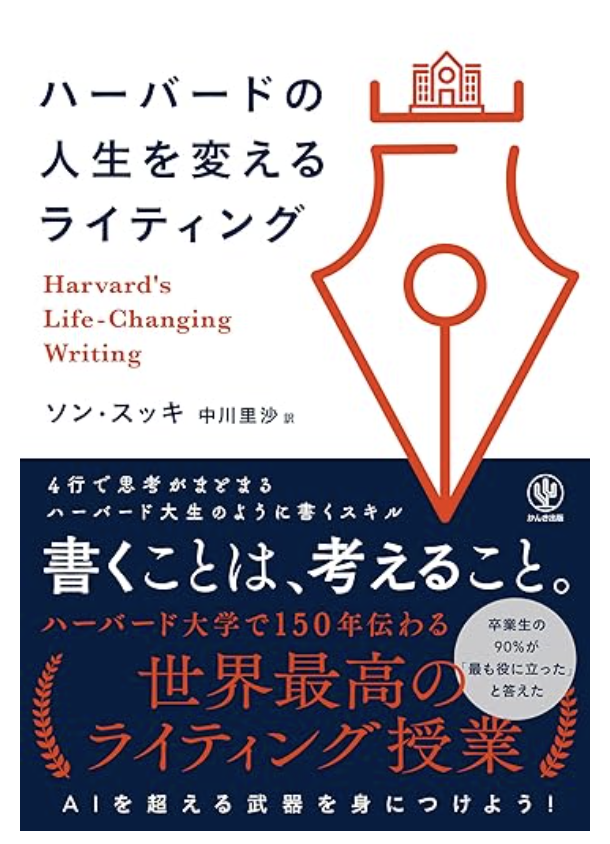
ハーバードの人生を変えるライティング(ソン・スッキ)の要約
ハーバード大学は、文章を書くことを思考力を磨く行為と位置づけ、全学生にライティングスキルを求めています。ライティングは単なる記述ではなく「伝える」行為であり、相手の理解を促し、行動へ導く力です。『ハーバードの人生を変えるライティング』は、「オレオ公式(O.R.E.O.)」によって、論理的かつ感情に響く文章を構築するための実践的な方法を提示しています。
ライティング能力を高める「オレオ公式(O.R.E.O.)」
ハーバード大学がライティング教育にこだわるのは、文章を書く行為は考える行為であり、考えながら文章を書くとき、思考力がより磨かれるためだ。だから、AIが文章をうまく書く時代であればあるほど、私たちは自ら文章を書かなくてはならないのだ。(ソン・スッキ)
気持ちはあるのに、いざ文章を書こうとすると言葉が出てこない。書き始めても途中で迷子になり、何を伝えたいのか自分でもわからなくなる。仕上げたはずなのに、読み返すと説得力がなく、相手に響く気がしない――そんな経験を繰り返していませんか?
SNSやブログ、メール、企画書やプレゼン資料など、文章を書く場面は日常的に増えています。それにもかかわらず、自分の考えを的確に伝える力を持つ人は驚くほど少なく、多くの人が言葉に振り回されているのが現実です。
小説家のロバート・L・スティーヴンソンはこう語っています。「書くことが難しいのは、自分の意図する文章を書かなければならないからであり、読み手に影響を与え、行動させなければならないからだ」。これは、ライティングが単なる「書く」行為ではなく、「伝える」行為であることを的確に表しています。
ところが私たちはこれまで、伝える内容を練るよりも「書くこと」そのものに時間を費やしてきました。伝えたいことがなければ、何をどう書こうとも相手には届きません。伝達力の核心は、自分が伝えたい内容を、相手に素早く理解させ、意図した行動を引き出すことにあります。
この行き詰まりを抜け出すカギが、ハーバードの人生を変えるライティングです。韓国のライティングコーチ、ソン・スッキは、「書くことは考えること」というテーマを徹底的に掘り下げ、ハーバード大学で150年以上受け継がれる文章教育を「オレオ公式(O.R.E.O.)」というフレームワークとして私たちに提示しています。
ハーバード大学が文章教育にこだわる理由は明快です。文章を書く行為は思考そのものであり、書きながら考えることで思考力が磨かれます。情報が氾濫し、AIが文章を生み出す現代であればなおさら、私たちは自らの頭で考え、自分の言葉で表現する力を手放すべきではありません。AIに業務の一部を委ねることはできても、思考力そのものを委ねることはできないのです。
ハーバードの狙いは、ロジカルシンキングの強化にあります。論理力はすべての思考の土台であり、個人や社会で成果を出すための基礎です。専攻を問わず、ハーバードの学生たちは在学中を通じて文章力を鍛え、簡潔かつ説得力のある表現を身につけます。
議論の余地があるテーマを選び、構造的にアイデアを組み立て、相手の理解を促す文章を作る――その積み重ねが、卒業後も世界で活躍できる力を育んでいると著者は指摘します。
本書の中心となる「オレオ公式(O.R.E.O.)」は、Opinion(意見を主張する)、Reason(理由や根拠を示す)、Example(具体例を挙げる)、Opinion(意見を再度強調する)というシンプルな流れです。この順番で考えや資料を並べれば、筋道が通った一貫性のある文章が生まれ、相手を納得させ、期待通りに動かすことができます。
さらに、この公式は「ターゲット(誰に伝えるか)」「アイデア(何を伝えるか)」「価値の提案(相手にとって魅力的な約束)」と組み合わせることで、強力な説得力を発揮します。
ハーバード大学が自負するライティングは、要点を相手の頭に直接届ける力があります。どんな文章であれ、論理的で客観的な構造を持てば、読み手の反応は早くなります。スピードが求められる時代において、ロジカル・ライティングは最適なコミュニケーション手段です。
だからこそ文章力が低いと、仕事の能力まで疑われかねません。筋が通り、読みやすい文章には必ず「何の話か(What)」「なぜ必要か(Why)」「どうすべきか(How)」の三要素が組み込まれているのです。
本書で示されているオレオの公式の4つのステップを以下に引用します。
①Opinion 〜なら、〜しよう
会社を辞め、好きなことをして食べていきたいなら、本を出そう。
②Reason なぜなら、〜だから
なぜなら、本を出せば専門的なスキルを持っているとみなされるからだ。講師協議会の発表によると、専門講師の内、著書がある人の方が謝礼が高いことが明らかになった。
③Example たとえば、〜 たとえば、公務員として働いていたAさんは「理系公務員のためのコミュニケーション術」という本を出してすぐ、公共機関から講演依頼が相次いだ。
④Opinion だから、〜なら、〜してみよう
だから、会社を辞めて独立し、一生現役でいたいなら本を出してみよう。まずはブログであなたのコンテンツを共有し、読者とコミュニケーションをとるのがよい。
伝達力がすべてを決める時代のライティング戦略
昔は知識こそが力だったが、今は考えることが力の時代に変わった。ある考えに世界中からお金が集まり、それを考えた人はあっという間にお金持ちになる時代。そういう時代では、考えそのものより、考えを伝えることのほうが重要だ。つまり、今の時代は伝達力こそがすべてなのである。他人よりたくさん知識があり、優れたことを考えたところで、それを相手の目線に合わせて伝えることができないなら、知識も考えも無用の長物だ。
私がビジネスを始めた頃は、知識が武器になる時代でした。しかし、今はその常識が覆っています。知識はAIから容易に手に入り、差別化は難しくなりました。現代において価値を持つのは、知識から新たな考えを生み出す力です。そして、時代はさらに進み、考えを生み出すだけでは不十分になりました。その考えを他者にわかりやすく伝え、行動を引き出すこと――伝達力こそがすべてなのです。
いくら優れた知識やアイデアを持っていても、それを相手の立場に合わせて伝えられなければ、存在しないのと同じです。知識や思考は、伝えることで初めて社会的な価値に変わります。そして、その価値を形に変える最も有効な手段がライティングです。
文章は知識や思考を社会とつなぐインターフェースであり、時代を動かす原動力です。 だからこそ、文章力は経営者やビジネスパーソン、学生や研究者など、立場を問わず誰もが身につけるべき基礎体力です。ライティングを磨くことは、自分の可能性を最大化するための投資であり、しかもリスクはほとんどありません。パソコンと書くことを仕組み化できれば、今日からでも始められます。
私自身、このブログを15年間続けてきました。その中で、思考力と文章力を着実に鍛えることができました。その結果、書評家としてのブランディングや、”諦めない人”という自分の姿勢がしっかりと伝わるようになり、ビジネスにも良い影響を与えています
知識から思考へ、そして思考から伝達へ――時代の重心が確実に移っている今、自分の考えを形にして伝える力は最大の武器になります。 その重要性を裏付けるのが、ハーバード大学の教育方針です。
マーゴ・セルツァー教授は「なぜそう考えるのか、なぜ有益なのか、伝えられなければ誰も私を信じないだろう。ライティングの目標は、あなたのアイデアが価値あるものだと人々に確信させることだ」と述べています。
また、ナンシー・サマーズ教授も、卒業後に真のプロとして活躍するためには文章力の鍛錬が不可欠であり、それが新たな問題を解決する力につながると強調します。
ハーバード大生にとって、フィードバックは日常的に行われています。書いた文章に意見をもらい、修正を重ねることで完成度を高めます。この過程でテーマへの理解が深まり、新たなアイデアが生まれます。フィードバックは批判ではなく、共に壁を越えるための手段なのです。文章が上達するとは、「書く・受け取る・直す」というサイクルを繰り返すことにほかなりません。
さらに、ハーバード大学とカーネギーメロン大学の共同研究によれば、文章力の高い人はライティングに費やす時間の70%を修正に使っています。初稿を書いたら徹底的に見直し、構成を組み替える――この「修正の時間」こそが、主観的な文章を読み手が理解しやすく、納得できる形に変えるプロセスです。プロの文章は例外なく、この修正の積み重ねで生まれています。
文章力は、生まれ持った才能ではなく、鍛えられる技術です。そして、その鍛錬は時代が求める伝達力を確実に高めます。情報があふれる今こそ、自分の言葉で考えを伝える力を磨くことが、あなたの未来を切り拓く最短ルートになるのです。







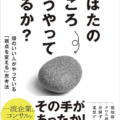



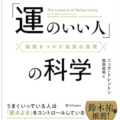

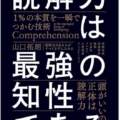




コメント