不夜脳 脳がほしがる本当の休息
東島威史
サンマーク出版
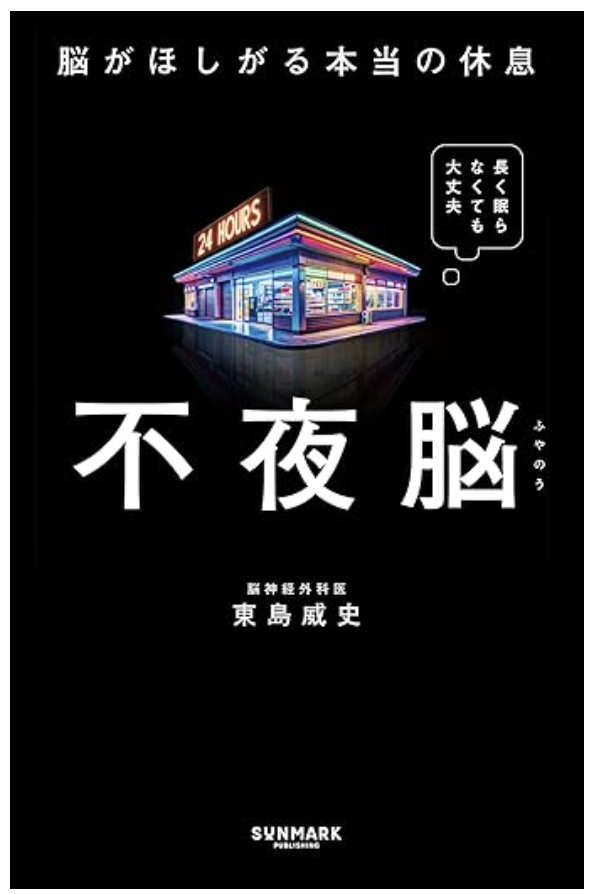
不夜脳 脳がほしがる本当の休息 (東島威史)の要約
脳神経外科医・東島威史氏による『不夜脳』は、「睡眠=脳の休息」という常識を覆し、脳は刺激によって活性化し、回復するという新たな視点を提示します。刺激こそが脳の真の休息であり、運動や読書、感情の高まりが脳を覚醒・活性化させると説きます。「眠る前に脳を動かす」ことで深い休息が得られるという逆説的な視点は、安眠の概念に一石を投じ、私たちの疲労対処や生活習慣を見直す契機となります。
脳の休息=睡眠なのか?
脳は年齢に負けない。脳の仕組みを理解し、脳に本当の休息を与え、かつ、適切に体を休ませることで、脳をいい状態で保つことができる。(東島威史)
不夜脳 脳がほしがる本当の休息というタイトルに惹かれ、私はこの本を手に取りました。長年、快眠を求めて多くの書籍を読み、さまざまな方法を試してきましたが、なかなか安眠にたどり着けずにいました。そんな中、本書はこれまでの常識を揺るがす新しい視点を私に与えてくれました。
著者の東島威史氏は脳神経外科医としての見地から、「脳の休息=睡眠」という定説に疑問を投げかけています。脳にとって必要なのは、ただ眠ることではなく、適切な刺激が必要なのだと語ります。脳の老廃物は睡眠中にしか排出されないという通説に対し、著者は、覚醒中にもその機能が働いていることを示し、むしろその方が進化的に理にかなっていると主張します。
脳はまるで24時間営業のコンビニのように、常に稼働し続けています。夜間のオフィスのように静まり返っているわけではなく、むしろ煌々と明かりを灯す「不夜城」のような存在だと言うのです。眠っているときでさえ、脳内では清掃作業のように老廃物の除去が進んでおり、それは「グリンパティックシステム」と呼ばれる仕組みによって行われています。
さらに著者は、脳の回復や活性化において「刺激」が重要だと繰り返します。年齢を重ねるほど、休息を優先しがちですが、実は刺激を与え続けることこそが脳にとっての真の休息なのだというメッセージは、私自身の思い込みを大きく覆しました。
「良質の睡眠」のためには、「良質の脳の覚醒」が欠かせない。
そして、本書を読み進める中で特に印象的だったのが、「ドキドキ」こそが最高の刺激であるという考え方です。胸のときめきや、恋愛、推し活の高揚感のように、脳は感情の高まりを強い刺激として受け取ります。ランニングなどの運動による心拍の上昇も、脳にとっては立派な刺激です。歩美のドキドキよりも、運動によるドキドキのほうが、より強く脳を揺さぶってくれる。 このような刺激は、脳の「覚醒度」と密接に関係しています。
ドキドキしているとき、脳は高い覚醒状態にあり、その結果として処理できる情報量が増えます。つまり、心が動く瞬間に、時間はより密度を増し、私たちは「濃い時間」を生きられるのです。
たとえそれがネガティブなドキドキ――たとえば、苦手な上司に詰められる瞬間や、大勢の前でプレゼンする前の緊張感であっても、それは脳にとっては明確な刺激であり、生産的な時間を生み出すエネルギー源になるのです。
脳が覚醒している時間は、実際の時間よりも「長く」感じられ、情報処理も効率的に行われます。だからこそ、私たちはドキドキすることで、24時間を25時間分に変えることができるのです。脳を刺激し、ドキドキを感じている人のもとにこそ、多くの時間が与えられている――この視点は私にとって非常に衝撃的でした。
著者は、脳疲労を解消するカギは睡眠ではなく、「活力」と「バランス」にあると語ります。たとえば、座りっぱなしのデスクワークで頭がぼんやりしてきたとき、眠るのではなく、身体を動かして「運動野」に刺激を与えると、不思議と脳がスッキリします。
また、言語や計算、論理的思考などで左側頭葉を酷使したときには、音楽を聴いたり、感覚的な刺激を受けることで右側頭葉が活性化され、脳のバランスが整います。 よく考えれば、脳が疲れたからといって、いちいち眠らないと仕事が続けられないという人はほとんどいません。
つまり、脳の疲労とは「使いすぎ」そのものではなく、特定の部位に偏った状態であり、「使われていない部分」を適切に刺激することで回復する――著者のこの視点は、脳との向き合い方を見直すヒントになります。
眠って回復するのではなく、動かして整える。この考え方に触れたとき、自分の中の疲労感への対処法も根底から変わる感覚がありました。
脳に適切な刺激を与える方法
脳は睡眠全体はもちろんのこと、最も深いノンレム睡眠中(徐波睡眠)であつても、決して眠ってはいない。脳波はゆっくり、だが大きく動いている。脳は、「いいことをたくさん起こすために」、静かに活動しているのだ。
著者は、世界基準での認知症リスク要因の中に「睡眠」は含まれておらず、むしろ重要なのは、脳に有害な病気――外傷や生活習慣病など――を避けること、そして適切な「刺激」を継続的に与え続けることだと指摘します。特に運動や音楽のように感覚を動かす刺激は、脳の健康維持にとって決定的な役割を果たすといいます。
脳は刺激によってこそ活性化されます。私たちは「脳が疲れた=睡眠で回復する」と考えがちですが、著者はこの常識に異を唱えます。脳疲労とは「使いすぎ」ではなく「使い方の偏り」であり、刺激が入っていない部分を働かせることでバランスが整い、回復するのです。
デスクワークで凝り固まったときには身体を動かし、「運動野」を刺激することで思考がすっきりする。左脳を酷使したときには右脳を使う活動――音楽、絵、香りなど――でバランスをとる。眠る前に一度脳を「動かす」ことで、逆に深い休息を得られるという逆説的な視点が、私の中の疲労回復への考え方を大きく変えてくれました。
そして、特に印象に残ったのが、「忘れること」の重要性についてです。私たちは「記憶力がいい=頭がいい」と信じがちですが、著者は「忘却こそが脳の本質的な機能である」と強調します。情報はすべてが意識に留まっているわけではなく、シナプスによってつながった記憶の多くは、脳の無意識の倉庫に静かにしまわれています。
「忘れた」と感じるのは、その情報が意識上に上がってきていないだけで、実際には記憶のネットワークの中に保持されています。同じ刺激が何度も繰り返されると、シナプスの結びつきが強化され、ある閾値を超えたときにようやく「意識」に上がってくる。まるでよく使う道具をバックヤードから取り出して、棚に並べていくような感覚です。
この記憶の整理・定着に深く関わっているのが、脳内のグリア細胞の一種である「アストロサイト」です。アストロサイトは、ニューロンの接続をコントールしています。アストロサイトの働きによって、必要な情報だけが脳内に残され、処理効率が高まる仕組みが支えられているのです。
さらに、脳の可塑性を高めるうえで欠かせないのが、「BDNF(脳由来神経栄養因子)」という物質です。BDNFは、神経細胞の成長や維持、シナプスの強化に関与し、学習や記憶に直接影響を与えます。運動や新しい刺激によってBDNFが増えることが知られており、脳に刺激を与える生活習慣そのものが、長期的に記憶力や判断力の維持につながるのです。
本書では、脳を活性化させるための具体的なアプローチが多く紹介されています。有酸素運動や、骨にダイレクトな刺激を与えるような身体の使い方――たとえば、早足で歩きながら時おりジャンプを加えるような動きが効果的だとされます。
また、あえて空腹時間をつくる「間欠的断食」も脳に良い刺激を与える方法の一つとして紹介されており、エネルギーの枯渇状態が脳の働きを一時的に鋭敏にするというのです。
さらに、オメガ3脂肪酸を豊富に含み、神経細胞の膜やシナプスの材料となる「クルミ」の摂取も推奨されています。食事による神経環境の改善が、思考の柔軟性や感情の安定に直結するという視点は、脳にとっての「栄養」が単なるエネルギーではないことを示しています。
読書という行為は、脳に対して特別な刺激を与える。
知的活動においては、外国語学習やスマホゲーム、麻雀なども脳の刺激に寄与するとされますが、特に著者が強調しているのが「読書」です。
読書という行為は、脳にとって極めてユニークな刺激をもたらします。 私たちの脳は日常的に前頭前野を使っていますが、読書中は「聴覚情報がない」「視覚情報も文字だけ」という、外部からの刺激が非常に少ない環境に置かれます。ところが、刺激を求めてやまない脳は、それを補うために「内部刺激」を自ら生み出し始めるのです。
登場人物の顔や声、動きや場面の風景――それらを一つひとつ想像し、組み立て、物語を立体的に再構築していくプロセスが、まさに脳の中の創造エンジンをフル稼働させます。
読書は、単に情報を受け取るだけの行為ではありません。読者自身が登場人物や情景を想像し、物語の世界を自ら作り上げていく、非常に高度な知的活動です。こうした脳の使い方を見ていくと、「脳を休ませること」よりも「どう刺激するか」が、脳を若々しく保つ鍵であるという著者の主張に、より深い説得力を感じます。
さらに本書では、睡眠不足を和らげる具体的な方法も紹介されています。たとえば、瞑想を行ったり、右側を下にして寝ることで、脳内の老廃物が排出されやすくなるといいます。また、就寝前のカモミールティなどのハーブティーも安眠をサポートしてくれます。
「眠らない脳こそが、老いない脳」――この考え方は、これまで当然のように信じていた「脳を休めるために眠る」という常識を根底から覆しました。
そして、良質な睡眠は適切な刺激によってもたらされるという視点にも大きく共感しました。日中に脳がどれだけ活性化され、刺激を受けていたかによって、夜の眠りの質が決まる。
つまり、しっかり働いた脳こそ、しっかりと休めるのです。この考え方は、どう休むかではなく、どう活動するかを見直すきっかけになりました。 本を読み終えたとき、私が目指すべきなのは「安眠」そのものではなく、脳が求めている「刺激」と「リズム」に意識を向けることなのだと気づかされました。
睡眠は「不足を補うもの」ではなく、「脳が自ら選び取る休息の一形態」として捉える。その発想の転換が、長年私が悩んでいた睡眠不足という問題に、一筋の光を差し込んでくれたように思います。 「睡眠時間は人それぞれであり、平均値はあくまで参考にすぎない」という著者のメッセージにも、安心感を覚えました。




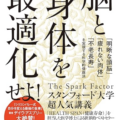
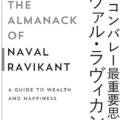
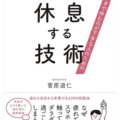

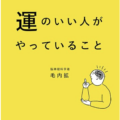
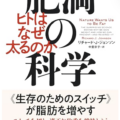
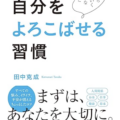

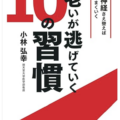

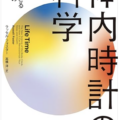
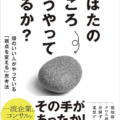


コメント