 戦略
戦略 ずっと幸せなら本なんて読まなかった 人生の悩み・苦しみに効く名作33 (三宅香帆)の書評
「人生に絶望したり、自分の不幸に直面したとき、本は助けとなる」と三宅香帆氏は述べています。従来の文学鑑賞とは異なり、著者は書籍を日常の問題や感情に対処するツールとして捉え直しています。読書は私たちに様々な課題解決のヒントをもたらし、幸せへと導いてくれるのです。
 戦略
戦略 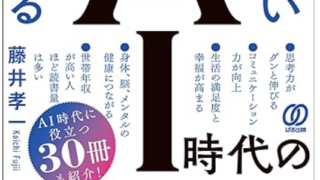 AI
AI 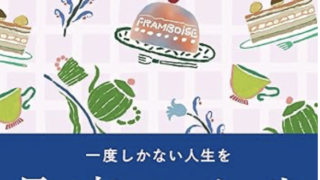 哲学
哲学  パーパス
パーパス 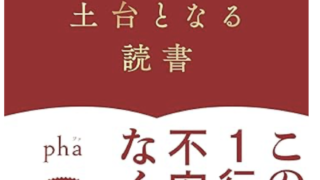 習慣化
習慣化  投資
投資 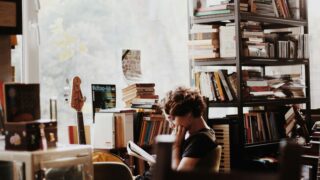 パーパス
パーパス  哲学
哲学  哲学
哲学  戦略
戦略