センスを磨く読書生活 私たちは本でできている
奥村くみ
オレンジページ
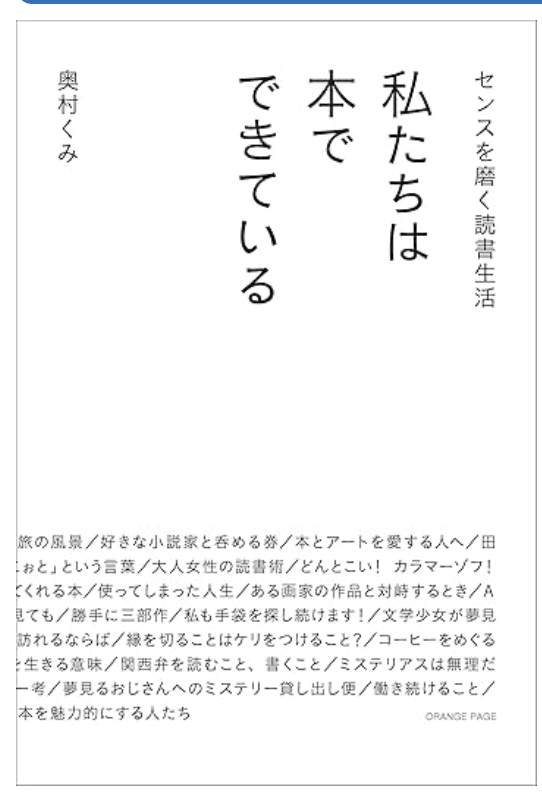
センスを磨く読書生活 私たちは本でできている(奥村くみ)の要約
アートアドバイザー・奥村くみ氏の『センスを磨く読書生活』は、読書が人生に与える深い影響を実感させてくれる一冊です。本を通じて感性が磨かれ、視点が広がり、時に行動さえも変えてくれる。「読むこと」は「生きること」そのものであり、未知の本との出会いが、新たな一歩を踏み出す力になると教えてくれます。
読書の楽しみは、人生に彩りをもたらす作家を持つこと
人生の岐路に立ったとき、いつも私を支えてくれたのは本の存在。思えば物心ついてから本と離れたことはありません。どの時期においても、私の心の根幹を成していたのは本でした。(奥村くみ)
本を読むこと。それは、単に知識を得るためだけの行為ではありません。 先人の知恵に耳を傾けながら、自分の価値観や生き方を問い直し、センスを磨き、人生を豊かにしていく道のりでもあります。 そして何より、本を読む時間は、自分自身と静かに向き合い、対話するための大切なひとときでもあるのです。
アートアドバイザー・奥村くみ氏のセンスを磨く読書生活 私たちは本でできているは、まさにその道のり=読書の価値を再認識させてくれる一冊です。本を通して自分を整える。その積み重ねが、人生を少しずつ変えていくのだと気づかされます。
著者の奥村氏は、人生の岐路に立つたびに本に支えられてきたと語ります。その言葉に、私も深くうなずかざるを得ませんでした。私自身も、本に救われた経験を何度も持っています。
彼女が愛し、人生の支えとしてきた書籍との出会いを通じて、読書がいかに私たちのセンスを磨き、日常に彩りを添えてくれるかが、美しい写真とともに丁寧に綴られています。まるで著者の本棚=人生を一緒にのぞき込んでいるような感覚に包まれます。読書案内としても質が高く、良質な読書ガイドとしても楽しめます。
本書では、村上春樹氏の職業としての小説家に登場する、作家ジョン・アーヴィングの印象的な言葉が紹介されています。 『職業としての小説家』は私も何度も読み返している作品なので、著者のこの引用をとても嬉しく感じました。
「あのね、作家にとっていちばん大事なのは、読者にメインラインをヒットすることなんだ。言葉はちょっと悪いけどね」——ジョン・アーヴィング
この「メインラインをヒットする」という表現は、アメリカの俗語で「相手を常用者(アディクト)にする」という意味があるそうです。つまり、読者が作品に夢中になり、繰り返し求めてしまうような強い魅力を与えることが、作家にとって最も重要なことなのです。
私にとって、まさにその“メインライン”をヒットする作家は、アダム・グラント、ローレンス・ブロック、宮城谷昌光、そして村上春樹です。彼らの作品は、一度読み始めると止まらなくなり、何度でもその世界に浸りたくなるような、深い中毒性のある読書体験をもたらしてくれます。
こうした没入感のある読書体験は、日々の暮らしに刺激と豊かさをもたらし、人生に彩りを添えてくれる、かけがえのないものです。最近では、オーディオブックも積極的に取り入れ、新作や旧作を耳から楽しむスタイルも気に入っています。移動中やリラックスタイムにも作品の世界に触れられることで、読書の楽しみがさらに広がりました。
今の時代の作家の本を読む、そしてアート作品を見る。彼ら、彼女たちと一緒の時代を今、生きているんだ、そんな風に思うと、本を夢中で読んでいる時間、展覧会で作品に対峙するひととき、それらがとても大切な奇跡の瞬間に思えてくるのです。
私自身にとって、特に村上春樹氏との出会いは、まさにそのような奇跡のひとつでした。17歳の頃、『風の歌を聴け』『1973年のピンボール』を手に取った瞬間から、その旅は始まりました。村上氏のデビュー直後からの付き合いになりますから、彼の作品は私の人生のさまざまな節目を彩り、共に歩んできたと言えます。
彼の小説やエッセーを読みながら、私は実際にいくつもの街を訪れました。また、村上氏が訳した翻訳本を通じて、新たな魅力的な作家とも出会うことができました。作品を通して知ったその土地は、ただの旅先ではなく、物語の中に自分が入り込んだかのような特別な意味を持つようになりました。それはまさに、文学が持つ「現実を超えた力」の証明でした。
同じ時代に生き、同じ空気を吸い、作家の視点を共有する。私たち読者は、こうした奇跡的な出会いによって、人生をより深く、豊かにしているのだと思います。村上春樹氏や彼が紹介した英米文学との旅はまだ続いています。これからも、彼の新しい言葉を通じて新たな場所、新たな自分と出会えることを楽しみにしています。
「読むこと」は「生きること」
人類が本をつくってから何世紀が過ぎようと、その存在は変わることなく、どの時代にも人々に希望の光を与え、読書は人間にとって尊く、美しい行為の一つであり続けています。
著者は「読むこと」は「生きること」というディヴィッド・トリッグの書物のある風景の帯文を紹介しています。私の人生は、まさにこの言葉通りで、幼い頃からの読書体験によって形作られてきました。
その原点となったのは、司馬遼太郎の『太閤記』を文庫本で読んだことです。この一冊との出会いが、のちの人生を大きく方向づけたと言っても過言ではありません。あの日、小さな手で文庫本を開いた瞬間から、私の活字中毒は始まりました。
歴史小説から始まり、古典文学、海外小説、哲学書、そしてビジネス書へと、ジャンルを超えてさまざまな本の世界を渡り歩いてきました。最近では、毎朝、この書評ブログに投稿するためにビジネス書を読み続けることが日課となっています。この習慣のおかげで、日々新たな視点に触れ、自分の思考を更新し続けることができています。
10代、20代の頃には、レイモンド・チャンドラーやダシール・ハメット、ロバート・B・パーカーといったハードボイルド小説の巨匠たちの作品に夢中になっていた時期もあります。乾いたユーモア、鋭い観察眼、そして張り詰めた空気感が魅力のこのジャンルは、人生の裏側や人間の本質をあぶり出し、他のジャンルとはまったく異なる深い読書体験をもたらしてくれました。
「読むことは生きること」——この言葉は、今では私の人生哲学そのものです。本を通して異なる時代を生き、数えきれない人生を疑似体験し、自分ひとりでは到達できないような思考の高みにも触れることができます。
人類が本をつくってから何世紀が過ぎようと、その存在は変わることなく、どの時代にも人々に希望の光を与え、読書は人間にとって尊く、美しい行為の一つであり続けています。
私たちは時に、習慣の中で同じジャンルや同じ作家の本ばかりを選んでしまいがちです。 しかし、あえてそのパターンから抜け出し、未知の作品に触れてみることで、思いもよらない発見や感動に出会えることがあります。
本書は、そんな新しい読書体験へと背中を押してくれる、良質なガイドブックです。 普段あまり手に取らないジャンルの本も数多く紹介されており、新たな視点を得るきっかけになりました。 また、過去に読んだ本も、著者の解釈を通して改めて読み返したくなりました。カズオ・イシグロのクララとお日さまと、クリス・ウィタカーのわれら闇より天を見るは、まさにそんな一冊です。
人生を少し前に進める――そのきっかけは、本の中にこそあるのだと改めて感じさせられました。 著者が教えてくれたのは、多様な本との出会いが、人生の新たな可能性を広げてくれるということです。 著者が最後に述べているように、「私たちは本でできている」のです。過去の読書体験が、今の私たちを形作っているのだと思います。
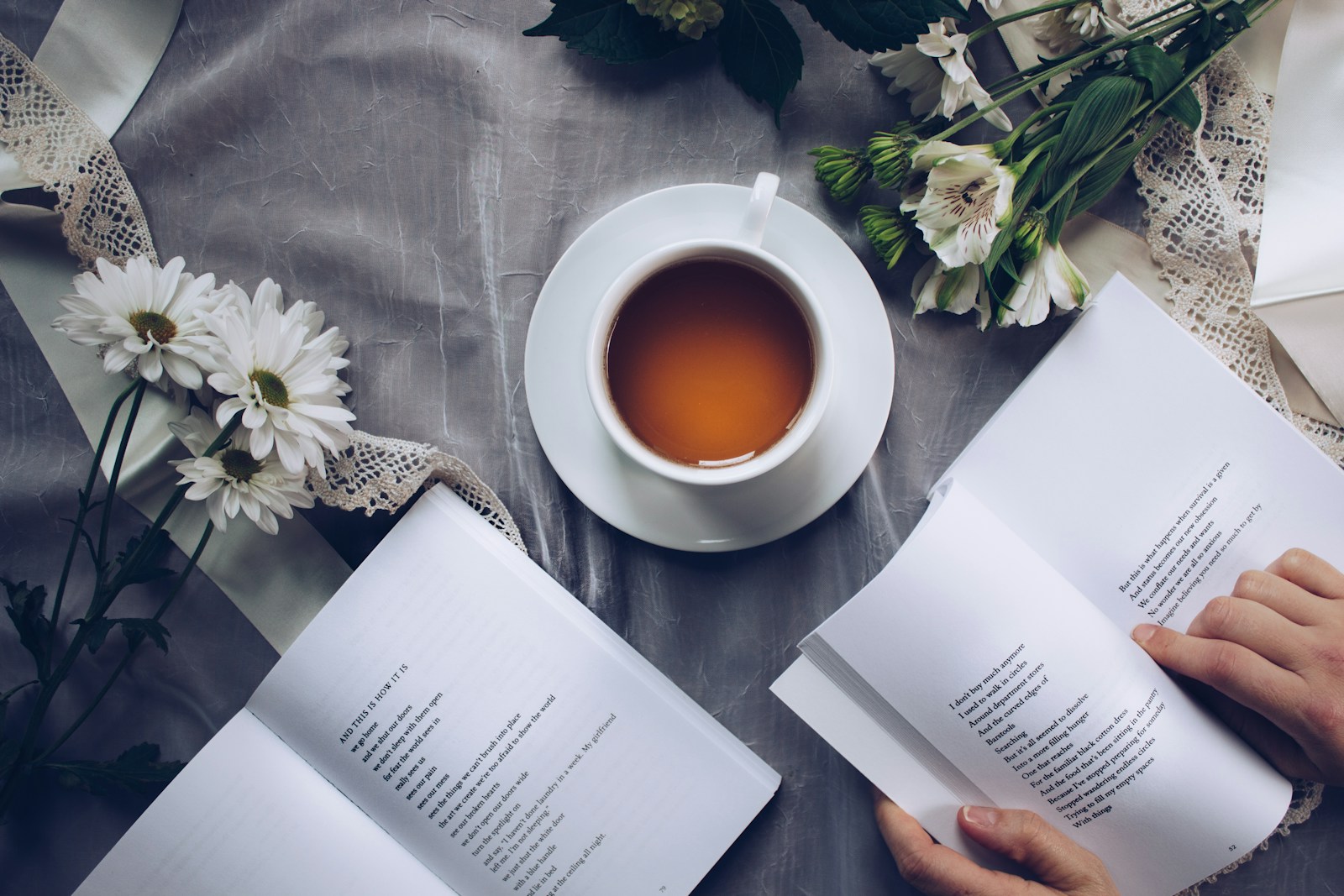




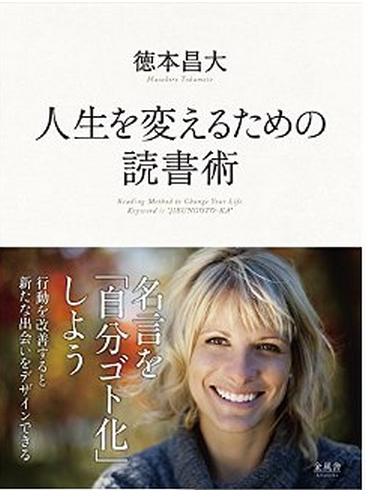






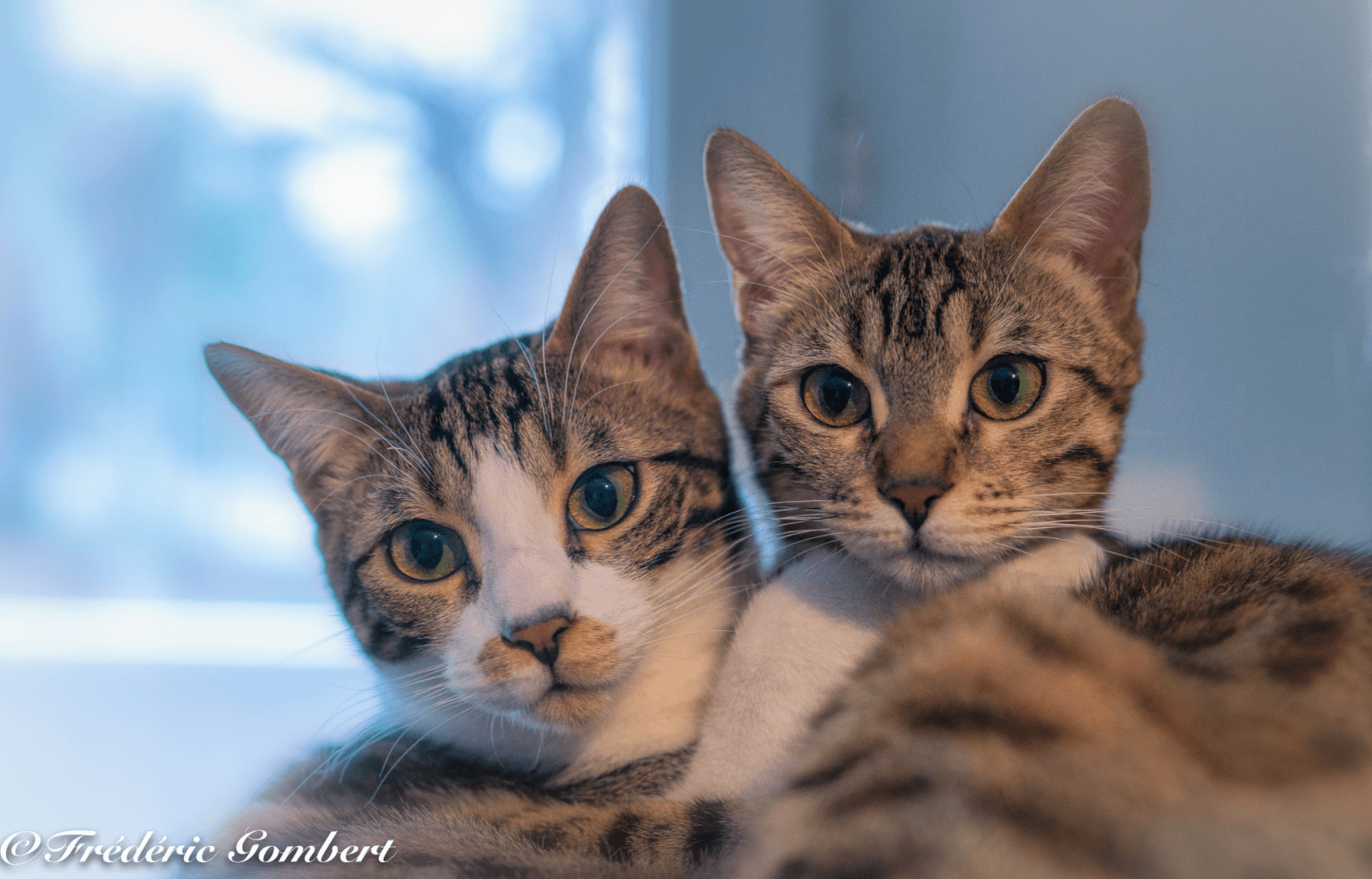





コメント