忙しいのに退化する人たち やってはいけない働き方
デニス・ノルマーク , アナス・フォウ・イェンスン
サンマーク出版
忙しいのに退化する人たち やってはいけない働き方(デニス・ノルマーク , アナス・フォウ・イェンスン)の要約
現代人の多くは「忙しさ」に埋もれ、本質的な成果を生まない“偽仕事”に時間と労力を費やしています。メールや会議、タスク処理に追われているにもかかわらず、成長実感が薄れ、慢性的な疲労だけが残る──そうした働き方の根本的な問題を、デニス・ノルマークとアナス・フォウ・イェンスンは文化的・歴史的視点から鋭く分析します。本書は仕事の意味を問い直し、「時間」ではなく「価値」で働きを測る思考への転換を促す知的フレームです。
私たちの労働時間が減らない理由、偽仕事とは?
誰かがプロセスを効率化して時間を節約する方法を編み出すたびに、ほかの誰かがその時間を使う新しい手段を見つけるのだ。(デニス・ノルマーク , アナス・フォウ・イェンスン)
毎日、予定はぎっしり詰まっている。会議、メール、チャット、資料作成、タスク管理──息つく暇もないほど働いているのに、なぜか成果が見えないことが多いのではないでしょうか?
時間も体力も使っているのに、仕事への充実感は得られず、成長の実感も薄れていく。むしろ、思考は浅くなり、疲労だけが蓄積していくように感じる。このような感覚は、決して一部のビジネスパーソンだけの悩みではありません。多くの人が同じような停滞感を抱えながら、今日も忙しさに追われています。
忙しいのに退化する人たち やってはいけない働き方は、現代の働き方に潜む根本的な矛盾──「忙しさ」と「成果」の関係──に鋭く切り込み、その背景にある構造的な問題、「偽仕事(pseudowork)」の存在を明らかにした一冊です。
人類学者のデニス・ノルマークと哲学者のアナス・フォウ・イェンスンは、忙しさ=生産性という常識を、歴史的・文化的背景をふまえて丁寧に問い直しています。経歴や立場の異なる2人の視点が交差することで、現代の働き方に潜む「思考の落とし穴」が浮かび上がってきます。
さらに、ケーススタディや豊富な文献・論文に基づいた議論を通じて、「私たちは本当に意味のある仕事に時間を使っているのか?」という根源的な問いに向き合うきっかけを得られます。
石器時代の人々の年間労働時間はおよそ700時間程度だったとされます。農耕社会への移行により、13世紀イングランドの農民は平均して年間1,620時間を働くようになりました。そして現代のオフィスワーカーは、週40時間労働を前提とすれば、年間2,000時間を超える労働に従事しています。
文明の発展とともに生産性は向上してきたはずですが、皮肉にも私たちの労働時間はむしろ増加しているのです。この歴史的推移は、「なぜ私たちは今もなおこれほど長く働いているのか?」という疑問を改めて投げかけています。
現代のビジネスパーソンが陥りがちなのは、「偽りの生産性」という罠です。たとえば、即時のメール返信、目的の曖昧な会議、あるいは誰の意思決定にもつながらない報告──これらの行為は外から見ると忙しく働いているように映りますが、実際には本質的な価値を生み出していないケースが少なくありません。
著者たちは、私たちが日々当たり前のようにこなしている仕事のなかに、驚くほど多くの実体のない作業が紛れ込んでいると指摘します。表面的には忙しそうに見えても、実際には何の成果も生み出していない──それが彼らの言う「偽仕事(pseudowork)」です。そして、この偽仕事こそが、現代人を慢性的な疲労や無力感へと追い込んでいる主な要因だと断言します。
とくに現代のオフィスワークでは、「何もしていない」と感じながら時間が過ぎていく瞬間が少なくありません。これは単なる怠慢ではなく、「偽仕事」の一形態です。仕事の一部に意味を見出せず、成果にもつながっていないと感じているなら、その時間は実質的に“働いていない”のと同じかもしれません。
この「偽(pseudo-)」という接頭辞は、ギリシア語のプセウドス(pseudos)を語源とし、“偽り”や“嘘”を意味します。単語の先頭につけることで、見た目とは異なる実態を示します。たとえば偽名(pseudonym)は本名ではなく、偽科学(pseudoscience)は科学の体裁をとりながら科学的根拠を欠いています。つまり、偽仕事とは“仕事のふりをしているが、実際には本質を持たない働き”を意味するのです。
重要なのは、どれだけ働いているかではなく、そこから何が生まれているのかという視点です。人目を気にして動き回り、空虚なタスクをこなしていても、成果も成長も得られません。むしろ、ただ時間とエネルギーを消耗し、充実感とは程遠い働き方に身を置くことになるのです。
「仕事の一部は実体のないナンセンスにすぎず、なんの意義もなかったのだ」──デニス・ノルマークのこの言葉は、私たちの働き方に対する認識を根底から揺さぶります。見せかけの仕事に時間を奪われている現代人にとって、それは決して他人事ではありません。
さらに著者たちは、この「偽仕事」の多くは観客を前提に成立していると指摘します。つまり、誰かに見られていること、評価されていると感じることによって意味づけられている仕事が数多く存在するのです。
その証拠に、COVID-19のパンデミックによって多くの企業がリモートワークに移行した際、私たちは「誰の目にも触れない」状態で仕事をすることになりました。そしてそのとき初めて、普段やっていた仕事の中に「やらなくても問題がなかったこと」が少なからず含まれていたことに気づいたのです。
リモート環境では、単なる存在感やパフォーマンスでは評価されにくくなります。その結果、「やっているように見せる仕事」が次第に姿を消し、仕事の本質や価値そのものを問い直す機会が生まれました。観客がいなくなったことで、見せかけの仕事の多くが不要だったと明らかになったのです。私たちは何か重要な仕事をしていると見せかけ、忙しさを演技しているのです。
偽仕事とは何か?
偽仕事は無意味であり、重要な成果は何も生まず、影響力もない──それに取り組む人がどう考えていようと同じである。中身のない仕事は偽仕事だ。怠けは故意の偽仕事だ。 だが、ほかにも偽仕事はある。たとえば、やることをでっちあげるのも偽仕事だ。わざと仕事を避けているわけでは必ずしもなく、中身がまったくないわけでもないが、結局は瑣末なのでやはり偽といえる。 偽仕事は誰にも影響を与えない。少なくとも「本物の仕事」をしている人にはなんの影響も及ぼさない。偽仕事がなくても、世界は何事もなかったかのようにそのまま続いていくだろう。
私たちは今も忙しなく働き続けています。かつてケインズが予測したように、技術の進歩が労働時間を劇的に短縮し、週15時間労働が現実のものとなる──そのような未来は、未だ訪れていません。
原因は効率性の不足ではありません。むしろ、技術が進化するたびに、私たちは新たな業務やルール、手続きに囲まれ、終わりの見えない会議や読まれることのない報告書、実質的な成果の伴わないプロジェクトに日々の労力を費やすようになったのです。
効率化の果てに現れたのは、「働いているように見えるが、実際には何も生み出していない」という、疑似労働という現象でした。
ギャラップの調査によれば、西欧諸国における労働者のうち、仕事に積極的に関与している人は13%に過ぎず、大半が仕事への関心を失っているという現状が示されています。この数字は、私たちの働き方が無自覚と退屈に覆われていることを物語っています。
実は、疑似労働の本質は、成果も影響力ももたらさない業務に、相当な時間と資源が投じられているという点にあります。表面的には業務に見えるかもしれませんが、それは本質的な意味を欠いており、何かを変革したり前進させたりする力を持っていないのです。
著者らは、それを単なる怠慢とは切り離し、むしろシステムの中で生まれ続ける「必要そうに見えるが実質は瑣末な活動」と定義づけています。 とりわけデジタル化は、この問題をより複雑にしています。
本来、新しいテクノロジーは生産性を高めるための手段であるはずです。しかし現実には、入力や登録といった作業が増え、業務の可視化や監視のためのタスクが日常を圧迫する場面が少なくありません。ツールの導入自体が目的化し、「そもそも何のために導入するのか」という問いが置き去りにされてしまうケースも見受けられます。
デジタル化は決して万能ではなく、設計や運用を誤れば、現場にとって新たな負担となるリスクを抱えています。特に注意すべきなのは、デジタル化がしばしば疑似労働、すなわち本質的な価値を生まない余分な作業を生み出す点です。確かに、テクノロジーは何かをより速く、より効率的に行う可能性を秘めていますが、新たな「解決策」を導入する前に、そもそもそこに解決すべき問題が存在するのかどうか、自問する姿勢が求められます。
さらに、デジタル化は避けられない潮流として語られることが多く、私たちはその流れに「参加しなければならない」という無言の圧力を感じています。その結果として、新しいツールは本来の意味で業務を支援する存在ではなく、「これまで行ってきた作業を別の場所に登録するための仕組み」として受け止められがちです。
こうした状況では、テクノロジーがもたらすはずの効率性や自由が、むしろ逆に働く可能性もあるのです。 さらにトーンをカジュアルに、あるいはフォーマルに調整することも可能です。ご希望があればお知らせください。
著者らこうした課題に対処するためには、表面的な合理化や最適化ではなく、根源的な問い直しが必要だと述べています。つまり、「この業務は、何の目的で、誰にとっての価値を生んでいるのか」。こうした問いに向き合うことこそが、偽仕事から抜け出す第一歩になります。ときに愚問とされるような素朴な問いかけこそが、本質への道を開くのです。
本書に込められたメッセージは、著者たち自身の経験に裏打ちされたものです。ノーマークは、自身の職業生活の中で、「自分は意味のあることをしているのか?」という違和感を持ち始め、それが本書の出発点となったと語ります。同じ疑問を多くの人々が抱えていたことは、出版後に届いた無数の反響によって裏づけられました。
「忙しくはしているが、何もしていないに等しい」と語る声が、各地から寄せられたのです。 この問題は、民間企業だけでなく公共部門においても深刻です。たとえば、医師が患者のためというよりは、管理指標の達成のために栄養スクリーニングを行わなければならなかったり、成功の見込みが不透明なプロジェクトが管理職の思いつきで、次々と走り出したりする状況が紹介されています。
偽仕事とは、単に「何もしないこと」ではありません。それは、いかにも仕事らしく見えるが実質的に意味を持たない行動や、成果につながらない活動を指します。たとえば、忙しいふりをして過ごす時間、成果を生まないタスク、あるいは無意味なことを言ったり始めたりするための準備なども、すべて偽仕事の一部です。
明らかに時間の無駄であるとわかっていながら、新人社員にあてがうプロジェクトも同様です。また、やることがないことを隠すために必要もない文書整理を始め、自尊心を保つといった行動も、偽仕事に含まれると著者は指摘します。
Eメールは、本来私たちに自由をもたらすはずのツールでした。手紙よりはるかに速く、手軽にメッセージを送れると期待されていたのです。しかし実際には、1日に数通の手紙を書く代わりに、何百ものメールをさばくのに数時間を費やすようになったのです。メール以外にもSlackやメッセンジャーなど様々なツールに私たちは多くの時間を使うことで、自分を浪費させています。
パーキンソンの法則を逆さまにする!
世界一重要な法則 制限時間が短いほうが効率が上がる
テクノロジーの導入は加速を生む一方で、人を解放するどころか、より深く縛ることにもつながっています。時間を節約するはずの新技術が、逆に時間を奪う。これが、いわゆる「加速の合理的な不合理」と呼ばれる現象です。この逆説を理解することが、偽仕事の存在を理解する手がかりになります。
パーキンソンの法則によれば、ある仕事に10時間を与えれば10時間かかり、25時間を与えれば25時間かかるといいます。これは人が怠けるからではなく、与えられた時間の分だけ、仕事が複雑で重要なものに見えてしまうからです。職場では余剰人員に見られることを避けるため、誰もが時間を埋める何かをしようとします。こうして「やることがあるふり」をするための仕事が増え続けていくのです。
現代では、パワーポイントのスライドの枚数に応じて仕事の時間が伸びるという新たなパターンまで生まれています。 偽仕事の厄介な点は、それが一部の人の時間を奪うだけでなく、連鎖的に周囲の人々の時間も奪っていくことにあります。だからこそ、早く家に帰るべきだという主張は、単なる働き方の提案ではなく、生産性の向上に直結する考え方なのです。
かつての貴族にとって、何もしないことは地位や余裕の象徴でした。しかし現代では、その価値観が反転し、むしろ「忙しさ」こそが尊敬の対象となっています。企業の経営者やコンサルタントといった現代の成功者たちは、しばしば“新しい貴族”として見なされ、その多忙なライフスタイルが模倣されていきました。その結果、社会全体に「忙しいこと=有能で価値のある人間」という認識が根づき、忙しさそのものが一種のステータスと化してしまったのです。
実際にやることが増えたというよりも、忙しさ自体が価値を持つようになったのです。 このような価値観が職場にも影響を及ぼしています。たとえば、仕事には常に熱意を持って取り組むべきだという暗黙の期待があります。仮にそれが退屈で無意味な仕事であっても、熱意が感じられないと評価を下げられる。その結果、誰もが忙しいふりをし、予定表に虚偽の予定を入れて仕事を選び、偽仕事が増えていくのです。
「家に帰るべき」と言うこと自体が、非現実的な発言と受け取られてしまうような空気が出来上がっています。 製造業が海外に外注されても、オフィスワークの管理職は増え続けています。人はやるべきことを求め、組織は労働時間で賃金を支払う。そこで過ごす時間が成果に結びついているかは問われず、働いている「ふり」さえしていれば許容される風潮が根強く残っています。
このような考え方は、「忙しいこと」が美徳であるという誤った合理性に支えられています。いつか自由な時間が得られるという幻想もまた、その延長線上にあります。しかし、その「いつか」がやって来ることはないのです。
そして、労働時間と生産性が比例するという信念も、現実とはかけ離れている可能性があります。余計な時間は、往々にして他人の邪魔をしたり、無意味なプロジェクトを立ち上げることに使われるのです。 実際、一定の仕事が終わったら社員を帰宅させる企業ほど、生産性が高く、成長している傾向があります。だからこそ、組織は「忙しいのは良いことだ」という信仰を手放さなければなりません。
求められた価値を生み出したら、迷わず社員を家に帰す。このシンプルな判断が、働き方改革の本質であり、私たちが目指すべき働き方の未来ではないでしょうか。
使える時間いっぱいまで仕事がふくれあがるのなら、その反対もまた真でなければならない。仕事時間を減らしたら、与えられた短い時間で仕事を終えられるようになる。
時間を制限すれば、仕事のスピードは自然と上がる。パーキンソンの法則の裏を返せば、それは明らかです。実際にスタンフォード大学の研究では、労働時間が週50時間を超えると、生産性との相関が著しく下がることが明らかになっています。つまり、長く働けば働くほど良いという考えは、科学的にも根拠が乏しいのです。
偽仕事から脱却する方法
誰もが多忙でなくてはならず、絶えず世界と接触している必要があるというのは思いちがいだった。必要なのはコミュニケーションに時間を費やすのをやめ、本来の仕事を進めることだったのだ。
多忙であることが社会的な価値とされ、常に世界とつながっていなければならないという認識は、私たちの思い込みにすぎなかったのかもしれません。真に必要だったのは、ひたすらコミュニケーションに時間を費やすのではなく、自分の本来の仕事に集中することだったのです。
たとえばボストンコンサルティンググループでは、週に一度オフラインで働くことで、驚くほどの生産性向上が見られたと報告されています。常時接続を前提とした働き方が、必ずしも成果を生むとは限らないという事実を、私たちはもっと直視すべきです。
現在の働き方には、工業化社会の遺産が色濃く残っています。社会が変化したように見えても、実際にはかつての労働モデルに従って仕事の枠組みを維持しているだけです。私たちは自らを欺き、長時間働くことで高い成果が得られるという過去の常識に縛られています。
偽仕事を回避するためには、まず「仕事とは何か」「何に報いるべきか」という根本的な問いを再構築しなければなりません。労働時間が長いほど評価されるという価値観が、不要なタスクを温存し、新たな偽仕事を生み出す原因となっているからです。
管理や人事評価、出来高契約といった制度の複雑化は、果たして本当に組織のパフォーマンスを向上させるわけではないのです。
その一方で、ここ数十年のうちに監査、定量化、報告、会議といった管理的業務に携わる人々が激増したのは疑いようのない事実です。信頼が欠如した結果として、誰もがハムスターのように回し車を走り続けるような仕事環境に置かれていると著者たちは述べています。
多くの人が仕事を自らの価値の証明と結びつけており、労働時間を減らすことが自尊心への脅威と感じられてしまう現実も見逃せません。本来は人を自由にするはずの変化が、逆に心理的な抵抗を引き起こすのです。 では、私たちはどうすれば偽仕事から抜け出せるのでしょうか。
著者たちは、限られた時間のなかで集中して働き、仕事を終えたら早く家に帰るという、ごくシンプルな行動が大きな変化を生むと語ります。たとえ初めは周囲から浮いて見えたとしても、その行動が他の人にとっての選択肢となる可能性があります。仕事から離れた時間を、地域活動や生活の再構築にあてることが、人間らしさを取り戻す第一歩なのです。
日本の労働時間の大部分は、真の価値をあまり生み出さない仕事に費やされているのにちがいないのだ。
日本に目を向ければ、その問題の深刻さがいっそう明らかになります。OECD諸国のなかでも長時間労働が常態化しており、それに見合った生産性を確保できていないという矛盾が根底にあります。その背景には、複雑な承認フローや形式的な会議、「見せるための仕事」が根深く存在していることがあると著者たちは指摘しています。
私たちは何のために働いているのか。誰のために価値を届けているのか。この根本的な問いに向き合うことなくして、働き方の本質的な転換はありえません。ただ時間を埋めるように働くのではなく、どのような成果を生み出せたのかに焦点を移すべきです。
また、テクノロジーの進化に対する誤解も少なくありません。AIやデジタルツールは、本来、人間がより創造的で戦略的なタスクに集中できるようにするための支援装置であるべきです。ところが現実には、その運用が現場の声と乖離し、登録や入力といった事務的作業が増えただけで終わってしまうこともあります。新しい技術を導入する前に、解決すべき問題が本当に存在するのかを見極める視点が不可欠です。
無駄な会議を減らすためにまず必要なのは、その会議に本当に意味があるのかを疑い、「ノー」と言う勇気を持つことです。そして、会議を開催する際には、明確なアジェンダを事前に共有し、終了時刻を決めた上で時間管理を徹底することが、生産性を高める上で欠かせません。
仕事とは、単なるタスクの集積ではなく、人と人との関係性の中でこそ意味を持つ営みです。どれだけ専門性の高いスキルを持っていたとしても、そこに信頼や共感といった土台がなければ、持続的な成果にはつながりません。
多忙であることが評価の指標となってしまった現代の働き方において、私たちは改めて「本当に何を成し遂げたのか」という成果に目を向ける必要があります。そしてその成果を、時間ではなく意味で測るという新しい視点を育てることが求められています。
本書は、単なる働き方改革のマニュアルではありません。それは、私たちの時間の使い方、思考の枠組み、そして人生そのものの質に対して問いを投げかける知的なフレームであり、具体的な行動への呼びかけでもあります。
一見すると合理的に見える仕事の多くが、実は自由を奪う構造の一部になっているという指摘は、非常に示唆に富んでいます。 テクノロジー、制度、文化、そして私たち自身の意識。こうした複数の要素を同時に見つめ直すことで、ようやく未来の働き方を構想することができるのです。
本書が優れているのは、現状への批判にとどまらず、次に進むための実践的な視座を提示している点にあります。 今の働き方をそのまま続けていくことこそが、最大のリスクであることを教えてくれます。
そして著者たちは明確に提案します。まずは、早く家に帰ることを職場の当たり前にすることから始めようと。上司も部下もそれを当然のこととして受け入れ、仕事を終えたら退社する。そんな小さな一歩こそが、働き方の大きな転換につながるのだと語っています。
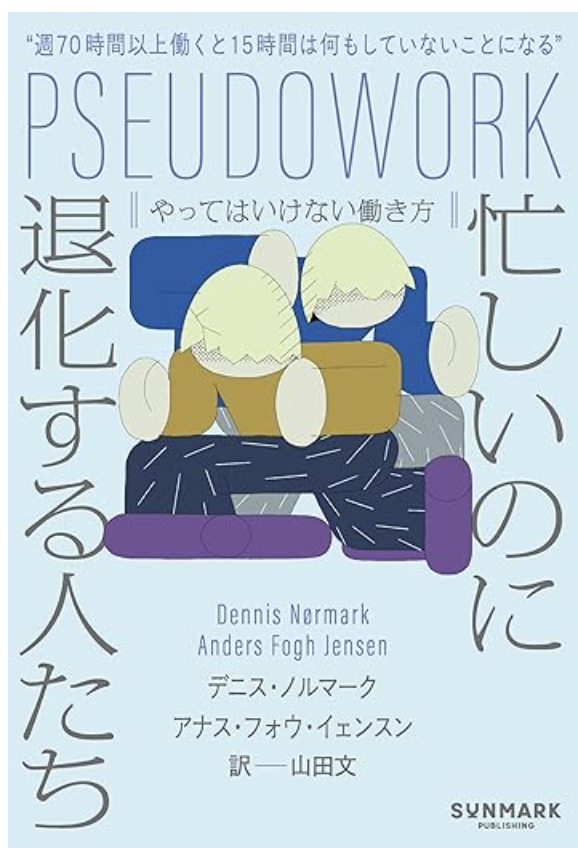




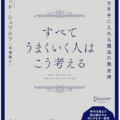


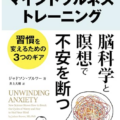

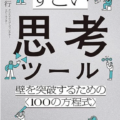
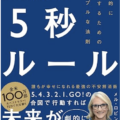
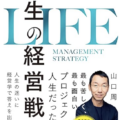


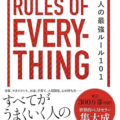



コメント