できる人の最強ルール101
リチャード・テンプラー
ディスカヴァー・トゥエンティワン
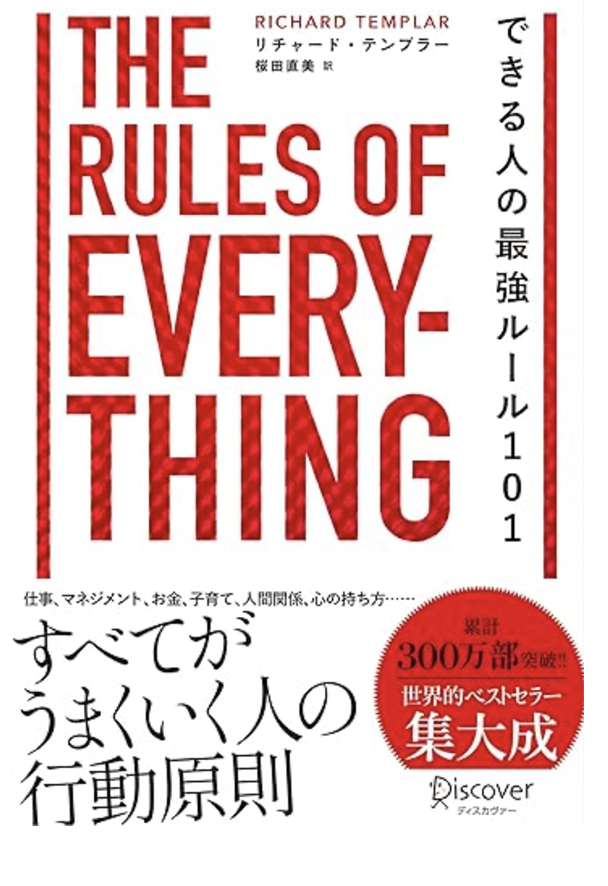
できる人の最強ルール101(リチャード・テンプラー)の要約
リチャード・テンプラーは25年以上の研究から、成功者の行動原理を分析し、仕事、人間関係、子育て、金銭管理など多分野での成功に共通するルールを見出しました。彼が提示するルールは制約ではなく、思考を柔軟にし、行動にポジティブな変化をもたらすもので、私たちの可能性を広げる鍵となっています。
できる人たちのよいルールとはなにか?
よいルールとは、態度や考え方を変えるきっかけになる力を持つルールだ。よいルールを活用すれば、今までとは別の角度から問題や状況に対処することができるようになる。(リチャード・テンプラー)
リチャード・テンプラーが25年以上にわたる研究の集大成として発表した最新作は、成功者たちの行動原理に深く迫った一冊です。彼は幸せで成功している人々の日常や決断のプロセスを丹念に観察し、そこから普遍的なルールを見出すことに尽力してきました。
その分析対象は、仕事での成果、人間関係の構築、子育て、金銭管理など多岐にわたり、これらの分野で成果を上げるための共通の原則が存在することを明らかにしています。
一般的に、ルールという言葉は制約や縛りといった否定的なイメージを持たれがちです。しかし、テンプラーが提示するルールはそれとは異なり、私たちの思考を柔軟にし、行動にポジティブな変化をもたらすものです。これらは私たちの可能性を広げ、新たな視点を与える鍵となります。
彼の研究の特徴は、単なる理論や仮説にとどまらず、実際に成功を収めた人々の行動をもとにルールを構築している点にあります。テンプラーが挙げるルールの中には、一見すると平凡なものもあれば、例えば、変な人と付き合うなど一度自分の考え方を変えないと理解しにくいようなものもあります。
今日は101のルールから私が重要だと思ったルールを紹介します。テンプラーは自分の存在感を際出させることが大事だといいます。
あわただしく働いていると忘れてしまいがちだが、オフィスであなたの存在感を際立たせるというのは大切なことだ。自分の手柄をきちんと周りに気づかせることで初めて、あなたは一目置かれるようになり、ひいては昇進のチャンスにもつながる。
著者は、職場での存在感を高めることの重要性を強調しています。忙しい日常の中では、自分自身の価値や成果を周囲に示すことを忘れがちですが、それがキャリアにおける成功の鍵であると彼は述べています。オフィスでの存在感を際立たせることで、一目置かれる存在となり、昇進や新しいチャンスが訪れる可能性が高まるのです。
存在感を示す第一歩として、何よりも重要なのは自分の仕事を誰よりもうまくやることです。優れた成果を出すことが、最も説得力のあるアピールになります。
そして、成果を出すためには、自分の時間とエネルギーを本当の仕事に集中させることが必要です。テンプラーは、社内政治やゴシップ、人間関係の駆け引きといった仕事の本質とは関係のない活動に振り回されないようにすべきだと語ります。それらに時間を費やすのではなく、業務の質を高めることに注力するべきなのです。
このアプローチの中核にあるのは、「本当の仕事」とは何かを見極め、それに集中する力です。仕事に対する真剣な姿勢や、徹底的なコミットメントは、周囲の評価を自然と高めます。他の同僚が余計な雑務や無駄話に時間を使っている間に、自分の役割を確実に果たし、成果を積み重ねることで、リーダーシップを発揮できるようになります。
また、存在感を示すためには、成果を適切に伝えることも重要です。謙虚さは美徳ですが、自分の努力や達成を周囲に理解してもらわなければ、成果は評価されません。テンプラーは、自分の手柄をしっかりと周囲に認識させることが必要だと述べています。
ただし、それは押しつけがましい自己アピールではなく、自然な形で成果を共有する方法を模索するべきです。たとえば、会議や報告の場で自分の取り組みを説明すること、上司に進捗を適切に報告することなどが考えられます。
さらに、自分の仕事に全力を注ぐことで得られる充実感や自信は、仕事以外の場面でもプラスに働きます。仕事に集中し、周囲にポジティブな影響を与える姿勢は、職場の文化をも向上させる可能性があります。テンプラーの教えは、ただ個人の成功を目指すだけではなく、周囲との協力や職場全体の発展にも寄与するものです。
チームの力を引き出すためのルール
その仕事が社会にどう貢献するかを語る。
自分の仕事が社会にどのように貢献しているのかを考えることは、働く上で極めて重要です。それは、ただ日々の業務をこなす以上に、自分の役割や使命を理解し、より深い意義を見出すことにつながります。しかし、忙しい日々の中でその意識を持つのは難しいと感じる人も多いかもしれません。
自分の仕事がどのように世の中の役に立っているのかを実感するためには、まず自身の仕事が生み出す影響に目を向ける必要があります。たとえば、直接顧客と接する職業では、自分の提供する商品やサービスが人々の生活をどのように向上させているかを意識することができます。
一方で、裏方の業務や間接的な仕事に従事している場合、その成果が組織全体を支え、結果的に社会に貢献しているというつながりを見つけることが求められます。 自分の仕事が社会に与える価値を信じるためには、内省が欠かせません。自分の心の奥深くにある「なぜこの仕事をしているのか」という問いに向き合い、本当の動機や情熱を探るのです。
そこに見つかるのは、単なる報酬や生活のためではなく、他者や社会に対する貢献の意識であることが多いのです。その気づきが、日々の業務に対する取り組み方を根本から変えるきっかけとなります。
また、自分の仕事が社会に与える影響を明確にすることは、モチベーションを高めるだけでなく、周囲の人々と仕事の意義を共有する助けにもなります。
職場の同僚や上司、さらには顧客に対して、自分の仕事がどのように世の中のためになっているかを語ることができれば、それが信頼や共感を生み、より良い協力関係を築けるようになります。
あなたのチームに、他人をほめる文化を定着させよう。上司が部下をほめるだけでなく、メンバー同士でもほめ合う環境が理想だ。「きみならできる」という言葉がいつも聞こえてくるようなチームを目指さなければならない。
チームに他人をほめる文化を定着させることは、単なる士気の向上にとどまらず、個々のメンバーの成長を促し、チーム全体のパフォーマンスを引き上げる重要な要素です。ほめる文化は、単に「よくやった」と言葉をかけるだけではありません。
それは、他者の努力や成果を心から認識し、それを言葉にして伝えることで、相手に承認と信頼を与える行為です。 この文化を根付かせるには、リーダーが模範を示すことが欠かせません。上司が部下をほめるのはもちろんのこと、メンバー同士でも自然にほめ合える環境を築くことが理想です。
たとえば、「そのアイデア、素晴らしいね」「このタスクの進め方、すごく効率的だったよ」といった具体的なほめ言葉が、日常的に交わされるチームを目指します。
このような言葉が飛び交う職場は、心理的安全性が高まり、メンバーが互いに安心して力を発揮できる場となります。 「きみならできる」という言葉が常に聞こえてくるようなチームは、単に結果を求めるだけでなく、メンバー一人ひとりの可能性を信じ、背中を押す空気が根付いています。このような環境では、失敗や課題に直面した際も、メンバーが恐れずに挑戦し続けることができます。
ほめる行為は、相手の自己肯定感を高めるだけでなく、その人自身に「もっとできる」という信念を抱かせる強力なツールとなるのです。 また、ほめる文化は、チームの一体感を生む効果もあります。他者の努力を認めることで、メンバー同士の信頼関係が深まり、それが協力や助け合いの土台となります。
たとえば、誰かが困難なタスクを乗り越えたとき、その努力を全員で称賛することは、チーム全体にポジティブな影響を与えます。そうした瞬間が積み重なることで、チームは「共に成長し、成功する集団」という強いアイデンティティを持つようになります。
ただし、ほめる文化を定着させるには、ほめ方にも注意が必要です。安易なほめ言葉や心のこもっていない賞賛は、かえって逆効果となる場合があります。ほめる際には、具体的で誠実な言葉を選び、相手の努力や成果をきちんと理解していることを伝えることが大切です。
最終的に、他人をほめる文化が根付いたチームは、仕事の成果だけでなく、人間関係の質や働きがいの向上にもつながります。それは、単にタスクをこなす場所ではなく、メンバーが自分自身の成長を感じられる場所へと変わります。このようなチームを築くことは、リーダーとしての最大の挑戦であり、最高の成果でもあるのです。
自分らしいルールをつくる!
もしかすると、あなたが今まで会った中で、いちばんおもしろい人かもしれない。”変な人”を遠ざけていたら、本当におもしろい人に出会うチャンスをみすみす逃してしまう。安全地帯の外に出ると人生が豊かになるということも知らないままだ。失うものなど何もない。自分から話しかけてみよう。
「変わっている」という言葉は、しばしば私たちの偏見や先入観を映し出す鏡となっています。日々の生活の中で、周囲と異なる行動や考え方を持つ人を目にすると、つい「変な人」というレッテルを貼ってしまいがちです。しかし、その人たちは単に自分の信念や価値観に従って、誠実に生きているだけなのかもしれません。 私たちは無意識のうちに、社会の規範や周囲の期待に合わせようとする傾向があります。
その中で、既存の枠にとらわれず、自分の道を歩む人々は、ある意味で大きな勇気を持っているとも言えるでしょう。彼らの生き方には、型にはまらない自由さと、自分の信念を貫く強さが垣間見えます。
そういった「変わった人」との出会いは、私たちの人生を豊かにする貴重な機会となりえます。一見すると理解しがたい行動や考え方も、その人と対話を重ねることで、新しい視点や気づきをもたらしてくれるかもしれません。
実際、歴史上の偉大な発見や革新的なアイデアの多くは、常識にとらわれない「変わった人」たちによってもたらされてきました。 私たちが「変な人」と距離を置くとき、それは実は自分自身を守ろうとする防衛本能かもしれません。
しかし、その壁を取り払い、心を開いて接してみると、思いがけない発見や刺激的な交流が待っているかもしれないのです。 社会の中で「変わっている」と見なされる人々は、実は私たちに大切なことを教えてくれています。それは、他人の目を気にしすぎずに、自分らしく生きることの大切さです。彼らの存在は、私たちの社会に多様性をもたらし、新しい可能性を示してくれる貴重な存在なのです。
失敗をしても嘆くことはない。できるだけたくさん失敗をやらかしておけば、その後の人生が順調になるのだから。
人は誰しも年を取ります。しかし、年齢を重ねることがそのまま賢さや成功に直結するわけではありません。むしろ、人生が豊かになり、より良いものになるためには、若い頃からの経験や積み重ねが重要です。その中でも特に大切なのが、「失敗」という経験です。
失敗は、誰もが避けたいと思うものです。それは挫折感や恥ずかしさ、後悔といった感情を伴うことが多いためでしょう。しかし、失敗を恐れずに挑戦することが、後の人生を大きく左右します。若い頃にたくさん失敗しておくと、年齢を重ねたときに新しい失敗の数が自然と減ります。
それは、失敗の経験を通じて、何がうまくいくのか、どのように行動すれば失敗を回避できるのかを学ぶからです。 若い頃の失敗は、ある意味で「リスクを取る余地」がまだ大きい時期に起こるため、ダメージが相対的に小さいことが多いです。
例えば、学生時代やキャリアの初期段階では、大きな責任を伴わない失敗であれば、比較的簡単に修正することが可能です。その時期に多くの試行錯誤を経験し、自分の限界や能力を知ることで、将来的な選択や行動が洗練されていきます。
また、失敗は私たちに重要な学びを提供してくれます。それは、自分自身を見つめ直す機会であり、成長のきっかけとなるものです。失敗を通じて得られる知識や洞察は、成功体験から得られるものとは異なります。成功は一時的な満足感をもたらしますが、失敗は深い自己反省を促し、次に進むための糧を与えてくれるのです。
さらに、若い頃にたくさん失敗を経験しておくことは、心理的な柔軟性を育む助けにもなります。失敗への耐性がつくことで、予想外の事態や困難に直面したときも、冷静に対処できるようになります。このような「失敗の免疫力」が備わっていると、年を重ねた後の人生で、大きなトラブルに見舞われても動じることが少なくなります。
最初のうちはルールを厳格に守る。やがてルールが完全に身につき、第二の本能になる。そうなったら、自分の直感を信じよう。 折に触れてルールを読み直し、忘れていることや、誤解していることがないか確認し、自分が苦手なルールに真剣に取り組んでほしい。いずれ自分の判断に自信を持ち、直感のほうが本よりも頼りになると確信できるようになるだろう。
テンプラーが提案するルールの実践方法は、私たちの成長のプロセスそのものを示唆しています。彼は、最初はルールを厳格に守ることの重要性を強調しています。
この段階では、ルールを完全に理解し、自分の行動の基盤に据えることが求められます。慣れないうちは意識的に取り組む必要がありますが、やがてそれが習慣となり、第二の本能として自然と身についていくのです。
ルールが完全に身についた段階では、テンプラーは自分の直感を信じることを推奨しています。これは、ルールを忠実に守る経験を重ねることで、自らの判断力に対する自信が培われるからです。
ただし、直感を頼りにする際も、ルールに立ち返る習慣を忘れてはなりません。折に触れてルールを読み直し、忘れてしまったり誤解したりしている部分がないかを確認することが重要です。特に自分が苦手とするルールについては真剣に取り組むべきだ、とテンプラーは述べています。
このプロセスを繰り返すことで、私たちはルールを自分の中で生きたものにし、最終的には本能的な判断の質を高めることができるのです。 現代社会において、このようなルールの実践は特に重要な意味を持ちます。私たちは情報過多の中で多くの選択肢に迫られ、時に迷いや不安を感じることがあります。
このような状況では、シンプルで明確なルールが指針となり、思考や行動に確実性をもたらしてくれます。そして、この指針がただ効率を向上させるだけでなく、私たちの人生そのものをより豊かで満足のいくものにしてくれるのです。
さらに、ルールの実践には自己成長という側面もあります。厳格にルールを守ることから始め、徐々にそれを自分のものにし、最終的には直感を磨く。この過程は、自分自身を深く理解し、成長させるための貴重な機会となります。
そして、最終的にはルールを超え、自分自身の判断に自信を持つことで、より自由で力強い生き方を手に入れることができるのです。 テンプラーの提案するルールは、単なる規範ではなく、私たちを新しい次元へと導く道しるべです。それは、私たちが迷いや混乱に直面したときの支えであり、また、さらなる成長を遂げるための鍵となります。この考え方を実践することで、私たちはより充実した人生を築いていけることでしょう。
本書は、成功を目指す人々にとって実践的な指南書であると同時に、日々の行動や考え方を見直す機会を提供するものです。ルールがもたらす可能性に目を向け、それを自分自身の成長や幸福のために活用することの意義を、テンプラーは私たちに教えてくれます。








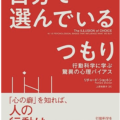





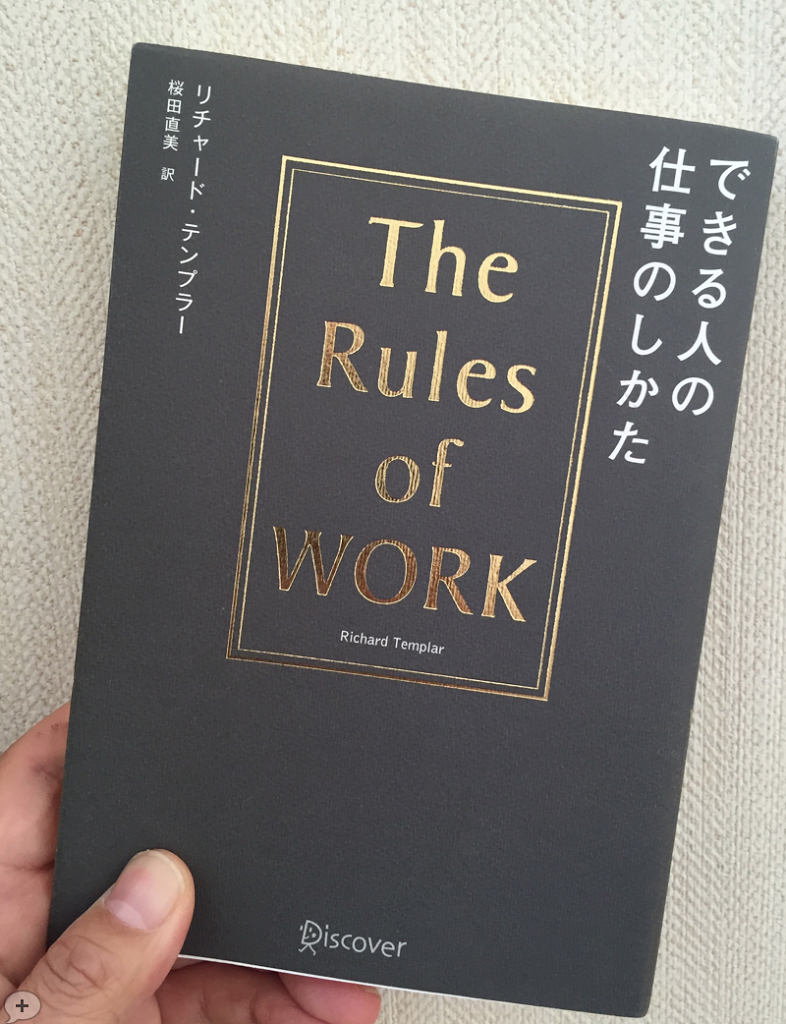
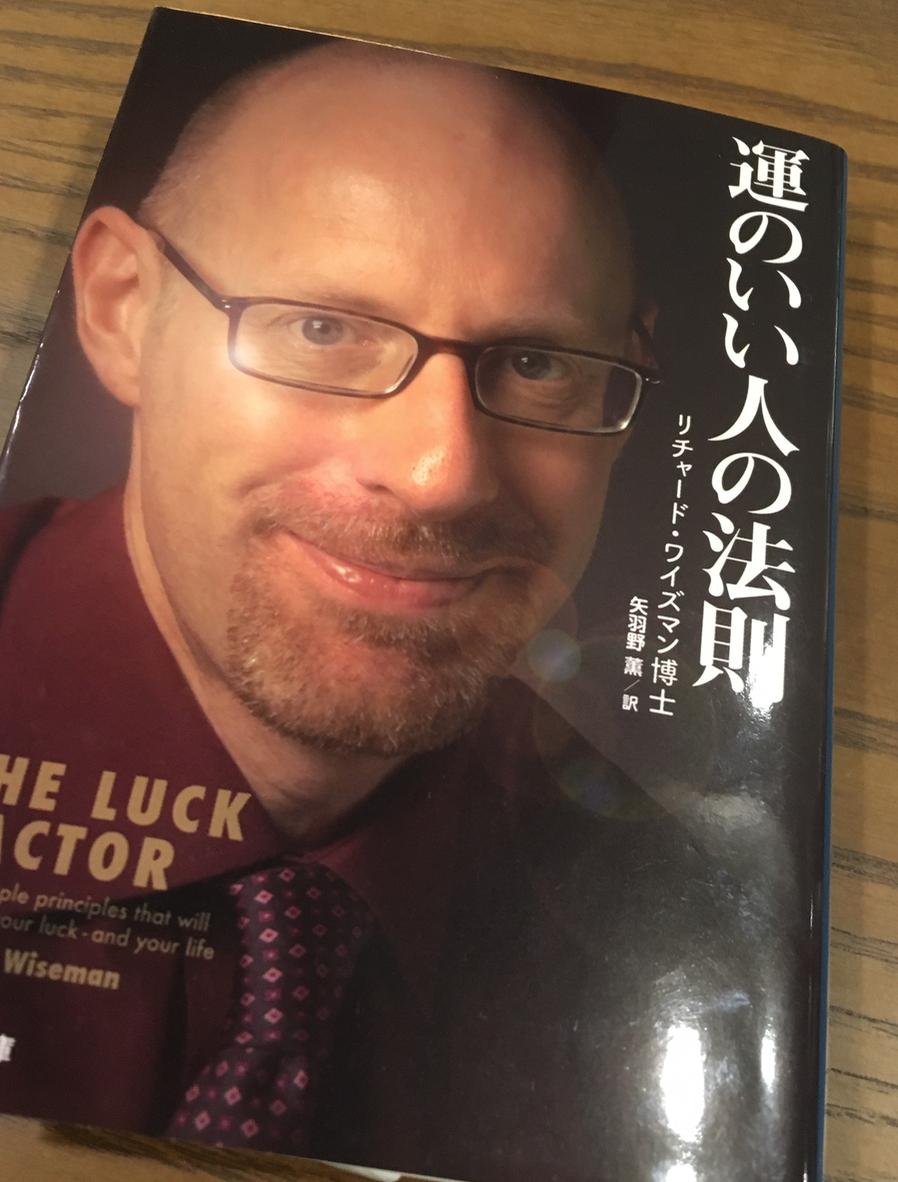


コメント