 ノスタルジアは世界を滅ぼすのか: ある危険な感情の歴史
ノスタルジアは世界を滅ぼすのか: ある危険な感情の歴史
アグネス・アーノルド=フォースター
東洋経済新報社
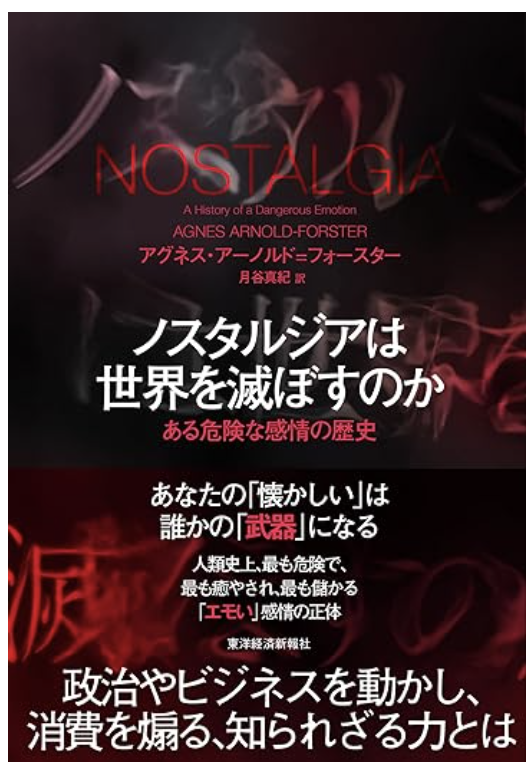
ノスタルジアは世界を滅ぼすのか: ある危険な感情の歴史(アグネス・アーノルド=フォースター)の要約
『ノスタルジアは世界を滅ぼすのか』は、懐かしさという感情が歴史や政治、文化にどう結びついてきたかを描く一冊です。かつては「望郷病」と恐れられたノスタルジアは、今では心理学や脳科学でセラピー効果を持つ感情と再評価されています。しかし広告や政治に利用され、過去を美化し現実を曇らせる危うさもあります。その力を未来にどう生かすかが問われています。
ノスタルジアの変遷とは?17世紀の病が、21世紀の処方箋になるまで
今のノスタルジアは昔のとは違う。(アグネス・アーノルド=フォースター)
「ノスタルジア」という響きには、不思議な力があります。懐かしさと切なさ、安心と痛みが同時に押し寄せ、私たちを一瞬で過去へ連れ戻す感覚を呼び起こします。
ノスタルジアは世界を滅ぼすのか: ある危険な感情の歴史は、そんな複雑な感情が歴史の中でどのように意味づけられ、政治や社会、医学や文化と結びついてきたのかを多角的に探る意欲的な一冊です。
著者のアグネス・アーノルド=フォースターは歴史学者であり、TVドラマやドキュメンタリーのコンサルタントとしても活動するなど幅広い領域で活躍しています。本書では、南北戦争や1970年代の広告業界、トランプやブレグジット、中世趣味や脳科学まで、多彩な事例を通してノスタルジアの二面性を鮮やかに浮かび上がらせています。
そもそもノスタルジアという言葉は、1688年にスイス人医師ヨハネス・ホーファーが命名したとされています。「nostos(帰郷)」と「algos(痛み)」というギリシャ語を組み合わせた造語で、当時は「物理的に離れた故郷への強い思慕」による心身の不調を指していました。
戦乱が続いていた17世紀ヨーロッパでは、スイス出身の傭兵たちがノスタルジア(望郷病)に陥り、食欲不振や不眠、抑うつ症状などを訴え、時には命を落とすこともあったといいます。アメリカ南北戦争でも同様の症状が多くの兵士に見られましたが、20世紀初頭には、ノスタルジアは医学的な診断名から姿を消していきます。
興味深いのは、この感情がもともとは「時間」ではなく「場所」に向けられていたという点です。つまり、ノスタルジアとは過去の時代ではなく、「今いる場所から遠く離れた、元いた場所」への帰属欲求だったのです。
しかし、交通インフラが整備され、鉄道や蒸気船、さらには航空機によって帰郷が現実的な選択肢になると、ノスタルジアの意味合いも変わっていきます。「行けるはずだった場所」ではなく、「二度と戻れない時間」への感傷へとそのベクトルが移行していったのです。
現代では、心理学や脳科学の分野において、ノスタルジアはむしろポジティブな感情として再評価されています。 かつては「過去にとらわれた後ろ向きな感情」と見なされがちでしたが、心の健康に寄与する面が多くあることが明らかになってきたのです。
たとえばノスタルジアに浸ったあと、人は気分が前向きになり、自分の人生に意味や目的を感じやすくなる傾向があります。自尊心が高まり、未来への楽観的な見通しが生まれやすくなるといった心理効果も確認されています。
さらに、友情や人とのつながりを強く実感し、「自分は守られている」「愛されている」という感覚が育まれることもあります。こうした感情が、不安をやわらげ、他者への思いやりや友好的な行動を引き出すといった報告もあるのです。
脳科学の進展により、「古き良き時代」を思い出すときに抱く懐かしさには、セラピー的な効果があることもわかってきました。ノスタルジアは、ただの感傷ではなく、心のコンディションを整える“感情のサプリメント”のような役割を果たしているのです。
ノスタルジアは、政治やビジネスの世界でも戦略的に活用されてきました。 たとえば広告や商品開発、ライフスタイル提案などにおいて、「かつての良き時代」への憧れが購買意欲や共感を喚起する仕組みが定着しています。
ノスタルジアの力は、政治の世界でも強力な武器になります。ドナルド・トランプ前大統領が掲げた「Make America Great Again」は、まさにその典型例です。過去の栄光を理想化し、現代の不安を懐かしさで包み込みながら、人々の感情を動かす。ここには論理も事実も必要ありません。必要なのは、「あの頃はよかった」と信じたくなる感情だけです。
ノスタルジアは、不安定な現代に対する防御本能としても機能しています。経済格差、気候変動、政治不信。未来を信じきれない多くの人々が、「かつて確かに存在した安心感」へと目を向けるのは、ごく自然な流れかもしれません。
しかし同時に、そうした感情を巧みに利用しようとする力も存在します。権力を持つエリート層が、ノスタルジアを都合よく再構成し、非道な手段で人々の支持を集める。ブレグジット(イギリスのEU離脱)もまた、そうしたノスタルジア政治の文脈の中で語られるべき事例だと言えます。
この現象は西側に限ったものではありません。ソビエト連邦の崩壊から長い年月が経った現在も、ロシアや東欧の多くの地域では、かつての社会主義体制へのノスタルジアが根強く存在しています。自由民主主義や市場経済への移行は、紙の上では「解放」だったかもしれませんが、現実には多くの人にとって困難な時代でした。
深刻な失業、雇用の不安定さ、経済の停滞と格差の拡大。1990年代から2000年代にかけての混乱は、「資本主義=希望」という物語を急速に色あせさせました。
その結果、人々の関心は、現実から目をそらすように、かつての保障された生活への回顧に向かっていきました。たとえそれが実際の社会主義の姿とは異なるとしても、「今よりはマシだったかもしれない」という想像上の過去は、人々にとって十分に魅力的だったのです。
ノスタルジアは、私たちに意味やつながりを感じさせ、心を落ち着けてくれる力があります。けれども同時に、過去を美化することで、現実から目をそらさせてしまうリスクも抱えています。
広告や政治に悪用されるノスタルジア
心理学者によれば、50~65歳の年齢層は楽しかった思い出を喚起する持ち物に特に愛着を示すという。その理由づけはなんともわびしい。将来楽しいことが起きる可能性が小さくなるにつれて、過去の楽しい思い出は増大するつまり、人生が終わりに近づくほどノスタルジックな傾向は高まるのだという。
ノスタルジアという感情が、マーケティングの現場で本格的に活用され始めたのは、1970年代のことです。広告会社やメディアは、「懐かしさ」に訴える演出を通じて、中高年層の感情を刺激し、消費行動につなげる手法を積極的に展開していきました。
たとえば、ギャツビー風のファッションが再流行し、過去をテーマにしたCMや映画が立て続けに作られ、骨董品や収集品の市場が急成長したのもこの時期です。それらは単なるレトロブームではなく、50〜60代の記憶と価値観に響くよう計算された「ノスタルジック・マーケティング」の表れでした。
しかし、1970年代にノスタルジアに駆られた人々が求めた「過去」には、一貫性がありませんでした。 過去のものであれば何でもよく、時代背景などはほとんど関係なかったのです。求められさえすれば、歴史上のどの時点でも「古き良き時代」の役を担わされました。
1975年に『アメリカ』誌は、「1920年代へのノスタルジアは終わったかもしれないが、新たな波が水平線上に現れている」と報じ、次に注目されたのは1870年代でした。 つまり、ノスタルジアは選び抜かれた過去への敬意というより、「今」に対する失望を埋め合わせるための素材として、時代を問わず利用されていたのです。
このようにして、ノスタルジアは感情であると同時に商品にもなりました。 ビジネスとして成立する以上、ノスタルジアの再利用はどんどん加速していきます。 メディア産業は、かつて自分たちが生み出した過去のコンテンツを、より速いスパンで掘り返すようになります。
技術革新の急速な進展も、ノスタルジアの高まりに拍車をかけてきました。TVプロデューサーのリンジー・ターナーは、90年代は「人々が画面を見上げていた最後の時代だった。下を向いてスマホ画面を見るのではなく」と指摘します。ノスタルジアには人々を安心させる効力もあるのです。
時代が進むほど、あの頃のあたりまえが、今では特別な価値を持つようになります。 たとえば、スマートフォンで音楽を聴くのが日常となった今、あえてレコードプレーヤーやカセットテープで音楽を楽しむ若者が増えています。ノイズ混じりの音質や、手で扱う手間そのものが「新鮮」で「味わい深い」体験として受け止められているのです。
こうした現象は、実は目新しいことではありません。 電話や鉄道といった新しい技術が登場した時代にも、人々は「かつてのシンプルな生活」に戻りたいと感じていました。技術によって生活が便利になる一方で、どこかで「何か大切なものが失われていく」という感覚が、時代を超えて共有されてきたのです。
急激な変化に伴う不安やストレスを和らげるために、人々は昔も今も、スローな暮らしや穏やかな時間を求めてきました。 ノスタルジアは、その揺れる気持ちにそっと寄り添い、過去の記憶を優しく呼び起こしてくれる存在なのです。
本書が際立っているのは、ノスタルジアという感情の二重性に対する深い理解にあります。ノスタルジアは、私たちの心を慰め、安らぎを与えてくれる存在である一方で、社会や政治の不安定さを助長し、現実から目をそらす装置にもなり得ます。個人の内面に留まる感情でありながら、集団心理や制度の方向性にまで影響を及ぼすという点で、きわめて複雑な性質を持っています。
社会理論家のスヴェトラーナ・ボイムは、ノスタルジアにはユートピア的理想主義の要素さえあると述べ、ノスタルジアと進歩はジキルとハイドのように対比をなすが、実は同じコインの裏表なのだと指摘しました。彼女はまた、ノスタルジアは必ずしも過去志向に限らず、未来志向にもなり得ると語っています。
つまり、過去を懐かしむことが、かえって未来のビジョンを描くきっかけにもなるということです。 さらに彼女は、ノスタルジアを「復興的ノスタルジア」と「反省的ノスタルジア」に分類しています。復興的ノスタルジアは、過去をそのまま取り戻そうとする保守的な態度であり、制度や秩序の復元を求める傾向があります。
一方、反省的ノスタルジアは、過去を批判的に見つめ直し、「なぜ懐かしさを感じるのか」を問いかけるような、開かれた態度を持っています。つまり、ノスタルジアは「過去を再定義し、変化への支持を勝ち取るための道具」としても機能するのです。
ノスタルジアはありふれた存在であり、心の痛みと喜びの両方をもたらす。
今がどれだけ悪く見えても、「古き良き時代」は本当に良かったのでしょうか。 ノスタルジアが理想化する過去は、しばしば都合よく編集された記憶にすぎません。 実際の歴史を冷静に振り返ってみれば、今よりも不平等で、不便で、不寛容だった時代の方が多かったことに気づきます。
だからこそ、「今がひどい」と感じるときこそ、「かつてはもっとひどかった」という現実に目を向ける視点が、必要なのかもしれません。 ノスタルジアには、「昔の方がよかった」と思わせる、不思議な魅力があります。 その魅力に心を委ねること自体は、決して悪いことではありません。ただ、その甘さに酔いすぎると、今を生きる視野が曇ってしまうこともあるのです。
大切なのは、懐かしさに浸るだけで終わらせず、それをどう生かすかを考えること。 ノスタルジアを過去への逃避ではなく、未来への糧として扱うには、感情の奥にある構造や欲望を見つめ直す必要があります。
ノスタルジアは、私たちを過去へ連れていく感情であると同時に、未来へ向かう想像力を呼び覚ます力でもあります。どのように向き合うかによって、それは現実からの逃避にもなれば、新しい希望を見出すきっかけにもなり得るのです。だからこそ、著者が語る「人によって何にでもなれるノスタルジアの力のせいなのだ」という言葉を、忘れずに心に留めておきたいと思います。




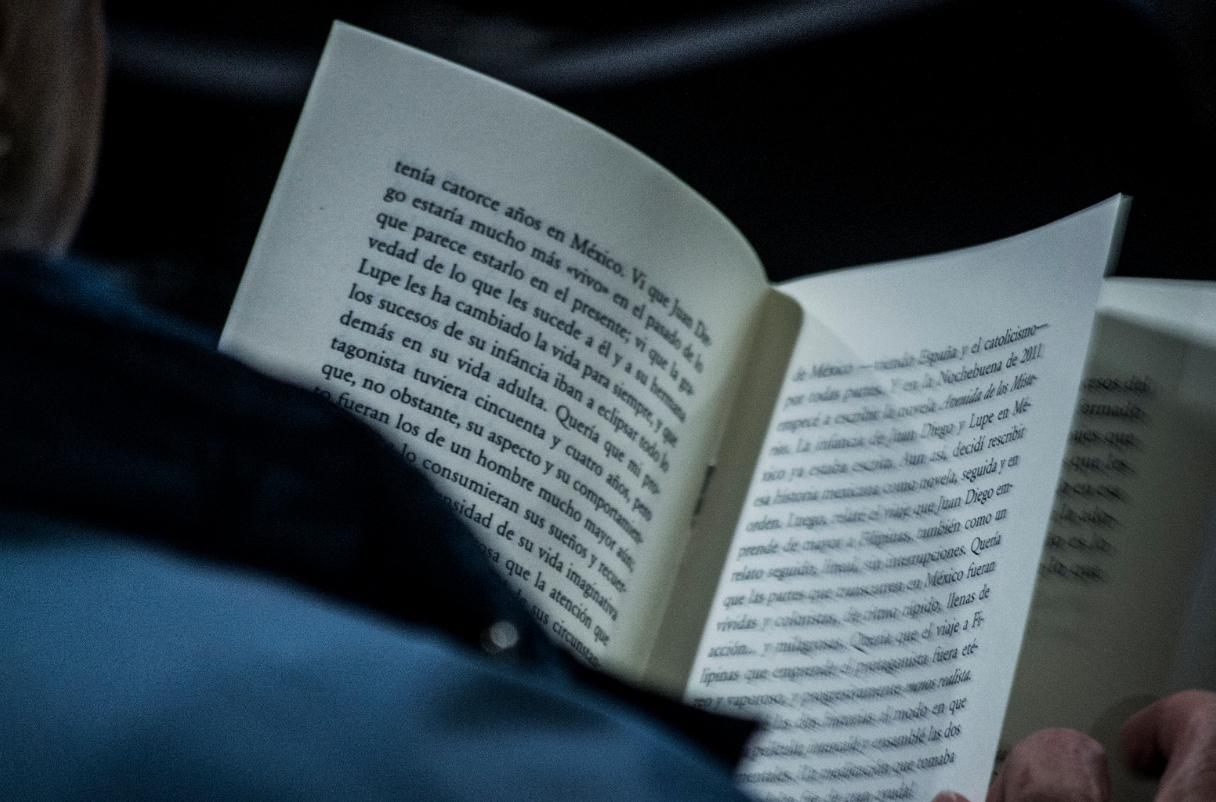



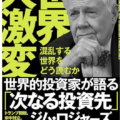

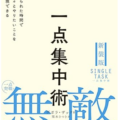

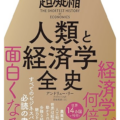
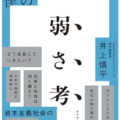


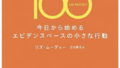
コメント