ヒトの意識の進化をたどる
ジョン・パリントン
丸善出版

ヒトの意識の進化をたどる (ジョン・パリントン)の要約
『ヒトの意識の進化をたどる』は、人間の意識を神秘ではなく、進化・生物学・社会の連続の中で捉え直す一冊です。言語と道具使用が脳を変え、情動さえも文脈化したことを示し、人間の意識が動物の延長でありながら質的に異なる理由を明らかにします。脳・身体・社会の相互作用として意識を描き、なぜ人間の心はコンピュータでは再現できないのかを静かに問いかけます。
ヒトの脳の力とは?
ヒトにユニークな特徴である体系的な道具使用と言語を支えているのは、これらの特徴を有意義に扱う能力を与えてくれるように進化した脳である。私たちが、道具を使ってまわりの世界を変容させ、言語を使って互いにコミュニケーションをとることは、進化の過程で、また個々のヒトの発達の過程で、明らかにほかとは異なる方法でヒトの脳を変容させたのである。 (ジョン・パリントン)
ヒトの意識の進化をたどるは、人間の意識という、あまりにも身近でありながら正体のつかめないテーマを、驚くほど現実的かつさまざまな視点から掘り下げていく一冊です。オックスフォード大学の生物学者のジョン・パリントンは、意識を神秘や哲学的思考の中に閉じ込めるのではなく、進化学・生物学・社会学という連続した時間軸の中に置き直そうとします。
本書で繰り返し語られる中心的な考えは、人間の自己意識が偶然に芽生えたものではなく、進化の過程で積み重なってきたいくつかの特徴の相互作用の結果だという点です。
特に強調されるのが、言語能力と道具を設計し使用する能力です。人間は環境に適応するだけの存在ではなく、環境そのものを変えながら生きてきました。その行為が再び脳に跳ね返り、思考の仕方や意識のあり方を変えてきたという循環的な視点が、本書全体を貫いています。
言語についての記述は、とりわけ印象的です。人間の言語は、単なる音声や合図の集合ではなく、抽象的な表象同士を文法によって結びつける精密なシステムです。この仕組みがあるからこそ、過去や未来、個人と社会、さらには目に見えない価値や意味といったものまで共有できるようになりました。
1970年代に行われた、チンパンジーやゴリラに手話を教える試みが紹介されますが、彼らが文法を獲得できなかったという事実は、人間の言語能力が量的な違いではなく、質的に異なるものであることを示しています。ここに、人間と類人猿のあいだに横たわる決定的な断絶があるのです。
ただし、言語だけを切り離して人間を理解することはできません。本書が強調するのは、言語と道具、そして脳が三位一体となって進化してきたという点です。人間の脳は、サル類よりも大きいというだけでなく、構造や機能の結びつき方そのものが異なっています。
道具を使い、言語で考え、社会の中で他者と関わるという経験が、進化の過程でも、個人の成長過程でも、脳を変容させてきました。ここで語られる脳は、固定されたハードウェアではなく、経験によって書き換えられ続ける動的な存在として描かれています。
重要なことに、ヒトの内的意識が言語で構成されていることにより、他の動物にはないヒトの意識に特別な社会的次元を与えている。言葉は社会の中で生まれたものなので、必然的に私たちの思考に社会的な意味をもたせることになる。
発話、いわゆる外言を研究することによって、脳がどのように言葉を生み出しているのかを手がかりにしながら、内言の性質を推測することができます。さらに、人は自分自身の内言を内省的に観察し、その特徴をある程度まで把握することも可能です。
複数の研究や方法を総合すると、内言は他者との会話で用いられる発話とは、いくつかの重要な点で異なっていることが示唆されます。 内言は、外言と比べてはるかに速く進み、意味の流れもより滑らかであるように見えます。
また、内言には単一の形しかないわけではなく、十分に言葉にならない未完成な思考に近いものから、他者に向けた発話を組み立てる直前の段階にあるものまで、いくつかのタイプが存在すると考えられます。
重要なのは、人間の内的意識が言語によって構成されていることで、人間の意識には他の動物には見られない社会的な次元が付与されている点です。
言葉は社会の中で生まれ、社会の中で使われてきたものである以上、私たちの思考もまた必然的に社会的な意味を帯びることになります。内言が現在の状況だけでなく過去の記憶を伴っているとすれば、私たちの内的意識には、両親や兄弟、教師、友人、同僚といった他者との過去の相互作用が深く染み込んでいると考えるのが自然でしょう。
言語が人間の内的意識の主要な構造であることは確かですが、それと同時に、道具もまた人間であることの意味を形づくる重要な要素です。
人間の特徴は、道具を通して周囲の世界と相互作用することにとどまらず、世代を超えて道具を改良し、変化させ続けてきた点にあります。この累積的な変化は、人類全体のあり方だけでなく、個々の人間の意識にも長期的な影響を及ぼしてきたと考えられます。
人間の意識はどこまで動物で、どこから言語なのか?
脳と他の身体部位の間の神経結合が示されていることと、器官自体が化学物質を放出し、他の身体部位や脳に影響を及ぼしていることが最近の研究により明らかになってきたからである。
人間の意識を考えるとき、どうしても避けて通れない問いがあります。それは、人間の意識がどこまで動物に由来するもので、どこからが人間に固有のものなのか、という問いです。怒りや恐怖、性欲といった情動を動物が示すことについては、多くの人が自然に受け入れるでしょう。
しかし、妬みのような感情になると、話は一気に複雑になります。 妬みという感情は、自分が持っていないものを、他者が持っているという状況を想像できなければ成立しません。この「想像する」という能力は、抽象的な表象を操作する力と深く結びついています。
その意味で、妬みは単なる感情というよりも、言語や概念を扱う能力に支えられた、人間に特有の情動だと考えられます。
もっとも、私たちは日常生活の中で、ペットのネコやイヌが飼い主に愛情を示したり、他の動物に関心が向いたときに嫉妬しているように見えたりする場面に何度も出会います。
そのため、動物も人間と同じように愛や嫉妬を感じているのではないか、という直感が生まれるのも無理はありません。この点については、確かに簡単に結論を出すことはできず、さらなる議論が必要でしょう。
ただし、こうした感情をそのまま動物にも当てはめてしまう姿勢には注意が必要だと著者は指摘します。それは、人間の意図や感情を、無自覚のうちに動物に投影してしまう擬人観につながる危険を含んでいるからです。ネコやイヌは、人間と共に暮らすよう特別に進化してきた動物であり、その意味で非常に特異な存在です。
たとえば、イヌが悪さをして叱られそうになったときに反省しているかのような態度を見せたり、食卓の食べ物を欲しそうに見つめたりする行動は、人間の感情を読み取り、人間社会に適応するために発達してきた組み込まれた行動だと考えられます。
それは人間的に見えるかもしれませんが、人間と同じ内的意識を持っていることの直接的な証拠とは限りません。 情動を、より動物的なものと人間にユニークなものに分けることは、一つの整理の方法ではあります。
しかし本書がより強く打ち出しているのは、人間の意識そのものが、言語と道具使用によって根本的に変容してきたという点です。その結果、空腹や恐怖といった、一見すると最も原始的で生物学的に見える情動でさえ、人間においては動物とは異なる形をとっているはずだと著者は指摘します。
砂漠で命の危険にさらされながら感じる空腹と、高級レストランで料理を待ちながら感じる空腹とでは、同じ「空腹」という言葉で表されていても、その意味はまったく異なります。ここで重要なのは、情動が常に文脈に依存しているという点です。
そして人間の場合、その文脈は言語と文化によって極度に複雑化しています。情動は、身体反応であると同時に、意味づけられた経験でもあるのです。 嫌悪、怒り、恐怖、欲望、愛、幸福、嫉妬、妬み、悲しみ、驚き、退屈といった情動は、いずれも人間社会の中で経験されますが、それを引き起こす出来事は実に多様です。
その多様性こそが、情動反応そのものの質を変えていると考えられます。こうした情動に深く関与する脳領域として、扁桃核の存在が知られています。扁桃核は恐怖や不安、さらには喜びにも関与する、進化的に古い脳領域で、いわゆる辺縁系の一部です。
しかし近年の研究によって、人間の脳には、他の動物には見られない新たな脳領域間の結合が存在することが明らかになってきました。そして、こうした結合が情動反応のあり方そのものに影響を与えていると考えられています。概念的かつ抽象的に考える能力は、情動をそのまま受け取るのではなく、距離を取ることを可能にします。
これは、前頭前野のような高次の意識と関係する脳領域が、扁桃核のような情動中枢を強く制御していることを示していると考えられます。 さらに近年では、意識や情動が脳だけで完結しているわけではないという理解も広がっています。脳と身体の間には密接な神経結合があり、各器官が分泌する化学物質が、脳を含む他の部位に影響を与えていることが分かってきました。
情報は脳から身体へ一方的に流れているのではなく、身体から脳へも常に送り返されています。 その複雑な相互作用を象徴する存在が、オキシトシンというホルモンです。オキシトシンは妊娠や出産、授乳に関わる物質として知られていますが、同時に脳内でも機能し、社会的認知や絆形成、親行動などに影響を与えます。
恋愛や性的興奮とも関係があり、「恋愛ホルモン」と呼ばれることもありますが、この呼び方は誤解を招きやすいものです。オキシトシンは良好な絆だけでなく、否定的な関係性の記憶を強化したり、集団の外にいる他者を排除する方向に働いたりすることもあります。ここからも、情動が社会的文脈と切り離せないことが見えてきます。
こうした議論を踏まえると、人間の意識は、脳内の情報処理だけで説明できるものではありません。言語を通じた社会との関係、道具や文化的技術との相互作用、そして身体全体で生じる化学的・生理的変化が、長い時間をかけて重なり合うことで成立しています。意識とは固定された機能ではなく、環境との関係の中で絶えず変化し続ける過程なのです。
この視点に立つと、コンピュータと人間の違いもはっきりと見えてきます。コンピュータは、与えられたルールとデータに基づいて計算を行う装置であり、自身の経験によって世界との関係性そのものを変えていく存在ではありません。
一方、人間の意識は、言語や道具、社会的文脈、身体感覚によって常に書き換えられています。同じ刺激であっても、それをどう感じ、どう意味づけるかは、その人がどのような環境で生き、どのような関係性を築いてきたかによって大きく異なります。
人工知能がどれほど高度になったとしても、人間の意識をそのまま再現することが難しい理由はここにあります。情動は単なるデータではなく、身体と社会の中で形成された文脈そのものだからです。
コンピュータは人間の思考を模倣することはできても、人間のように世界の中で生き、その世界に意味を与えながら変化していく存在にはならないのです。
ヒトと他の動物の差異は何から生まれたか?
ヒトだけが言語を介してまわりの世界を概念化できるので、ヒトの意識は他の動物の意識とは異なるというものである。このことにより、過去から学び、未来に異なるタイプの世界を想像することができる。
言語は単なる情報伝達の手段ではなく、社会の中でつねに変化し続ける実践です。一般に言語使用域は、コミュニケーションに一定の規則性を与える一方で、社会的・政治的な変動の影響を受け、同時に日常生活の中で生じる微細な変化にも開かれています。
話者同士の関係性、互いの能力や地位、会話の目的や主題、さらにはその発話がどのような文脈に位置づけられるのかといった要素が、言語使用域の中に一時的に凝縮されます。
言語がこのように社会的力学を内包する存在であることを、ロシアの思想家ヴァレンティン・ヴォロシノフは、きわめて象徴的に表現しました。彼は、単語とは「異なる方向性をもった社会的アクセントが衝突し交差する小さな闘技場」であり、個人の口から発せられる言葉は、社会的諸力の生きた相互作用の産物であると述べています。
言葉は辞書的な意味を運ぶだけではなく、社会の緊張や価値観、力関係をその都度引き受けながら使われるものなのです。 この点に注目すると、言語使用域が単に人と人との相互作用を媒介するだけでなく、人間の意識そのものに深く関与していることが見えてきます。
もし人間の意識が、あるレベルでは複数の声がせめぎ合う対話的な構造をもっているのだとすれば、意識を物質的に説明しようとする際には、言語がどのように意識を組織化しているのかという問題と、意識が生物学的な脳の活動として生じているという事実とを、切り離すことはできません。 そのためには、脳の構造と機能を具体的に結びつけて理解する必要があります。神経科学はこの数十年で、この課題に対して着実に前進してきました。
たとえば視床下部は、脳深部に位置する小さな構造でありながら、体温、食欲、渇き、体内時計、性欲といった生存に不可欠な機能を調節しています。この領域が損傷すれば生存そのものが脅かされることからも、その重要性は明らかです。
脳損傷の研究は、視床下部に限らず、脳の各部位の役割を理解するうえで重要な手がかりを与えてきました。手術や事故、戦争などによって生じた脳損傷の症例から、海馬が記憶において中心的な役割を果たしていることや、小脳が反復運動の制御に関与していること、扁桃核が恐怖反応に深く関係していることなどが明らかになっています。
また、モデル動物の特定の脳領域を選択的に操作する研究手法も、こうした知見の蓄積に大きく貢献してきました。 ただし、神経科学で多用されてきたマウスやラットといったげっ歯類の脳は、人間の脳とは大きさだけでなく構造や分子レベルの性質においても大きく異なります。このため、人間の意識を理解するためには、サル類を含む霊長類の脳研究が今なお重要な意味を持ち続けています。
人類は二足歩行を獲得し、手を自由に使えるようになったことで、道具の設計と使用を本格化させました。それに伴い、社会構造が変化し、言語の発達や脳の大型化、構造的再編が連鎖的に進んだと考えられます。ただし、こうした変化は、すでに他の動物とは異なる進化の道を歩んでいた霊長類の脳を基盤として起こったものです。
人類の歴史の大部分は、小規模な狩猟採集集団としての生活でした。そのため、狩猟採集社会を理解することは、人間の意識が最初に形成された社会環境を考えるうえで重要な手がかりとなります。
ただし、現存する狩猟採集社会は現代文明の影響を受けており、先史時代の直接的な証拠も限られています。道具の痕跡から一定の推測は可能であっても、当時の人々の内面を直接知ることはできません。それでも、協力や役割の尊重、争いの抑制を重視する傾向が強かったことは、多くの研究から示唆されています。
言語が人間の意識を変容させてきた以上、内言やその他の表象が脳内過程にどのような影響を与えているのかを検討することは、意識のダイナミクスを理解するうえで不可欠です。ただし最終的には、意識を脳内の分子や細胞レベルのメカニズムとして説明しなければなりません。その際、神経科学が明らかにしてきた脳の構築や、人間と他の動物との生物学的差異が重要な手がかりとなります。
本書では、脳波が複数の脳領域の活動を調整し、とりわけワーキングメモリに関わる過程を統合している点が強調されています。脳波が意識理解の鍵となる可能性は、人間以外の動物にも当てはまるでしょう。
しかし人間の場合、注意の切り替えを支えるこの仕組みに加えて、言語が脳波を通じて作用し、他の動物には見られない高次で先導的な役割を果たしている点が決定的に異なります。単語の意味や文法構造をもつ言語が、脳内活動の組織化に深く関与しているからです。
私たちは他者の意識の内部に直接アクセスすることはできませんが、人間は発話に加え、文学や芸術、音楽や映画といった文化的営みを通じて、他者の知性や感受性に触れることができます。
これらの表現は、個人の内面を超えて、人間社会の矛盾や、人間であることの意味そのものに対する洞察をもたらすことがあります。 人間の意識と脳機能の関係を探究する理由は、哲学的関心にとどまりません。統合失調症や感情障害といった精神障害を理解し、よりよい診断や治療につなげることも重要な目的です。
本書の中心的な主張は、人間だけが言語を通じて世界を概念化できる存在であり、その結果として人間の意識は他の動物の意識とは質的に異なるという点にあります。
人間は過去から学び、未来の異なる世界を想像し、さらに世代ごとに新しい道具や技術を設計することで、計画的に世界を形づくる力を獲得しました。その力は破壊にも創造にも向かい得ますが、創造力と想像力を正しく用いるならば、自然と調和し、技術が人間の生活を豊かにする社会を築く可能性も残されています。
重さ1.5キログラムほどの、無機質に見える脳から、こうした文明と想像力が生み出されてきたという事実そのものが、人間の意識の特異性を静かに物語っているのです。
本書は、意識を特別視しすぎることも、単なる錯覚として切り捨てることもありません。私たちが日常的に当然のものとして受け取っている「考える」「感じる」「自分である」という感覚が、いかに長い時間と複雑な相互作用の積み重ねによって形づくられてきたのかを、わかりやすく教えてくれる一冊です。
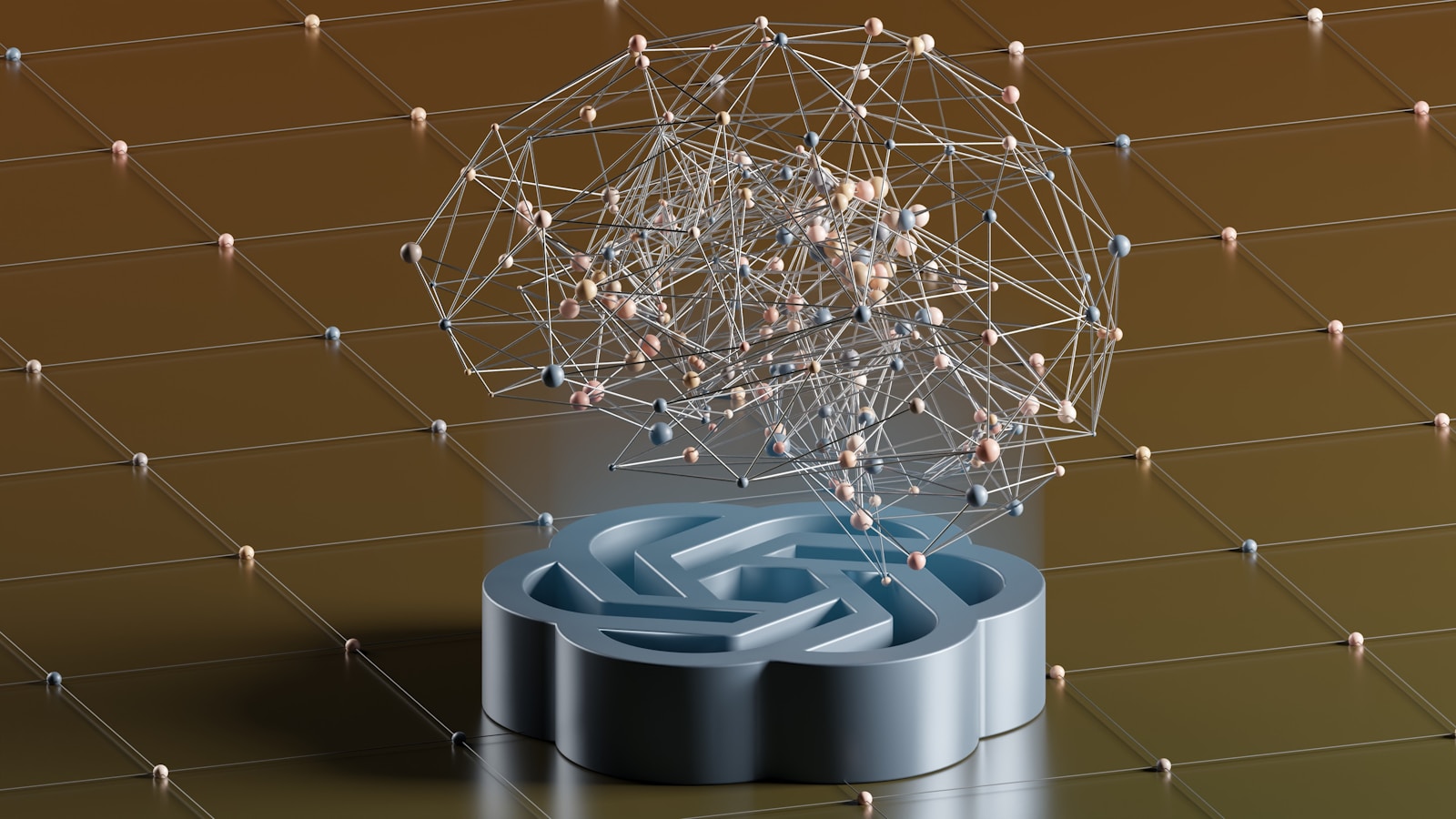


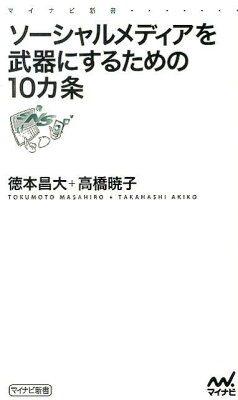





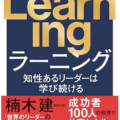








コメント