カウンセリングとは何か 変化するということ
東畑開人
講談社

カウンセリングとは何か 変化するということ (東畑開人)の書評
臨床心理士の東畑開人氏の『カウンセリングとは何か』は、「作戦会議」と「冒険」という二つの視点から、生活支援と実存的変化の両面を描き出します。アセスメントを謎解きとして捉える洞察、インテーク面接の役割、心の働きを捉えるケーススタディを通じて、現代のカウンセリングの実態を明らかにしています。
カウンセリングとは何か?
晴れの日ではなく、雨の日の心。日常ではなく、非常時の心。これを謎解きして、理解する。ここに僕らの専門性があり、それを専門用語で「アセスメント」と呼びます。カウンセリングで話を聞くのは、究極的には「理解」するためである。(東畑開人)
「カウンセリング」という言葉を知らない人は、いまやほとんどいないでしょう。けれど、その実態について、具体的なイメージを持てている人がどれほどいるでしょうか。話を聞いてもらう場所、心の悩みを相談するところ──そうした印象はあっても、そこで実際に何が行われているのか、そしてそれがどんな専門的意味を持つ営みなのかを、言葉で明確に説明できる人は多くありません。
むしろ、何となく縁遠いもの、あるいは特別な人のためのものとして、どこか自分の生活の外側に置いてしまっている人が大半ではないでしょうか。
しかし、心の問題は、私たちの誰もが人生のどこかで直面しうる可能性のあるものです。特に、何かが崩れたとき、大切なものを失ったとき、自分自身の存在が揺らいだとき――そんな「雨の日の心」「非常時の心」において、カウンセリングの本当の意味と価値が浮かび上がってきます。
晴れやかで安定した日常の中では見過ごされがちな心の動きも、嵐の中では大きく揺れ、その背後にある深いテーマが浮き彫りになります。カウンセラーの専門性とは、まさにこうしたトラブルに際した心に潜む謎を読み解き、言葉にして、理解しようとすることにあります。
この「理解する」という営みは、単に話を聞くという行為にとどまりません。カウンセラーは、クライエントが語るエピソードの中に現れる微細な違和感や言葉の選び方、沈黙の意味にまで耳を澄ませ、そこから問題の構造や背景にある人生の脚本を読み取ろうとします。
その謎解きのプロセスを、専門的には「アセスメント」と呼びます。アセスメントとは、単なる状況把握ではなく、非常時の心を深く理解するための高度な心理的分析であり、カウンセリングの核心に位置づけられる重要なステップです。晴れの日ではなく、雨の日の心をこそ読み解く。そこに、カウンセリングの真の価値があるのです。
カウンセリングとは、心の問題で苦しんでいる人に対して、心理学的に深く理解し、その理解に基づいて、必要な心理的な介入を行う専門的な営みです。ただ話を聞くだけではなく、「その人の苦しみはどこから生まれているのか」「どこにその人らしさが隠れているのか」を見つけ出し、少しずつ変化の芽を育てていく。そしてその変化は、ときに人生そのものを変える力を持ちます。
本書カウンセリングとは何か 変化するということは、そんなカウンセリングの営みを、専門家の立場から――しかし驚くほど分かりやすく描き出しています。
著者は「謎解き」というメタファーを用いながら、名探偵シャーロック・ホームズやワトソンとの対比を通じて、カウンセリングの実態をわかりやすく解き明かしていきます。
東畑開人氏は、20年にわたる臨床経験をもとに、「カウンセリングとは何をする営みなのか」「そこで何が起きているのか」、そして「なぜ“話す”ことで人は変わるのか」という本質的な問いに真正面から向き合います。 これまでどこか遠く、つかみにくかったカウンセリングの姿が、本書を通してぐっと身近に感じられるようになるはずです。
カウンセリングは終わりに至るまで、ずっとアセスメントが行われ続ける営みです。心はすぐにわからなくなるからこそ、何度も何度も理解し直し、その都度「謎解き」を積み重ねていく。そのプロセスそのものが、まさにカウンセリングの本質なのです。
この「謎解き」がもっとも戦略的に行われる特別な時間、それが「インテーク面接」と呼ばれるカウンセリングの導入段階です。 この最初の出会いの場で、カウンセラーは専門家としての力を発揮します。ユーザーの生活環境や性格、問題の経緯を丁寧に聴き取りながら、「何が原因で問題が起きているのか」「どうすれば改善できるのか」という仮説=“説明モデル”を組み立てていきます。
インテーク面接の時間は、ざっくり3つに分かれています。最初の40分で情報を集め、頭をフル回転させて原因を分析します(解明)。次の10分で、その仮説をユーザーにわかりやすく語り(説明)、最後の10分で今後の方針について提案し、一緒に決めていきます(提案)。この一連のやり取りを通じて、カウンセリングの方向性が共有され、土台が築かれます。
また、実はインテーク面接は、申し込みから当日までの「待つ時間」も含めて始まっています。まるでお見合い前の探り合いのように、カウンセラーはすでにユーザーに想像力を向け始めているのです。
この面接は、単なる準備段階ではありません。ユーザーが「変われるかもしれない」と感じ始める、大切な出発点です。 丁寧な見立てとわかりやすい説明、そして「ここから一緒にやっていく」という姿勢が、これから時間をかけて変化を育てていくための、確かな土台となるのです。
作戦会議としてのカウンセリングと冒険としてのカウンセリング
作戦会議としてのカウンセリングは生活に関わります。日常を立て直すこと、毎日を維持すること、現実を破局の脅威から守ることを目指す。生存を守る。冒険としてのカウンセリングは人生に関わる。誰とともに生きるか、何のために生きるか、自分とは何か。今まで生きてきた物語をつまびらかにし、紡ぎ直すことが試みられる。実在に取り組む。
本書でとりわけ印象的なのは、「作戦会議としてのカウンセリング」と「冒険としてのカウンセリング」という二つのフレームを提示している点です。前者は「生活を守るため」の支援、後者は「人生を生き直すため」の取り組みです。
作戦会議としてのカウンセリングは、日々の生活を立て直すための現実的な支援です。経済的な不安、仕事や家庭でのストレス、人間関係の軋轢など、目の前の現実に破綻の危機があるとき、まず必要なのは「生き延びる」ための知恵とサポートです。
カウンセラーはそのとき、ボクシングのセコンドのように、冷静な第三者としてクライエントを支えます。必要があれば医療や制度とも連携し、身体や生活のリズムを整える。身体や環境への介入によって、まず現実を動かし、生活を再建する。それが作戦会議の目標です。
ここで行われるのは、主に現実に働きかけるための4つの介入です。身体そのものにアプローチする〈バイオロジカルな介入〉、周囲の環境や支援資源を動かす〈ソーシャルな介入〉、身体と心の接点に働きかける〈ソマティックな介入〉、そして認知や思考の枠組みを変える〈コグニティブな介入〉。この4つを状況に応じて組み合わせながら、崩れかけた生活を少しずつ立て直していきます。
どんなに高尚な理想があっても、生き延びることができなければ、その先の人生は描けません。だからこそ、カウンセリングの原則は「外から内へ」。現実や身体の立て直しがあってこそ、その奥にある心に向き合う準備が整うのです。
一方で、ある程度生活が安定し、自分を振り返る余裕が出てきたときに、はじめて「冒険としてのカウンセリング」の扉が開かれます。こちらは、より根本的に「自分とは何か」「何のために生きるのか」といった問いに向き合う営みです。
過去の人間関係の中で形づくられた「人生の脚本」が、今を生きる自分の振る舞いや感情、対人パターンに影を落とすことがあります。そうした無意識の繰り返しに気づき、それを丁寧にほどいていく。冒険とは、まさにそのプロセスに他なりません。
著者は、こうした深い心の働きを「スライム」と「鎧」というユニークな比喩で表現します。私たちの心は本来、やわらかく、形を持たないスライムのような存在です。
しかし、傷つくことから身を守るために、次第に「鎧」をまとっていく。やがてその鎧が硬くなりすぎると、スライムは凍りつき、動けなくなる。
冒険としてのカウンセリングは、この凍結したスライムをもう一度動かす試みです。鎧を緩め、その隙間から心の奥に入り、凍っていた感情や物語を再起動させていく。
そのプロセスでは、「転移」と呼ばれるカウンセラーとの関係の中で、過去の重要な他者との関係が再演され、癒しと変容の可能性が開かれていきます。 心を揺らし、意図的に破局を起こすことさえある。それは、心の中でいったん物語を終わらせるためです。
古い物語を閉じることで、新しい物語が始まる。生存を優先するあまり置き去りにされてきた「実存」が、ようやく取り戻されるのです。これは単なる感情の整理や問題解決ではなく、自分自身を深く理解し直すという、時間のかかるプロセスです。
著者は、カウンセリングには二つのゴールがあると語ります。一つは、日々の生活を守ること。もう一つは、自分の人生をきちんと生きること。どちらも欠かすことはできませんが、順番があります。
まずは「生き延びる」ことが必要です。その上でようやく、自分の物語をもう一度紡ぎ直すことができるのです。 本書は、カウンセリングがこの両方を支える営みであることを、鮮やかに、かつ静かに教えてくれます。
そして本書が示すもう一つの大切な視点は、人生の根本に関わる変化――いわば「文学的変化」の存在です。これは、本人の内側で確かに実感される変化であり、合理的な対処や目に見える改善とは異なる、深い実存的な変化です。
心のもっとも個人的な層に触れる、そうした変化があることを、著者は私たちに伝えてくれます。 心は、世界と科学的に向き合いながらも、同時に文学的にも世界を生きています。目の前の現実を客観的に捉え、適切に対処する。これが科学的な側面であり、作戦会議としてのカウンセリングが機能する場面です。
一方で、心は現実を意味づけ、物語として捉え直す力も持っています。過去の出来事に意味を与え、自分の人生を「語り直す」。この営みこそが、冒険としてのカウンセリングの真髄なのです。
生活は科学的に変化していき、人生は文学的に変化していく。心にはその両方の車輪があります。合理と物語。その二つが同時に回ることで、僕らの生活と人生は少しずつ前に進んでいくのです。 この二つの側面は、作戦会議型のカウンセリングでも、冒険型のカウンセリングでも、常に響き合っています。
人と人が言葉を交わすという行為そのものに、変化の力が宿っているからです。話すことは、同時に“離す”ことでもあります。過去を語るというのは、過去の出来事を今の自分から少し距離を取り、過去として置いておくことなのです。
人は、生活が立ち行かなくなったときや、人生の意味を見失ったときにカウンセリングを訪れます。現実の困難と心理的な混乱が重なり、状況が限界を迎える。そのような破局的な局面を、カウンセラーとともに何とか乗り越えたあとで、多くの人が気づくことがあります。かつて苦しかったあの時期は、すでに過去になっていたのだと。そして、それまで自分を縛っていた物語も、ようやく終わりを迎えていたのだと。
カウンセリングとは何か――それは、現実を立て直すための科学的な営みであると同時に、個人の物語を過去として位置づけ直すための文学的な営みでもあると著者は指摘します。言葉を交わすなかで、自らの過去を語り、それに距離を取っていく。
話すことは離すことでもある。過去を物語るのは起きた出来事を現在から引きはがし、過去に置いておくためです。苦しい時期にカウンセリングにやってくる。生活が脅かされる時期があり、人生の危機がある。カウンセラーの手助けを借りながら、その破局を生き延びる。すると、人生のある時期が終わっていたことに気づく。古い物語がかつてのものになっている。
話すという行為には、語ることと「離すこと」の両義的な意味が含まれています。 本書が描き出すのは、カウンセリングという営みのそうした多層的な側面です。それは単に症状を軽減するための技術ではなく、近代における孤独や断絶のなかで、人が自分自身の物語を再構築しようとするプロセスでもあるのです。
カウンセリングとは、可能な限り正直に、率直に、そして誠実に「ほんとうの話」をしようとする場です。その意味で、きわめて人間的で、関係性に根ざした営みだと言えるでしょう。著者の真摯な問いかけと、3つのカウンセリング事例を通じて、本書はこの営みの持つ役割と、そこに流れる時間の重さを丁寧に描き出しています。
そして私たちは気づかされます。人は、対話によって変わることができるのだということを。私自身も、断酒とコーチングを通じて人生を立て直してきましたが、その背後には、変化の前と後をつなぐ物語があり、人とのつながりが確かに存在していたのです。



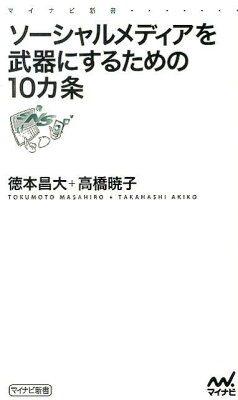














コメント