創作者のための読書術
エリン・M・プッシュマン
フィルムアート社

創作者のための読書術 (エリン・M・プッシュマン)の要約
書く力は経験だけでは伸びにくく、鍵となるのは「どう読むか」です。本書は『創作者のための読書術』として、読書を娯楽ではなく創作そのものと捉え、文章・構造・視点・ジャンルなどを批評的に読み解く方法を体系化します。作家は感覚ではなく判断の積み重ねで書いており、その判断力は精読によって鍛えられる。読む解像度を高めることが、再現可能な形で書く力を育てる――その実践的視点を示した一冊です。
批評的読書が作品づくりに有効な理由
作家は執筆という行為が何をしていて、どんな可能性を秘めているかを学ぶために、そして他の作家から学ぶために、自身の技巧を磨くために本を読むのだ。 (エリン・M・プッシュマン)
書くことは、経験を重ねてもなお簡単には上達しません。私も本を一冊出すたびに、「今回は何が足りなかったのか」「自分の書き手としての可能性は、本当に広がっているのか」という問いが、必ず立ち上がってきます。
一方で、売れている本や長く読み継がれている本を手に取ると、共通する特徴も見えてきます。文章がうまい、構成が緻密、テーマに深みがある――そうした要素はいくつも挙げられますが、それ以前に決定的なのは、徹底して読者の側に立って書かれている点です。読者がどこで立ち止まり、どこで理解し、どこで心を動かされるのか。その流れが、偶然に任されるのではなく、あらかじめ設計されたものとして文章の中に組み込まれています。
頭では理解していても、自分がその領域に本当に到達できているのかと問われると、どうしても言葉に詰まってしまいます。 その迷いに、明確な答えを出してくれたのが、創作者のための読書術(原題:How to Read Like a Writer)です。
本書のタイトルが示す通り、「書くために読む」という行為を、再現可能な技術として整理した一冊です。著者のエリン・M・プッシュマンは、米国ライムストーン大学の教授であり、クリエイティブ・ノンフィクションの専門家でもあります。作家として書き続け、同時に教育者として書くことを教えてきた経験が、本書の基調を形づくっています。
本書が明確に線を引くのは、「作家も読者と同じように、本を楽しんで読んでいる」というイメージです。もちろん作家も読書を楽しみます。しかしそれだけではありません。
著者のプッシュマンが強調するのは、作家は娯楽として読むだけでなく、常に批評的に読んでいる、という点です。ここで言う批評とは、否定や評価を下すことではありません。
「推敲の結果、なぜこの表現が選ばれたのか」「なぜここで登場人物の視点が切り替わったのか」「もし作者が、別の選択をしていたら、読者体験はどう変わったのか」。そうした問いを立てながら読む姿勢そのものを指しています。
本書が体系化しているのは、「Reading like a writer(書くために読む)」という思考法です。プロの作家は、他人の作品を前にするとき、物語に身を委ねるだけでは終わりません。どの言葉に引っかかり、どの構造に違和感や納得を覚えたのかを意識的に捉え、それを自分の中で分解し、再利用可能な知識へと変換していくと言うのです。
本書は、その読みの解像度を引き上げるための視点を、丁寧に提示していきます。 プッシュマンが繰り返し伝えるのは、作家が本を読む理由は、気分転換やインスピレーション探しにとどまらない、ということです。
作家は、執筆という行為が実際には何をしているのか、どこに可能性があり、どこに限界があるのかを理解するために読みます。
作家は、他の作家がどのような判断を積み重ね、その結果として読者にどのような体験が届けられているのかを見極めるために本を読みます。物語の流れ、視点の選択、言葉の密度や間の取り方。その一つひとつが、どんな効果を生んでいるのかを観察するために読むのです。
そして、その観察によって得られた気づきを、自分の作品への応用、テクニックを磨くために意識的な批評的読書を重ねていきます。読むことは、書き始める前の準備段階ではありません。読む行為そのものが、書く力を直接鍛える実践だという認識が、ここにははっきりとあります。
その批評的読書が成立する前提には、作家がジャンルという文脈の中で書いているという理解があります。多くの作家は、ジャンルごとに共有されてきた伝統や約束事にしたがって書いていますし、時にはその線引きを意図的に曖昧にすることで、新しい表現を生み出します。
フィクションは、物語を通じて読者を楽しませ、驚かせ、感情を揺さぶるために構築されます。クリエイティブ・ノンフィクションは、実際に起こった出来事を素材にしながら、読者を引き込み、あたかも物語のように体験させることを目指します。
詩は、物語や説明といった方法では掬い取れない感情や思考を、言葉の凝縮や飛躍によって伝えようとします。 作家が批評的に読むとは、こうしたジャンルごとの役割や期待を踏まえたうえで、「なぜこの表現や言葉が選ばれたのか」「なぜこの文体でなければならなかったのか」を考え続けることでもあります。
その読みの積み重ねが、ジャンルを守る書き方にも、境界を越える書き方にも対応できる柔軟な書き手を育てていきます。読むことは、単なるインプットではありません。書く行為と地続きの、極めて能動的な創作の一部なのです。
良い作品を書くための10のレッスン
ジャンルを融合した作品を読むことは、その文学的な家の外へと足を踏み出す行為なのだ。そして作家として(人としても)成長するためには、今まで学んできたカテゴリーの視野を広げる必要がある。簡単に言えば、ジャンルの制限を破る作品を読むことは、その制限のなかで書き続ける必要はないということを思い出させてくれる。すべての読み手と書き手はこのことを覚えておかねばならない──もちろんこの本を書いている私も含めて。
本書は、物語作りを感覚や才能の問題として扱うのではなく、ジャンル、構造、キャラクター、視点、言葉といった要素に分解し、学習可能な10のレッスンとして整理しています。創作とはひらめきではなく判断の連続であり、その判断力は「どう読むか」によって鍛えられる、という立場が一貫しています。
作家はジャンルの伝統に沿って書くこともあれば、あえて境界を曖昧にし、複数のジャンルを行き来しながら表現することもあります。ジャンルをまたぐ作品を読むことは、自分が慣れ親しんできた枠組みの外に出る行為です。それは新しい書き方を知るというよりも、ものの見方そのものを広げる体験に近いものです。ジャンルを越えて書くためには、まずジャンルを越えて読む必要がある。その前提が、本書の出発点になっています。
次に焦点となるのが、作品の長さや形式です。短い作品はなぜ成立するのか、デジタルメディアではなぜ表現の重心が変わるのか。本書は、長編か短編かといった単純な区別ではなく、「その長さは、どんな読者体験を生んでいるのか」という視点で読むことを促します。
長さや媒体は制約ではなく、作家が意図を実現するための設計要素であり、選択そのものが表現であるという理解が積み上げられていきます。
やがて話題は物語の力へと移っていきます。プロットやナラティブアーク(物語の時系列の流れや構造)、対立構造といった要素は、理論として説明されるのではなく、読者の関心をいかに保つかという実践的な課題として扱われます。同時に、本書では、さまざまな作品を事例に、文章の魅力について解説しています。
テーマや着想、印象的なイメージや感覚、感情の流れが、物語の代わりに読者を導くこともある。その読み方を知ることで、創作の可能性は大きく広がります。
構造についての説明も分かりやすく整理されています。文章をどの順番で提示するのか、どこで区切り、どう移行するのか。そうした構造上の判断が、意味や読者体験に直結していることが丁寧に示されます。文章と画像の関係に触れている点からも、現代的な表現を視野に入れていることが分かります。
人物の扱いについても、本書は一貫して実践的です。登場人物を設定の集合として見るのではなく、行動や反応の積み重ねとして読むことが重要だと説かれます。身体や感情、心理、習慣、他者との関係性が絡み合うことで、キャラクターは立体的になります。その結果、当初想定していたプロットが変わることもあるのです。
語り手自身が登場人物である場合や、非物語形式で人物性がどう立ち上がるのかを読むことで、キャラクター造形が物語専用の技法ではないことも理解できます。
語りの視点については、視点をレンズとして捉える考え方が示されます。誰の目線で語るのかという選択は、読者との距離をどう設計するかという判断でもあります。
一人称、二人称、三人称の違いは、単なる文体の問題ではありません。特にクリエイティブ・ノンフィクションでは、語り手と作者が重なることで生じる複雑さがあり、それは批評的に読むことで初めて意識されます。視覚的要素が加わることで、視点が拡張される点にも触れられています。
舞台設定やシーン、そして言葉についての章では、場所や時間、情景描写、語彙やリズム、音が、どのように読者体験を形づくっているのかが確認されます。舞台は単なる説明ではなく意味を支える要素であり、シーンを書くか省くかも明確な表現上の選択です。
作家としてのルールの土台になっているのは、作家とは言葉を扱う、という考え方だ。そして私たちが言葉を扱うのは、読者の目をページの上に釘付けにしつつその言葉を確実に届けるためであり、その言葉の細部に工夫を施し読者を驚かせるためであり、そうして言葉が読者の側を離れず、記憶に残るようにするためである。
10のレッスンの最後に、著者は言葉そのものへと立ち返ります。文章を意味だけでなく音として捉え、ルールとの距離を意識しながら言葉を選ぶことの重要性が強調されます。言葉に注意を向けることで、プロットや構造、キャラクター、舞台設定が、実際にページの上でどう形になっているのかが見えてきます。
言葉とは、作家が作品をつくり、読者に届けるための唯一の材料です。作家は、選ぶ単語や文の組み立て、守るルールと破るルールに目を配りながら、言葉を通して世界を立ち上げているのです。
結論として本書が示しているのは、読書はインプットで終わる行為ではなく、新しい題材を生み出すための創作そのものだという視点です。優れた作品を精読し、批評的に読み込むことで、ひらめきが生まれ、まったく新しいテーマで書き始めることができたり、すでに書いている原稿の方向性を修正する手がかりが見えてきたりします。
読むことは、書く前段階ではなく、創作を動かすエンジンなのです。 本書の核心にあるのは、読む解像度を高めることで、「書く力」も確実に高められるという考え方です。
ただ物語を追い、感動して読み終えるだけの読書では、書く力はなかなか育ちません。「優れた書き手になるための第一歩は、優れた読書家になること」。この言葉は、感情論ではなく、再現可能な技術論として提示されています。 構成面でも本書はきわめて実践的です。
私たちが言葉を扱うのは、読者の視線をページの上に留め、意味を正確に届けるためであり、同時に言葉の細部に工夫を施すことで読者を驚かせ、その言葉が記憶に残るようにするためです。
読むときには常に、「この作品から何を学べるか」「自分の文章はどう変えられるか」と自問する。その姿勢を身につけたとき、読書は娯楽を超え、書き手を次の段階へと導く、もっとも信頼できる創作の道具になるはずです。
本記事は書評ブロガー・ビジネスプロデューサーの徳本昌大が執筆しました。



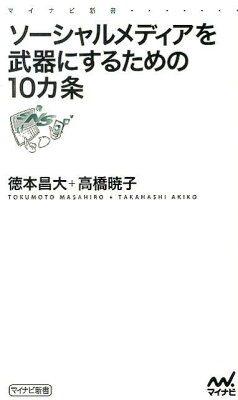






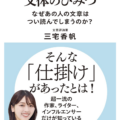





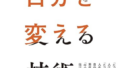
コメント