
いい経営者は「いい経営」ができるのか――18年間、探究し続けてたどり着いた経営哲学
高家正行
英治出版
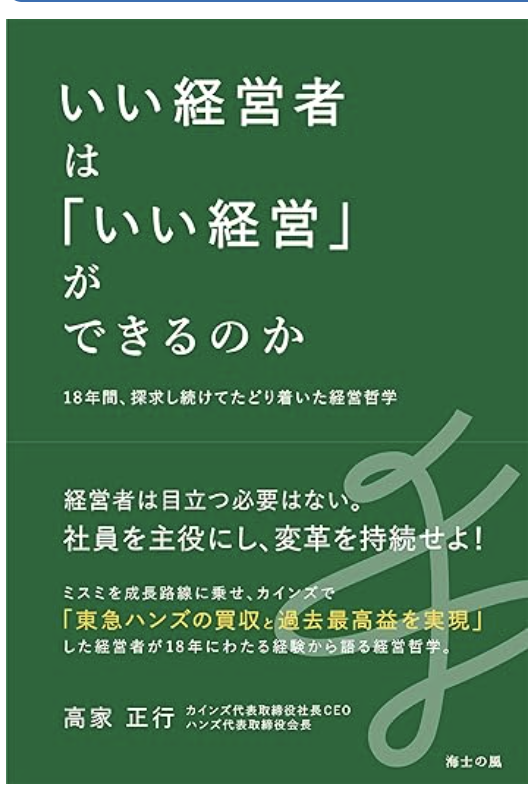
本書の3行要約
本書は、「いい経営者」とは誰かではなく、「変化が持続する経営」とは何かを問い直す一冊です。 平時に変革を起こし、その変化を組織に定着させるための思想と実践が、カインズのDX事例を通して語られます。 経営者が主役であり続けるほど、経営は弱くなるという逆説が、静かに腑に落ちてきます。
30秒でわかる本書の要点
結論: いい経営とは、変化を起こすことではなく、変化が持続する状態をつくることです。
原因: 多くの経営は、危機が起きてからの改革や、トップ主導の一過性の変革で終わってしまうからです。
対策: 平時に小さな成功体験を積み、WhyとWhatを共有し、変革の主役を組織へ移していくことが必要です。
こんな人におすすめ
・短期的な業績改善だけでなく、経営者が交代しても成長し続ける「強い組織」をつくりたいと考えている経営者
やオーナー
・DXや変革を進めたいが、号令や制度設計だけでは現場が動かず、やり方に限界を感じている事業責任者、CXO
・トップダウンで成果は出してきたものの、自分自身がボトルネックになりつつあることに違和感を覚えている経営幹部、マネージャー
・「いいリーダー」「いい経営」とは何かを、成功論ではなく、持続性と人の自律という視点から深く考えたいビジネスパーソン
読者が得られるメリット
・「いい経営者=強いリーダー」という固定観念から離れ、変化が持続する組織をつくるための本質的な視点を持てる
・危機が起きてから動くのではなく、平時に変革を仕掛けるための考え方と時間軸の取り方が理解できる
・DXや組織変革を進める際に、Why・Whatをどう共有すれば現場が自律的に動き出すのかが具体的にわかる
・アーリーサクセスやキンクのつくり方を通じて、変革を「計画」ではなく「現実」に変えるヒントを得られる ・経営者自身がボトルネックになってしまう構造的な罠に気づき、変革を手放していく覚悟と方法論を学べる
・人材育成をコストではなく投資として捉え直し、プロフェッショナリティと自律性が育つ組織設計の視点を持てる
「いい経営」とは、変化そのものが持続すること
多くの社員にとって、危機は遠い出来事なのである。 (高家正行)
「いい経営者」と聞くと、多くの人は強いビジョンを掲げ、即断即決で組織を引っ張り、短期間で業績を伸ばす人物像を思い浮かべるかもしれません。市場環境が激変する時代においては、迷わず決断し、結果を出すリーダーこそが評価されやすいのも事実です。
しかし、その評価軸は本当に「いい経営」に結びついているのでしょうか。短期的な成功を重ねた経営者が去ったあと、組織は変化し続けられるのか。この問いに18年間向き合い続けた記録が、いい経営者は「いい経営」ができるのか――18年間、探究し続けてたどり着いた経営哲学
ミスミで成長路線を確立し、カインズでは東急ハンズの買収と32年ぶりの過去最高益を実現した高家正行氏は、外形的には「成功したプロ経営者」に見える存在です。しかし本書で語られるのは、成功体験の再現方法ではありません。
むしろ、社長就任と同時に「いったん減益にする」と宣言し、DXや店舗空間への大規模投資に踏み切った決断に象徴されるように、目先の利益を犠牲にしてでも未来の変化に賭ける姿勢です。
著者はこれを「いったんかがむ」と表現しますが、その根底にあるのは、変革とは一度きりの成果ではなく、変化が続く状態をつくることだという一貫した思想です。
そもそも変革は、危機が訪れてから行うものではありません。事業不振に陥る前、まだ多くの社員が危機を実感していない平時にこそ手を打つ。それが経営者の仕事だと、著者は考えるようになります。
平時の変革は、戦時の改革よりも難易度が高い。危機感で人を動かすことができず、痛みを伴う強権的な手段も取りにくいからです。それでもなお、選択肢が多く、未来に向けた投資ができるのは平時しかありません。
変化とは、一つのキンク(屈折)が起きること。一方、持続とは、ある状態が安定して継続すること。つまり、変化と持続というのは、一見両立しがたい。しかしながら、「変化→持続→変化→」と独立して連続していくのではなく、「変化=持続」、つまり変化そのものが持続することこそが「いい経営」であると考えている。
ここで著者は、「変化」と「持続」という、一見すると相反する概念を丁寧に捉え直します。変化とは、一つの「キンク」、つまり屈折や転換点が生じることです。一方で持続とは、ある状態が安定して続くことを指します。
この定義だけを見ると、変化と持続は両立しないように思えます。変わり続ければ安定しないし、安定すれば変わらない。その矛盾をどう乗り越えるかが、経営の核心になります。 高家氏がたどり着いた答えは、「変化→持続→変化」と断続的に繰り返すモデルではありません。「変化そのものが持続する状態」、すなわち「変化=持続」という考え方です。
変えることが特別なイベントではなく、問い直し、試し、学び、更新し続けることが組織の日常になる状態。これこそが、著者の定義する「いい経営」です。
この視点に立つと、変革の時間軸は一気に引き伸ばされます。変革とは数カ月や数年で完結するプロジェクトではなく、どんなに短く見積もっても十年、時に数十年先を見据えて仕掛けるものになります。
そのために経営者が果たすべき役割も変わります。経営者とは、常に前に立ち、全てを決め続ける人ではありません。強いリーダーシップで変革を立ち上げながらも、最終的には自分がいなくても変わり続けられる組織をつくる人なのです。
カインズのDX成功事例:なぜ現場は動いたのか?
顧客体験の向上を生み出すことができ、その後一気にデジタル活用は現場へ浸透していった。これが、カインズにおけるDX成功の要諦だと考えている。
この思想が、最も具体的な形で表れたのが、カインズにおけるDXの進め方でした。カインズのDXが比較的スムーズに現場へ浸透していった背景には、顧客体験の向上を起点にデジタル活用を設計したという、きわめて明確な意図があります。
デジタルを目的にしなかったこと、あくまで顧客体験を良くするための手段として位置づけたことが、結果として現場の理解と納得を引き出しました。 現場は当初、デジタルに対して「仕事が増えるのではないか」「現場を管理・監視する道具になるのではないか」という不安を抱えていました。
しかし、実際に顧客体験が良くなっているという手応えが生まれた瞬間、認識は一変します。デジタルは現場を縛るものではなく、顧客と自分たちの仕事を助けるものだと理解されたのです。その理解が共有されたとき、デジタル活用はトップの号令ではなく、現場の意思として一気に浸透していきました。これこそが、カインズにおけるDX成功の要諦だったといえます。
人を動かすためには、理想や戦略を繰り返し語ることも必要です。しかし、それだけで思考や行動が変わることはほとんどありません。人が変わるきっかけは、理屈ではなく実感です。現場が変わるかどうかは、アーリーサクセスを生み出せるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。
これまでのやり方を変えるとき、人は必ず不安を感じます。その不安を払拭し、「こうすればいいのか」「自分たちの仕事が楽になる」「お客さまが喜んでいる」と腑に落ちた瞬間に、変革はキンクを迎えます。
カインズでは、現場に対してHowを指示するのではなく、WhyとWhatを徹底的に共有しました。「このツールを使ってください」「この手順に従ってください」という指示は、短期的には動かせても、思考を止めてしまいます。そうではなく、「何を実現したいのか」「なぜそれが必要なのか」を語るようにします。
たとえば、顧客単価を上げたい、来店体験を良くしたい、その背景には競争環境の変化がある。こうした文脈が共有されることで、現場は自分たちでHowを考え始めます。 その象徴的な事例が「Find in CAINZ」です。お客様が欲しい商品を迷わず見つけられるという、きわめてシンプルな体験改善でしたが、この一手によってデジタルの価値が一気に可視化されました。
デジタルは難しいものでも、特別な人のものでもなく、日々の現場と顧客体験を確実に良くするものだという共通理解が生まれたのです。
平時に全社レベルで変革を一気呵成に進めるのは、現実的ではありません。だからこそ、まず突破口を探し、小さなキンクを起こすことが重要になります。その突破口は、必ずしも社内の本流である必要はありません。
むしろ、これまで手つかずだった領域や、注目度の低かった分野のほうが制約が少なく、短期で劇的な変化を生み出せることもあります。一定数が使い始めれば一気に広がるという臨界点を意識することで、変化は「計画」から「現実」へと変わっていきます。
この考え方は、数値の扱い方にも表れています。顧客データを見て数値が小さいと、「市場が小さい」「意味がない」と判断してしまいがちです。しかし、それは単に育ててこなかった結果かもしれません。
ハンズで使われていた「小人モデル」という言葉が示すように、今は小さくても、大きくなる可能性を秘めた兆しを見逃さないようにすべきです。このような共通言語は、抽象的な理念よりもはるかに強く、組織の思考と行動を具体的に変えていくのです。
優れた経営者は大胆な変革と、変化の持続を両立させる!
「いい経営」をするためには人が育つ環境を整えること。そのためには、人が育つ時間的猶予のある状況をつくることである。人材育成は投資だ。目先の利益と相反するが、私から見れば、目先の利益を盤石にするためにこそ、人が育つ環境を整えることが前提条件となる。
こうした実践を通じて、あらためて浮かび上がるのが、「いい経営者」とは何かという問いです。高家氏が18年の探究の末にたどり着いた結論は、平時にこそ変革を起こし、その変化を持続させる構造をつくることでした。そのためには、論理や強いリーダーシップだけでは足りません。
合理性を超えた道理性、つまり「それは人として、組織として正しいのか」という問いを引き受ける姿勢と、信頼と共感によって人を動かす力が必要になります。
大胆な変革と、変化の持続。この二つは、一見すると両立しがたいものです。大胆な変革は、強いリーダーシップのもとで大きなインパクトを起こすからこそ、止まっていた大企業という岩を動かすことができます。
しかし、そのインパクトを永遠に続けることはできません。それは、ダッシュしながらマラソンを走り続けるようなものです。
どちらか一方だけでは、企業は持続的に成長できません。 目指すべきは、変革が全社に広がることで、変革そのもののスピードが上がっていく状態です。
数年前に立てた変革プランを、ただ実行し続けることが正解とは限りません。環境変化に応じて問い直し、新たな変化を生み出し続けることが求められます。そのために重要なのは、変革の主役を自分から自律したリーダーへとスイッチしていくことです。
1人の経営者から、自律したリーダーたちへ変革のバトンが渡されることで、最初のキンクによって生まれた変化は、拡大し、スピードを上げながら持続していきます。
「いい経営」をするためには、人が育つ環境を整えることが欠かせません。そのためには、人が育つ時間的猶予のある状況をつくる必要があります。人材育成は投資であり、目先の利益とは相反するように見えます。しかし、目先の利益を本当に盤石なものにするためにこそ、人が育つ環境を整えることが前提条件になるのだと、著者は考えています。
変化が早く不確実な時代には、さまざまなレイヤーで自律的な変化を生み出す人材がいること自体が、組織の競争力になります。同質的で、指示待ちの組織ほど危うい時代はありません。求められるのは、自分ならではの強みを持ち、質の高い仕事を提供し、「自分にしかできないこと」を追求しながら社会や組織に貢献するプロフェッショナリティです。
会社にできることは、そのプロフェッショナリティを最大限に発揮できる環境や機会を整えられるかどうかに尽きます。 自律性を引き出すとは、仕事を丸投げすることではありません。権限を委譲しつつ、ゴールを明確にし、認識を共有することは、上司や経営層の責任です。CXOや本部長には、具体的なHowではなく、「何を実現したいのか」「なぜそれが必要なのか」を伝えることが求められます。
その結果、現場から多様なアイデアが生まれ、変革は一部の取り組みではなく、組織の力として広がっていきます。 多様な意見を集め、議論を尽くすことも欠かせません。自分のバイアスに気づくには、異なる視点を浴びるしかないからです。
テクノロジーや価値観がめまぐるしく変化するなか、これまでの常識や法則は、どんどんアップデートされていく。なにより自分のバイアスに気づくには、多様な意見を浴びることである。判断を誤らないためには、なるべく多様な意見を出して、さまざまな角度から議論してもらうことが大切だと考えている。一方で、さまざまな意見を集め議論を尽くしたうえで、リーダーの役割である。ここは独裁がいいと思っている。
「いい経営者」を実現すればするほど、「いい経営」からは遠ざかっていく。本書が突きつけるこの逆説は、経営という営みのなかでも、最も厄介であり、同時に最も本質的な真実だと感じます。強い意思決定力とリーダーシップで変革を成し遂げた経営者ほど、その成功体験ゆえに、組織の中心に居続けてしまいがちです。
その結果、変化は経営者個人に依存し、組織全体の学習速度や変化のスピードは、いつしかその人一人分に制約されてしまいます。 だからこそ高家氏は、経営者が自らを小さくし、変革を手放していく必要があると語ります。
それは決して責任放棄ではありません。むしろ、経営者としての役割を、変革の「実行者」から、変革が持続する「構造の設計者」へと移していく行為だといえます。自分が前に立たなくても問いが立ち続け、試行錯誤が繰り返され、学びが更新されていく状態を意図的につくること。その状態が生まれてはじめて、変化は一過性のイベントではなく、組織の文化として根づいていきます。
変革を手放したとき、変革は止まるのではありません。むしろその逆で、変革の規模は拡大し、スピードは上がっていきます。一人の経営者の判断速度には限界がありますが、自律したリーダーが各所で意思決定を行う組織には、その限界がありません。
最初は小さなキンクとして始まった変化が、連鎖し、増幅され、やがて全社の動きへと広がっていきます。その状態こそが、高家氏のいう「変化が持続する経営」なのだと理解できます。
本書を通じて見えてくるのは、経営者に求められる覚悟の質です。それは、平時に変革を起こす勇気だけではありません。その変革を自分の手柄にせず、すべてをコントロールし続けようとせず、やがて手放していく覚悟でもあります。
変革を「自分が起こした物語」として完結させるのではなく、「組織が生き続けるための前提条件」として埋め込んでいく。その姿勢がなければ、どれほど優秀な経営者であっても、「いい経営」には到達できないのだと、本書は教えてくれます。
本記事は書評ブロガー・ビジネスプロデューサーの徳本昌大が執筆しました。


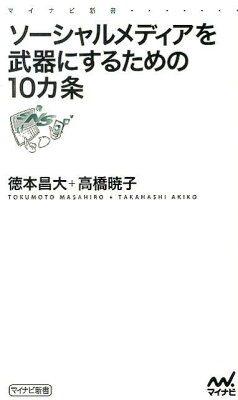













コメント