「一万円選書」でつながる架け橋 北海道の小さな町の本屋・いわた書店
岩田徹
竹書房
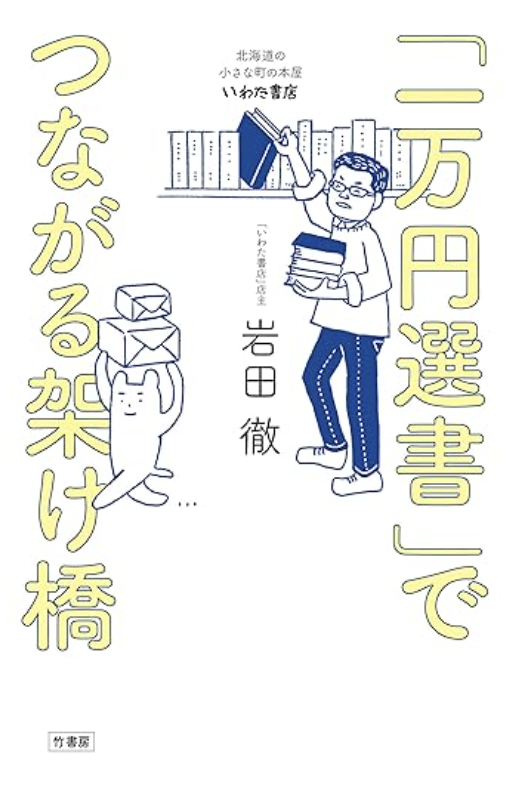
「一万円選書」でつながる架け橋 (岩田徹)の要約
地方の書店が姿を消す中、北海道砂川市の「いわた書店」も何度も廃業の危機に直面してきました。そんな逆境を転機に変えたのが、店主・岩田徹氏の「一万円選書」です。高校時代の先輩の「心がホッとする本を選んでほしい」という一言をきっかけに始まったこのサービスは、「本を選ぶとは何か」という本質的な問いに向き合いながら、読書文化の再生に挑む地方書店経営者の真摯なチャレンジです。
いわた書店を救った一万円選書とは何か?
一言で言えば、読んで字の如く、書店主(僕)が一万円ほどのご予算でお客さん一人ひとりに合った本を選びますよ、というものです。肝心なのは、どんな本を選ぶか。ここに僕なりのこだわりと工夫があります。(岩田徹)
出版不況が続き、地方の書店が確実に姿を消しつつあります。かつては町のいたるところに存在していた小さな本屋も、今ではそのほとんどが閉店し、大型チェーン店だけが営業を続けている地域が珍しくなくなりました。
私の暮らす街でも、歩いてすぐの距離にあった個性的な書店が姿を消してから、随分と時間が経ちました。そこは本好きにとっての憩いの場所であり、自分の感性を磨く静かな空間でもありました。 このような変化は決して一地域に限ったものではありません。日本全体で書店数は減少を続けており、ピークだった平成8年以降、その数は右肩下がりを描いています。
電子書籍の普及やオンラインショッピングの利便性、YouTubeなどのSNSを通じた無料の情報入手といった背景要因は多く存在します。しかし、問題の本質は、単なる流通や技術の変化にとどまりません。読書という行為そのものが、文化として社会に根付かなくなりつつあることが、より深刻な課題なのです。
そのような流れの中で、「本を愛する人」が少しずつこの国から姿を消しつつあることこそが、本質的な課題だと感じています。これは単なる文化の衰退にとどまらず、学ぶ姿勢そのものが社会から失われていく兆しであり、長期的には、国家の知的基盤が損なわれる結果につながると私は考えています。
北海道のほぼ中央に位置する砂川市でも、同様の問題が起きています。札幌市と旭川市を結ぶ国道12号線沿い、約29.2kmにわたる日本一の直線道路の途中に、「いわた書店」はあります。
砂川市の人口は2万人に満たず、いわゆる過疎地域に分類される町です。こうした地域において、書店が営業を続けることは決して容易ではありません。実際、「いわた書店」も幾度となく廃業の危機に直面してきました。地方都市における小規模書店が、時代の流れに抗い続けることは、並大抵の努力では実現できないのです。
そんなある日、高校時代の先輩がふいに発したひと言――「一万円で本を見繕ってくれないか。心がホッとするような本を送ってくれよ」。その一見さりげない依頼に応えたことが、やがて「一万円選書」というユニークなサービスへと結実していきます。
実際、「いわた書店」も幾度となく廃業の瀬戸際に立たされてきました。地方都市における小規模書店として、時代の流れに抗うことは容易ではありません。そんな折、高校時代の先輩がふいに発したひと言——「一万円で本を見繕ってくれないか。心がホッとするような本を送ってくれよ」。その一見さりげない依頼に応えたことが、やがて「一万円選書」へとつながっていきます。
先の見えない日々のなかで、店主・岩田徹氏は“目の前のひとり”のために本を選ぶという行為に、静かに心を傾け続けました。それは単なる注文への対応ではなく、選書を通じて本を読みたい、新たな読書体験をしたいという顧客との丁寧な対話を行うことでした。
現代社会において、私たちは多くの場合、会社のこと、人間関係のことなど、身近な問題に心を奪われがちです。そうした日常の雑事に埋もれたとき、自分自身の思考や感情を見つめ直す機会を、本は静かに提供してくれます。岩田氏の選書は、そうした内省の時間を、読者一人ひとりにそっと手渡す営みになっています。
「一万円選書」の仕組みは、きわめてシンプルです。読者一人ひとりのプロフィールや関心に応じて、一万円分の書籍を選び、届ける。ただ、それだけのことです。 しかしながら、重要なのは“何を選ぶか”ではなく、“いかに選ぶか”という姿勢にこそ、本質が宿るという点です。表面的には単なる選書サービスのように見えるかもしれませんが、その根底には、書店主による顧客一人ひとりへの深い思慮と、寄り添おうとする姿勢が確かに存在しています。
サービスの希望者には、まず「選書カルテ」と呼ばれる詳細なアンケートに回答してもらいます。そこに並ぶ設問は、単なる嗜好や興味関心を問うものにとどまりません。
カルテでは、もっとマクロな視野の質問を投げかけたいのです。将来どんな生活をしていたい?というような。大きな視野で人生を見渡すと、身近なことや些細なことを気にしなくなります。
「これまでに読んだ本BEST20」「人生でうれしかったこと」「あなたにとって幸福とは?」「何歳の自分が好きですか?」「これだけはしないと決めていることは?」——選書カルテには、個人の内面に深く踏み込む問いが並びます。 岩田氏はその回答を読み解きながら、文字通り一冊一冊を選び抜いていきます。
流行や売上ランキングではなく、その人の人生に“今”必要な本を届ける。その選書はテンプレートではなく、ひとつの文脈に寄り添うパーソナルな提案です。選ばれるのは、誰かのためではなく、「その人のため」の良書です。
AIのアルゴリズムやマニュアルに頼らない、極めて人間的なプロセスから生まれる選書は、ときに読者自身が思いもよらなかったジャンルの本を届けます。そして、それが新たな読書体験や価値観との出会いにつながる。丁寧で誠実なこの手法が、多くの読者の心を動かし、深い信頼を築いている理由です。
スタート当初の応募数はごくわずかでした。しかし、この取り組みは口コミやメディアの力でじわじわと広がり、今では3000人を超える待機リストを抱えるほどの反響を呼んでいます。商品というよりも、選書という営みによって生まれる“体験”が、今の時代において希少な価値として認識され始めている証拠かもしれません。
良書を絶滅させないために必要なこと
仮に10冊を選ぶとしましょう。僕は10冊の本を選ぶということは、10人の賢者を紹介するということだと思っています。選書カルテによって自分のことを客観的に把握して、心がスーッと開いた人たちに向けて「10人の賢者を紹介しますから、耳を傾けてみてください」という気持ちで1冊1冊選書するわけです。
岩田氏は、書店主という仕事の本質を「これ、面白いから読んでみて」と誰かに薦める、その単純でいて誠実な行為に集約できると語ります。たとえ読者が敬遠してきたジャンルであっても、あえてその扉を開かせる――それが読書の幅を広げ、新たな本との出会いを生むきっかけとなるからです。
岩田氏自身もまた、多様なジャンルにわたって本を読む多読家です。複数の書籍を並行して読み進めることで、読書を日々のリズムの中に自然に組み込み、無理なく継続する。その読書習慣が、一人ひとりに合った本を的確に選ぶための幅広い知識と、相手に合わせて選ぶ力を育んでいるのです。
取次による配本制度は、量と効率を優先するあまり、「誰にとっての本か」という視点を見落としてきました。しかし今、1日に200冊を超える新刊が刊行されるこの時代において、本当に求められているのは、“売れる本”を並べる力ではなく、“届けるべき本”を見極める力なのです。
本が読まれなくなる社会では、言葉の力そのものが衰えていきます。想像力が鈍り、他者の視点を想像する力が失われる――それは文化の退行であり、同時に社会の感受性の低下にもつながります。だからこそ、選書には意味があるのです。
良書が絶滅してしまう。そのすべては無理でも、ほんの一部でもなんとか救い出したい。良書を救い出し、「こんな本があるんですよ!」と読者に結び付ける。これこそが本屋の使命だと思うんです。
良書を絶やさずに読者へ届けること。岩田氏はそれを、書店の使命であり、存在理由そのものだと語ります。
彼が示したのは、読書を一部の知的好奇心旺盛な人のためだけの営みから、誰にでも開かれた“日常の選択肢”へと変える方法でした。2%の本好きが熱狂する本は、実は98%の“読まない人”にとっても、新たな世界の扉になり得る。その可能性に懸けているのです。
だからこそ、あえて「これまで本に縁のなかった人」に届ける意義があるのです。そこにこそ、文化の再生と拡張のヒントが秘められています。 読書を、誰にとっても当たり前の営みにする。それは、未来の読者を育てていくための地方書店の小さなチャレンジですが、これが書店業界を動かし始めています。
たった一冊の本が、人の視点を変え、思考をより深く、より広く導いていく――そんな可能性が、読書には確かに宿っているのです。目の前の現実は変わらなくとも、ものの見方や意味づけが変わるだけで、人は前に進む力を得られます。
仮に1日20分だけを読書に充てるとすれば、それだけで平日5日間で100分。新書一冊を読み終えるには十分な時間です。これを1年間、50週続ければ50冊――つまり、50人の新たな著者、50通りの価値観、そして50の思考世界と出会うことになります。 もしこの読書時間を倍にすれば、年間100冊。100人の知性と対話を重ねることができるわけです。
もちろん、読書量の多寡がすべてではありませんが、継続的な読書体験は、思考の厚みや判断の幅を確実に変えていきます。日々積み重ねられる20分、あるいは40分の静かな時間が、やがて大きな知の蓄積となって自分を支えてくれる。その実感こそが、読書の本質的な価値なのではないでしょうか。
私自身、書評ブロガーとして年間365冊のビジネス書を紹介しています。中でも意識しているのは、経営者やリーダー層にこそ届いてほしい一冊を選ぶこと。時代の変化が加速度的に進むなかで、確かな軸を持ち続けるためには、単なる情報ではなく“思考の技術”が求められます。
本はその技術を磨き、内省を深め、決断の質を高めるための、極めて有効な道具だと私は信じています。 このブログを通じて、読書という営みを日々の暮らしの中に根づかせていく仲間を、一人でも多く増やしたい。そう願いながら、今日も一冊の本に向き合っています。
本を読むという行為は、単なる知識の獲得ではありません。それは、他者と出会い、未知の世界に触れ、自分自身の枠組みを静かに広げていく営みです。ときに迷い、ときに立ち止まる私たちに、新たな視点を与え、行動のための内なる足場を築かせてくれる――それが読書という体験の本質なのです。






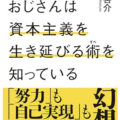







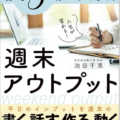



コメント