京都出町のエスノグラフィ: ミセノマの商世界
有馬恵子
青土社

京都出町のエスノグラフィ: ミセノマの商世界(有馬恵子)の要約
有馬恵子氏の『京都出町のエスノグラフィ』は、商店街というミクロな現場から、人と空間、時間が織りなす「まちの生成」を描いた作品です。ミセノマ(店先の間)を通じて、経済と文化、個人と共同体が重なり合う関係を丁寧にすくい上げ、衰退とされた小商いに潜む再生の知恵を示しています。空き家やスキマを活かした新しい営みを描きながら、著者は「まちと共に生きる」とは何かを私たちに問いかけています。
町の力を引き出すミセノマとは何か?
ミセノマとは人が集まるしかけでもあり、活動を生みだす場である。(有馬恵子)
月に2回ほど仕事で京都を訪れていますが、定期的に通ううちに、町の小さな変化にも気づけるようになりました。絶えず移り変わる風景や人の営みを観察していると、「エスノグラフィ(ethnography)」という手法の本質が少しわかる気がします。
東京とは異なり、京都には老舗や小さな商店が今も息づいており、街全体に独特のリズムと温もりを与えています。
下鴨神社を参拝するときや、馴染みのイタリアンに立ち寄るために、本書の舞台でもある出町をよく訪れます。歩くたびに見慣れた店先の佇まいや人々の何気ない会話に、京都という町が積み重ねてきた時間の厚みを感じます。
エスノグラフィとは、文化人類学を起源とする質的調査手法で、人々の行動や価値観、文化を現場での観察や参与を通して深く理解する研究アプローチです。数値や統計では捉えきれない社会の「意味」を明らかにするこの姿勢は、学問だけでなく、組織や地域の理解にも応用できる思考法です。
有馬恵子氏の京都出町のエスノグラフィ: ミセノマの商世界は、この手法を都市のミクロな現場に適用した極めて示唆的な研究です。京都市北部の出町エリアを対象に、商店街での日常を通して、人と空間と時間が織りなす「まちの生成」を描き出しています。
グローバル資本主義のなかで小規模店舗がいずれ消滅すると言われてきた時代にあって、有馬氏はその物語に抗い、現場に根づく柔軟な適応の知を丁寧にすくい上げます。 たとえば、呉服店が外国人観光客向けのレンタル事業を展開し、倉庫の一角に喫茶店が生まれるなど、商業空間の再構成が静かに進んでいます。これらは単なる延命策ではなく、変化のなかで新たな価値を創り出す試みです。
経済活動と文化的創造が重なり合うことで、まちは緩やかに再生していく。出町には、そうした生き延びる知恵が脈打っています。
出町の「枡形通」では、ほとんどの店が通りとミセノマ(店先の間)を隔てる明確な境界を持ちません。夏も冬も扉は開け放たれ、風や声が通り抜ける。通りの幅は約3メートル、店の間口は一間から三間。わずか163メートルの道に30軒ほどの店が並び、人が行き交う光景が絶えません。
狭い通りには車が入れず、聞こえてくるのは店先からこぼれる声。 「まいど〜」「おおきに〜」「いらっしゃ〜い」「太い切り干し大根ある?」。 店で交わされる言葉はそのまま通りに滲み、通行人の会話やアーケードのBGMと混じり合います。夕方になると「ただいま〜」と子どもたちが声をかけながら帰っていく。そこには、経済と生活が溶け合うリズムがあり、まちが呼吸しているようです。
この通りで重要なのが、空間の二重構造です。 ひとつは、店と外界をつなぐ「店の間(ミセノマ)」──人や声、モノが出入りする“あいだ”の空間。 もうひとつは、店が接する外部空間「通/通り(トオリ)」──人々の移動と交錯の場。 この二つが重なりあうことで、まちは単なる商業エリアではなく、関係が生成する“社会的な舞台”へと変わっていきます。 有馬恵子氏は言います。
「ミセノマとは、人が集まるしかけでもあり、活動を生みだす場である」。 この言葉は、まちの生命そのものを表しています。
ミセノマは経済的な取引の場を超え、人と人、人と環境を媒介する装置です。開かれた構造は偶発的な出会いや会話を生み出し、そこに新しい関係と活動が芽吹いていく。計画された都市空間が効率性を追求するのに対し、出町のまちは偶然と多様性のなかで共在を育む「生成的な生態系」として機能しているのです。
〈店・まち・アート〉の交錯──共在と再生のフィールドとしての出町
都市の〈スキマ〉や空き地・空き家という〈穴場〉を利用することによる〈ミセノマのアート〉というパースペクティブが浮かびあがる。
著者は、店、まち、そしてアートという3つのパースペクティブを重ね合わせることで、「商世界(バザールワールド)」を描き出しています。それは、単なる商取引の場としてのまちではなく、創造と生活が交錯し、芸術的な生成が日常の中に潜む「生きたフィールド」としてのまちです。
日常の営みのなかで、ミセノマとまちにうごめくものの間には、バラバラでありながらも、ときに結びつきが生まれます。適応しながら、そこでしか生きられないものが根を張る。結果的に、加茂川と高野川が合流する出町界隈では、隣り合うものと離れたものが同じ空間のなかで共在し、まちとしてのまとまりを形成しています。多様な存在が共に生きていくための「まちの土壌」は、時間をかけてゆっくりと耕されていくのです。
かつて衰退が避けられないとみなされていた独立自営の小さな店も、環境に応じて自らの新たな可能性を見出せば、必ずしも滅びるとは限りません。むしろ、地域のリズムや社会的ネットワークの中で、柔軟に形を変えながら新たな生命を育んでいく。京都の出町は、その可能性を証明しています。
京都は大学が多く、学生の街として知られています。古都の風情と知の拠点が共存するこの街には、研究者、職人、アーティスト、そして多様な働き方を選ぶ若者たちが混ざり合いながら暮らしています。一方で、京都府は高卒・大卒を対象とした「新卒フリーター率」が全国で二位という現実を抱えています。
フリーターに加え、近年では「フリーランス」と呼ばれる新しい働き方を選ぶ人々が増えています。職種はデザイナーなどのクリエイティブ系から、エンジニアなどのビジネス系、さらにハンドメイド作家やカフェ経営といった生活密着型の職人系まで多岐にわたります。知識集約型職種と単純労働型職種のどちらにも分類できない、あるいはその中間に位置する「しなやかな働き手」たちが、まちの中で新しい生態系をつくり出しているのです。
彼らは安定よりも自立を選び、組織の外で自らの手で生活をデザインしています。出町のまちにも、そうした柔軟な働き方を実践する人々が多く見られます。彼らは経済の周縁にいながら、地域の創造力の中心に位置しており、「ミセノマ」という開かれた場が、彼らの活動を媒介し、偶然の出会いや小さな経済圏を生み出しています。そこに息づくのは、個人の自由と共同体の関係性を両立させる、しなやかな共在の知恵です。
人口減少や高齢化の進行、そしてUターンやIターンなど多様なライフスタイルの広がりによって、京都の商業空間では店の流動性が高まっています。店を営む人々も、かつての「家族自営業」を中心とした構造から変化し、地域組織に属さず、独自の価値観のもとで小規模な店舗を営む層が増えています。
家族経営を前提に発展してきた「商店街」は衰退傾向にありますが、依然としてまちの維持・管理といった社会的役割を担い続けています。 出町周辺では空き地や空き家が増えていますが、それは同時に、限られた資本で新しい挑戦を始めたい人々にとって「潜り込む余地」ともなっています。
まるでスポンジのように穴が空く「都市のスポンジ化」は行政的には問題視される一方で、創造的な活動を生む余白でもあると著者は指摘します。空き家が文化やアートの拠点として再生され、人々が技芸を磨き、共有し、交換する場へと変化していく。ミセノマ的空間は、私的なクラブのような親密さを持ちながら、時に公的なインフラやパブリックスペースとしての役割を果たしています。
〈スキマ〉が生まれることで都市に流動性が生まれ、〈空き家〉が生じることで「異なる世界を結びつける技術」が生まれます。建物の不完全さに想像力を働かせ、空間を美的に変える。このアマチュア的感性が、都市の隙間を文化的な装置へと変えていくのです。
エスノグラフィの本質とは、まさにこの「うごめく関係性」の中にこそ、文化や社会の再生の芽を見出すことにあります。京都出町という小さなフィールドに刻まれた声、空気、光の交錯を丁寧に記述することで、有馬氏は「変化しながら続くまち」の知恵を可視化しました。それは、データでは捉えられない、人間の暮らしのレイヤーを読み解くための思考の実践でもあるのです。
ものとまちのあいだ ミセノマが生み出す文化的リズムと商世界の再定義
まちという水準でぼんやりと全体を見ることと、店という水準において細部をしっかりと観察することを往復すると、ものそれ自体に取り組む商世界の態様が浮かびあがる。ミセノマにおける〈もの〉の絡まりあいがどのように文化的、社会的価値を発生させているのかに目を向けると、〈もの〉自体と、〈もの〉を巧みにあやつる多種多様な〈アート〉が姿をあらわす。
〈スキマ〉と〈空き家〉は、もはや「問題」ではなく、「魅力」として都市に存在しています。そこでは本音を交わし、感情を共有する小さな「クラブ」のような親密な空間が生まれます。しかし一歩外に出れば、そこは取引や交渉が支配する公的な場──すなわち「バザール(商世界)」です。
哲学者リチャード・ローティが語るように、バザールとは、心地よい会員制クラブとは正反対の、偶然と交錯に満ちた公共空間なのです。
著者の描く「ミセノマのアート」は、まさに〈スキマ〉と〈バザール〉のあいだに広がる柔らかな境界です。そこでは、個人の創造性と社会的関係性が交わり、新しい文化と経済の形が同時に立ち上がっていきます。 「まち」にあるのは、表に見える店だけではありません。裏の倉庫や台所、そして時間の移ろい──朝と夜、季節の変化──によって、路上販売や観光客、アートプロジェクトなど、さまざまな存在が姿を見せます。
その境界は曖昧で、どこまでが「まち」で、どこからが「店」なのかを判別することさえ難しくなっています。そこでは異なる声や音、リズムが交錯し、ポリフォニック(多声的)な響き合いが絶えず生まれています。 現代の「店」は、もはやものを売り買いするだけの場ではありません。そこには、社会的・文化的機能が拡張されています。
たとえば、ミニシアターにカフェや本屋を併設する店、商店街の中にカフェ兼自宅を構え「芸術祭」を主催する人、喫茶店の壁を展示空間に変え、週末には農家と作家が並ぶマーケットを開く──こうした動きが京都各地で見られます。
都市の空き地や廃ビルといったかつての空白が、文化の回路として再解釈され、暮らしの一部として受け入れられるようになったのです。 まちという広いスケールで全体を眺めることと、店という小さなスケールで細部を観察すること。その往復の中に、商世界のリアルな様相が浮かび上がってきます。
遠景と近景を往還しながら見えてくるのは、〈もの〉を介した人と人の関係、そして「まち」が持つ多層的なリズムです。 ミセノマにおける〈もの〉の絡まりあいに目を向けると、そこには経済的価値を超えた文化的・社会的価値の生成が見えてきます。
商品としての〈もの〉は単なる物体ではなく、関係を媒介する存在であり、人々の手や感性を通して新たな意味を帯びていきます。その過程で、〈もの〉を巧みにあやつる多種多様な〈アート〉が姿をあらわすのです。 つまり、店とは単なる販売の場ではなく、都市における創造的な実験場であり、人々の生活と想像力が交錯する文化装置なのです。
そこでは、経済と表現、日常とアート、個人と社会が緩やかに結びつきながら、絶えず新しい「商世界(バザールワールド)」が生成され続けています。
鰹節店でのフィールドワークのなかで、著者は、血縁関係のない人々が働く職場にも、家族的経営の感情が息づいていることに気づきます。小豆や昆布といった「味覚」を伴うモノの共有は、強い連帯感を生み出し、まるで血のつながりに近い有機的な結びつきを生み出しているのです。
現代の老舗は、そうしたモノの力──味覚と記憶が結びつく共同体的経験──によって支えられています。 店の表と裏、内と外というミセノマで生じる小さな空隙が、人と人、個と共同体の関係を媒介しています。そのあいだにこそ、令和の「家族的経営」、すなわち「家族ではない者たちによる家族経営体」が成立しているのです。
効率や制度で説明できない信頼と協働のリズムが、店という空間を通じて今も息づいている──その姿を著者は丹念に描き出しています。
出町には、新たなスペース〈DELTA / KYOTOGRAPHIE Permanent Space〉が生まれています。軒先に設けられたテラス席は、客席としてだけでなく、打ち合わせやミーティングの場としても機能しています。。
テラスという装置の登場によって、「商店街を眺める」という新しい観客的まなざしが生まれました。テラスはカフェの付属空間であると同時に、まちへとにじみ出る半公共的な場でもあります。店内と通りのあいだに生まれたこの中間領域が、商店街そのものを「鑑賞する空間」へと変容させたのです。
このような構造は、従来の出町に見られたミセノマの形態には存在しませんでした。場所そのものが持つ価値──すなわちKYOTOGRAPHIEがもたらした空間的発想──が、まちに新たなミセノマの概念を導入したのです。 写真祭KYOTOGRAPHIEの展示拠点である〈DELTA〉は、商店街とギャラリーという二つの関係を重ね合わせることで、ブランドと地域の双方に新しいイメージをもたらしています。
文化と商い、鑑賞と参加のあいだに橋をかけるこの空間は、まちの新たな呼吸の仕方を示しているといえます。その空間は、カフェスペースとして商いを支え、ミーティングの場として交流を生み、子どもの遊びを見守る場として日常に寄り添っています。テラスという開かれたあいだの空間が、出町に新しい社会的リズムをもたらしているのです。
スキマを貸し借りする関係は、その都度の「目的」を共有する友人や仲間を得ることでもある。このような行為推行的な互酬的関係を構築することは、手段というよりもむしろ双方のミセノマを維持し可能にするために欠かせない技芸ともいえるものとなっているのである。
著者は、〈スキマ〉を貸し借りする関係を、単なる場所の共有ではなく、その都度の「目的」を共有する仲間を得る行為として描いています。こうした互酬的な関係は、手段というよりも、双方のミセノマを維持し、可能にするための「技芸(アート)」として機能しているのです。
本書では、軒先や倉庫といったスキマから新しいビジネスを始める人々が紹介されています。たとえば、倉庫の一角を間借りして営業するカフェは、スーパー前という立地を活かしながら、狭い空間を丁寧に整えています。壁には絵を飾り、入口には椅子と棚を置くなど、限られたスペースに店の世界を凝縮させています。 この店では、ベトナム産のロブスタ種という珍しい豆を自家焙煎し、独特の苦味と風味をもつコーヒーを提供しています。
地道な手作業の積み重ねを通じて、若い店主は買い物客や地元の商店主たちとの関係を少しずつ築いています。ミセノマを共有するとは、狭い空間の中で〈もの〉や技芸が重なり合い、新たな関係性が生まれていくことにほかなりません。
私も京都の商店街で買い物をするたびに、店の人との距離の近さを感じますが、本書を読んでその理由が明確になりました。それは、単なる接客ではなく、モノを介した共創や互酬の関係が今もなお生きているからです。小さなスキマに宿る人間的なつながりこそが、商店街というまちの持続力を支えているのだと感じます。
ミセノマは、店舗空間を持つものから路上やカウンター、軒先といった路上と建物のスキマを流用するものまでさまざまな者たちによって営まれている。
「まち」は、単にものを交換し、売買を行うだけの場所ではありません。そこには、文化的なつながりや、目には見えない相互作用が息づいています。言葉を交わすことで関係が芽吹き、声をかけることで社会が呼吸を始める。ミセノマは、そうした関係が立ち上がる「現場」であり、文化と経済、個人と共同体のあいだをなめらかにつなぐ柔らかな境界領域なのです。
本書は、まちを単なる背景ではなく、絶えず生成し続ける関係の舞台として描いています。人々の営みが織りなすリズムのなかに、都市が変化し続けるための知恵と、そこに生きる人々が紡ぎ出す力強い生命の鼓動があるのです。
エスノグラフィとは、そのリズムを聴き取り、記述するための方法であり、私たちが「まち」と共に生きるとはどういうことなのかを問いかけることだと、著者は本書で教えてくれています。
まちを観察することは、他者の営みを理解する行為であると同時に、自分自身の立ち位置を見つめ直す試みでもあります。人と人、店と通り、過去と現在が交差する場所に耳を澄ませると、そこには生きることそのもののリズムが聞こえてくるのです。



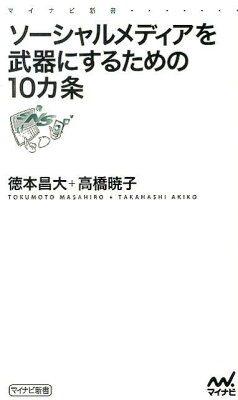














コメント