世界はいつまで食べていけるのか 人類史から読み解く食料問題
バーツラフ・シュミル
NHK出版

本書の30秒でわかる要点
結論: 80億(将来的に100億)人を養うことは可能だが、新技術による「破壊的イノベーション」に頼るのではなく、既存の仕組みの「漸進的な改善」が不可欠である。
原因: 食料問題は単なる「生産不足」ではない。生産プロセスの低いエネルギー効率、膨大な食品廃棄(30〜40%)、そして肉食中心の非効率な資源消費が根底にある。
対策: 食品ロスの削減、過剰な食肉消費の抑制と種類の転換、窒素肥料や水の利用効率の向上。これらを日常生活の延長線上で少しずつ変えていくこと。
本書の3行要約
農業を「文明を築く時間を生む仕組み」と定義する著者は、食料問題を単なる生産不足ではなく資源の変換効率と分配の歪みとして分析します。 特効薬的なイノベーションに頼るのではなく、食品廃棄の削減や食肉消費の緩やかな調整など、既存の仕組みの無駄を一つずつ潰す現実的な解決策を提示します。
おすすめな人
・食料自給率や輸入依存に不安を感じている人
・「ヴィーガン」や「培養肉」といった極端な言説に違和感があり、中立的なデータを知りたい人
・ビル・ゲイツが絶賛するバーツラフ・シュミルの、冷静かつ緻密な分析手法を学びたい人
読書が得られるメリット
・多角的な視点: 農業を「エネルギー変換」の歴史として捉え直すことができる。
・リスク管理能力: 気候変動や地政学リスクに対し、何が本当の脅威で、どこに改善の余地があるのかが明確になる。
・情報の選別眼: 危機を煽るメディアの報道に惑わされず、数字の裏付けを持って未来を予測できるようになる。
世界はいつまで食べていけるのか?バーツラフ・シュミルが読み解く食料問題
日本の人口は現在、年間約100万人のペースで減少しているが、少なくとも2040年代後半までは1億人以上を維持する見込みだ。長期的な傾向を踏まえると、輸入食料への依存度はさらに高まるだろう。この理由だけでも、次世代の世界の人々をどう養うかという問題について、日本は真剣に考えなければならない。(バーツラフ・シュミル)
昨今は米価格の上昇が目立ち、円安による輸入品の値上がりも重なって、日本でも食料問題が話題になっています。食費の上昇=インフレという形で家計に表れると、食料問題の話は一気に現実になります。
日本の人口は減少していますが、少なくとも2040年代後半までは1億人以上を維持する見込みです。当面は大きな人口を支える食料が必要であり続けますし、長期的には農業の担い手不足やコスト構造の問題もあって、輸入依存は高まりやすい状況です。
だからこそ食料安全保障や食料自給率は、理想論ではなくリスク管理として考える必要があります。国際価格、為替、物流、気候変動、地政学リスクのどれが揺れても、影響は輸入依存の高い国ほど先に出やすいからです。
メディアの報道を見ると悲観的になりがちですが、バーツラフ・シュミルの世界はいつまで食べていけるのか 人類史から読み解く食料問題(原題 How to Feed the World)を読むと食料問題の解決策が見つかります。本書は世界をデータで読み解き、何を優先して手を打つべきかを考えるための「見取り図」を与えてくれます。
著者はマニトバ大学の名誉教授で、約50年にわたり食糧を含むエネルギーや環境の問題を研究・執筆してきました。危機を煽るより、数字で仕組みを確かめる。この姿勢が本書の一貫した特徴です。
前著世界の本当の仕組み:エネルギー、食料、材料、 グローバル化 、リスク、環境、そして未来(原題 How the World Really Works)を読んだ方には「食」をテーマに絞った続編として読めますし、初めての方も食料問題の全貌を読み解ける内容になっています。(バーツラフ・シュミルの関連記事)
本書の前半で、著者は「私たちはなぜ農業を始めたのか?」と問いかけます。シュミルによれば、大勢の人を安定して養うには、作物を育て、動物を家畜にする以外の道はありませんでした。採集だけに頼る暮らしでは、食べ物を探して歩くだけで一日が終わってしまい、人口が増えるほどその負担は重くなります。
そこで著者は、チンパンジーの生活を引き合いに出します。果実を探して移動し続ける日々から、文字や都市、科学のような「余剰の上に成り立つもの」が生まれるとは考えにくい、というのです。農業は単に食べるための工夫ではなく、食料を安定させて“時間”を生み出す仕組みでもありました。
その時間が学びや仕事に振り向けられたからこそ、人間の社会は複雑になり、文明が形になっていった。シュミルはそう整理しています。
人類の食生活は、多種多様な植物を食べる方向ではなく、「少数の主食」を中心に組み立てられてきました。小麦・米・トウモロコシが主役になれたのは、たまたまではありません。育つのが比較的早く、たくさん収穫でき、長く保存できて、食べやすい。しかも、必要な栄養もある程度とれます。
主食になるには高い条件をいくつも同時に満たす必要があり、主要穀物はそれをクリアしました。だからこそ世界の食の土台になれたのです。
ただ、穀物だけで食事が完結するわけではありません。小麦や米だけでは、脂質とタンパク質が不足しやすくなります。そこで重要になるのがマメ科の穀物です。穀物はエネルギー源として優秀ですが、タンパク質の質には偏りが出やすい。一方、豆はタンパク質が多く、穀物の弱点を補いやすい。だからイネ科とマメ科を組み合わせる食べ方が、広い地域で長く続いてきたのだ、とシュミルは指摘します。
これは文化の違いというより、人間の体と生活に合った「合理的な組み合わせ」だった、という説明です。 さらに人類は、この土台に塊茎と油を足していきました。ジャガイモのような塊茎は、同じ面積からとれるカロリーが多く、環境によっては穀物より安定します。
油糧種子は、少ない量でもエネルギーが高く、脂溶性の栄養も補えます。こうして食事の質が上がり、季節や不作の影響が小さくなるほど、暮らしは安定します。長い時間軸で見れば、栄養状態の改善は体の弱さを減らし、平均寿命の伸びにもつながった、というのがシュミルの見立てです。
一方で、食料生産には「どこまでも増やせるわけではない」という現実もあります。作物づくりは、光合成という仕組みに依存していますが、光合成の効率は高くありません。
さらに、作物を育てるには大量の水と肥料(窒素)が必要です。水や肥料が足りなければ、収量はそこで頭打ちになります。たとえばコーヒー1杯分の豆を作るのに約130リットルの水が必要だという目安は、日常の「一杯」の裏側に、どれだけの資源が使われているかを思い出させます。食料は魔法のように増えるのではなく、限りある資源を変換して作られている、ということです。
食料供給は「作る」だけでなく、「届く・捨てない」の設計が重要
世界的に見れば、これは世界の膨大な食品廃棄物を削減することを意味し(この懸念にはようやく関心が向けられるようになった)、富裕国では大量の食肉消費量を減らし、食肉の種類の割合を変えることを意味する(これらのプロセスは以前から進行中ではあるものの、いっそう推進できるようになる)。そして、これが奏功するか否かは、日常生活で漸進的に変化を起こせるかどうかにかかっている。つまり、度肝を抜くほどの破壊的イノベーションとか、急進的な変化による大変動などという要素は皆無なのだ。日常生活で少しずつ変化を起こす。
シュミルが本書で強調するのは「漸進的な改善」です。食料問題というと、新技術で一気に解決する話が好まれがちですが、彼はそこに飛びつきません。すでにある仕組みの中にある無駄を減らし、効率を少しずつ上げるほうが、現実的で効果も大きいと考えます。 その象徴が食品ロスです。
生産された食料の30〜40%が、収穫後や流通・消費の段階で失われているという指摘は、問題の見方を変えます。シュミルは、食品廃棄物の削減こそ、追加の資源をいっさい投入せずに食料供給を拡大できる最も明確な方法なのに、たいてい軽視されていると述べます。
なぜなら、廃棄される食料の多くはすでに収穫され、加工や流通まで済んでいるからです。だからこそ、廃棄を減らせば、ほぼコストゼロ、あるいは非常に小さなコストで供給を増やせます。 同時に、すでに投入した水や肥料(窒素)、エネルギーの“無駄な消費”も減るため、食料生産による環境負荷も下げられます。増産は時間も資源も要しますが、廃棄削減は「すでにある分」を取り戻す話なのです。
だから著者は、柔軟な価格設定で売れ残りを減らすことや、容量やパッケージを工夫して「使い切れない」を減らすことを重視します。消費者が注意しても、店頭の売り方や家庭の冷蔵庫の容量、調理の手間、賞味期限の設定が噛み合わなければ、結局は余ります。食品ロスは「意識の問題」というより、仕組みの中で起きやすい失敗なので、失敗しにくい設計に変えるほうが成果が出やすい、という発想です。
肉の議論でも、シュミルは極端に走りません。牛肉を中心とした工業的畜産が、土地・水・飼料の面で効率が悪くなりやすいことを数字で示します。たとえば、世界の食肉が人間の摂取エネルギーに占める割合は大きくない一方、投入される資源は膨大です。
仮に「肉中心の食生活」で必要なエネルギーやタンパク質をまかなう方向へ社会全体が傾けば、家畜をいまより大幅に増やす必要が出てきます。そうなれば家畜の頭数だけでなく、飼料(牧草、イネ科穀物、塊茎、マメ科植物など)の生産量も増やさなければならず、土地、水、肥料、エネルギーへの負荷が一気に跳ね上がります。シュミルは、この種の「増やすほど苦しくなる構造」を数字で示し、現実的な落としどころを探ります。
ただし著者は、全員が菜食主義やヴィーガンになるという極端な提案にも問題があると指摘します。理由は現実的です。まず、人によって体質や栄養の必要量が違い、食習慣は文化や生活に深く結びついています。
さらに、厳格な菜食へ一斉に移行すると、豆類だけでは満足しにくくなり、結果として野菜、果物、ナッツ類などの比重が高まりやすいと見ます。ここで重要なのは、「何を減らすか」と同じくらい、「何が増えるか」を見ないと議論が片手落ちになる、という点です。
家畜飼料が不要になれば、豆類や主食用穀物を食用に回せる農地が増えるため、新たな土地やエネルギーの投入が不要になる可能性はあります。しかし、野菜、果物、ナッツ類の栽培は主食用穀物より労働力がかかりやすく、水の制約も強く受けます。
たとえばナッツ類は灌漑が必要になりやすく、単位エネルギー当たりの水消費が主食用穀物より大きいという指摘があります。
つまり「肉を減らせば万能」という話ではなく、代わりに増える作物が必要とする水や労働、物流まで含めて、全体の効率を評価する必要があります。シュミルが極端な主張を避けるのは、こうしたトレードオフを数字で捉えているからです。
もちろん、より多く、より良質な食料を生産することは今も重要です。特にサハラ以南のアフリカのように、単純に不足している地域ではなおさらです。ただし、世界人口が100億人に近づく中で、農業生産性を上げるだけでは飢餓と栄養失調は解決しません。
食料を手に入れやすくし、価格を抑え、食品ロスを減らし、量と同時に栄養価も確保する必要があります。ここで言う栄養価とは、カロリーだけを満たしても十分ではない、という意味です。安いカロリーがあっても栄養が欠ければ健康は支えられませんし、栄養価の高い食料があっても高すぎたり届かなければ意味がありません。
食料安全保障は「作る力」だけではなく、「届く仕組み」と「捨てない仕組み」まで含めた設計の問題です。気候変動が不確実性を増す時代には、食料自給率の議論も含めて、現実的なリスク管理として整理し直す価値があります。
日本でも米価格や輸入品価格の変動が示したように、「食は安定していて当然」という前提は揺れています。だからこそ、生産、流通、価格、廃棄、栄養というそれぞれの要素を切り離さず、どこに一番大きな改善余地があるのかを見極める必要があります。
著者は、80億人を養うという大きな課題を、感情に訴えるのではなく、データを使って論点の解像度を上げながら整理し、現実的な解決策を提示しています。本書を読むと、食料問題が「なんとなく不安な話」から、「どこを直せば改善できるかが見える話」へと変わっていきます。
長期予測には慎重であるべきだとしつつも、効率を少しずつ改善し続ければ、大規模な紛争や前例のない社会崩壊がない限り、世界は21世紀半ば以降も人口を養える可能性がある――そうした著者の条件付きの楽観は、私たちに過度な安心ではなく、現実を直視したうえで前に進むための手がかりを与えてくれます。
本記事は書評ブロガー・ビジネスプロデューサーの徳本昌大が執筆しました。



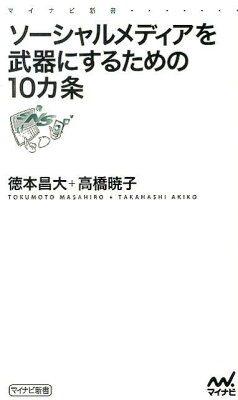












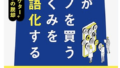
コメント