仕事と人生で削っていいこと、いけないこと 「理想の毎日」は自分でデザインできる
秋田道夫
PHP研究所
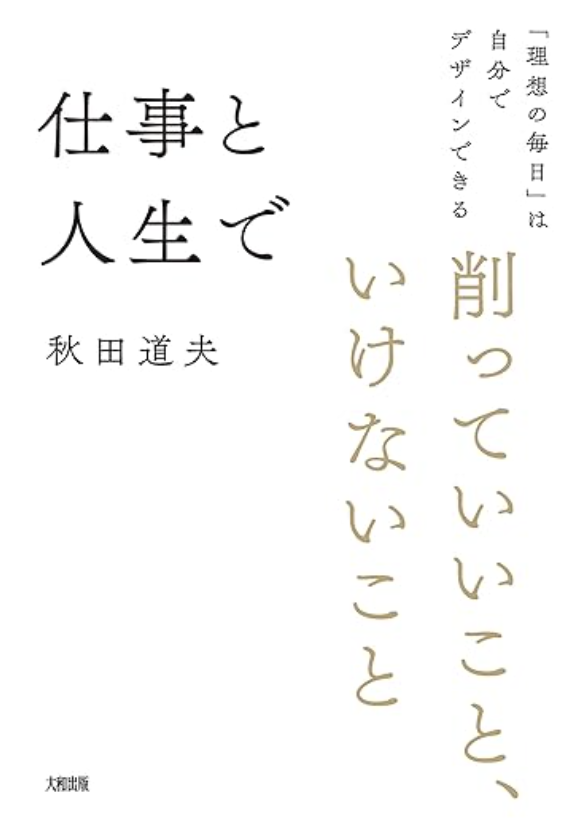
仕事と人生で削っていいこと、いけないこと (秋田道夫)の要約
秋田道夫氏は、「無駄」と思われがちな経験を「微細」と表現し、それを再評価する重要性を説きます。本書では、新たな価値観として「エスパ(Experience Performance)」を提唱します。コスパやタイパではなく、経験そのものの価値に注目し、成長や喜び、人との出会いを大切にする視点を提示します。効率だけに囚われず、人生を豊かにする小さな積み重ねの意義を考えるきっかけを与えてくれます。
Zoomだけでなく、直接人に会いにいくメリットとは?
仕事における問題を「速やかに」解決しないといけません。放っておくと、日に日に解決が難しくなっていきますよね。 つまり「穏やか」でいるのが遠のいてしまいます。 それを可能にするのは、先行して、積極的に取り組むことです。 そしてやはり、何事も、楽しむことが一番だと思います。(秋田道夫)
「仕事は速やかに、人生は穏やかに」。これは、プロダクトデザイナー・秋田道夫氏が自身の経験をもとに、生きる上での指針を説いた言葉です。
秋田氏は、効率化が重視される現代において、本当に大切なものを見極め、自分らしい生き方を見つけるためのヒントを提供します。本書を通じて、私たちが日々の生活で何を大切にすべきかを考えてみたいと思います。
現代社会では、すべてにスピードが求められます。仕事では「タイムパフォーマンス(タイパ)」、消費活動では「コストパフォーマンス(コスパ)」が重視され、効率が最優先される傾向にあります。その中で、秋田氏は「無駄」と見なされるものの中にこそ、人生を豊かにする要素があるのではないかと問いかけます。 秋田氏は、効率化至上主義に警鐘を鳴らします。
現代人は「無駄なもの」を徹底的に排除しようとしますが、その姿勢が私たちから大切な何かを奪っているのではないかと指摘します。例えば、「目で見るだけではなく、実際に手に取る」ことで得られる触感や重み、質感は、単なる画像では得られない深い理解や感動をもたらします。
また、「オンラインで済ませずに直接会う」ことも重要です。オンラインミーティングは移動時間を省略できる利点がありますが、対面でのコミュニケーションには、微妙な表情や空気感、予期せぬ会話の展開といった豊かな要素が含まれています。これらは人間関係を深め、信頼関係を築く上で欠かせません。 さらに、「移動時間を仕事で埋めようとせず、ぼんやり過ごす」ことにも価値があります。
私自身もZoomと対面のミーティングを使い分けながら、人に会いに行くことを大切にしています。画面越しではなく、会議の前後に雑談をすることで、相手の本音を引き出しやすくなり、人間関係をより深められることを再確認できます。
生産性の観点からは「無駄」と思われがちですが、こうした「何もしない時間」こそが脳に休息を与え、創造性を育むのです。電車の窓から景色を眺めたり、雲の形を想像したりすることで、新たな発想が生まれることもあると著者は言います。
「エスパ」で学び、アウトプットで活かす!
タイパ、コスパより、エスパ
秋田氏は、一見「無駄」と思われがちな経験や時間を「微細」と表現し、それらを再評価することの重要性を説きます。私たちの生活は、大きな出来事だけでなく、日々の小さな積み重ねによって形作られています。その「微細」な経験こそが、人生を豊かにする要素になり得るのです。 本書では、新たな価値観として「エスパ(Experience Performance)」という概念が紹介されます。
これは、コストパフォーマンス(コスパ)やタイムパフォーマンス(タイパ)とは異なり、経験そのものの価値に焦点を当てた考え方です。「エスパ」の視点では、その経験が自分にとってどれほど価値があり、人生を豊かにするのかが重視されます。
最初は失敗が多く、時間やお金もかかるかもしれません。コスパやタイパの観点からは「非効率」とされることもあります。しかし、「エスパ」の視点では、喜びや成長、人との出会いなど、目に見えない価値が重要視されるのです。
秋田氏は、「エスパ」の実践には「損を覚悟でやり始めること」が大切だと述べています。最初から完璧を求めるのではなく、まずは気楽に挑戦すること。そうすることで、失敗を恐れずに新たな経験を積み重ねられます。これこそが、「エスパ(経験価値)」の本質なのです。 たとえ失敗したとしても、その経験は人生の糧となります。行動を続けるうちに、思いがけないチャンスが巡ってくるものです
秋田氏は「エスパ」の重要性を強調しつつ、コスパやタイパの概念を否定しているわけではありません。むしろ、仕事や日常のルーティンは効率的にこなすことで、より多くの時間を本当に大切なことに使えるようになります。「仕事は速やかに、人生は穏やかに」——この考え方こそが、忙しさに追われがちな現代人にとって有効な生き方のヒントとなるのです。
私たちはしばしば「忙しい」ことを美徳とし、常に何かに追われています。しかし、その中で本当に大切なものを見失っていないでしょうか。秋田氏は、効率化すべきところは徹底的に効率化し、その分、真に価値のあることに時間とエネルギーを注ぐ生き方を提案しています
世の中を見ていると、どうも「インプット(情報)命」というか、情報を集めた時点で満足してしまう人が多いように思います。メディアが流す記事にしても、SNSにあふれる投稿にしても、情報を精査しないであれもこれも信じて、振り回されすぎていないでしょうか。これからは、インプッターではなくて、アウトプッターになりましょう。
学びにおいて「アウトプット」は非常に重要です。知識を得るためにインプットを重視しがちですが、実際にはアウトプットすることで学習が深まり、定着します。 私は「アウトプットのないインプットは、存在しないのと同じ」という考え方で、この書評ブログを書き続けています。
アウトプットを通じて、自分の理解度を確認し、足りない部分に気づくことができます。ときには厳しいフィードバックを受けたり、恥をかいたりすることもありますが、こうした経験が学習効果を高めるのです。
恥をかくことを恐れずに挑戦することで、知識は確実に自分のものになります。 また、誰かに説明することで、知識が整理され、インプットが促進されます。ブログを書く、人に教える、議論に参加するなど、さまざまな方法でアウトプットを続けることが大切です。 インプットとアウトプットのバランスを意識し、得た知識をすぐに活用する習慣をつけることで、効率的に学びを深めることができると考えています。
日常の中に学びがあり、その学びを人に語ることで、知恵とコミュニケーションカになっていきます。その「扉を開ける」のは笑顔です。つまり、なんでもない毎日を輝かせるのは自分次第だということです。
日常には多くの学びが隠れており、それを意識的に捉えることで成長の糧とできます。気づきを仲間に伝えたり、ブログやSNSで発信することは、単なる情報共有にとどまらず、大きな価値を生み出します。発信することで思考が整理され、言語化のプロセスでその内容への理解がより深まるからです。さらに、フィードバックを通じて新たな視点や考え方を得ることもできます。
この著者の言葉は、アウトプットが人生に彩りを与えることを示しています。自分の毎日を輝かせる鍵を握っているのは、ほかならぬ自分自身なのです。
To Enjoyリストが人生に喜びをもたらす!
わたしはTo Doリストを作りません。「今日これとこれをしなくっちゃ」というプレッシャーがいやなんですね。いやなことは忘れたい(忘れないためにリストを作るわけですが)。あえて作るとしたら、To DoリストではなくTo Enjoyリストがいいですね。「やらなきゃいけない」ではなく、「今日はこれをやるから楽しいよ」というふうにすると、前向きになれます。
現代社会では To Doリスト が生産性向上の基本とされていますが、それが逆に プレッシャー となり、ストレス を生み出すこともあります。そこで、著者はTo Doリストの代わりに 「To Enjoyリスト」 を作ることで、日常の取り組み方を根本から変えられると言います。
一般的なTo Doリストは「やるべきこと」の羅列になりがちです。そのため、タスクを達成できなかったときに 罪悪感 を感じやすく、次第に モチベーション低下 や 抵抗感 を引き起こしてしまいます。 一方で、To Enjoyリストは「今日楽しめること」に意識を向けます。同じ活動でも捉え方を変えるだけで、心理的な負担が軽減され、より前向きに取り組めるようになりそうです。
また、To Enjoyリストは脳の報酬系を活性化させ、自然なモチベーション向上 に役立ちます。これを習慣化すると、日々の活動が義務ではなく喜びの源 へと変化します。「やらなければならない」からではなく、「やりたいから」行動する生活は 自己決定感 を高め、結果的に 人生の満足度向上 につながるのです。
行動心理学的な観点からすると、思ったことを実際に行動する人は、継続できる人となると、100人に25人程度で、わずか5人(5%)になってしまうそうです。
行動心理学によると、新しいアイデアを実際に行動に移せる人は約25%、さらにそれを長期間継続できるのはわずか5%と言われています。多くの人が「明日から始める」と決意しても、実際に行動し続けるのはごく一部です。 著者はブログを20年継続していると述べていますが、私自身も15年間毎日書評ブログを更新し続けてきました。振り返ると、ブログを始めた時点で25%の行動する人に属し、1年以上続けることで5%の継続者の一員となっていました。
この習慣は単なる記事の蓄積ではなく、自己信頼感を育み、「言葉と行動を一致させる力」を鍛える貴重な経験でした。 「15年間毎日更新」という事実は、単なる数字ではなく、書き続けた証です。継続は複利のように効果を生み、15年間で7,000以上の書評を積み重ねた結果、文章力や思考力が磨かれ、新たな機会を引き寄せました。
継続には困難や停滞期がつきものですが、それを乗り越えることで精神的な強さが養われます。「忙しい」「調子が悪い」といった言い訳が浮かぶ日もありましたが、それでも更新を続けることで、困難を言い訳にしない姿勢が身につきました。5%の継続者になるために特別な才能は必要なく、毎朝パソコンを開き、書き始めること、それを習慣にする力があれば、誰にでも達成できるのです。
秋田氏は、自身の経験を交えながら、「理想の毎日」を実現するための具体的なヒントを紹介しています。例えば、「大事なことこそ朝にやる」、「まず自分に優しく、その余裕で人にも優しく」、「アンバランスな自分を見せる」、「損を覚悟で行動する」「元を取ろうをやめる」など、日常で実践できる方法が示されています。これらは小さな変化かもしれませんが、継続することで大きな効果をもたらします。
本書は、効率化が重視される現代社会において、立ち止まって自分自身を見つめ直すための指針となる一冊です。「仕事は速やかに、人生は穏やかに」という秋田氏のメッセージを大切にしながら、日々の生活を見つめ直していきます。




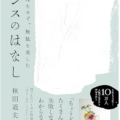










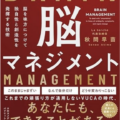

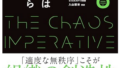
コメント