決めつけてはいけません、他人を。何より自分を。: 気楽さとやさしさの倫理学
秋田道夫
夜間飛行
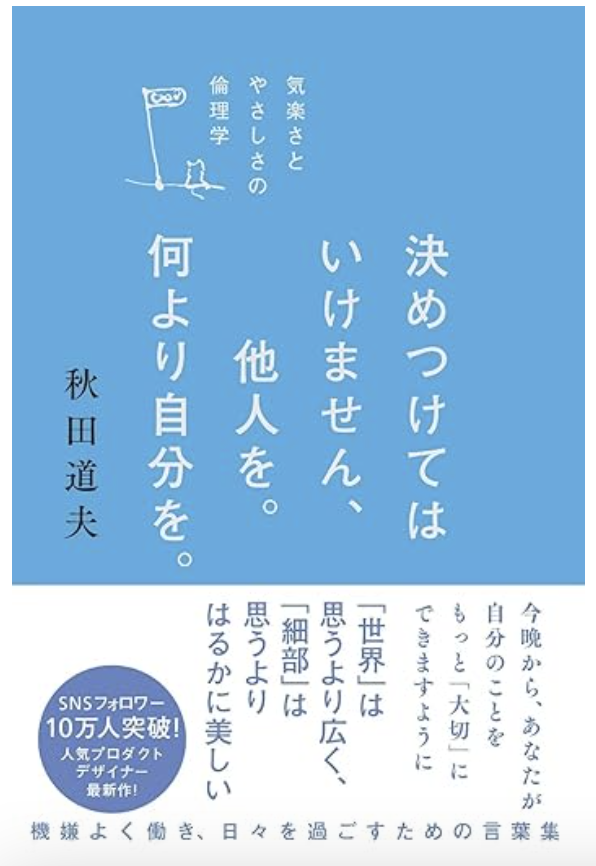
決めつけてはいけません、他人を。何より自分を。(秋田道夫)の要約
人生には偶然と必然が交錯し、私たちはその二つの力に導かれながら生きています。偶然に見える出会いや出来事の背後には、過去の選択や行動の積み重ねがあり、実は必然だったのかもしれません挑戦や失敗は新たな偶然を生む源であり、行動することで人生の意味が深まります。偶然という包装紙を開くたびに、私たちは成長と発見の喜びに出会うのです。
「年」ではなく、「日」単位で行動しよう!
70歳になった日から、「年」で考えることをやめました。「年」で考えるのではなくて、「月」も「週」も飛ばして、「日」で考えるようにした。 今日やれることは今日やってしまう。それを積み重ねていって、結果的に「○歳」になればいいじゃないかと考えるようにした。 こうしてみたら、驚きました。 毎日がとても新鮮に感じられるんです。毎日がすごく面白いんですね。(秋田道夫)
プロダクトデザイナーの秋田道夫氏の決めつけてはいけません、他人を。何より自分を。: 気楽さとやさしさの倫理学は、穏やかでありながらも鋭い視点を持つ一冊です。本書を通じて私たちは、日常生活におけるさまざまな「決めつけ」から解放され、より気楽に、そして他者に対して優しく接するためのヒントを得ることができます。
著者は「価値観の共有とは、価値観の違いの共有である」と指摘しています。 この言葉は一見、矛盾しているようにも感じられますが、そこには深い意味があります。人と人は、それぞれ異なる経験や背景を持っています。当然、考え方や感じ方も異なるものです。
大切なのは、その違いを否定するのではなく、違いがあるという前提のもとで向き合い、対話を重ねていくこと。つまり「違っていてもいい」と認め合うことこそが、真の意味での価値観の共有なのです。
著者は、70歳になった日から「年」で考えるのをやめたと言います。「年」どころか、「月」も「週」も飛ばして、「日」で考えるようにしたそうです。 「今日やれることは今日やってしまう。それを積み重ねた結果、気づけば○歳になっていればいい」。そう考えるようにしてから、毎日が驚くほど新鮮に感じられるようになった、と秋田氏は語っています。
私たちはつい、「今年中に目標を達成しよう」「今月こそ頑張ろう」といったように、大きなスパンで物事を捉えがちです。しかし、それはときに漠然とした不安やプレッシャーを生み、行動を先延ばしにしてしまう原因にもなります。
秋田氏の経験は、時間の単位を「日」に変えることで、行動が明確化され、日々の充実感や達成感が高まることを示しています。実際に「一日」という小さなスパンで考えることで、日々やるべきことが明確に把握でき、着実な行動が促されたと言います。
また、小さな成功体験が積み重なることで自信が生まれ、結果的に大きな目標達成にも近づいていくのです。 人生の折り返し地点を過ぎた時期にこそ、このような日単位の考え方がより意義深いものになります。将来の漠然とした不安に縛られるよりも、「今日をどう楽しむか」という具体的な問いにフォーカスすることが、精神的にも生産的にも優れた選択肢となるでしょう。
私も、残された時間を数えるのではなく、一日一日の質を高めることに意識を向けるようになってから、自分にとって、価値のあることに時間を使えるようになりました。また、「やらないこと」を明確に決めることで、時間をより有効に活用できるようになりました。
私の周りを見渡すと、年齢に関係なく生き生きとしている人々には、「今日」を大切にするという共通点があります。彼らは「もう歳だから」とは言わず、常に「今日はどんな発見があるだろう」という好奇心を持ち続けています。
今日を楽しむという姿勢こそが、心の若さを保つ秘訣です。「年」という大きな単位で人生を測るのではなく、「日」という小さな単位で味わい尽くす――この視点の転換は、日常の見え方を一変させます。特別なことをする必要はありません。今日一日、自分にとっての「面白いこと」を見つける。それだけで、人生は豊かさに満ちていくのです。
私の大好きな作家のアーネスト・ヘミングウェイの「毎日が新しい日だ」という言葉を著者は紹介していますが、過去に縛られず、未来に怯えず、「今日」というたった一日をまっすぐに生きる。そんな姿勢が、人生を本当の意味で豊かにしてくれるのです。
「偶然」に見える必然──人生の転機を生む行動と思考の力
「偶然」とは「必然」を包んだ包装紙の名前。
私たちの人生は、「偶然」と「必然」という二つの力に導かれているように見えます。道を歩いていて旧友とばったり再会することがありますが、これは果たして偶然なのでしょうか。それとも、何かしらの流れによって導かれた必然なのでしょうか。
長年の努力の末に手に入れた成功も、ただの結果ではなく、その過程における選択と行動の積み重ねによって生まれた、避けられない結末だったのかもしれません。
『「偶然」とは「必然」を包んだ包装紙の名前』と秋田氏は言います。何かが突然起きたように見えても、実はそれまでの歩みや価値観、思考、行動の積み重ねがそれを引き寄せていた──そのように考えると、偶然に対する見方が大きく変わってきます。
人生を振り返ると、思いがけない出会いや出来事が、大きな転機となっていることが少なくありません。たとえば転職のきっかけとなったのが、ふと立ち寄った場所での出会いだったり、人生のパートナーとの出会いが、何気ない日常の一場面に潜んでいたりすることがあります。旧友との再会が人生の方向を変えた経験を持つ人もいるでしょう。
自分にとって「都合の良い人」「好きなモノ」に囲まれる時間は必要です。大事なことは「それ以外の時間」も受け入れることです。
本当に大切なのは、予定された時間や計画通りの出来事ではなく、それ以外の時間──すなわち、予期せぬ出会いや思いがけない環境の変化を、しなやかに受け入れていく姿勢なのかもしれません。そうした意外性の中にこそ、これまでの自分を超えていくきっかけが潜んでいることがあるのです。
そして、自分を変えたように思える「偶然」の瞬間も、その背景を辿ってみると、自分が積み重ねてきた価値観や選択の軌跡と密接につながっていることに気づきます。あの日、あの場所にいたことも、まるで偶然のようでいて、実はそれまでの生き方が静かに導いていた、ごく自然な結果だったのかもしれません。偶然という包装紙をそっと剥がしてみれば、その中からは、確かに「必然」の姿が浮かび上がってくるのです。
東洋思想にも、偶然と必然に対する深い思考が見られます。禅の教えの中には「縁起」という考え方があります。これは、すべての出来事が相互に依存し合い、複雑に絡み合った条件のもとで起きるものであるという思想です。私たちが偶然だと感じる出会いも、実は無数の要素が重なった末の必然であり、その一つひとつがなければ成立しなかった出来事なのです。
また、思い通りにいかなかった出来事、予期せぬ挫折や失敗に対しても、ただの不運として片付けるのではなく、それが自分に何を教えてくれているのかを考えることができるようになります。「なぜ自分だけがこんな目に?」という問いから、「これは自分に何を気づかせるための出来事だったのだろう?」という問いへと意識が移っていくとき、その出来事の意味が少しずつ明らかになってきます。
人生における出会いや転機に意味を見出すことができるようになると、目の前にある現実がより豊かに、そして前向きに感じられるようになるのです。
スタンフォード大学のクランボルツ博士によって提唱された「計画的偶発性理論」は、偶然の出来事を人生や仕事のチャンスとして活かすという考え方です。多くの人が、思いがけない出会いや予期せぬ出来事をきっかけに、新たな進路を切り拓いてきました。しかし、それを好機として生かせるかどうかは、自分の姿勢や意識の持ち方にかかっているのです。
新しい経験に対して開かれ、柔軟に対応し、前向きな気持ちを持ちながら、時にはリスクを取って一歩を踏み出す──こうした姿勢こそが、偶然をただの出来事で終わらせず、自らの人生を動かす力へと転換する鍵となります。 私たちは偶然に見える出来事の中に意味を見出し、それを自分自身のストーリーとして編み上げていくことができます。
偶然を装った必然を、ただ受け入れるだけでなく、そこから何かをつかみ取り、自らの人生を形作る素材として活かすことができるのです。
人生における偶然もまた、私たちに驚きや感動をもたらし、思いがけない気づきや成長のきっかけを与えてくれる大切な存在なのです。その美しい包装紙を手に取るたびに、私たちは自分の人生がどれほど豊かで、予想を超えたものであるかを思い出すことができるでしょう。
いまだに恥ずかしい経験をしています。それだけ『新しいことをしている』ということにしています。
居心地の良い環境にいることで、失敗は少なくできますが、成長もまたゆるやかになってしまいます。だからこそ、未知の世界に一歩踏み出し、ときに戸惑い、ときに失敗することが、人生を豊かにし、偶然と必然の糸を新たに紡いでいくのだと思うのです。
偶然の出来事は、挑戦し続ける人のもとにこそ訪れます。その偶然の扉を開ける鍵は、私たちの行動の中にあるのです。
本書は、私たちが日々の生活の中でつい忘れてしまいがちな、他者へのやさしさや寛容さ、そして自分自身への許しを思い出させてくれる一冊です。本書を読むことで、より気楽に、そして心穏やかに生きていくためのヒントを得ることができるでしょう。




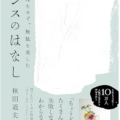
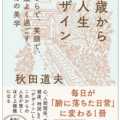







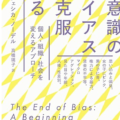
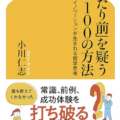
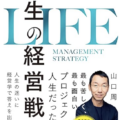
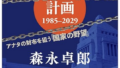
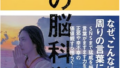
コメント