敵とのコラボレーション――賛同できない人、好きではない人、信頼できない人と協働する方法
アダム・カヘン
英治出版
敵とのコラボレーション(アダム・カヘン)の要約
ストレッチ・コラボレーションとは、従来の協働の枠を越え、対立とつながりの両立、多様な視点を取り入れた実験的な進行、自らの関与による変化という3つの姿勢を重視するアプローチです。これは、相手を変えるのではなく、自分も変わる覚悟を持ち、他者との違いを受け入れながら共に前進することを意味します。ときに「敵」と感じるような相手さえも、対話と協力を通じて貴重な学びをもたらす存在になります。
ストレッチ・コラボレーションが求められている理由
非従来型のコラボレーションの方法、ストレッチ・コラボレーションは、コントロールという想定を捨て去るものだ。調和、確実性、従順という非現実的な幻想をあきらめ、不協和音、試行錯誤、共創という混乱した現実を受け入れるのだ。武術の稽古のようなイメージだ。ストレッチ・コラボレーションなら、複雑な状況であっても、賛同できない人、好きではない人、信頼できない人と一緒に物事を成し遂げられる。(アダム・カヘン)
トランプ大統領による国際秩序の再編は、世界に大きな影響を与えています。これまでの政治的常識が通用しない局面が増える中、私たちは新たな協力のかたち――より柔軟で、より現実的なコラボレーションの在り方を模索せざるを得なくなっています。
そうした時代背景の中で注目されているのが、レオス・パートナーズ社のパートナーであり、国際的な対話ファシリテーターとして知られるアダム・カヘンです。彼は著書敵とのコラボレーションにおいて、私たちが「賛同できない人」「好きではない人」「信頼できない人」とも協働しなければならない時代に生きていることを前提とし、従来の協働の枠を超えた新たな方法論を提示しています。
カヘンは、南アフリカのアパルトヘイト後の和平プロセスをはじめ、中東や中南米など、深刻な分断の続く地域において、異なる立場や価値観を持つ人々の間で対話を設計し、合意形成を支援してきた経験を持ちます。その豊富な実践知は、本書の中にも随所に息づいており、単なる理論書ではなく、現実に根ざした「使える知恵」として読者に訴えかけます。
特にカヘン氏が提唱する「敵化」という概念は、現代の協働を考えるうえで示唆に富んでいます。私たちは、自分と異なる存在を敵と見なすことで、安心感や自己肯定感、あるいは一種の正義感を得ようとする傾向があります。敵を設定することで、物語は単純になり、自らの立場が明快になります。
しかし、この構図が問題の核心を見えにくくしてしまうことも少なくありません。 敵対的な枠組みにとらわれてしまうと、対話の余地は狭まり、協働の芽は摘まれてしまいます。カヘン氏は、まさにそのような固定化された対立構造に「橋をかける」視点の重要性を説いています。違いに目をつぶるのではなく、その違いとどう向き合うか。そこに、これからの協働の可能性があるのではないでしょうか。
敵がいるという構図は、一見ドラマチックで魅力的に映りますが、その背後には「決定的な勝利」という現実離れした幻想が伴いがちです。そしてその幻想が、私たちの注意を実際に取り組むべき現実的な課題から遠ざけてしまうのです。
私たちは、政治、仕事、家庭といったあらゆる場面において、基本的に4つの反応――すなわち「協働(コラボレーション)」「強制」「適応」「離脱」という選択肢を持って行動しています。もっとも、実際の状況においては、常にこの4つすべての選択肢が等しく存在するとは限りません。たとえば、強制という手段をとるための権限や条件がそろっていないこともあります。
それでも、私たちは常にこの4つのうちどれかを選びながら対応しているのです。多くの人は、協働こそが最善であり、道徳的にも正しい「標準」の選択肢だと考えがちです。私たちは皆、互いに依存し合い、つながって生きているのだから、協力すべきだという前提を自然と持っているのです。
ただ、私たちは、誰とでも常に協力できるわけではありませんし、また誰とも協力できないというわけでもありません。だからこそ、協働は「常に正しい」とも「常に誤りである」とも言い切れないのです。 重要なのは、抽象的な善悪の判断ではなく、具体的な状況ごとに「協働すべきか否か」を冷静に見極める姿勢です。現実の中で私たちが直面するのは、正解のない選択であり、その都度最適な判断を下すことが求められているのです。
カヘンはまた、従来型の協働の限界を明確に指摘しています。例えば病院における組織改革を例に取り、従来のコラボレーションでは、統一した計画や共通の利益に基づいてチーム内の価値観や利害を一時的に棚上げしようとしますが、結果として現場スタッフからの反発や計画の停滞が頻繁に起きることを指摘しています。
この問題の根源は、単一の正解への固執、トップダウンによる価値観の押し付け、そして現場のモチベーション不足にあります。 そこで提唱されるのが、「ストレッチ・コラボレーション」という新しい概念です。
この方法論は、組織や社会が単一の全体ではなく、複数の部分的な全体が重なり合って成立していることを認め、唯一の正解を求めるのではなく、試行錯誤のプロセスを重視します。また、他者を一方的に変えようとするのではなく、自分自身も変化を受け入れる柔軟性が求められます。対立を無理に解消しようとはせず、異質な相手と共に新しい道を創り出すことが重要とされています。
ストレッチ・コラボレーションの3つのストレッチ
自分の敵だと思う人が、意外にも、協力的な役割を果たす可能性がある。ストレッチ・コラボレーションでは、異質な他者から遠ざかるのではなく、そういつ人に向かっていくことが求められる。最も難しいと感じるような状況、すなわち、こちらの期待するように相手が動かず、いったん休止して新しい前進の道を見つけざるをえないときこそ、学びが最大になる。そう、敵は最大の師になりうるのだ。
ストレッチ・コラボレーションとは、これまでの協働の枠組みを根本から見直し、柔軟かつ実験的な姿勢で協働を再構築するアプローチです。この考え方では、「3つのストレッチ」が重要な土台となります。
まず1つ目は、「関係性のストレッチ」です。従来のようにチーム内の目標達成にのみ集中するのではなく、対立や緊張感を避けず、むしろ積極的に関係性の幅を広げていく必要があります。仲間との調和だけでなく、対立する意見との接点にこそ、新たな可能性が生まれるのです。
2つ目は、「進行方法のストレッチ」です。問題・解決策・計画に対する明確な合意を前提にするのではなく、多様な視点と意見をもとに、段階的に試しながら前進していくことが求められます。ここでは、単なる議論(ディベート)ではなく、対話(ダイアログ)と「いまここ」に深くつながるプレゼンシングが鍵になります。話す力と同じくらい、偏りなく聴く力が大切なのです。
3つ目は、「自己関与のストレッチ」です。人を変えようとする前に、自分自身も変化の一部であるという前提に立つ必要があります。つまり、自らも「ゲームに足を踏み入れる」という覚悟を持つこと。傍観者ではなく、実践者として関与し続ける姿勢が求められます。
これら3つのストレッチは、簡単なことではありません。むしろ、違和感や不安を伴う挑戦です。しかし、最初から完璧を目指すのではなく、小さな行動を積み重ねることが大切です。実験するように動き、結果を観察し、少しずつ軌道修正していく。即興演劇のように、柔軟に状況を受け入れながら進んでいく感覚が有効です。
加えて、自分の影響力を客観的に見つめること、そして信頼できる仲間にフィードバックを求めることも重要です。自分自身の枠を広げるためには、外からの視点が不可欠だからです。
ストレッチ・コラボレーションでは、「コントロール」という幻想を手放します。完璧な計画や理想的な秩序に頼るのではなく、不確実性や混乱、摩擦を前提とした現実を受け入れるのです。そして、そこから生まれる偶発的な成果を尊重します。予想外の出来事や計画外の成果が、新たな価値につながることも少なくありません。
ここで大切なのが、「関わる(愛)」と「主張する(力)」のバランスです。どちらか一方に偏るのではなく、状況に応じて交互に用いることで、建設的な関係性を築くことができます。愛がなければ共感は生まれず、力がなければ変化は起こりません。この両輪が噛み合ってはじめて、協働の質が高まるのです。
このアプローチは、国家間の紛争や政治的な対立といった大きな文脈に限らず、企業経営や教育現場、地域活動、さらには家庭内の関係性に至るまで、幅広く応用可能です。複雑で先の見えない時代においては、誰が正しいかを争うことよりも、「関係性をどう築くか」がより重要な問いとなっています。 そして、見落としてはならないのは、自分にとって「敵」と映る相手の中にも、実は深い学びの種があるという視点です。違いを恐れるのではなく、その違いに向き合い続けることで、初めて新しい可能性が開かれます。
本手法の実践者である著者自身が、このアプローチを用いて実際に国際的な紛争の現場で成果を上げてきたという事実は、理論にとどまらない強い説得力を持っています。理念と現場の両面を兼ね備えているからこそ、この手法は私たちの日常にも確かなヒントをもたらしてくれるのです。
ストレッチ・コラボレーションでは、異質な他者を遠ざけるのではなく、意識的に近づいていくことが求められます。思うように進まず、いったん立ち止まるような状況こそが、深い気づきをもたらす場になりえます。
そう、敵は最大の師になりうるのです。 違いを解消するのではなく、違いの中で「共にいる」ことを選び続ける。それが、現代社会における本質的なコラボレーションのあり方だといえるでしょう。
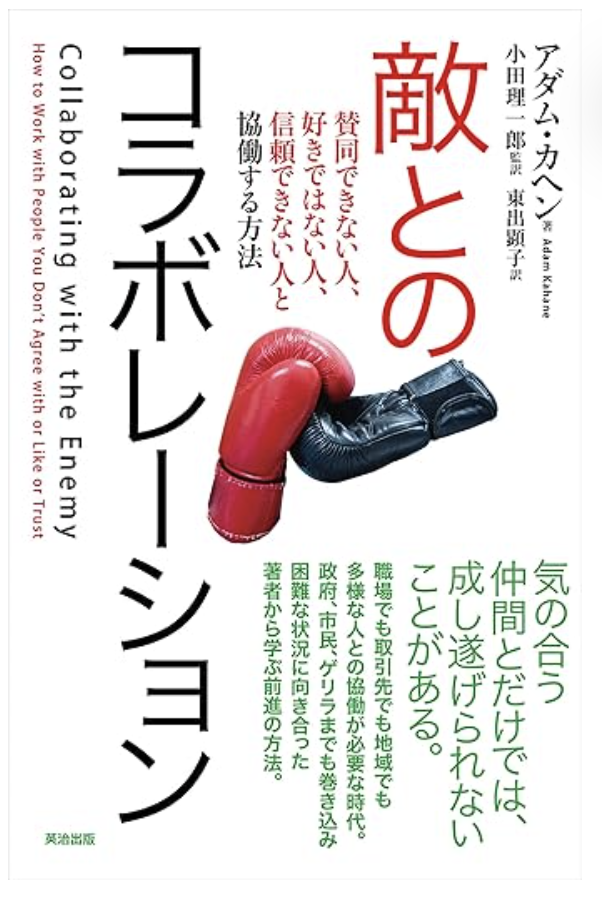


















コメント