行動探求 ― 個人・チーム・組織の変容をもたらすリーダーシップ
ビル・トルバート
英治出版
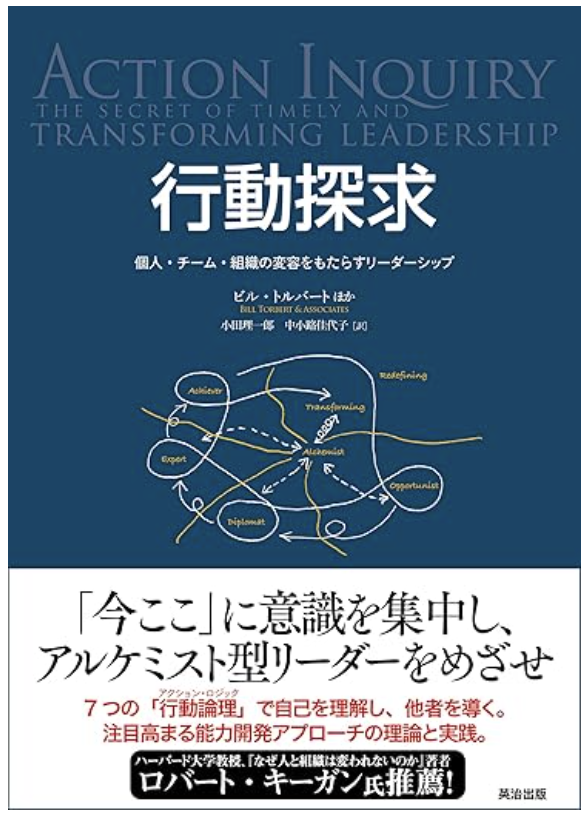
行動探求 ― 個人・チーム・組織の変容をもたらすリーダーシップ(ビル・トルバート)の要約
ビル・トルバート著『行動探求』は、リーダーが行動しながら同時に内省し、自己と組織の変容を促す実践的アプローチを提唱しています。行動と探求を統合し、「今この瞬間」における判断力や意識の深さを高めることで、より誠実で持続可能なリーダーシップを育みます。自己の行動論理の成長段階を理解し、「トリプル・ループ学習」を通じて思考の枠組みそのものを問い直すことが、真の変容をもたらす鍵となります。
リーダーが身につけるべき行動探求とは?
行動探求は、私たちの行動のより幅広い効果を高める、律されたリーダーシップ習慣として、行動と探求を同時に行う方法である。これができれば、個人も、チームも、組織も、さらに大きな機関も、もっと自己変容できるようになり、それによって、より創造的で、より自覚的で、より正しく、より持続可能になることができる。(ビル・トルバート)
リーダーシップとは、しばしば「他者を導く力」と定義されます。しかし、実際の組織運営やチームマネジメントの現場で、その力をどのように育て、どう機能させるべきかを体系的に教わる機会は意外なほど少ないのが現実です。
成果へのプレッシャー、部下との信頼関係、複雑化する組織構造、そして変化の激しい市場環境――そうした中で、多くのリーダーが自らの判断に自信を持てず、孤独と葛藤の中で模索を続けています。どこに軸を置き、何を拠り所にすればよいのか。
その問いに真正面から向き合った一冊が、ビル・トルバートの行動探求 ― 個人・チーム・組織の変容をもたらすリーダーシップです。 その「在り方」に変容をもたらす鍵として、本書が提唱するのが「行動探求(アクション・インクワイアリー)」というアプローチです。
トルバートは、ハーバード教育大学院や南メソジスト大学でリーダーシップ教育に携わった後、1978年から2008年までの30年間、ボストン・カレッジ経営大学院(現在のボストン・カレッジ・ウォレス・E・キャロル経営大学院)で学長として教育と研究に尽力しました。
理論と実践を行き来しながら、「人がどうすればよりよく変わり続けられるのか」「リーダーシップとは何をもって磨かれるのか」といった根源的な問いに挑み続けた人物です。彼のアプローチは、単なる理論の提示ではなく、読者自身がそのプロセスを通じて「探求」し、気づきを得ていくよう設計されています。
行動探求は、私たちの行動のより幅広い効果を高める、律されたリーダーシップ習慣であり、行動と探求を同時に行う実践を意味します。目の前の出来事に反応するだけでなく、その瞬間に「なぜそうするのか」「他の選択肢は何か」といった問いを内包しながら行動することができれば、個人もチームも、そして組織全体も自己変容を遂げることが可能になります。その結果として、私たちはより創造的で、より自覚的で、より正しく、そしてより持続可能な存在へと進化できるのです。
行動探求は、単なる一時的なスキルではありません。これは、生涯にわたる「変容をもたらす学習のプロセス」であり、個人から組織レベルにまで及ぶ実践です。
そして、次のような目標に取り組む人にとって、極めて有効な手段となります。
・将来のビジョンを実現する能力を高めたい
・今起きている危機やチャンスにいっそう敏感になりたい
・いっそう効果的かつ変容につながるやり方で行動できるようになりたい
私たちはしばしば、行動と内省を別物として扱いがちです。忙しさに流され、日々の判断や対応が「こなす」ことに偏ってしまうこともあるでしょう。そうした中で、いまこの瞬間の行動が、自分自身の内面や組織の未来にどう影響するのかを問い直す視点は、どうしても後回しになりがちです。そんな状況に一石を投じるのが、ビル・トルバート氏の提唱する「行動探求」なのです。
「いつ」――時間という概念には、実は二重の意味合いがあります。ひとつは、誰もが思い浮かべるであろう、過去・現在・未来という時間の流れの中で、どのタイミングで物事に手を打つべきかという視点です。
たとえば、新しい事業を展開するのは今年なのか、来年か、あるいは5年後なのか。リーダーとしての意思決定において、時宜を得た判断を下す力は重要です。戦略的な長期視点を持つことは、未来の可能性を見極めるうえで不可欠です。
しかし、見落とされがちな「もうひとつの“いつ”」があります。 それは、時間のより繊細で即時的な次元――つまり、「今この瞬間に何をどう行うか」というリアルタイムでの判断です。 たとえば、会議の場では、言葉の背後に流れる感情の変化や対話のリズム、沈黙が持つ意味など、さまざまな要素が交錯しています。
それら一つひとつに細やかに注意を向け、「この瞬間における最善の対応は何か」を見極める力が求められます。 誰かが何かを主張したその瞬間に、反論すべきか受け止めるべきかを判断する。 議論を優位に進める言葉を投げかけるべきか、それとも数秒間、静かに相手の表情を見守るべきか。 こうした瞬時の判断の積み重ねが、リーダーとしての影響力の質を大きく左右するのです。
行動探求は主に内から外に機能する。
つまり、「行動」の適切さは、「探求」の深さに比例するということです。今この瞬間に集中し、その瞬間に起きていることを深く観察し、自分自身の反応や内面の動きを同時に捉える。そこにこそ、真に効果的なリーダーシップが生まれます。
ここで重要なのは、「行動」と「探求」を決して切り離して考えないことです。行動が先で、探求はその後――という順序では、変容は起きません。逆に、探求だけに偏り、行動を先送りにしていては、組織やチームに実際の変化を起こすことはできない。
トルバートが本書の中で繰り返し強調するのは、まさに行動と探求の統合の重要性です。行動の最中にこそ、自己を観察し、状況を観察し、そこで得た気づきをもとに次のアクションを微調整していく。このプロセスそのものが「行動探求」であり、単なる反応や反省とは根本的に異なる在り方なのです。
問題を単に解決するだけでなく、前提そのものを問い直し、さらには「現実をどのように認識しているのか」という思考の枠組み自体を探求することによって、個人や組織の存在様式を変容させることができます。 この「変容をもたらす力」こそが、行動探求の特別な強みであり、その力は複数の要素が組み合わさることによって生まれます。
たとえば、自分たちの意図や共有ビジョンに忠実であろうとする姿勢を持つことが挙げられます。また、自分自身や他者のビジョン、戦略、パフォーマンス、そして実際の結果とのあいだにあるギャップを敏感に察知する力を持つことも大切です。 さらに重要なのは、私たち自身が変化の影響を受けることを恐れず、自らをその変化の中にさらけ出す覚悟を持つことです。
そのうえで、組織や社会の変容において他の人々とともに指導的な役割を果たす意志を持つことが求められます。こうした意識と行動を一体化させることで、真の意味でのトランスフォーメーション、すなわち変容を実現することができるのです。
行動探求におけるトリプルループ
深い精神的存在、つまりスーパービジョンは、自己像に基づいているのではなく、私たちの体験における4つの領域ー私たちの注意、戦略、行動、結果ーの間で起こっている実際の相互作用を体験することに基づく。
行動探求における最も深遠な側面の一つが、「スーパービジョン(深い精神的存在)」という概念です。これは、固定された自己像や静的なアイデンティティに依拠するものではありません。むしろ、私たちが日常の体験を通して接している4つの領域――すなわち「注意」「戦略」「行動」「結果」――のあいだに生じているリアルタイムな相互作用を、体験として捉える能力に基づいています。
この相互作用のプロセスは、システム理論の観点から「3次ループ(トリプルループ)のフィードバック」として説明されます。私たちが外の世界で生み出す「結果」から、「行動」や「挙動」(1次ループのフィードバック)が生まれます。
さらに、行動の背景にある「戦略」「構造」「目標」などが見直されることで、1次ループのフィードバックが生じます。そして最も深いレベルでは、「注意」や「意図」「ビジョン」といった、私たちの認識の根底にある意識そのものが問われ、そこに3次ループのフィードバックが働くのです。
この3次ループの視点に立つことで、私たちは単に行動を変えるのではなく、行動を生み出している思考の構造や意識の焦点そのものを見直すことが可能になります。つまり、外側の世界で得られた結果と、自らの注意、戦略、行動とのあいだにある現時点での関係性に深く気づくことこそが、このフィードバックの本質なのです。
このような「スーパービジョン」の状態――すなわち、自分の意識の動きとそれに連なる現実との関係を同時に見つめる在り方――は、行動探求が目指す成熟したリーダーシップの核心と言えるでしょう。
これは、単に「何をしたのか」や「なぜそうしたのか」を振り返るだけにとどまりません。「自分は今、どこに意識を向けていたのか」「何を見落としていたのか」といった、行動以前の状態をも含めた、より根源的な自己認識へとつながっていきます。
このトリプルループのフィードバックにおいては、行動の結果を分析するだけでは不十分です。重要なのは、「いま、ここ」において、自分の注意が何を捉え、何を見落としているのかを観察することです。そしてその観察のなかに、自分自身の戦略や行動の背後にある無意識の前提を照らし出す鍵が隠されています。
このように、私たちが「自分自身とともにある」状態――つまり、自分の内面の動きと外部での行動を統合的に体験している状態――に入ることが、リーダーシップの成熟にとって不可欠なのです。
行動探求におけるこの深い精神的存在は、単なる内省や哲学的思索とは異なり、極めて現実的なリーダーシップの実践へと直結しています。変化のただ中において、いかに冷静かつ鋭敏に自分自身を観察できるか。いかに状況の全体像を捉え、自らの影響力を意識的に用いることができるか。それこそが、行動探求を通じて育まれる「あり方」の核であり、真の意味でのリーダーシップの基盤なのです。
動探求の実践は、私たちが「どのように意識を働かせているのか」という問いを深く掘り下げるものです。その鍵となるのが、「4つの体験領域」の理解です。これは、私たちの注意が向けられる異なる次元を明示したものであり、行動と意識の関係性を明らかにする枠組みとして、本書の中核を成しています。
第1領域は「外部の出来事」です。ここには、私たちが環境に与えた結果や行動に対する評価、観察可能な成果、さらには他者や社会への影響などが含まれます。目に見えるアウトカムが中心となる領域であり、状況に対する問いかけと他者への傾聴が重要になります。
第2領域は「自分が認識する行動パフォーマンス」です。この領域では、自分自身の動作、スキル、行動パターンを自覚的に捉えることが求められます。自らの具現化された行為を内側から観察し、「自分がどのように行動しているのか」「どのように周囲に影響を与えているのか」を説明する姿勢が問われます。
第3領域は「行為を導く行動論理」です。ここでは、私たちの戦略や行動の前提となる思考パターン、スキーマ、行動計画などが含まれます。体験の認知を通じて、自分の思考や価値観に気づき、たとえ相違があっても、協調的な姿勢で目標に向けた手法を模索することが良好なコミュニケーションを生む鍵となります。
第4領域は「意図に関する注意」です。最も深い層に位置するこの領域では、私たちのビジョンや価値観、目的、そして「今ここ」に意識を置くプレゼンシングといった内的な注意が扱われます。自分が何を大切にしているのか、どのような未来に向かいたいのかといった、存在の源に近い次元を見つめ直すことが求められます。
行動探求の真価は、これら4つの領域すべてに意識的にアクセスし、それらのあいだに起きている相互作用をタイムリーに捉えながら、自らの行動と判断を調整していくことにあります。つまり、単に「やり方」を変えるのではなく、「なぜそうするのか」「どこからその選択が生まれているのか」といった根源的な問いに目を向けることが、真のリーダーシップ変容を導くのです。
そして、行動探求の本質をさらに深めるうえで欠かせないのが、「誠実さ」と「相互性」の意識です。いかに高度な理論やフレームワークを身につけたとしても、それを実践に生かすには、まず自分自身に対して誠実であること――すなわち、自らの意図や注意、行動の源泉に真摯に向き合う姿勢が必要です。
そこには、自分の思考や行動がもたらす影響に責任を持とうとする覚悟が伴います。 また、行動探求は決して個人だけの営みではありません。他者との関係性のなかでこそ、その価値は試され、深まっていきます。
相互性を重んじるとは、相手の視点や意図に敬意を払い、変容のプロセスを共に歩む姿勢を持つことを意味します。一方的な指導ではなく、共鳴と対話を通じて新たな可能性を共創することこそが、行動探求の真の力を発揮する鍵となります。 誠実さと相互性。
この2つの価値は、リーダーが他者を導くだけでなく、自らも変化の一部として関わり続けるための土台となります。行動探求は、そのような誠実で共創的な生き方と働き方を支える、極めて実践的なリーダーシップの道なのです。
リーダーシップの7つの成長段階
「行動探求」とは、何かを生み出すと同時に自己評価する行動パターンである。複数のことを同時に行うのだ。展開していく状況に耳を傾ける。優先順位が高いと思う、やるべきことをやる。そして必要であれば、そのやるべきこと(と自分自身の行動)を目的に遡って修正する。行動探求はつねにタイムリーな行動の規律となる。
「行動探求」とは、何かを生み出すと同時に、自分自身の行動を観察し、評価し、必要に応じて軌道修正していく行動のあり方です。言い換えれば、それは複数のことを同時に行う、極めて能動的で自律的な実践です。状況の変化に耳を澄ませ、今まさに何が起きているのかを感じ取り、優先順位が高いと思われる「今なすべきこと」を選び取り、実行に移します。
そして、それが本当に目的にかなっているのかを吟味し、必要であればその行動自体、あるいは目的そのものを問い直し、再定義します。
このように、行動探求はただ行動するだけの手法ではなく、目的と行動を絶えず照らし合わせながら、より適切な方向へと調整していくプロセスそのものです。したがって、行動探求は、リーダーとしての「タイムリーで的確な意思決定」を導くための規律ある習慣とも言えるでしょう。
本書では、こうした行動探求の力を支える基盤として、リーダーシップの成長段階を7つの「行動論理」によって分類しています。それぞれの段階は、単なる能力の差を表すものではなく、現実のとらえ方や価値観、そこから導かれる行動の質の違いを示しています。自らの現在地を知り、次の成長ステージに向けてどのような意識と態度が求められるのかを理解する上で、非常に実用的かつ深遠な指針となっています。
最初の段階である「機会獲得型」は、物理的な成果や外的な結果のみを現実とみなし、自分にとって有利な機会を逃さず掴もうとする傾向があります。 手段を問わず結果を追い求める姿勢は、非常時や短期的な判断が求められる場面では有効です。 しかしその一方で、長期的な信頼関係の構築には適さないとされています。
次の「外交官型」では、自分の行動が周囲からどう見られるかを重視し、社会的な規範やルールに従うことに価値を置きます。 この姿勢は、組織内での協調性や安定感を支える要素となりますが、急激な変化への柔軟性にはやや欠ける傾向があります。 また、親しい集団への忠誠や体面の維持を重んじ、「良きメンバー」としてふるまうことが求められます。
「専門家型」の段階では、経験から培った専門性や論理性を大切にし、問題解決や効率の向上に強い関心を持ちます。 その一方で、自らの論理に固執するあまり、他者との視点の違いを調整することが難しくなることもあります。 自分自身にも他者にも批判的な姿勢を持ちやすく、理論的には正しくても、対人関係において摩擦を生むことがあります。
「達成者型」になると、目標達成に対して強い意欲を示し、チームとの協働や合意形成も大切にします。 フィードバックを前向きに受け入れ、自己成長にも意欲的です。 ただし、自分の行動を支える枠組みや価値観そのものを深く問い直す意識はまだ希薄であり、活動の範囲は既存の価値観に基づいたものにとどまりがちです。
この上に位置づけられるのが「再定義型」です。 この段階では、これまで当たり前とされてきた前提やルールから距離を置き、複数の視点から物事を再構成しようとする姿勢が見られます。 変化を先読みする力に優れている一方で、明確な枠組みを重視する従来型の人々からは、頼りなく映ることもあります。
「変容者型」に至ると、行動しながら同時に自分と他者の状態を観察し、直感やフィードバックを活用して柔軟に行動を調整する能力が発達します。 この段階では、個人・組織・社会といった多層的な関係性に目を向け、発達の共通性を理解しながら、全体に働きかけるリーダーシップが発揮されます。
そして最も高度な段階である「アルケミスト型」は、調和を保ちながら同時に変容をもたらすことができる稀有なリーダー像です。状況の枠組みそのものを再定義し、想像力と感性を駆使して未来を創り出す存在として描かれます。
アルケミスト型の行動論理の核心
絶えず自分自身の注意を働かせ、直感、思考、行動、外の世界への影響の相互作用に対する1次ループ 2次ループ 3次ループのフィードバックを追求する。明るい面と暗い面、永続的なパターンの反復、以前暗示されていたものの出現を認識して、他者を包摂する現在に根ざしている。反するものの間の緊張の中に立ち、その融合を追求する。
トルバートはアルケミスト型を、「複数のことを同時に行うこと」に最も熟練した状態と表現しており、言語や論理を超えてストーリーや体験を通じた理解が求められます。 これらの発達段階は優劣を示すものではなく、自己理解の地図として捉えることが推奨されています。リーダーとしての意識の成熟度を把握することで、自らの次なる成長の方向性を見出すことができるのです。
アルケミスト型の行動論理の核心は、言葉や数値といった固定的な形式では捉えきれない、流動的で深遠な現実への開かれた姿勢にあります。このタイプのリーダーは、状況の不条理と常識という相反する側面の両方を同時に認識し、そこから新たな課題を見出し、それを誰もが理解できる明瞭な言葉で表現することを重視します。
このような姿勢は、「社会的柔術効果」を生み出します。すなわち、極限状況において人や組織が想像を超える柔軟性と力を発揮する現象です。歴史的には、チェコのヴァーツラフ・ハヴェルや南アフリカのネルソン・マンデラが体現したように、既存の枠組みを越える行動が、社会に深い変容をもたらしてきました。
アルケミスト型は、「善と悪」「勝利と敗北」「私たちとあの人たち」といった二項対立の見方にとらわれません。むしろ、そうした分断が、私たちの固定化された世界観によって日々再生産されていることを自覚し、それに対して意識的に向き合い続けるのです。
アルケミスト型のリーダーは、会話や体験を通じて、個々人の生活や歴史、そして過去と未来のコンテクストに根ざした「いま、ここ」に深く関与します。彼らが創出しようとするのは、単なる共感や協働ではなく、「探求の基盤コミュニティ」であり、最も困難な課題に対して共に向き合い、そこから変容を生み出す場です。
トルバートが本書の中で繰り返し強調するのは、まさにこの統合の重要性です。行動の最中にこそ、自己を観察し、状況を観察し、そこで得た気づきをもとに次のアクションを微調整していく。このプロセスそのものが「行動探求」であり、単なる反応や反省とは根本的に異なる在り方なのです。
最も魅力的な点は「トリプル・ループ学習」の概念です。問題を単に解決するだけでなく、前提そのものを問い直し、さらには「現実をどう認識しているのか」という思考の枠組み自体を探求することで、個人や組織の存在様式に変容をもたらします。
本書は、人を動かすリーダーシップを身につけたいビジネスパーソンにとって、極めて実践的かつ示唆に富んだガイドブックです。自己認識を深め、より効果的なリーダーシップを発揮したいと願う方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。
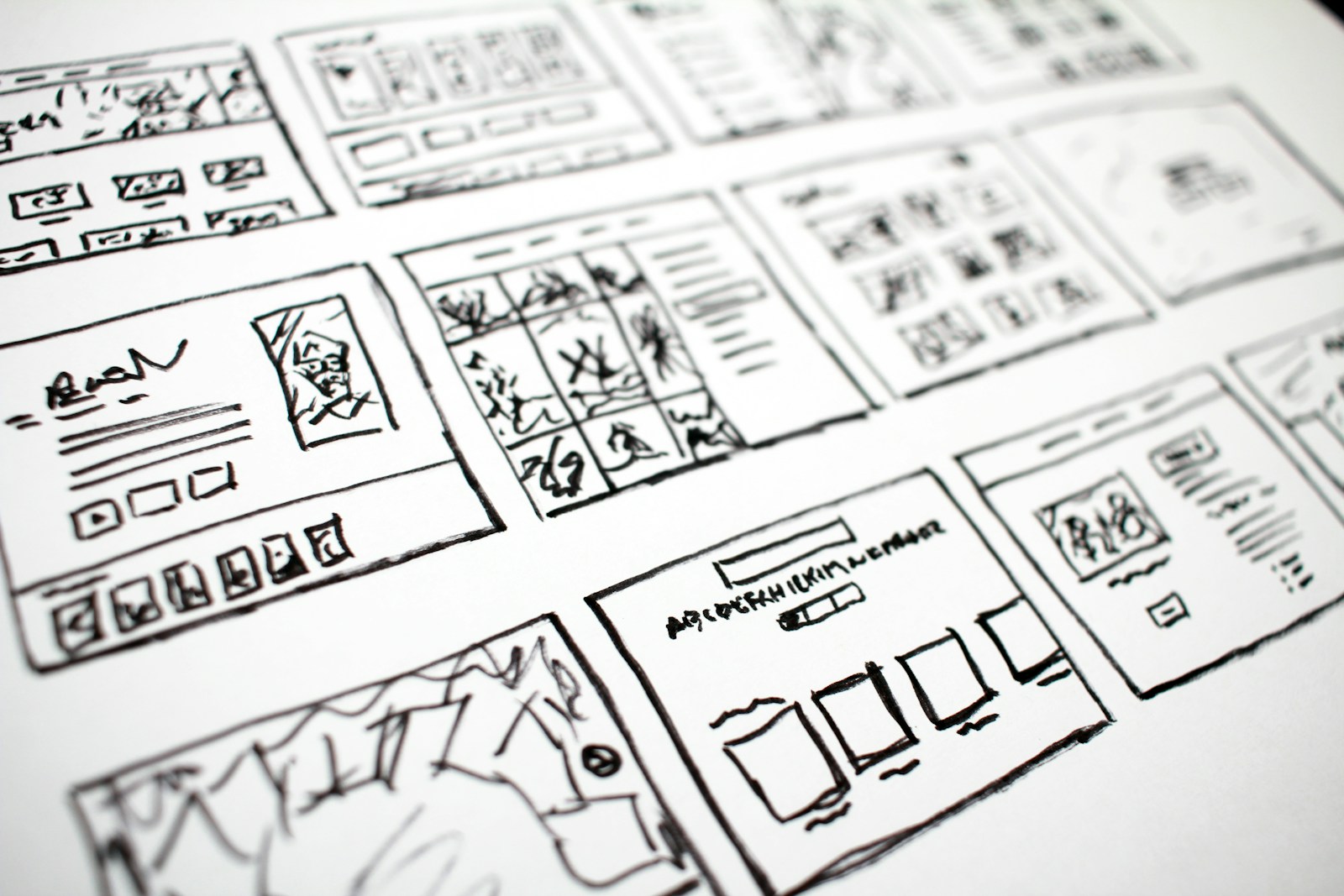















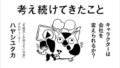

コメント