世界経済の死角
河野龍太郎,唐鎌大輔
幻冬舎
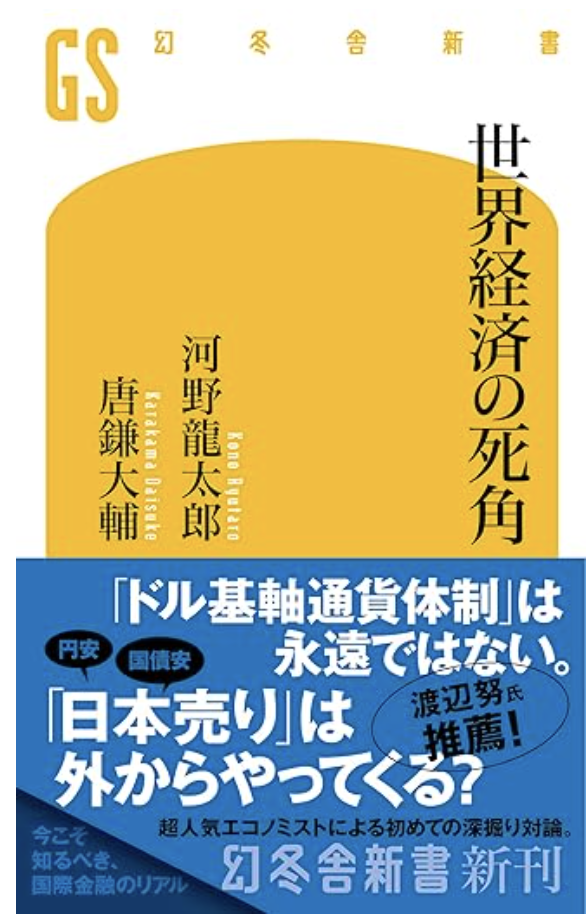
世界経済の死角 (河野龍太郎,唐鎌大輔)の要約
自民党敗退の背景には物価高と賃金停滞があり、特に中低所得層の生活水準低下が影響しています。日本は欧米の利上げ期も金融緩和を続け、円安で輸入物価が高騰しましたが、企業利益は賃上げに回らず内部留保が増加しました。河野龍太郎氏と唐鎌大輔氏は、生産性向上が賃金に結びつかない構造や、円安だけでは説明できない国際的価格差を指摘します。
日本人の暮らしが良くならない理由
「値札」の違いはどこから来るのか。おそらく「賃金の違い」に起因するはずです。(唐鎌大輔)
私たちの暮らしが豊かにならないのは、特定の誰かが悪いという話ではありません。私は、2010年代に入る頃から、「バッド・ラック(不運)」、「バッド・ポリシー(まずい政策)」、「バッド・マネジメント(よくない企業経営)」という3つの要因が複合的に重なった結果だと考えてきました。(河野龍太郎)
昨年の衆院選挙、そして今年の参院選挙で自民党が相次いで敗退した背景には、単なる政権批判を超えた深層の経済問題があります。物価の上昇が止まらない一方で、日本人の給料はほとんど上がらず、実質賃金は長期にわたり低迷しています。
家計は日常の食料品や光熱費の高騰に直面し、特に中低所得層では生活水準の低下を強く実感するようになっています。この感覚は統計の数字以上に、人々の選挙行動に直接的な影響を与えたと考えられます。
コロナが終息し、欧米各国が金利を上げ始めた2022年以降のタイミングでも、日本は異次元の金融緩和を継続し、マイナス金利政策を維持しました。その結果、急速な円安が進み、輸入物価が高騰します。特にエネルギーや食料といった必需品の価格上昇は、低所得世帯ほど負担が重くのしかかります。購買力の低下は消費活動を抑制し、景気全体を冷え込ませる要因となりました。
一方で、円安は輸出企業にとって追い風となり、過去最高益を更新する企業も少なくありません。しかし、その利益は労働者への賃上げとして還元されず、多くは内部留保として積み上げられました。
日本企業は1990年代後半以降、ベースアップを抑制し、非正規雇用を増やすことで利益率を確保する経営戦略を続けてきました。結果として、企業の利益剰余金は過去最高水準に達したにもかかわらず、個人消費は低迷し続けています。この構造的な問題が、経済の活性化を阻む最大の要因となっています。
こうした状況を分析しているのが、BNPパリバ証券経済調査本部長の河野龍太郎氏とみずほ銀行チーフマーケット・エコノミストの唐鎌大輔氏による世界経済の死角です。両氏は、日本経済の停滞を単に「生産性が低いから」と片づけるのではなく、賃金構造、企業の利益配分、国際経済環境、そして政策決定の歴史的経緯までを含めて複合的に捉えています。(河野龍太郎氏の関連記事、唐鎌大輔氏の関連記事)
物価高の議論は、多くの場合「円安の影響」に注目しがちだと唐鎌氏は指摘します。しかし、実際には為替だけでは説明できない国際的な価格差も存在します。
たとえば、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港で600mlの水が3.6ドルで売られています。円安の現在なら約540円ですが、仮に1ドル80円の超円高でも約290円と、日本の150円未満という水価格を大きく上回ります。
つまり、為替変動は価格差を広げる一因であっても、根本的には海外の「値札」自体が高いという構造があります。これは現地の人件費や賃料、物流コスト、ブランド戦略など複数の要因が積み重なった結果であり、単純に円安だけで説明することはできません。
河野氏は、生産性が向上しても賃金に結びつかない現実を最大の課題と捉え、企業経営や労使関係の抜本的な見直しを訴えています。唐鎌氏も、OECDのデータを用いて日本の労働生産性が先進国の中でも低位にあることを示し、国際競争力の強化が不可欠だと指摘します。 私たちの暮らしが豊かにならない理由を、単純に「誰かの責任」と決めつけることはできません。
2010年代以降の日本経済を振り返ると、「バッド・ラック(不運)」「バッド・ポリシー(まずい政策)」「バッド・マネジメント(よくない企業経営)」という3つの要因が複雑に重なっていると河野氏は指摘します。
東日本大震災や世界的な金融危機、パンデミックなど避けられない不運もありましたが、政策対応の遅れや判断ミスは「まずい政策」としての側面を持ちます。そして、内部留保の偏重や非正規雇用への依存といった企業行動は、長期的に経済の体力を奪う「よくない経営」として作用してきたのです。
インフレ税が国民生活を破壊する?
政府には「支出を減らす」、「税収を増やす」、「インフレを進める」の3つの選択肢しかないのに、最初の2つを避けた結果、3つ目のインフレ税が進み、家計の負担がどんどん重くなってしまっているということです。
財政運営において政府の選択肢は、「支出を減らす」「税収を増やす」「インフレを進める」の3つしかありません。ところが、日本は最初の2つを避けた結果、3つ目の「インフレ税」が進行し、家計の負担がじわじわと増しています。
実質的な消費量が同じでも価格が上がれば納める消費税は増え、実質所得が変わらなくても名目所得が上がれば所得税は増えます。累進課税下では、名目所得の上昇で税率が一段上がることもあります。こうした仕組みは、事実上の増税と同じ効果を持つため「インフレ税」と呼ばれます。
貯蓄のある世帯は、物価上昇時にも蓄えを取り崩すことで消費水準を維持できますが、十分な貯蓄のない世帯は支出を減らすほかなく、結果として生活水準を下げざるを得ません。インフレが社会全体に与える影響は一様ではなく、むしろ格差を拡大させる傾向を持つことを理解する必要があります。
中央銀行は長期国債の購入資金として、準備預金などの負債、すなわちマネタリーベースを理論上は無制限に発行できます。言い換えれば、お金をいくらでも刷ることができるということです。しかし、それによってインフレ率は上昇し、金利は低く抑えられ続けるため、実質金利は低下します。
この状況は円安をさらに進め、インフレと円安のスパイラルを引き起こします。金利上昇を抑えることで国債のデフォルトを回避できたとしても、その副作用として為替と物価の安定を失うという本質的なジレンマが横たわっていルノです。
メインバンク制の崩壊後、日本企業は長期雇用制度を維持しながら銀行依存から脱却するため、自己資本を積み増してきました。その手段として選ばれたのは、正社員のベースアップを事実上凍結する「実質ゼロベア」と、セーフティネットのない非正規雇用の拡大です。その結果、四半世紀にわたって生産性が上昇しても正社員の実質賃金は伸びず、利益は労働者に還元されませんでした。この分配の歪みは個人消費を抑え、国内需要の低迷、そして経済の長期停滞へとつながっています。
経済学の古典的な理論では、労働力や資本が国境を越えなくても、自由貿易を通じて経済的利益を享受できるとされてきました。ところが近年は、「労働力や資本が自由に移動できなければ豊かになれない」という前提が当然視されるようになっています。こうした動きは各国経済や社会の同質化を促し、文化や制度といった多様性を損ないます。
逆に、労働力や資本の移動を一定程度制限しつつ、財やサービスの貿易を活発にすることで、多様性を保ちながら利益を確保する道もあり得ます。 移民は経済的な利点をもたらす一方で、政治的な副作用も伴います。企業や高スキル層は恩恵を受けますが、その利益の源泉は移民と競合する国内労働者からの所得移転です。
格差拡大による社会分断に加え、日本ではほとんど意識されていないのが「ディアスポラ」の存在です。ウクライナ戦争におけるロシア系住民や、米国中東外交に影響を与えるユダヤ系団体は、その一例です。
日本における最大の移民グループは中国人であり、中国は経済的パートナーであると同時に、安全保障上の懸念国でもあります。大多数は日本で平和に暮らしていますが、一部が本国政府の意向で動く可能性は否定できません。人手不足を理由に移民受け入れを拡大する場合、こうしたリスクも踏まえた慎重な議論が必要です。 不動産市場では、アジアの主要都市と比べても、東京の不動産価格が依然として低いという現実も見逃せません。
これでは日本人が都心の物件を手に入れられなくなるのも当然であり、サラリーマンが自力で住宅を購入することはますます難しくなってしまいます。
今回のインフレを契機に賃金上昇の流れが生まれれば多少は改善するかもしれませんが、中国の富裕層は資本規制をかいくぐって日本の不動産を買い続けることが予想されます。エリート層はあらゆる手段を駆使し、資産を海外に振り向けています。
国内では高収入の共働き世帯や50年ローンの利用といった動きも見られますが、こうした要因は不動産市場の資金供給を押し上げ、日銀が多少の利上げを行ったとしても価格の下支えが続く可能性が高いのです。結局、国内外のさまざまな力が複合的に働き、不動産価格の上昇圧力を保っている状況を無視することはできません。
イノベーションの推進でも移民政策でも、恩恵を受ける側ばかりが支援され、不利益を被る層への対策は後回しにされがちです。本来必要なのは、影響を受ける人々への包摂的な施策であり、それが社会の安定を守る条件です。
結局のところ、経済政策の目的は数字としての成長ではなく、一人ひとりが安心して暮らせる環境を整えることにあります。生産性向上と賃金上昇の両立は不可欠であり、その先にこそ「善き生」を追求できる社会があります。生活基盤の安定、購買力の回復は出発点にすぎません。
経済の果実を公平に分かち合う仕組みを構築し、成長と幸福の両立を実現することこそが、今求められている本質的な課題だという河野氏の指摘に共感を覚えまそた。




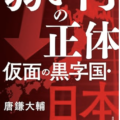
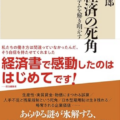





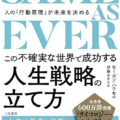
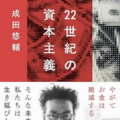
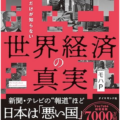

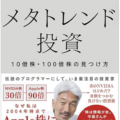


コメント