ハーバード式 脳を最適化する食事法
ジョージア・イード
朝日新聞出版社
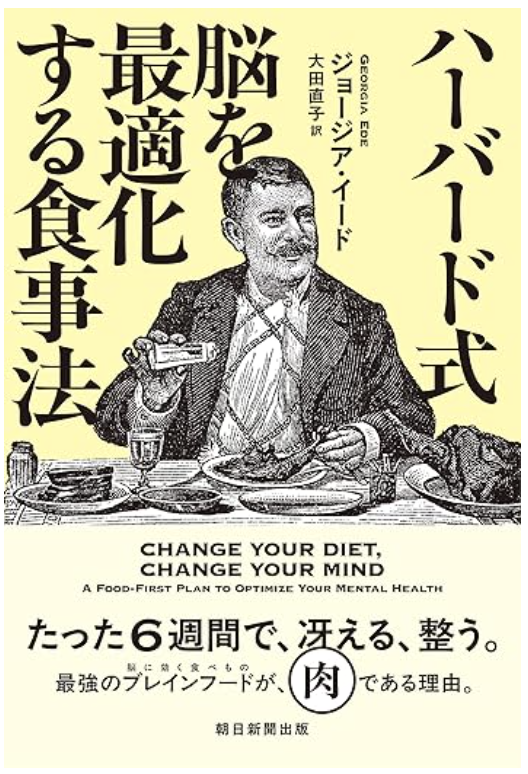
ハーバード式 脳を最適化する食事法(ジョージア・イード)の要約
『ハーバード式 脳を最適化する食事法』は、メンタルの不調は脳の「燃料不足」によって起こるという視点から、食事による改善を提案します。インスリン抵抗性や栄養不足が脳の機能を妨げる一因であり、ケトン食や静かなパレオ食が効果的であると説きます。思考や感情を整える鍵は、まず「食事への思い込み」を手放すこと。原題「Change Your Diet, Change Your Mind」が示す通り、食の選択が心と人生を根本から変えるのです。
間違った食事は脳をダメにする?
食生活は脳の発達、神経伝達物質、ストレスホルモン、炎症、抗酸化能力、脳のエネルギー産生、脳の老化、そして脳の回復に深い影響を与えるからだ。(ジョージア・イード)
集中力が続かない。感情の波が激しくなった。なんとなく常に疲れていて、頭がぼんやりしている。そんな日々が続いているとき、人は「性格の問題かもしれない」「ただのストレスだろう」と自分を責めがちです。しかし、その不調の原因は、もっと根本的なところ──すなわち脳そのものの状態にあるのかもしれません。
もしあなたが、感情や思考、そして日々の判断力さえも自分で制御しにくくなっていると感じているなら、それは意志の力ではなく、脳が本来の働きをできていないという生物学的なサインです。
ハーバード式 脳を最適化する食事法の著者、精神科医ジョージア・イード博士は、メンタルヘルスの不調の多くが「脳の燃料不足」によって引き起こされていると語ります。本書のタイトルは原書で Change Your Diet, Change Your Mind──「食事を変えれば、心が変わる」。このシンプルなメッセージが、実は本書全体の核心です。
私たちの感情、集中力、意志力、ストレス耐性といった「心のはたらき」はすべて、食事から始まります。神経伝達物質もホルモンも、原材料は口にする食べ物から作られているからです。 けれども、「食事で心を変える」ためには、その前提として「食事に対する心のあり方」を変える必要があります。
著者はこう述べます──「やり直すことができるように、食品について抱いている先入観をすべて心から取り除くこと。 野菜は体によい、脂肪は悪い、動物性食品は控えめに、──こうした刷り込まれた前提が、むしろあなたの脳の働きを邪魔しているかもしれません。
1980年代、アメリカで発表された食生活指針は、飽和脂肪とコレステロールを悪者とし、卵やバター、赤身肉を排除するよう呼びかけました。その代わりに推奨されたのは、無脂肪スイーツや精製植物油、シリアル、全粒パンといった超加工食品です。この誤った指針はアメリカだけでなく、世界中に広まり、いまや「SAD(Standard American Diet)」──高糖質・低栄養の食生活が、精神と身体の両面で人々の健康を蝕んでいるのです。
イード博士は、これらの誤った常識をデータと臨床的証拠をもとに解体していきます。とりわけ重要なのは、「インスリン抵抗性」という概念です。これは糖質過剰の食生活がもたらす、脳のエネルギー利用効率の低下を指します。
この状態が慢性化すると、感情が不安定になり、思考は鈍り、ストレス耐性が低下します。本人は「腹が立って仕方がない」「やる気が出ない」と自覚していても、実際には脳のガス欠が起きているのです。
そもそも、脳が最高の状態で機能するためには、とことん健康でなくてはならず、それは適切な栄養を与えることから始まります。 必須アミノ酸がひとつでも不足すれば、神経伝達物質、受容体、カルシウムチャネルといった、脳に必要なきわめて重要な分子を合成する材料が足りなくなります。
適切な脂肪が適切な割合で供給されなければ、脳の発達に支障が出たり、細胞膜がもろくなる・硬くなるといったリスクも生じます。さらに、膜の状態が損なわれれば、脳の免疫系すら機能不全に陥る可能性があります。 本書の中で、イード博士が特に重要視しているのがインスリン抵抗性です。 これは、体が糖をうまく使えなくなっている状態を指し、脳においても深刻な影響を与えます。
さらに問題なのは、そうしたストレスに対抗する力が、インスリン抵抗性のある脳には残されていないこと。脳はエネルギー不足のまま、ダメージだけを受け続ける状態に陥ります。 これは、うつ病や不安障害、認知機能の低下など、さまざまなメンタルの不調と深く関係しています。このように、脳の健全な機能には「何を食べるか」が決定的に重要なのです。
そして、これらの不調の根幹にあるインスリン抵抗性もまた、生活習慣──とりわけ食事の変更──によって回復が可能です。
脳を健康にするケトン食とは?
食事で心を変えるためには、食事についての心を変える必要がある。そのための第一歩は、やり直すことができるように、食品について抱いている先入観をすべて心から取り除くことである。
イード博士は「脳を健康にする食事」を次のように定義しています。
・脳を健康にする食事 脳に栄養を与えるために、必須栄養素すべてを適正量含まなくてはならない。
・脳を保護するために、損傷を与える材料を排除しなくてはならない。
・脳にエネルギーを与えるために、血中の糖とインスリンの濃度を健康な範囲に保つ必要がある。
脳が最高の状態で働くためには、健康そのものが土台にならなければなりません。適切な栄養がなければ、どんなに良い睡眠や運動を心がけていても、脳は力を出しきれません。必須アミノ酸がひとつでも足りなければ、神経伝達物質や受容体といった、脳内の情報をやり取りする重要な分子が作られません。
脂肪の種類や比率が適切でなければ、脳細胞の膜がもろくなったり、硬くなったりしてしまい、免疫の働きすら鈍ってしまいます。こうした状況では、脳の持つ本来の回復力すら発揮されません。 エネルギー不足への対策として、本書が推奨するのが「ケトン食」です。
これは脂肪を燃やして、体内でケトン体という代替エネルギーを生み出す代謝モードに体を導く食事法です。ケトーシスと呼ばれる状態に入ることで、血糖値が安定し、脳は糖の代わりにケトン体を使ってエネルギーを得られるようになります。
ケトン体の生成にはインスリン濃度の低下が不可欠であり、炭水化物を極力減らす必要があります。タンパク質の摂取も適度に保たなければなりません。脂肪はインスリンにほとんど影響を与えないため、エネルギー源として最も安定した栄養素といえます。
ケトン食の恩恵は多岐にわたり、炎症の抑制、ミトコンドリアの修復、神経伝達物質のバランス調整、さらには脳内ネットワークの安定化にもつながります。食事だけでうまくいかない場合には、断続的断食を取り入れることも有効です。食事を取らない時間を戦略的に設けることで、インスリンを下げ、自然なケトン生成を促すことができます。
断食はとくに、すでに静かな食事法(低インスリン・低刺激の食事)を行っている人にとっては、より簡単に実行できます。 本書では、こうした食事戦略を支える具体的な食材として、卵と肉の重要性を繰り返し説いています。
加熱調理された卵は、鉄とビタミンCを除けば、ほぼすべての必須栄養素を含む、完全に近い食品です。卵黄にはコリン、ビタミンA、そして脳が好む形であるビタミンK2(MK-4)が豊富に含まれています。さらに、卵に多く含まれるコレステロールは、体にとって欠かせない栄養素であり、食事から摂取するコレステロールの量は血中コレステロール値と関係がないことも明らかになっています。
一方、乳製品に含まれる特有の分子は、インスリン抵抗性や代謝機能の乱れを引き起こし、体重増加や食欲異常の原因になる可能性があるとされています。心身の健康を真剣に考えるなら、乳製品を完全に避けるという選択肢も検討すべきかもしれません。
また、穀類や豆類、種子類などの植物は、動物に食べられないように自らを防御する毒性物質を備えています。これらは消化器官や免疫系、甲状腺やミトコンドリア、さらにはメンタルヘルスにも影響を及ぼす可能性があります。
ビーガン食のように植物性食品に極端に偏った食生活では、ビタミンB12のような重要な栄養素が不足しがちです。B12の不足は、うつ病や認知症、さらには幻覚などの深刻な精神的障害につながる可能性があることが、多くの症例報告から示されています。
脳の働きを改善するブレインフードのルールとは?
メンタルヘルスの問題は代謝と栄養で説明がつき、改善の可能性がある。それを判断する最善の方法は、食事を変えて、それが心を変えるかどうかを確かめることである。
イード博士は、食事の理想形として「ブレインフードのルール」を提示しています。それは、栄養を満たし、脳を保護し、エネルギーを安定供給するという生物学的観点に基づくものです。
動物性食品を積極的に取り入れ、穀類・豆類・乳製品・精製炭水化物・アルコール・植物油などの炎症性食品を避けることが中心となります。 これに照らせば、一般に推奨されがちな地中海食やビーガン食は最適とは言えないのです。
パレオ食がもっとも緩やかにこのルールに近づいており、特にインスリン抵抗性や糖尿病がある場合には、低炭水化物型のパレオ食か、ケトン食への移行が勧められます。消化管や免疫系に深刻な問題を抱えている人は、一時的に植物を除いた肉食を実践することで回復の糸口が見えるかもしれません。その上で、著者は「静かなパレオ食」「静かなケトン食」「静かな肉食」によって、脳機能を改善できると述べています。
静かなパレオ食は、肉、魚、卵などの動物性食品を中心に構成され、一部の低糖・低刺激な野菜や果物を取り入れます。排除されるのは、穀類、豆類、乳製品、精製炭水化物、アルコール、植物油、そして超加工食品です。特に野菜の選定は慎重で、消化に負担をかけず、毒性化合物を含まない穏やかな品目のみが許容されます。
静かなケトン食は、ケトジェニックな代謝状態を維持することを目的とし、炭水化物を極限まで抑えます。そのうえで、静かなパレオ食の食品リストをベースに構成することで、栄養密度を損なうことなくインスリン抵抗性に働きかけます。血糖値とホルモンバランスの安定を図ることで、脳のエネルギー源としてのケトン利用がスムーズに進み、集中力や気分の安定にも良い影響が期待できます。
静かな肉食は、最も制限の厳しい食事スタイルであり、植物性食品を完全に除外します。さらに、乳製品、卵、加工肉といった過敏症を引き起こす可能性のある動物性食品までも排除することが基本です。このスタイルは、従来の食事法で改善が見られなかった自己免疫疾患や慢性消化器症状、原因不明の疲労・ブレインフォグに悩む人々にとって、身体をゼロベースにリセットするという意味で価値のある選択肢となり得ます。
いずれの方法にも共通しているのは、「体にとって静かな食事環境をつくる」というコンセプトです。インスリンや炎症反応を過剰に刺激せず、代謝と神経系が本来持つリズムに調和するよう、余計な要素を削ぎ落としていく。まさにこれは、現代人の脳を内側から整える「静けさの栄養学」なのです。
著者が焦点を当てているのは、意識的な食の選択が人生にもたらす肯定的な影響です。 何を食べるかという日々の決断が、自分の思考、感情、ひいては人生の質そのものを変えていく──この視点を持つことが、これからの時代のウェルビーイングの核心になるでしょう。 メンタルヘルスの問題の多くは、実は代謝と栄養によって説明でき、改善の可能性があります。
そして、それを判断する最も確かな方法は、まず食事を変えてみることです。 その変化が心にどんな影響を与えるか──それこそが、回復の糸口になるのです。 栄養を思慮深く取り入れることで、健康と人生を向上させたいと願うすべての人にとって、本書はかけがえのないガイドとなるはずです。巻末のレシピも参考になります。
原題である「Change Your Diet, Change Your Mind」(食事を変えれば、心が変わる)は、その本質を余すことなく語っています。 気分を整え、不安を乗り越え、記憶を守りながら、一生涯にわたって最適なメンタルヘルスを保つ──そのための最も根本的で、持続可能な戦略こそが「正しい食事」なのです。 これは単なるダイエットの話ではありません。 これは、「生き方の再設計」の提案なのです。








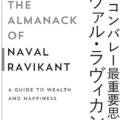
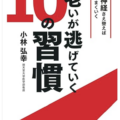
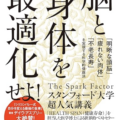
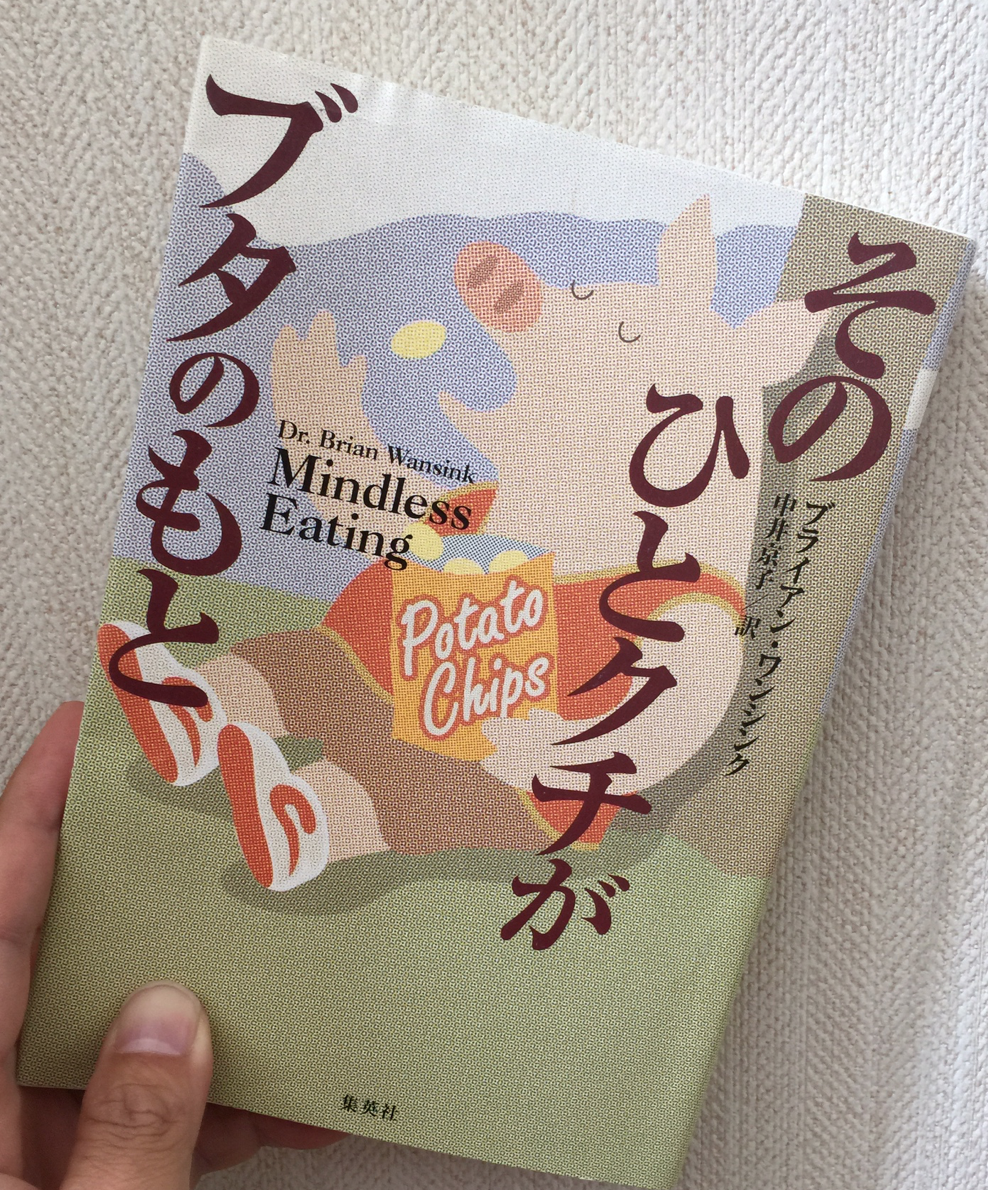





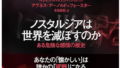
コメント