ヒップホップ経営学 お金儲けのことはラッパーに訊け
ネルス・アビー
DU BOOKS
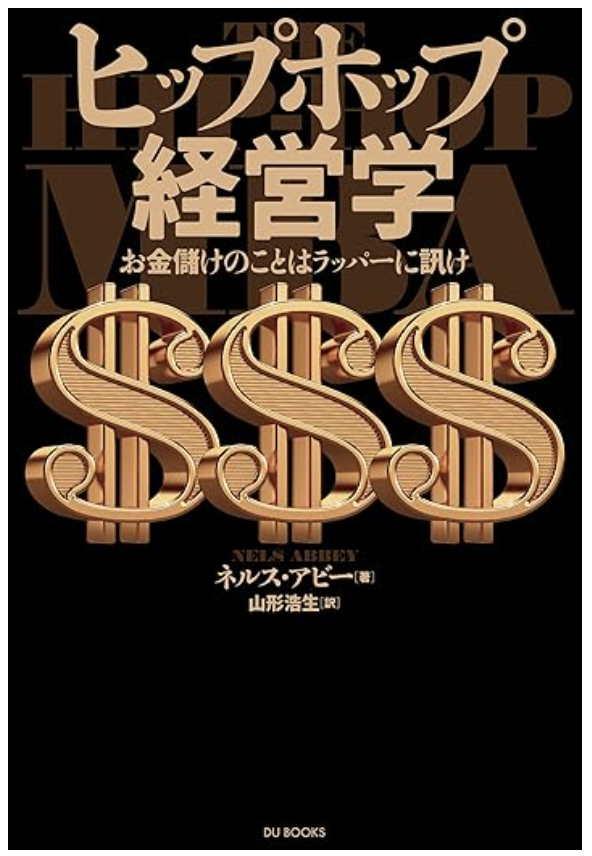
ヒップホップ経営学 お金儲けのことはラッパーに訊け(ネルス・アビー)の要約
『ヒップホップ経営学』は、ストリート文化から生まれた実践的な経営哲学を描いた書です。著者ネルス・アビーは、ジェイ・Zやカニエ・ウェストらの成功を分析し、MBAでは学べないリアルな経営を明らかにします。音楽を核にブランドを構築し、「3つのE(Endorsement・Empowerment・Equity)」の視点から文化と資本の融合を論じます。
ストリートから生まれたヒップホップから経営学を学ぶ
活動分野はぜんぜんちがうけど、株を選ぶ者(つまりプロの投資家)とビートを選ぶ者(つまりラッパー)は本質的には同じことをやってるんだ。どちらもノイズや気を散らすものをかき分けて、儲かるヒット(株か歌)を選び、そこから長期の価値を引き出そうとしてるんだ。成功した株の選択者の精神は、長期の儲け目的に奉仕してくれる(つまり収益をもたらす)と思われる企業に惹かれる。成功したビート選択者の心は、同じような長期の便益をもたらすと信じる音楽やベンチャーに 惹かれる。 (ネルス・アビー)
ハーバードのMBAプログラムには載っていない経営学があります。それは、ストリートから生まれ、数十億ドル産業へと成長したヒップホップの世界で磨かれた知恵です。
ヒップホップ経営学 お金儲けのことはラッパーに訊けは、従来のビジネス書とは全く異なるアプローチで、経営の本質に迫ります。この本が注目するのは、正規のビジネス教育を受けずに帝国を築いた起業家たち—ジェイ・Z、パフ・ダディ、50セントといったラップ界の大物たちです。
英国系ナイジェリア人作家で元ブラックロックのネルス・アビーは、金融のプロとしての視点と批評家としての鋭い洞察力を駆使して、ラッパーという起業家の視点から私たちに新たな学びを与えてくれます。
ヒップホップは、1970年代初期のニューヨーク、特にブロンクスという経済的にも社会的にも最もハードな街で生まれました。音楽教育も楽器も不足する環境で、補助的な手段として始まったこのクリエイティブな文化は、やがて「街のニーズ」を代表するアイデンティティとして成長し、商業化され、市場を強く制するまでに拡大しました。
その背景には「ギャング文化」が色濃く存在します。グループと連帯、忠誠と縄張り、そして「名声」の価値が、ラップという表現を通してストリートの戦略に変換されていったのです。荒ぶれたストリート文化が商業化され、経営的視点で分析できるほどの規模を持つようになった代表例が、ジェイ・Zです。
音楽を中核としたブランドの構築、そしてその拡張の先には、見事に構築されたビジネスモデルが存在しています。本書の核心本書は、ジェイ・Z、シュグ・ナイト、シルヴィア・ロビンソン、パフ・ダディ、50セントといったラッパーたちが、いかにして慢性的な経済的困難を圧倒的な成功に変えたかを探求しています。
彼らの武器は、MBAの学位ではなく、ストリートで培ったビジネス感覚でした。アビーは彼らのストーリーをケーススタディとして使用し、リスク管理や市場支配から、金銭心理学や企業の多様性まで、ビジネスの基本原則を説明しています。
ジェイ・Zは、ブルックリンの街でのドラッグ売買から出発し、ミュージックビジネスを実践の場として、レーベルの起業、服飾ブランドの立ち上げ、ラグジャリーブランドのアンバサダー、ストリーミングサービスの買収などを展開しながら、そのブランドの中核を「音楽」に結びつけて維持しています。
本書ではヒップホップにおけるブランドの構造を、「中核」「相補物」「腐食物」という三層モデルで表現しています。
「中核」はアーティストやラッパーの主要な活動、つまり音楽そのものであり、これはブランドの本体です。「相補物」は中核を強化・拡張するあらゆる活動で、ファッションや慈善事業、メディア出演、さらにはストリートとのつながりまでも含みます。そして「腐食物」は中核のアイデンティティと矛盾し、ブランドを損なう行為やビジネスを指します。
興味深いのは、ストリートでの信用が、他の業界ではブランドの足を引っ張る要素である一方で、ヒップホップでは相補物としてブランドを強化する要素になり得るという点です。
ジェイ・Zがかつて実際に暴力事件を起こし、その後にヒット曲で自らの正当性を主張し、最終的に罪を認めるという一連の流れも、音楽上のペルソナを強化する動きとして機能しました。
他業界では致命的なスキャンダルも、ヒップホップではリアリティとして中核を支えることがある。このパラドックスこそが、本書の提示する「ビジネスとしてのヒップホップ」の核心でもあります。
さらに本書では、ブランド戦略を理解するうえでのキーワードとして「3つのE(Endorsement、Empowerment、Equity)」が紹介されます。
エンドースメントとは、ラッパーが製品名を歌詞に入れたり、ミュージックビデオに登場させたりすることで、商品の売れ行きに影響を与える仕組みです。
Run-DMCが「My Adidas」でアディダスと契約したケースは、その代表例として今も語り継がれています。この楽曲によって、アディダスの売上は爆発的に伸び、ヒップホップと企業の提携という新しいビジネスモデルが確立されました。
私自身、東京でRun-DMCのライブを体験したことがあります。会場を見渡すと、私を含めた観客の多くがアディダスのシューズを履いていました。それは単なる偶然ではなく、彼らの音楽とメッセージに共鳴した結果でした。その瞬間、私たちは知らず知らずのうちに、Run-DMCのビジネス戦略に「参加」していたのです。
音楽を通じてブランドへの忠誠心が生まれ、それが消費行動に直結する——これほど強力なマーケティングがあるでしょうか。 これは単なる広告以上のものでした。ラッパーたちは、自分たちが実際に愛用し、ストリート文化の一部として受け入れられている製品だけを推奨することで、商業的成功を収める方法を編み出したのです。
エンパワーメントは、アーティスト自身がブランドを所有し始めた段階です。プロモーションの対象からブランドの主体へと移行したヒップホップは、ファッションや飲料、テクノロジーにおいて独自のプレイヤーとして存在感を持つようになりました。彼らが作ったブランドは、単なる音楽の延長ではなく、文化の権利主張でもありました。
そしてエクイティ。これは企業の一部を実際に所有すること、つまり資本への参加を意味します。カニエ・ウェストはアディダスと共同でYeezyを展開し、13億ドルを超える売上を記録しました。
GAPとの提携を発表した際には、株価が1日で42%も上昇しました。このように、エンドースメントとエクイティが融合することで、文化と資本が結びつくのです。
カニエ・ウェストとジョブズの共通性
カニエ・ウェストはヒップホップの最も成功したイノベーターであり、ヒップホップのアップル社だ。彼の持つイノベーションの手法は、常にオリジナルであることではなく、他人のオリジナリティやアイデアを活用して他のだれより革新的になるという手法なのだ。
本書で特に印象的だったのは、アップルとヒップホップのプレゼンテーションの比較です。スティーブ・ジョブズが製品発表で人々の感情を動かすように、カニエ・ウェストはリスニングパーティーでファンとの親密なイベントをビジネス機会に変えました。彼は制作中のアルバムのドラフトをスタジアムツアーにアップグレードし、100万ドル以上を稼ぎ出したのです。
この比較が示すのは、商品が単なるプロダクトではなく、物語や文化と結びついた意味を持つものになるという現代マーケティングの本質です。この意味で、ヒップホップは現代の最先端マーケティングの実践そのものと言えます。
現代のマーケティングにおいて「商品」は単なるプロダクトではなく、ストーリーや文化と強く結びついた意味を伴うものだということです。ヒップホップはまさに、その本質を何年も前から体現してきたカルチャーです。誰よりも早く、「人は物語に惹かれ、そこに価値を感じてお金を払う」ことを理解していたのです。
アビーは本書の中で、製品ローンチについてこう鋭く語っています。「想像力を刺激できず、関心も集められないローンチは、時間とお金の無駄だ。人目を引き、自分の存在と商品に注目させるユニークで大胆な方法を見つけることが重要です。
ただし、派手な仕掛けが肝心の商品より目立ちすぎないように、そこだけは注意しろ」。 これはヒップホップが長年実践してきた「注目経済」の原理そのものです。大胆で、目を引く演出を仕掛けながらも、本質である音楽やブランドの価値を決して見失わない。そのバランス感覚こそが、ヒップホップが単なる芸術を超えてビジネスとして成功してきた理由なのです。
ヒップホップは「当てれば金、外せば破滅」という極端なリスクとリターンの世界です。だからこそ、生き残り、成功を築いたアーティストたちは、経営戦略やブランド構築においても高度な知見を実地で身につけています。
そして彼らは、単に音楽で食っているのではなく、名声を核にして事業を多角化し、戦略的に“ラップの次”を構築しています。アーティストとしての収入よりも、ビジネスマンとしての収益の方が上回る構造をつくり上げているのです。
説教は嫌いだが、世界は絶えず変化し続けてる。変化する世界では時代とともに動くのが重要だ。
進化を続ける者だけが生き残る世界だからこそ、ドクター・ドレーはエミネムやケンドリック・ラマーを発掘し、文化とともに自身をアップデートし続けました。それは単なる成功譚ではなく、経営の本質そのものです。カルチャーの純粋性に固執せず、自分の核と向き合いながらも変化を受け入れるその姿勢は、現代の経営者像とも重なります。
『ヒップホップ経営学』は、ビジネスは論理ではなく文化の実践であることを証明する書です。音楽を起点にして、リスク、ブランド、所有、拡張、エクイティ、信用といった経営の基本原則を、まったく異なる文脈から明らかにしています。
ヒップホップの世界では、MBAで学ぶ理論の多くが実地で試され、そしてよりスピーディに改善されています。だからこそ、この本に登場する人物たちは、単なるケーススタディではなく、ビジネスを変えてきた当事者として語られるのです。
経営の知恵はどこから生まれるのか。その問いに真正面から向き合いたい読者にとって、本書は、知的刺激に満ちた示唆に富む一冊となるはずです。


















コメント