物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために
難波優輝
講談社
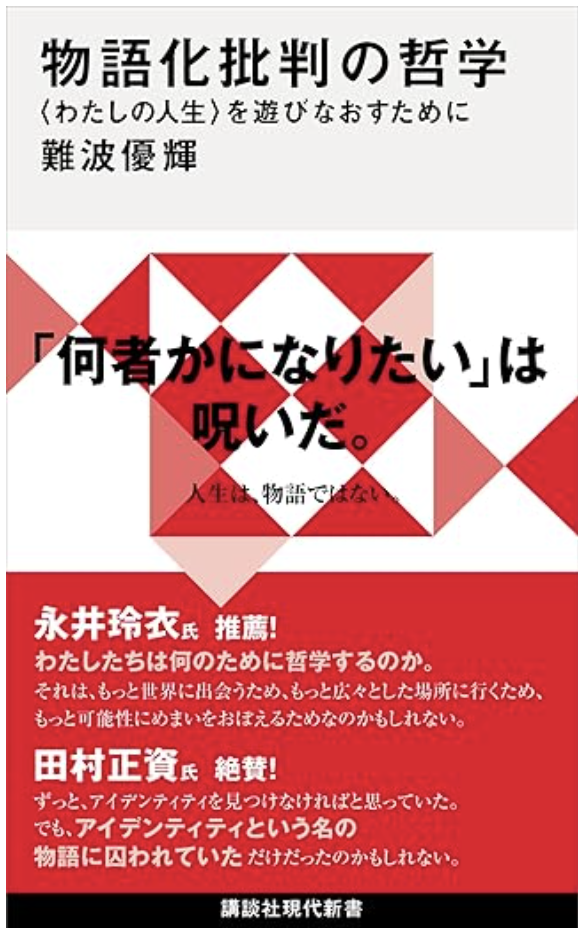
物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために (難波優輝)の要約
美学者・難波優輝氏による『物語化批判の哲学』は、現代社会における物語への過度な依存に警鐘を鳴らし、人生を物語だけで理解することの危うさを指摘します。物語的理解の限界やバイアスを明らかにし、代替として「ゲーム」「パズル」「ギャンブル」「おもちゃ」の4つの遊びを提示。多様な遊び方を横断的に体験することで、より柔軟で自由な生き方を模索する姿勢の重要性を説いています。
自らの物語を語ることの問題点
物語には確かに力がある。 だが、その力はもっぱら悪い方に作用しているのではないかと感じ始めた。(難波優輝)
美学者の難波優輝氏による物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすためには、現代社会における「物語」への過度な依存に警鐘を鳴らし、既存の枠組みにとらわれない生き方を模索する一冊です。
私たちが日常的に接しているマスメディアやSNS、企業理念、選挙活動など、あらゆる領域で「ストーリー」が重視されている現状に対し、著者はそれが本当に人間の生を豊かにしているのかを問い直しています。
たとえば政治の場面においても、候補者が語るのは自らの苦難や努力を描いた自伝的なストーリーばかりであり、具体的な政策論争や論理的な議論が軽視される傾向があります。そのような状況では、私たちは人物の「物語」に感情的に惹きつけられ、実際の政策内容を吟味することなく支持を決めてしまう危険性があります。これは、民主主義の健全な判断を曇らせ、私たち自身の選択を誤らせる要因にもなりかねません。
このように、ストーリーが社会のさまざまな領域で無批判に受け入れられ、影響力を強めている現状には、明確な危うさが潜んでいます。
ストーリーは人々の共感を集めやすく、複雑な事実や対立をなめらかに包み込む力を持つ一方で、それが過剰になることで、本来必要とされる批判的思考や理性的な対話が後景に追いやられてしまうのです。著者はそのような社会の傾向に対し、「私たちは本当にそのストーリーを必要としているのか」と問いかけています。
自己語りは本当に自己理解に寄与するのだろうか。自己語りを聴くことで、他人の理解が進むのだろうか。私たちの語りは知らぬ間に過去を歪め、理解を妨げ、自己の虚飾を作り上げ、さらには他人への不当な解釈という暴力へと転じる危険を隠し持ってはいないだろうか。
自分の人生をあたかも小説や映画のように語ることが求められ、「わかりやすさ」や「共感」を生む手段として称賛される時代において、著者はその語りが一体誰のために存在しているのかを問い直しています。語りの中で都合の悪い事実が無意識に排除され、物語が過度に美化されてしまうとき、私たちは本当に自分自身を理解していると言えるのでしょうか。本書は、そうした問いに正面から向き合っています。
自己語りは、他者からの客観的な検証や訂正を受けにくい環境で行われることが多いため、歪んだ自画像を私たち自身が繰り返し再生産してしまう傾向があります。哲学者のサリー・ラサムとマーク・ピンダーによれば、自己語りには記憶違いのほか、感情的な理由づけによって結論づける「情動的終結」、都合の良い情報だけを選ぶ「選択バイアス」、自分に都合のいい事実だけを信じやすくなる「確証バイアス」など、いくつもの認知の偏りが重なっているといいます。
さらに、美学者ピーター・ゴールディは、自己語りにおいて人は「正確であること」よりも「自分が感情的に納得できること」を優先して語る傾向があると指摘しています。つまり、私たちは真実に忠実であるよりも、自分の感情を整理しやすいように語りを構成してしまうのです。
このように、物語としての自己語りには、共感や納得を得やすいという魅力がある一方で、記憶の歪みやバイアス、感情への迎合といった落とし穴も存在しています。著者は、自己を語ることの意味と限界に改めて目を向ける必要があると訴えています。
著者は、私たちが他人を理解しようとするそのやり方に、無意識のうちに「物語的不正義」が潜んでいると指摘します。つまり、自分が納得できるストーリーを優先するあまり、相手を一方的に語ってしまい、その人の本当の姿や可能性を押し込めてしまうのです。
正義のつもりが、知らず知らずのうちに相手の自由を奪っている。そんなことが、日常のなかでいとも簡単に起こってしまいます。 では、どうすればその過ちを避けられるのでしょうか。
著者は「物語的徳」という態度を身につけることが必要だと説きます。それは、わかったつもりにならずに、自分の理解をいったん横に置いてみること。そして、相手を無理やり物語に押し込めない姿勢を持つことです。人の心や過去は、一本のストーリーでは語り尽くせないほど複雑で、いつも変わり続けているからです。
さらに大切なのは、「いま語られている物語」だけで判断せず、いつ・どのように物語を用いるべきかを見極める力を育てること。語るべきときに語り、語るべきでないときは沈黙し、耳を傾ける。それが、物語を扱うときの誠実さなのです。
そしてもう一つ、著者は「物語的徳」は個人の態度だけではなく、共同的な実践によって育まれるものだと語っています。つまり、他者とともに語り直す場を設け、多様な声が交わることによって、過去の出来事に複数の解釈を与え続ける。それが、ひとつの物語に固定されない豊かな時間の流れを生み出すのです。多元的な過去を確保することこそが、物語の暴力に抗い、人と人との理解を深める鍵になります。
物語には力があります。しかし、その力が正しく使われなければ、人を傷つけ、世界を狭めてしまうこともあるのです。だからこそ、語ることと、語らないことの両方に敏感でありたい。そして、自分一人で語るのではなく、他者とともに、語りを何度も編み直していくこと。それが、これからの時代に必要な「物語的徳」の実践なのです。
物語は、私たちの感情の感じ方や表し方にまで深く影響を及ぼします。よく練られた物語には、「感動の流れ」や「理想的な感情のあり方」が巧みに組み込まれており、読者や聞き手がある特定の感情を抱くように誘導されています。こうした構成は物語の魅力のひとつであり、必ずしも悪いものではありません。
しかし、その構造があまりにも強く作用すると、自分の正直な感情を押し込めてしまうようなことが起こります。「こう感じるべきだ」「ここで感動すべきだ」といった空気が、自然な感情の流れを妨げてしまうのです。
著者は、物語のもう一つの影響として、「キャラクター=理想の人物像」への憧れにも注意を促しています。誰かの生き方に感銘を受け、「自分もあのようになりたい」と願う気持ちは、私たちに前向きな力を与え、成長へと向かわせてくれます。
誰かを称賛することを通して、自分自身もよりよく生きようとする意欲が引き出されます。これは物語が持つ力の、肯定的な側面です。 一方で、その理想像が強すぎると、思わぬ弊害を生むことがあります。理想に合わせて自分を無理に変えようとした結果、苦しさを感じたり、「こうあるべきだ」という固定的なイメージに縛られて、本来の自分らしさを見失ってしまったりすることがあります。
また、自分の中にある理想を他人にも当てはめてしまうことで、「あの人は足りていない」「もっとこうすべきだ」と、無自覚のうちに他者を評価し、裁いてしまう危うさもあります。 著者は、このような理想化の作用には、光と影の両面があることを見据えています。理想を持つことそのものは否定されるべきではありません。
ただし、その理想が硬直せず、状況や他者に応じて見直され、問い直される柔軟性を保っていれば、それは人を縛るものではなく、むしろ支えとなる力になります。
物語や感情との健全なつきあい方には、硬直ではなくしなやかさが求められます。理想や感動に流されすぎず、自分の感情や立場に正直でいることが、自分らしく、自由に生きるための土台となっていきます。
問題点を乗り越えるためのオルタナティブとして、4つの「遊び」とは?
もし、物語を人生の遊び方の一種として捉えるとしたら、他にもさまざまな遊び方があるはずだ。
本書では、物語の問題点を乗り越えるためのオルタナティブとして、「遊び」という概念が提案されています。著者は、私たちが物語以外の形で世界と関わるための可能性として、「ゲーム」「パズル」「ギャンブル」「おもちゃ」という4つの遊びのあり方を紹介しています。
私たちの社会は、勝ち負けや成果、ゴールを求める「ゲーム的」な規律に満ちています。学校では成績、社会では実績、家庭では「よい親であること」といったゲームのルールが無数に存在し、人はそれに参加せざるをえない状況に置かれています。
ルールが明示されているぶん、がんばり方はわかりやすい。しかしその一方で、自分がそのゲームに心から同意しているのか、そもそも参加したいのかという問いはしばしば置き去りにされてしまいます。 こうした「すでに設定されたゲーム」への参加を当然のように強いられる社会のなかで、私たちはルールの外に出ることを忘れていきます。
けれども、著者はそのゲームの内側から「これは本当にこのままでいいのか?」と問い直す視点を提案します。遊びの枠組みを用いて、その構造そのものにツッコミを入れるような視線。それが「ゲーム内在的批判」として描かれています。
一方、パズル的な態度には、「正解があるはずだ」という強い欲望が宿っています。情報を集めて真実を突き止めたいという衝動が、私たちを考察文化や陰謀論にも導くことがあります。推理のように考え、答えに近づいていくプロセスには確かに魅力がありますが、問題は「一つの答え」だけに飛びついてしまう態度です。
著者はこの姿勢に対して、「パズル的徳」を提案します。つまり、問いがパズル化してもよいかを見極め、複数の仮説を並列に扱い、確定を急がず、じりじりと考え続ける粘り強さを持つこと。それが陰謀論に落ちない思考の作法であるといいます。
ギャンブル的な態度は、もっと過激です。人生のある瞬間に、自らを偶然にさらすことで、自分の存在を賭けるようなひりつきの感覚を味わいます。
ギャンブルは物語やゲームと違って、不可逆な選択によって切断を生み出します。だからこそ、そこに変容の可能性が生まれる。これまでの自分や人生を一旦断ち切り、偶然という大きな力に身を委ねることで、まったく違う自分に出会えます。その感覚を、人は「リアル」として体験するのです。
そして最後に、おもちゃ的な態度があります。子どものおもちゃ遊びには、ルールも意味も目的もありません。そこには破壊がありますが、それは赤ちゃんが積み木を崩すような、悪意のない、ただただ無邪気な破壊です。おもちゃ的主体は、物語を壊し、ゲームの勝敗を無視し、パズルの正解を笑い、ギャンブルの緊張感すらおもちゃにしてしまいます。
そうした無目的さのなかにこそ、真の自由が潜んでいます。 現代のネット空間もまた、おもちゃ的な場だといえます。言葉は切り貼りされ、人格はキャラとして扱われ、作品も関係性も「遊び終わったらポイ」されていきます。この構造はたしかに残酷かもしれませんが、同時に創造的でもあります。物語や規範に回収されないこの「ゆるさ」は、他者と一緒に何かを共有するための、別の形の接続方法を提示しています。
おもちゃ的主体は、「ゴールを目指す」とか「最適解を探す」といった考え方にあまり関心を持ちません。先のことを考えて行動するというよりも、ただ「いま、やりたいからやる」。そんな感覚で動いています。勝つことにもこだわらず、そもそもルールを守ろうという気すらないこともあるのです。
このおもちゃ的主体が面白いのは、物語やゲーム、パズル、ギャンブルといった他の遊びの枠組みすら、すべて「おもちゃ化」してしまうところにあります。ただし、そこに破滅的な意図があるわけではありません。深刻さを帯びた破壊ではなく、むしろ軽やかで、笑いながら壊してしまうような無邪気な行為です。
たとえば、子どもが丁寧に積み上げた積み木を、ふとした拍子に崩してはまた作り直すように。壊すことがそのまま創造にもなっていて、そこには悪意ではなく、遊びの純粋な快楽があります。
とはいえ、おもちゃ的な振る舞いは、真剣に物語を生きている人たち、ゲームのルールにのっとってがんばっている人たち、パズルの答えを探している人たち、あるいは人生を賭けて勝負している人たちにとっては、やっかいな存在に映るかもしれません。
実際、おもちゃ的主体はしばしば怒られます。空気を読まず、真面目なゲームを「ふざける」ことで邪魔をしてしまうからです。けれど、それこそが、おもちゃ的主体の存在意義でもあるのです。
異なる「世界」を生きながら、すなわち、物語的世界、ゲーム的世界、パズル的世界、ギャンブル的世界を生きながら、しかし、誰もがおもちゃ遊びをして、異なる「世界」を旅することに挑戦できる。そう。おそらく、おもちゃ的世界というものは、他のすべての世界とつながる交通経路のような細く伸びた世界なのかもしれない。
私たちの社会では、ゴール、正解、成果、勝利といったものが重視され、物語・ゲーム・パズル・ギャンブルそれぞれが、仕事や家庭や教育といった現実としっかり結びついています。そこでは真面目にやることが評価される一方で、ふざけたり逸脱したりすることは許されにくくなっています。
しかし、おもちゃ的なあり方は、それらすべての「真面目な遊び」を軽やかに横断し、ときには壊してしまうことで、逆に新しい可能性を開いてくれます。物語的世界、ゲーム的世界、パズル的世界、ギャンブル的世界。それぞれが持っている論理や前提を、おもちゃ的主体は意図的に無視し、壊し、別の形に変えてしまうのです。
その姿はときに暴力的にも見えますが、実際には非常に創造的で、解放的でもあります。 おもちゃ的世界は、あらゆる世界とつながるための細い通路のような存在かもしれません。どこか一つの遊びに飲み込まれそうになったときに、別の遊びへと移動するきっかけを与えてくれるのです。
ルールのない遊びの中で、異なる遊びを生きる人たちと、一時的にでも同じ場所で遊び、時間を共有することができます。
だからこそ、私たちはもっと子どもたちに学ぶべきなのかもしれません。大人たちは「おもちゃ遊びの熟練者」ではなく、むしろまだまだ未熟な存在です。真面目に働き、ルールを守り、成果を求めるその一方で、おもちゃのように遊ぶ力が、どこかで失われてしまっているのです。
個人が自身の関心や傾向に応じて、どのような「遊び」の形式に親和性を持つかを理解し、これまで試したことのない遊びの形態に意識的に取り組むことは、自己理解の深化および経験の多様化に資する行為です。
物語、ゲーム、パズル、ギャンブル、おもちゃといった複数の遊びの論理を横断的に体験することによって、私たちはそれぞれの枠組みにおける価値基準や認知の偏りに気づく機会を得ることができます。人生を楽しむために、物語だけに頼るのはやめた方が良さそうです。
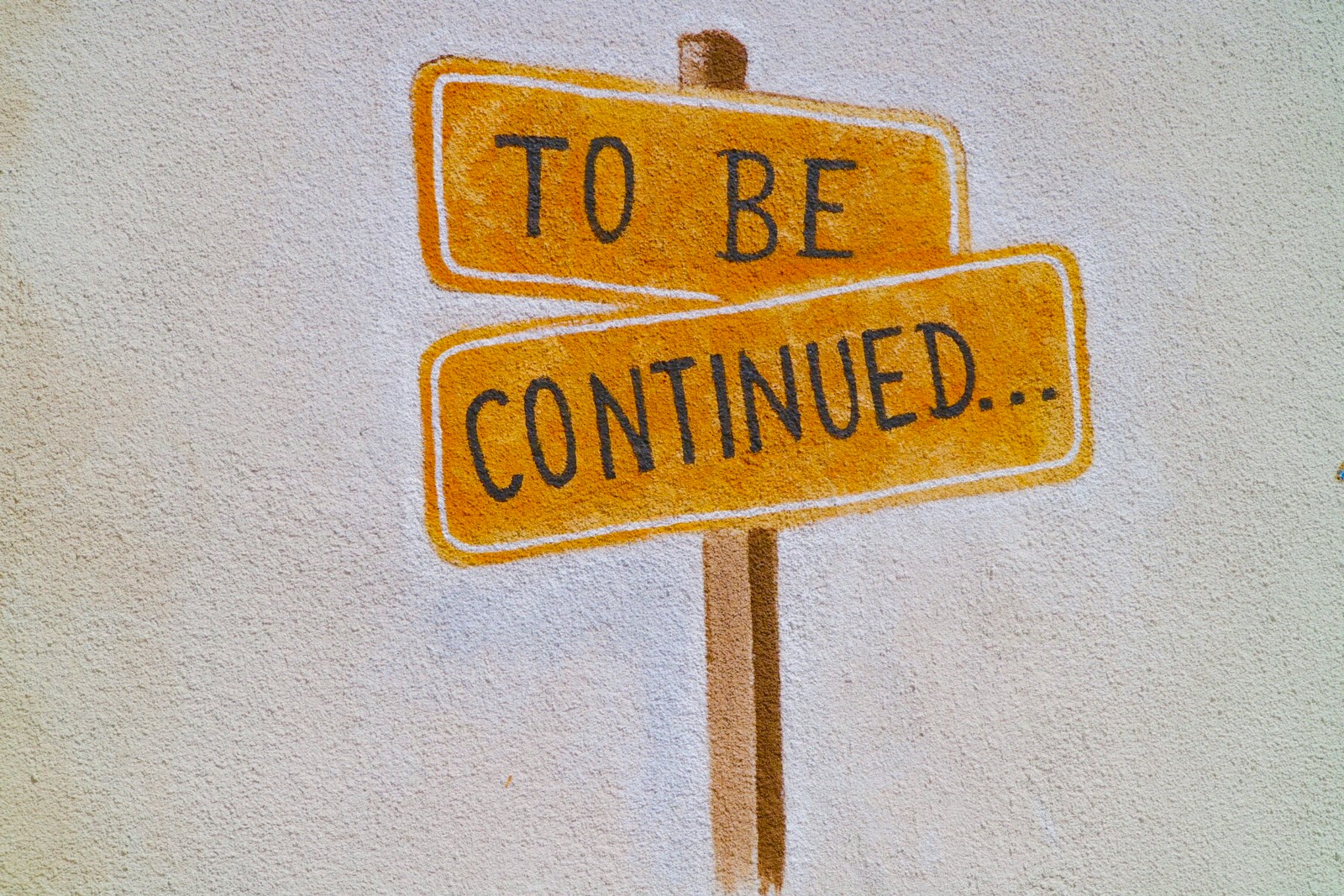



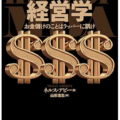
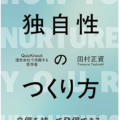





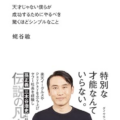
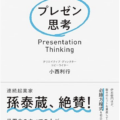
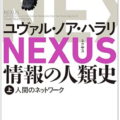

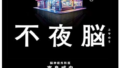

コメント